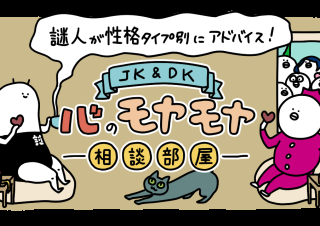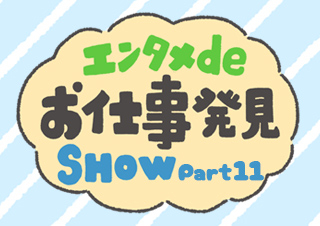市役所の仕事とは?仕事内容や必要な資格、難易度まで紹介! 実際に働く人にインタビューも!
リクルート進学総研の調査によると、高校生がなりたい職業の1位は公務員(※)。
人のために働ける仕事で、収入も安定していることが人気の理由だ。
公務員にはさまざまな仕事がある。
なかでも、身近なのが「市役所の仕事」だけど、どんな仕事をしているのか、案外、知らなかったりする。
そこで市役所の仕事を徹底解説!
実際に市役所で働く人のインタビューも紹介しよう。
市役所の仕事に興味がある人は、ぜひ参考にしてほしい。
(※)リクルート進学総研調べ 【第10回 高校生と保護者の進路に関する意識調査2021】より
目次
市役所の仕事とは?
市役所の仕事とは、市民が安心・安全に、快適に暮らせるよう、暮らしのあらゆる面にわたってサポートをする仕事。
その分野は教育、福祉から防災、産業振興、観光、都市計画などまで幅広く、どれも市民生活には欠かすことのできない、重要な仕事となっている。
そうした仕事を行う市役所職員は、身分は地方公務員。
市役所で働くためにはそれぞれの市が行う地方公務員試験(市職員採用試験)に合格することが必要だ。
市役所の仕事の種類と仕事内容とは?
市役所の仕事というと、頭に浮かんでくるのは窓口業務だけど、それだけが仕事ではない。
市民生活を支えるために、さまざまな仕事をしている。
仕事は、大きく「事務系(一般行政職)」と「技術系(技術職)」に分かれている。
それぞれについて、解説していこう。
事務系(一般行政職)
市役所の事務系の仕事は、一般行政職や行政事務、行政職などともよばれ、窓口業務や事務処理、政策の立案など、業務は多岐にわたる。
分野も幅広く、市民生活のあらゆる面に密接した仕事に取り組んでいる。
例えば、こんな仕事だ。
・市立小・中学校など学校や保育所の運営
・図書館やスポーツセンターなど公共施設の管理
・観光客を増やすための宣伝活動
・商店街の活性化のための政策立案
・ごみの収集・処理に関する管理
・健康診断の企画・運営
・自然災害に備えて食糧品の備蓄、避難所の整備など、対策を考えて実行
これらは市役所の事務系の仕事のごく一部。
こんな具合に市役所の事務系仕事は、行政全般の幅広い業務となっている。
.jpg?20260219)
※事務職の仕事は幅広い分野にわたっている。写真は、横浜市政策局で市のプロモーション業務に従事している難波茉由さん
地方公務員になるには 地方公務員を目指せる学校を探す
技術系(技術職)
市役所の技術系の仕事は、技術職とよばれている。
土木、建築、電気、機械などの区分で、理科系の専門技能を生かしてスペシャリストとして働く。
例えば、こんな仕事だ。
道路や橋、河川、ダム、上水道施設など、主にインフラ(社会生活を支える基盤)の整備にかかわる。
新設・改修の計画立案や設計・施工、工事の監理、維持管理といった業務を担当する。
土木施工管理技士になるには 土木施工管理技士を目指せる学校を探す
・建築
建築基準法に基づく建築物の確認審査や耐震の相談、市営住宅の整備、市民ホールやスポーツ施設など公共建築物の設計・工事監理など。
建築設備士になるには 建築設備士を目指せる学校を探す
・電気
廃棄物処理施設や上下水道施設、公共施設などの電気設備の設計・施工や工事の監理を行う。
また、それら施設の維持管理や検査といった業務も担当。
市営バス・地下鉄の送電設備や信号などの建設、保守・点検にも携わる。
電気主任技術者になるには 電気主任技術者を目指せる学校を探す
・機械
廃棄物処理施設や上下水道施設、公共施設など、幅広い分野で機械設備の設計・施工や工事の監理、設備の維持管理や検査といった業務も担当。
機械設計技術者になるには 機械設計技術者を目指せる学校を探す
・化学
ごみ処理施設や工場などの環境汚染の防止や環境保全対策、上下水道の水質検査や水質管理、公害防止対策の企画・立案、調査・研究などに携わる。
化学技術者・研究者になるには 化学技術者・研究者を目指せる学校を探す
・造園
公園や街路樹、緑地の企画・設計、工事監督、維持管理を行う。
このほか、市役所で働く技術職として、農業や畜産といった分野を設けている市もある。
農業は農業技術の改良や指導、研究、農家の育成といった業務に従事する。
畜産は、市立動物園の動物の飼育管理・調査研究、環境教育などの業務を行う。
造園士になるには 造園士を目指せる学校を探す
こうした技術職の場合、必ずしも市役所の本庁舎に勤務するわけではなく、出先機関などに配属されるケースも多い。
例えば、「土木」「造園」分野の技術職なら土木事務所、「電気」「機械」「化学」分野ならごみ処理施設や水処理施設などという具合だ。
その他(専門職)
市役所には、資格が必要な「専門職」の仕事もある。
市にもよるが、例えば、次のような職種がある。
市役所本庁舎に勤務する場合もあるが、出先機関などに配属されるケースが多い。
主な職種と勤務先は次のようになる。
市立病院や救急医療センター、市立保育所などに勤務し、看護、医療的なケアを行う。
看護師になるには 看護師を目指せる学校を探す
●薬剤師
医療衛生センター、環境衛生研究所などに勤務し、環境衛生指導、試験検査などの業務に携わる。
薬剤師になるには 薬剤師を目指せる学校を探す
●獣医師
食品衛生検査所、保健所などに勤務し、食肉や食品の安全性を確保するための食肉衛生検査や食品衛生に関する業務に携わる。
動物愛護センターなどで動物の愛護に関する業務にかかわるケースも。
獣医師になるには 獣医師を目指せる学校を探す
●保育士
市立保育所や児童福祉センターなどに勤務し、保育業務、保護者に対する子育て支援などの仕事に携わる。
保育士になるには 保育士を目指せる学校を探す
●管理栄養士
保健福祉センター、児童福祉センターなどに勤務し、健康増進のための栄養指導や献立作成などの仕事をする。
管理栄養士になるには 管理栄養士を目指せる学校を探す
●保健師
保健福祉センターなどに勤務し、母子、高齢者、障害者などに対する健康相談、訪問指導などに携わる。
保健師になるには 保健師を目指せる学校を探す
●心理職(※)
児童相談所や児童福祉センターなどに勤務し、相談業務、心理判定や指導などに携わる。
臨床心理士になるには 臨床心理士を目指せる学校を探す
●社会福祉職(※)
福祉事務所や児童相談所などに勤務し、相談業務や調査、指導、福祉に関する施策の企画・立案などに携わる。
社会福祉士(ソーシャルワーカー)になるには 社会福祉士(ソーシャルワーカー)を目指せる学校を探す
●情報・デジタル(※)
ICT(情報通信技術)を活用した施策の立案や、市役所の業務を効率的に行うためのシステムの企画・運用、サイバーセキュリティー対策などに携わる。
(※)「心理職」「社会福祉職」「情報・デジタル」は、市役所によっては「事務系(一般行政職)」のなかの区分としているケースもあるが、資格や専門性が必要な仕事であるため、この記事では「専門職」として紹介している。 情報処理士になるには 情報処理士を目指せる学校を探す
<市役所の仕事は異動が多い>
市役所の職員は、3年~5年くらいの周期でさまざまな部署を異動する。
技術系職員や専門職の職員は知識やスキルをいかせる部署や出先機関への異動になるけれど、事務系職員の場合は「福祉関連の部署から財政関連の部署へ」「都市計画関連の部署から教育関連の部署へ」などという具合に、まったく違う分野へ異動することも少なくない。
「異動が頻繁にあると、仕事の専門性を磨いていけないのでは…?」と思われがちだけど、いろいろな部署の仕事を経験することで幅広い知識と視野が身につき、市民生活を支えるゼネラリストとして成長していくことができる。
市役所の主な部署
市役所といっても、その市の人口がどのくらいかなどによって、市役所の規模や組織は違ってくる。
ここでは一般的な市役所の主な部署と業務内容を紹介しよう(※)。
(※)複数の自治体の組織を調べ、情報を整理。部署名、業務内容は自治体によって異なる。
市全体がより住みやすいまちになるように、市の規則を考え、将来についての計画を立てる。
また、ホームページや市報などを通して市民に情報を発信したり、市の人口などの調査や統計資料の作成、公共施設の管理・運営などを行う。
●総務部
市役所で働く職員の給料の支払いや福利厚生、研修、職員の採用にかかわる業務を担当。
このほか、市役所内でパソコンを使って効率よく業務を進めていけるように情報システムを企画・開発・管理する業務なども行う。
●財政部
市民が納めた税金をもとに、1年ごとの市の予算を決め、どんなことにいくら使うのか、お金の使い道を決める。
また、その年に市民が納める税金の金額を決め、納めるための手続きなどを市民に連絡するといった業務を行う。
●福祉保健部
高齢者や障がいのある人、生活に困っている人のために、安心して生活できるよう、相談に対応したり、支援を行う。
また、乳幼児から高齢者まで、市民の健康を守るために、健康診断、予防接種、健康相談といった業務を行っている。
●市民生活部
引っ越しや結婚、子どもが生まれたときなど、市民の暮らしにかかわるさまざまな届け出を受け付けて管理をする部署。
また、住民票や戸籍謄本、印鑑証明書、マイナンバーカード、年金、保険証などにかかわる業務を行う。
地震、台風など自然災害や、犯罪から市民を守るための業務にも携わる。
●子ども家庭部
子育てをしている家庭と子どもたちを支援。
子育てに関する各種手当ての手続きや、子育てについての悩み相談に対応する。
市立保育所や児童館、学童保育所などの運営も行う。
●都市整備部
住みやすいまちにするために、都市計画に取り組む。
安全で通りやすい道路を造ったり、道路の維持・管理、市内の交通の便が良くなるようコミュニティーバスの運行・管理、緑豊かな公園を造る、街の再開発計画の立案などといった業務に従事する。
●建設部
新たに建つ建物が建築基準法や各種条例を守っているかどうかを審査したり、建築許可・指導にかかわる業務を行う。
このほか、公共施設の設計・工事監理、市営住宅の管理・運営、空き家対策、歴史的建築物の保護といった業務を担当。
●上下水道部
市民がおいしくてきれいな水を飲めるよう、上水道の配水管の維持管理や水質管理を行う。
また、家庭や工場から出る汚水をきれいにして流すために下水道を整備。
このほか、ごみを処理してリサイクルする業務、公害問題や環境保全対策にも取り組む。
●経済観光部
農業や商業など、市の産業が盛んになるよう、さまざまな施策を考えたり、その産業で働く市民が増えるように支援する。
市内の特産物がたくさん売れるよう、全国に向けて宣伝活動を行うのも仕事。また、観光施設の管理やイベントの企画・宣伝、市の魅力の発信などにも携わる。
●教育部
学校の整備、児童・生徒の入学・転入・退学にかかわる業務、学校の備品をそろえたり、学校給食の管理などに携わる。
また、図書館や公民館、体育館、博物館など市の施設の管理、文化財の保存・活用なども行う。
このほか、市役所のお金の出し入れを記録する「会計管理」、市民からの税金が正しく使われているかどうかを監視する「監査委員会」、市議会を開く準備をしたり、市議会で話し合われたことの記録をまとめる「議会事務局」などの部署もある。
ここで紹介したのは、一般的な市の市役所のケース。
政令指定都市となると市役所の規模が大きくなる。
全国には792の「市」があって、そのうち20市が政令指定都市に指定されている(※)。
市役所の仕事に興味がある人は政令指定都市の役所のことも調べておくといい。
(※)出典 :「政府統計~市区町村の数(2023年9月現在)」
<政令指定都市の市役所>
政令指定都市とは、地方自治法によって、「政令で指定する人口50万以上の市」のことで、政令市、指定市とも呼ばれている。
現在、札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市、千葉市、新潟市、名古屋市、静岡市、浜松市、大阪市、堺市、神戸市、京都市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市の計20都市が政令指定都市になっている。
政令指定都市は社会福祉、教育、都市計画などの分野で、一般の市よりも広範囲に権限をもっているのが特徴。
例えば、福祉では「市」として児童相談所などを設置したり、教育では教員採用試験の実施など、都道府県がもっている権限を委託されている。
そのため、実施できる事業や財源の規模も大きく、市には複数の行政区がある。市役所の組織も一般的な「市」の体制とは異なり、「市役所(本庁)」のほか、行政区ごとに「区役所」が設けられている。
市役所(本庁)では主に施策の立案や職員の採用活動など、市全体にかかわる業務を行うのに対し、各区役所では住民票や転入・転出届け、福祉・保健分野など、地域に密着して業務を行う。
Q 政令指定都市の区は、東京都の区(23区)とどう違う?
政令指定都市の区は、「行政区」。
独立した自治体ではなく、市役所の組織のひとつなので、区長は市の職員のなかから市長が任命する。
政令指定都市に入庁し、区役所に配属されても区や部署の異動、本庁への異動もあり、同じ区でずっと働くということはない。
それに対し、東京都の区「23区」は「特別区」と呼ばれている。
東京都内の区役所で働くには、特別区職員採用試験に合格後、各区へ配属され、原則としてその区で働き続けることになっている。
市役所職員になるにはどうすればいいの? 必要な資格は?
それでは、市役所職員になるための方法について、詳しく見ていこう。
市役所試験(市職員採用試験)を受験する
市役所職員になるには、「市」が実施する市職員採用試験(地方公務員試験の一種)を受験し、合格することが必須。
採用試験は、大きく「事務系(一般行政職)」「技術系(技術職)」に分けて行われ、「その他(専門職)」は職種ごとに試験が実施される。
技術職、専門職については、採用区分(職種)は市によって異なっているうえ、年によっては募集しない職種があるので、注意が必要だ。
<市職員採用試験の受験資格>
全国には792の市があって、それぞれの市ごとに市職員採用試験を行っている。そのため、試験内容はもちろん、受験資格も市によって異なっている。
ここでは基本的なチェックポイントを紹介しよう。
■学歴の要件
市職員採用試験は、ほとんどの市では、学歴の条件を設けていない。
ただ、特徴的なのは、職種ごとに「高校卒業程度(初級)」「短期大学・高等専門学校卒業程度(中級)」「大学卒業程度(上級)」といった設定がなされていること。
これは「高卒程度の知識が必要」「大卒程度の知識が必要」という、試験問題の難易度を示すもの。
こうした場合、高卒であっても、ほかの受験資格(年齢要件など)を満たしていて、学力レベルに自信があるならば「大学卒業程度」の試験を受けることが可能。
ただし、一部の市では「上級試験の受験資格があるのは大学卒」「初級試験の受験資格があるのは高校卒」などという具合に、学歴の条件を設けているので、要注意。
また、基本的に学歴は問わないとしていても、事務職のなかの特定の職種(例:文化財担当など)や、「技術系」職員、専門職の職員などを目指す場合には、その職種に関して学んだことを示す学歴が受験資格に設定されているケースもある。
それぞれの市の受験案内を調べてみるといいだろう。
■年齢の要件
市職員採用試験では受験資格として、年齢の条件が設けられている。
市によって年齢の上限は異なっているが、「大学卒業程度」採用試験の場合なら、20代後半まで受験できる市が多い。
参考までに、政令指定都市・横浜市の職員採用試験の年齢要件を紹介しよう(※)。募集職種によっても違いがある。
〇横浜市 大学卒程度等採用試験(令和5年度)
△募集職種:事務、社会福祉、心理、デジタル、土木、建築、機械、電気、農業、造園、環境、学校事務、消防【一般】、消防【専門】、消防(救急救命士)⇒⇒1993年(平成5年)4月2日から2002年(平成14年)4月1日までに出生した人(21歳から30歳まで)
△募集職種:保健師、衛生監視員⇒⇒1993年(平成5年)4月2日以降に出生した人(30歳まで)
〇横浜市 高校卒程度、免許資格職など採用試験(令和5年度)
△募集職種:事務、土木、機械、電気、水道技術、消防、消防(救急救命士)⇒⇒2002年(平成14年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日までに出生した人(17歳から21歳まで)
△募集職種:保育士⇒⇒1989年(平成元年)4月2日以降に出生した人(34歳まで)
△募集職種:司書、栄養士、学校栄養⇒⇒1993年(平成5年)4月2日以降に出生した人(30歳まで)
※横浜市職員採用コンセプトページ
■必要な資格
市職員採用試験は、基本的には、受験するために必要な資格はない。
ただし、専門職など一部の職種については、業務を行うために必要な資格を取得していることが必須となっている(または採用時期までに取得見込みであること)ので注意したい。
例えば保育士、保健師、看護師、司書、栄養士・管理栄養士などの職種は、資格が必須。
★それぞれの職種の資格の取り方を確認しよう! 保育士になるには 保健師になるには 看護師になるには 図書館司書になるには 栄養士になるには 管理栄養士になるには このほか、社会福祉職なら国家資格の社会福祉士や任用資格の社会福祉主事(※)、心理職なら国家資格の公認心理師、情報・デジタルの職種なら国家資格のITパスポート試験、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験などのいずれかの資格の取得が受験要件になっている。
(※)任用資格
ある特定の職業や職務に任用されるために必要な資格のこと。 社会福祉主事は、大学などで厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業することで取得できる。
市役所で働くのは難しい?どんな試験? 難易度は?
市役所で働くためには市職員採用試験に合格しなければならないが、どんな試験が行われているのだろう?
難易度も気になる。
そこで試験の内容と難易度について調べてみた。
それぞれの市で試験内容は異なっているが、大学卒業程度(上級)試験の区分で一般的に実施されている試験方式をみていこう。
多くの市では1次試験(筆記)と2次試験(1次試験合格者のみ受験可:論文・面接)が行われ、市によっては3次試験、4次試験まで行うところもある。
試験の内容や出題分野、試験の配点、合格基準などは、それぞれの市の公式サイトで公開されているので、調べてみるといいだろう。
各試験種目にはそれぞれ基準点がある。
総合得点が高くても、ひとつでも合格基準に達していない種目があれば、不合格になることが多い。
また、市民と接する機会が多い仕事であるだけに、面接試験の配点が高い傾向にあるようだ。
事務系(一般行政職)の採用試験
事務系の採用試験(大学卒業程度試験)で一般的に行われている試験方式は次のようになる。
<1次試験>
■教養試験
市職員採用試験で行われることの多い試験形式。
大学卒業程度の「一般知識分野(人文科学、自然科学、社会科学、時事問題)」と、「一般知能分野(文章理解、英文理解、判断推理、数的推理、資料解釈など)」から出題される筆記試験。
■専門試験
憲法、行政法、民法、経済学、財政学、社会政策、政治学、行政学、国際関係、経営学などの専門的な知識を問う筆記試験。
※市によっては、1次試験に専門試験を実施せず教養試験のみのケースや、1次試験で筆記に加えて個別面接を行う場合もある。
<2次試験>
■論文
与えられた課題についての論文。
自分の考えや意見、論理性、表現力などが試される。
■面接
個別面接に加えて、グループワークや集団面接などの形で実施する市もある。
コミュニケーション力や協調性、責任感、積極性などのポイントで審査される。
技術系(技術職)の採用試験
技術系の採用試験(大学卒業程度試験)で一般的に行われている試験方式は次のようになる。
筆記では教養試験のほか、土木、電気など募集区分の仕事に必要な専門知識を問う専門試験が行われることが多く、大学で学んだ技能が生かされる。
<1次試験>
■教養試験
大学卒業程度の「一般知識分野(人文科学、自然科学、社会科学、時事問題)」と、「一般知能分野(文章理解、英文理解、判断推理、数的推理、資料解釈など)」から出題される筆記試験。
■専門試験
各募集区分に応じた専門知識を審査する筆記試験。例えば次のような試験が行われる。
・土木/数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、材料・施工
・建築/数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、都市計画、建築設備、建築施工
・機械/数学・物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力学・制御、機械設計、機械材料、機械工作
・電気/数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子工学、情報・通信工学
・化学/数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化学・有機工業化学、化学工学
・造園/造園学原論、造園材料・施工、造園管理、造園計画・設計(都市・地方計画を含む)、造園関連基礎
※市によっては、1次試験に教養試験を実施せず、専門試験のみというケースもある。
<2次試験>
■論文
与えられた課題についての論文試験。
■面接
個別面接
その他(専門職)の採用試験
専門職の採用試験で一般的に行われている試験方式は次のようになる。
筆記では、教養試験と専門試験が実施されることが多く、専門試験では、社会福祉、心理職など募集区分に応じて仕事に必要な専門知識を問われる。
<1次試験>
■教養試験
市職員採用試験で行われることの多い試験形式。
大学卒業程度の「一般知識分野(人文科学、自然科学、社会科学、時事問題)」と、「一般知能分野(文章理解、英文理解、判断推理、数的推理、資料解釈など)」から出題される筆記試験。
■専門試験
各募集区分に応じた専門知識を審査する筆記試験。例えば次のような試験が行われる。
・社会福祉/社会福祉概論(社会保障を含む)、社会学概論、心理学概論(社会心理学を含む)、社会調査
・心理職/一般心理学(心理学史、発達心理学、社会心理学を含む)、応用心理学(教育心理学・産業心理学・臨床心理学)、調査・研究法、統計学
・管理栄養士/社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論
<2次試験>
■論文
与えられた課題についての論文試験。
■面接
個別面接
導入する自治体が増加中。「特別枠」の試験とは
市職員採用試験に合格するには、どの職種でも、基本的には教養試験と専門試験の勉強が必要になる。
幅広い知識がなければ合格は難しいので、公務員試験の受験予備校などを利用して勉強する人も少なくない。
そんななか、「特別枠」という試験方式を導入する市が増えている。
これまで市役所職員を就職の選択肢として考えてこなかった人や、民間企業志望者など、幅広い層の人たちにチャレンジしてもらうことを目的に設けられている試験方式だ。
試験内容は、市によって異なっているが、筆記試験の負担が少ないというのが特色。
市役所試験の難易度
総務省「地方公務員における働き方改革に係る状況―令和3年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要―」(2022年12月発表)によると、市区職員採用試験の競争率は大学卒業程度試験で6.9倍という結果が出ている。
ちなみに高校卒業程度試験の競争率は7.5倍。
同じ調査で都道府県職員採用試験の大学卒業程度試験の競争率は4.6倍(高校卒業程度試験の競争率は6.5倍)。
全体の競争率はこのような調査結果が出ているが、市職員採用試験の競争率は、市や職種によって差がある。
全体的な傾向としては、技術職の採用試験の難易度は低くなっている。
また、「特別枠」試験の場合、市職員採用試験の筆記試験対策をしなくてもいいというメリットがある代わりに、受験者は民間企業とも併願しやすくなるため、試験の競争率が高くなる傾向がある。
市役所は官公庁? 国家公務員との違いは?
官公庁とは、国の行政機関と、地方公共団体の役所の総称のこと。地方公共団体の役所のひとつに市役所がある。
まとめると、こんな感じ。
<国の主な行政機関>
・内閣官房
・内閣法制局
・人事院
・内閣府(宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁など)
・中央省庁(デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省)
・会計検査院
など
<地方公共団体の主な役所>
・都道府県庁
・市役所
・区役所
・町役場
・村役場など
☆国家公務員と市役所職員との違い
国家公務員とは、国全体の政策や運営にかかわる業務を行う公務員。
上記で記述している<国の主な行政機関>のほか、裁判所、国会などで働く。
それに対し、地方公務員は、地域社会全体にかかわるさまざまな業務を行う公務員。
上記で記述している<地方公共団体の主な役所>で働くほか、公立学校の教員、警察官なども地方公務員だ。
地方公務員のなかで、都道府県庁職員と、市役所職員にはどんな違いがあるのだろう?
都道府県庁職員の仕事は、市町村の区域を超える事業や、国と市区町村との間の連絡・調整など、携わる業務の規模が大きく、広域にわたっているという特徴がある。
一方、市役所職員は、住民生活に密着した業務に従事。各種窓口業務や、地域の各種イベントなどで住民と接する機会も多く、住民にとって最も身近な存在に感じられる公務員だろう。
市役所職員の収入
市役所職員の給与は、勤務する市や職種などによって異なる。
「地方公務員給与実態調査」によると、政令指定都市の市役所に勤務する一般行政職職員(平均年齢は41.8歳)の平均給与月額は43万1588円(通勤手当や地域手当、住宅手当など諸手当を含む)。
こうした月々の給与のほか、年2回の賞与(期末・勤勉手当)が支給される。
推定平均年収は約682万円。
一方、政令指定都市以外の「市」の一般行政職職員(平均年齢42.0歳)の平均給与月額は39万4875円(諸手当を含む)。
この月々の給与に年2回の賞与(期末・勤勉手当)が加わり、推定平均年収は約629万円。
ちなみに地方公務員全体の一般行政職員(平均年齢42.1歳)の平均給与月額は40万1372円(諸手当を含む)。
この月々の給与に年2回の賞与(期末・勤勉手当)が支給され、推定平均年収は約638万円。
出典:令和4年「地方公務員給与実態調査」(総務省)
実際に市役所で働く人にインタビュー
それでは、実際に市役所で働く人に仕事内容ややりがいなど、お話を聞いてみよう!

難波茉由さん
横浜市政策局シティプロモーション推進室
広報戦略・プロモーション課
横浜市は人口約377万人の政令指定都市。市役所の組織も規模が大きく、政策局、市民局、国際局、温暖化対策統括本部など28の部局と、18の行政区が備わっている。
難波さんは横浜市の事務職員として、2016年に入庁。建築局情報相談課、人事委員会事務局任用課を経て、2023年4月より現職。
市役所で働きたいと思った理由は?
学校の先生も地方公務員。
また、私は部活動で剣道部に所属していて、監督として指導にきてくださっていた方が、県警の警察官だったことから、地方公務員の仕事に興味をもつようになったのです。
なかでも身近に感じていたのが市役所の仕事で、地元・横浜市の職員として働いたいと思うようになりました」
主な仕事内容は?
市民の方に対しては横浜市の知られざる魅力を伝えることや、横浜に住み続けたいと思ってもらえるよう情報を発信します。
横浜市外の方に向けては、横浜市のファンになってもらえるよう、プロモーション活動を行っています」
具体的な仕事内容について、さらに難波さんに聞いてみた。
主には次の3つ。
■横浜市役所の各部署で行う事業について、プロモーション活動をサポート
事業のプロモーションといえば、観光や文化、スポーツ関連のイベント開催など、横浜市内外の方を広く対象にした事業もありますが、市民の方向けのものも多くあります。
例えば、健康福祉局ならば健康診断やワクチン接種、各区役所のこども家庭支援課なら子育て支援サービス、地域振興課なら地域住民向けに歴史や文化を伝えるイベントの開催など多岐に渡りますが、多くの人に参加してもらい、サービスを利用してもらうためには、一つ一つの事業ごとにプロモーション活動が必要です。
主にはチラシなどをつくって情報発信しますが、その制作にあたり、担当課から相談を受けて、効果的なチラシなどに仕上がるようアドバイスをするのが私の仕事です。
その事業のターゲットや目的に沿って、必要な情報をわかりやすく、一人でも多くの市民の方に伝わるよう、工夫しなければなりません。
例えば、区内の小学生向けイベントのチラシをつくる場合、ターゲットとなる小学生やその保護者の方に読んでもらうために、親しみやすい表現になるよう工夫します。文字数が多くて読みにくいものは文字数を減らし、小学生の目を引くよう『写真を大きくしてみては?』といったアドバイスをします。
大切なのは、担当課が伝えたい情報と、市民の方がほしい情報は違うということ。その事業を企画した担当職員の思いに寄り添いながらも、受け手の目線に立ったアドバイスをするよう心がけています」

※これまでに難波さんがかかわって制作されたパンフレット類の一部。写真は横浜市内外の多数の人たちを対象につくられたもの
■横浜市のSNSを担当
私はそのなかの『Find Your Yokohama』というfacebookを担当しています。
観光情報ではなく、読んだ方に横浜愛を深めてもらうことを目的に運営していて、毎週金曜日の投稿にあわせて取り上げる内容を企画し、現地を訪ねて写真を撮り、原稿を書いて投稿するという、一連の業務を担当しています。
横浜の人気スポットの四季折々の風景や、街を彩るサイン、歴史的建造物、情緒あふれる町中華、横浜の秘境といわれている陣ケ下渓谷公園など、市民の方にもあまり知られていないようなディープな情報も紹介しています。
アクセス数を増やすことも重要ですが、私の投稿に対して『この場所、私も好きですよ』とか、コメントをくださる方がいらっしゃいます。
そうした方々とのコミュニケーションツールとして、大切にしていきたいです」
■横浜フィルムコミッションの業務を担当
映画やテレビドラマなどの制作会社から相談を受けて、撮影したい内容に合うロケ地のご紹介や、撮影を希望する施設との連絡調整、撮影許可が必要なスポットの申請手続きを案内しています。
場合によっては、映画やテレビドラマの撮影現場にも立ち会います。
撮影のアングルが斬新で、横浜の街の新たな表情を発見できたような、新鮮な驚きがあります」

※写真は撮影ポイントとして人気を集めている眺めのよい公園のひとつ、臨港パーク(みなとみらい21エリア)。
画像提供:横浜観光情報
1日の仕事の流れ
それでは、難波さんのある1日を紹介しよう。
●8時30分 出勤、朝礼
シティプロモーション推進室全体の朝礼。各担当で進行中の案件など、情報を共有。
●8時45分
メールチェック。
●9時
プロモーション関連業務の研修を受講(約2時間)
さまざまな研修講座が用意されているので、これからも知識を増やしていきたいです」
●11時
フィルムコミッションの業務で連絡調整。
テレビドラマの制作会社やロケ地となる施設の担当者と電話やメールで打ち合わせ。

※メールや電話のほか、対面でも打ち合せを行う
●12時
お昼休み
●13時
各部署からのチラシに関するプロモーション相談を受け、どうアドバイスをすればいいのか、上司とミーティングを行い、担当部署へ連絡
対象の事業について、どういう事業なのかといった基本的なことから、昨年はどんなチラシを作ってどれだけ効果があったのかを確認。
そして、今回のチラシに入れるべき情報や、どんな写真があるといいのか、どんなデザインがいいのかなど、類似している事業のチラシを参考にしながら、アドバイスする内容を決めます」

※広報戦略・プロモーション課のミーティングの様子
●15時
facebookの記事を作成。
投稿内容のテーマを考えたり、写真を撮るために外に出ることも。

※難波さんが担当している、横浜市のfacebook『Find Your Yokohama』
●17時15分
退庁
仕事で心がけていることは?
記者向けの各種報道資料、市内や、神奈川県全域の最新ニュースをチェックするようになりました。
また、業務を通じて職員やテレビ・映画製作会社の方、市内の施設の方など、いろいろな人に会う機会が多いです。
そして相談されることの多い仕事なので、なんでも気軽に相談していただけるよう、メールは丁寧な返信を心がけ、どんなときでも笑顔でいるよう心がけています」

※電話でも笑顔で話すように心がけているという難波さん
市役所の仕事の魅力、仕事のやりがい
いろいろな部署を経験して異なる専門知識が身につくので、スキルアップできているという実感があります。
横浜市の場合、およそ3~4年に1回、異動があり、私も入庁して8年間で3カ所、異動しています」
それでは、難波さんにこれまでの仕事と学んだことなどを語っていただこう。
入庁当時は、右も左もわからない状態でしたが、1年目には先輩がトレーナーとして指導してくれて、そのおかげで事務職の基礎スキルを養うことができたと思います。
4年目で職員採用試験にかかわる部署へ異動。
しかし異動先で1年を迎えたころにコロナで人との接触が制限されてしまい、思うように採用活動ができなくなってしまいました。
そこでオンラインを活用した説明会をしたり、職員採用サイトをよりわかりやすいものにリニューアルしたり、新たに動画を作って発信したりしました。この職員採用広報の仕事を通してものごとを企画し、企画内容を第三者に説明をする、計画を立てて仕事を進めるといったスキルが身についたと感じています。
現在入庁して8年目。2023年4月に、政策局シティプロモーション推進室広報戦略・プロモーション課へ異動し、現在に至ります。
自分が企画したことを形にできるというやりがいを感じながら、日々、業務に取り組んでいます。
私のような20代の若手職員でも企画やデザインの提案などの業務を任せてもらえていることも嬉しいです」

※「地域密着の事業から、規模の大きな事業まで、幅広い業務にかかわることができるところが横浜市職員として働く魅力だと思います」と、難波さん
私と同じ年に横浜市役所に入庁した同期の職員も、半数くらいは他の都市の出身でした。
そんな職員たちが、横浜市の職員を志望した理由はいろいろですが、『横浜に遊びにきて、キラキラした都市でいいなと思った』とか、『おじいちゃんが横浜に住んでいて、よく遊びに行っていたので、子どもの頃から親しんでいた』といった気軽なことがきっかけになって、横浜市職員になりたいと思うようになったという人も多いようです。
市役所の仕事を目指したい高校生のみなさんも、興味をもっている市や地域があるでしょう。
まず、その市役所について、調べてみてはいかがでしょうか。
それぞれの市役所で特徴があり、子育て支援、移住、観光、まちづくりなど、力を入れている事業もさまざまなので、働いてみたい市役所を見つけることができるかもしれません。
市役所の仕事は、決められた作業だけをやっているようなイメージがあるかもしれませんが、意外とクリエイティブな仕事が多いです。
今、市民の価値観やニーズが多様化しているので、そうしたことに対応できる柔軟性や発想力、多様なスキルが、市役所職員に求められています。
そのため、どんなことにも好奇心をもって取り組める人に向いていると思います。
高校生のみなさんも、いろいろなことに興味を広げていきながら、市役所の仕事を目指してみてくださいね」
市役所の仕事に興味のある人は、まずは、自分が住んでいる市の広報紙を眺めてみたり、市役所の事業を調べてみよう!
★横浜市人事委員会事務局公式Twitter @yokohama_ninyo
★横浜市職員採用広報公式Instagram「始動。」 @yokohama_recruit
地方公務員になるには オープンキャンパスをやっている学校を探す
取材・文/小林裕子 撮影/沼尻淳子 構成/黒川安弥(本誌)
※この記事の取材は2023年8月に実施されたものです。