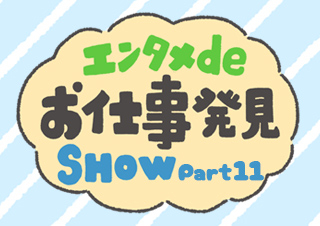新しい化粧品を生み出す「化粧品開発者」って? 仕事内容や必要な研究、向いている人を解説!
化粧品が好き、コスメの動画を必ずチェックしている、という高校生は少なくないだろう。女子高校生だけでなく、男子高校生もスキンケアに気を遣っている時代。
化粧品開発に興味がある、化粧品の研究をしてみたい、将来は化粧品にかかわる仕事に就きたいと考えている人もいるのでは。
そこで、化粧品にかかわる仕事について、どんな仕事があるのか、化粧品について研究して新商品を開発する化粧品開発者(研究者)とはどんな仕事内容なのか、化粧品を開発する仕事に就くには大学でどんな研究をすればいいのかを調べてみた。
さらに実際に、株式会社コーセーで、高校生に大人気のJILL STUART(ジルスチュアート)やVisée(ヴィセ)などの化粧品開発を手がけている研究者に、仕事内容ややりがいについて聞いてみた。
化粧品の開発って、どんな仕事?

化粧品は、“美しくありたい”という願いをかなえる商品。
男女問わず、肌をきれいに整えて、その人の魅力を引き出すことができる。
化粧品開発とは、化粧品のコンセプトの企画を考えたり、それを実際の化粧品として作りあげたりするのが仕事。
化粧品開発の主な仕事は、「商品企画」「商品開発」「研究開発」の3つに分けられる。
株式会社コーセーの場合、本社にマーケティング部門があり、その中に、どんな化粧品を作るのかを決める「商品企画部門」と、どんな品質にするのかを設計する「商品開発部門」がある。
商品企画部で決めた化粧品のコンセプトを基に、商品開発部が目標品質を設定し、「研究所」が商品の処方(化粧品のレシピ)を研究開発するという流れになっている。
処方ごとにサンプルを作り、研究所と商品開発部が共同して色や質感などの品質を目標に近づけていく。
その処方や製造方法を使って、生産部門である工場でみんなの手元に届く化粧品が作られている。

化粧品の"商品企画"の仕事とは?

化粧品会社のマーケティング部門の中にある「商品企画」では、どんな化粧品を作るのか、というコンセプト作りをしている。
消費者の好みや社会の流行・移り変わりを予測しながら、化粧品のコンセプトや商品設計を企画立案する。
多様なニーズに応えるため、さまざまな調査やトレンド予測を参考にしながら、みんな自身も気づいていないような隠れた心理まで洗い出して、企画に反映させていく。
基本的には数年かけて化粧品を作りあげていくので、先を見越したトレンドや消費者のニーズを考えることが大事。
誰をターゲットに、どんなイメージで、どんなふうに使われる商品で、どんな効果・効能があるのか、といった化粧品のコンセプトを作るのが商品企画の仕事になる。
化粧品の"商品開発"の仕事とは?

「商品開発」では、商品企画のコンセプトを具体的な形にして、化粧品の品質設計を行っている。
例えば、商品企画が「花をイメージしたアイカラーを作りたい」と考えたとしたら、「色は何にするのか」「ラメを入れるのか」など、商品企画のイメージやコンセプトを、実際に商品として形にするための品質設計をするのが仕事。
化粧品の効果感・使い心地・香り・色などがコンセプトやブランド観に合っているのか、さまざまな調査や検証を重ねて設計していく。
実際に化粧品を作る際には、研究者と試作品をもとに、もっとこの品質を高められないか、それが実現可能なのか、などの検討を重ねることで理想とする目標品質に近づけていく。
このように、研究者が作った試作品がコンセプトに合った品質に仕上がっているか、デザイナーが考えた商品パッケージが、実際にみんなが使うときに使いやすいものになっているのか、さまざまなチェックをする重要な役割を担っている。

※商品開発者と研究者がミーティングを重ねて、試作品を目標品質に近づけていく
化粧品の商品企画・商品開発の仕事に向いている人は?
化粧品の商品企画・商品開発の仕事に向いている人は、「化粧品が好き」という気持ちが強い人。
特別な資格やスキルは必須ではないが、それよりも「美」を通じて新たな価値創造にチャレンジしたい!コスメが大好き!という気持ちをもっていることが大切。
そのため、文系・理系を問わず、どんな学生でも目指すことができる。
商品企画・商品開発の仕事どちらも、さまざまな部門とミーティングや交渉を重ねながら商品を作りあげていくため、コミュニケーション能力があると役立つ。
化粧品開発者を目指せる学校を探す
化粧品開発者(研究者)の具体的な仕事内容は?

化粧品開発者(研究者)の具体的な仕事内容は、化粧品を作る「製品開発」と、肌・髪・美容成分などの知見を有用性や安全性評価などに活かす「基礎研究」が主だったものになる。
化粧品の製品開発の仕事とは?
例えば、株式会社コーセーの化粧品の製品開発の場合、
①スキンケア/化粧水や乳液など
②ベースメイク/ファンデーションなど
③ポイントメイク/リップやアイカラーなど
④ヘアケア/シャンプーやトリートメントなど
⑤香料/香水や各化粧品の香りなど
といった形で化粧品の分類ごとに担当するグループがあり、それぞれで専門的に製品開発をする研究者がいる。
商品の目標品質に対して、どんな原料を混ぜて、どういった工程で作れば、要望に合った製品になるかを具現化していくのが主な仕事。
まず原料を選定し、さまざまな原料を組み合せてみるビーカーワークで、試作品を作っていく。
その試作品のサンプルを比較して、どれが一番目標品質に近いのか、理想の製品が完成するまで試作をくり返し、”処方”と言われる化粧品のレシピを作る。
化粧品の基礎研究の仕事とは?
例えば、株式会社コーセーの化粧品の基礎研究の場合、「皮膚科学研究」「薬剤開発研究」「品質保証研究」「データサイエンス」がある。
①皮膚科学研究
肌の特徴や機能を研究することで、新しい研究知見を得る仕事。
例えば、肌のシミやシワのできるメカニズムを解明することができれば、それらに対する新しいアプローチ方法を提案することができる。
②薬剤開発研究
皮膚科学研究で得られた知見に基づいて、肌に有用な成分を開発する仕事。
例えば、植物エキスのような美容成分や医薬部外品に含まれる有効成分などの開発を担う。
③品質保証研究
化粧品による肌トラブルや保管時のトラブルを未然に防ぐ仕事。
例えば、塗ったら一日で肌が赤くなって荒れてしまった、保管中にカビが生えてしまった、などといったことがないよう、安心・安全に使える品質の保証やそのための評価の研究などを行う。
④データサイエンス
数値や画像などの膨大なデータを分析することで新たな発見に繋げたり、化粧品として有用なアプローチ方法を見いだしたりする仕事。
例えば、株式会社コーセーでは、7年間にわたるシワの変化を分析することで、5年後、10年後の未来のシワを予測するサービスの作成に繋げている。
新しい知見が得られる研究員だからこそ、新しい化粧品の可能性に気づくこともあり、商品開発の要望に応えるだけでなく、逆に商品を提案することもある。
化粧品開発者(研究者)はどんな人が向いている?

※化粧品開発者(研究者)は、化粧品が好きで、自分から考えて行動できる人が向いている
化粧品開発者(研究者)に向いている人は、「化粧品やその研究が好き」な人。
皮膚のことや化粧品作りの技術に興味があるという人も。
化粧品を使うことで、美しくありたいという願いをかなえたり、肌トラブルを改善したりすることも可能なので、人をよろこばせる仕事をしたいという人にもおすすめ。
化粧品が追求する美しさは人それぞれで、こんな化粧品を作ったら完成、とはいえないため、研究者同士で意見を出しあい、さまざまな提案のなかから、実際に化粧品を開発していくことが大切。
そのため、自分で考えて、自分から行動できる人は、化粧品開発者(研究者)に向いている。
化粧品開発者(研究者)になるには?
化粧品開発者(研究者)になるには、大学か大学院を卒業後、化粧品会社に就職して、研究所に配属されると、化粧品の開発の仕事をすることができる。
大学の学部はこれでないといけない、ということはないが、化学系・生物系・薬学系の勉強をしていると、扱う学術分野が近いこともあり、化粧品の研究開発に馴染みやすい部分はある。
仕事では実際に研究活動を行うため、大学院で研究活動していると、その経験が活きることもあるだろう。
また、化粧品開発の仕事は男女を問わない。
参考までに、株式会社コーセーの研究所の場合、男女比は半々くらい。
化粧品開発者を目指せる学校を探す
化粧品開発者(研究者)にインタビュー

※JILL STUARTやVisée などのポイントメイクを開発している有田大悟さん
株式会社コーセー メイク製品研究室 アイメイクグループに所属。
これまでJILL STUARTのアイカラーやViséeのアイブロウマスカラなどの開発を担当したこともある有田大悟さんにインタビュー。
化粧品開発者(研究者)になろうと思ったきっかけは?
「私の母は、メイクが好きなのに、あまり化粧品を買わず、いつもボロボロのアイシャドウやファンデーションを使っていました。
小学校の高学年のころ、母に『新しい化粧品を買えば?』と言ったら、『あなたと弟が大学院まで行くためには学費を貯めなくてはいけないから、今は私のことはいいの』と答えたのです。
そのとき、『ぼくが化粧品を作って、母にプレゼントしよう!』と決心。
高校は理系コースを選択して、大学では生命科学系の学部に進学。
大学院まで進み、卒業後に株式会社コーセーに就職しています。
入社後、初めて作った化粧品を母にプレゼントしたときは、泣いてよろこんでもらえましたよ」
(有田さん)
化粧品開発者(研究者)の仕事内容は?

※自分の顔につけてみて、化粧ノリや使用感などをチェック
「現在は、アイメイクグループで、アイカラー・アイブロウ・マスカラなど、さまざまな目元の化粧品を担当しています。
主な仕事内容としては、ミーティング本社の商品企画や商品開発、工場の担当者などと、開発のスケジュールやどのような化粧品をどうやって作っていくか、打ち合わせをします。
製品作り例えばアイカラーの場合、粉とオイルを組み合せて作りますが、ビーカーにさまざまな色や形の粉、重めのオイルや軽めのオイルなどを混ぜ合わせて、コンセプトに近い製品になるよう、試作を重ねていきます。
化粧品の成分などの基礎研究新しい成分の開発、化学のメカニズムを突きつめて理論を実証するなどの基礎研究も行っています。
その研究内容を、商品企画や商品開発に提案したり、論文にまとめて国際学会で発表したりすることもあります。
化粧品の開発は、商品化するまでに2~3年くらいが基本ですが、基礎研究から始める場合は合わせて3~5年を要するものもでてきます。
いろいろなブランドを担当することがあるため、さまざまなブランドイメージ、お客さまの年齢層に合わせた化粧品を作る楽しみがありますね。
4色パレットのアイカラーの4色すべてをひとりで黙々と作る場合もあれば、アイメイク担当の複数の研究員と議論しながら1品を開発することも。
お客さまに楽しく使っていただけるよう、使用感や扱いやすさなども工夫して、魅力を引き出せるような化粧品を心がけています。
とはいえ、使える材料費にも限りがありますし、高級な原料ばかり使えばいいというわけではありません。
目標とする品質に合わせて、原料を選りすぐる選球眼や組み合せの工夫も、研究者の腕の見せどころです」
(有田さん)
化粧品開発者(研究者)の仕事のやりがいは?
「自分で作った化粧品が、お客さまによろこんでもらえているのを知ったとき、とてもやりがいを感じます。
口コミサイトやSNSの書き込みをチェックして、高評価を得ているのを見ると嬉しいですね。
お店に行くこともありますが、お客さまが商品を手に取って『かわいい』と言ってくれたり、商品を購入してくれたりする姿を見たりすると、『作ってよかったな』と思います。
逆に『私には合わなかった』『好きじゃない』といったご指摘を見ると、どのような化粧品を作ればみんなに好きになってもらえるかを考えるきっかけになるので、どんな意見もすごく参考になって、ありがたいです。
研究所は、化粧品が大好きで、仕事に対して熱量をもっている人が多く、いろいろな意見を言いあい、切磋琢磨しながら、お互いを高めあっていける環境なので、毎日が充実しています」
(有田さん)
化粧品開発者(研究者)の仕事で大変なことはある?
「化粧品開発者は、研究者でありつつ、研究者でない部分もあります。
さまざまな担当者とミーティングをすることが多く、いろいろな考え方を知って、自分を高めることができる反面、それぞれの担当者の納得を得ながら仕事を進める必要があります。
同じ内容のことを話すとしても、本社の商品企画部門の人には理系の専門用語では通じにくい、逆に工場の現場担当者には専門用語じゃないと正確に伝わらない、などといった伝え方の難しさがあります。
処方どおりに製造してもらっても、自分がビーカーで混ぜたときと、工場で使っている機械で混ぜるときでは力のかかり方が変わって、微妙に色が違ってしまうといった思わぬトラブルもありました」
(有田さん)
化粧品開発者(研究者)を目指す高校生へのメッセージ

※化粧品が大好きな人なら誰でも化粧品にかかわる仕事ができる
「化粧品開発者(研究者)には、いろいろな学部出身の人がいます。
大切なのは、大学や大学院でどんな研究をしていたか、よりも、どう研究していたか。
自分で仮説を立てて、その仮説を証明するための理論を考えていくことで、理論構築力を身につけていくことが大事。
化粧品を開発する仕事には、さまざまな担当があり、マーケティング部門では文系出身の人も活躍しています。
化粧品が好き、人をよろこばせたいという気持ちがあれば、誰でも化粧品を作る仕事にかかわることができると思います。
当社の研究員の男女比は半々なので、性別に関係なく高校生のみなさんにも化粧品開発者(研究者)を目指してほしいですね」
(有田さん)
化粧品は、たくさんの人を幸せにする力があり、その人の人生がメイクで変わるかもしれない可能性を秘めている。
そんな化粧品にかかわる仕事には、さまざまな役割があるので、「化粧品が大好き」という気持ちがあれば、自分は何ができるのか、そのために大学で何を学ぶべきか、考えてみよう!
取材協力/株式会社コーセー、取材・文/やまだみちこ、撮影/沼尻淳子、構成/高木龍一
化粧品開発者を目指せる学校を探す