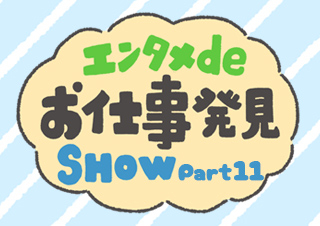簿記とは?資格の種類から難易度、取得するメリットまで徹底解説!
簿記とは、お金やモノの出入りなど、会社の取引のすべてを記録し、決算書にまとめていく一連の作業のこと。規模の大小や業種は関係なく、あらゆる事業活動で行われている。
経営成績や財政状態を知り、今後の経営方針を決めていくために欠かせないものなので、高校生の時に簿記のスキルを身につけ、簿記資格まで取っておくと、将来、役に立つことがたくさんある。
そこで、簿記とはどんなものなのか、簿記資格の種類や難易度、勉強方法、簿記資格を取得するメリットなど、詳しく解説していこう。

簿記の教室メイプル代表。公認会計士・税理士。
大学1年生の時に簿記の勉強を始め、日商簿記3級に合格。
さらに日商簿記2級に合格し、大学3年で日商簿記1級合格。
大学卒業後、24歳で公認会計士試験(旧公認会計士2次試験)に合格。
その後、大手監査法人で企業監査の実務を経験し、1997年に簿記の教室メイプルを開校。
講師として簿記の指導にあたるほか、簿記に関する書籍の執筆も行い、これまでに累計36冊の簿記関連の本が出版されている。
主な著書は、『イチバンやさしい簿記入門』『決算書の読み方』(共に西東社)、『日商簿記3級 テキスト&問題集』(成美堂出版)など。
簿記の教室を運営するかたわら、「メイプル会計事務所」を主宰し、企業の監査業務や経理・税務・財務に関するサポート業務も行っている。
簿記とは?
簿記とは、お金やモノの出入りなどを記録するスキルで、毎日の取引を会計帳簿に記録し、決算書にまとめていく一連の作業。あらゆる事業活動で必要不可欠なもので、簿記の知識を身につけておくと、ビジネスのしくみがわかるようになり、社会人になるための基礎固めにもなる。
簿記には資格もあり、取得すれば一定の知識をもつ証になり、就職やキャリアアップの際にも役に立つ。

日々のお金の出入りと取引を記録するスキル
簿記とは、お金やモノの出入りなど、会社の取引を記録するためのスキルで、日々の取引を会計帳簿に記録し、最終的に決算書にまとめていく一連の作業のこと。家計簿をつける作業にも似ているようではあるけれど、家計簿は何にお金を使ったのかを主に記録するものなのに対し、簿記は事業活動にかかわるすべての取引を記録するという違いがある。
簿記は、商品の仕入れなどで支払ったお金、従業員に支払った給料、商品を売って入ってきたお金など、出金・入金の記録をするだけではない。
例えば、次のような取引も記録する。
●自社の商品がいつ、何個売れたのかといったモノの動き。
●会社がもっている土地・建物、貯金などの財産の増減。
●商品を売った代金が、いつ入金されるのかという約束事。
●資金が不足しているときに借りたお金のこと(借りた金額、返済期限など)。
簿記では、こうしたすべての取引を記録・計算して整理し、事業活動の結果として決算書とよばれる報告書を作成する。
3カ月ごと、半年ごと、1年ごとなど、一定期間に会社がどのくらい儲かっているのか、どれくらいの現金や借金、財産があるのかといった金額が、すべて記載されています。
『何となく儲かっているみたい』というような感覚的なことではなく、結果は数字で示されるので、決算書を見ると、会社の経営がうまくいっているかどうか、事業の状況を正確に知ることができます。
決算書の内容をもとに、経営の改善点を考えたり、今後の事業展開を決める判断基準にもなりますので、会社にはなくてはならない書類です」(南先生・以下同)

簿記の知識はどんな時に役に立つ?
会社の取引のすべてを記録し、決算書を作るという簿記の知識は、経理の仕事に役に立つのはもちろんのこと、規模や業種に関係なく必要とされているものなので、あらゆる事業活動で役に立つ。どんなことにお金がかかっていて、どうやって利益を出しているのか、どんなしくみで事業が成り立っているのかがわかるので、就職して社会人になった時、業務にかかるコスト(費用)や得られる利益など、お金の流れを意識して仕事ができるようになります。
とすると、会社の中で自分が担当する業務の目的が見えてくるので、仕事がおもしろいと感じられるようにもなると思います。
また、簿記を通してビジネスに関する一般常識を身につけることもできるでしょう。
会社によっては、簿記を通して自社の事業を学んでもらうために、新入社員全員を数年間、経理に配属しているところもあります」
────────────────────
簿記の作業のゴールは決算書の作成。
決算書は、社長や部長など社内の人だけではなく、社外のたくさんの人に公開する経営報告書でもある。
例えば、社外の次のような立場の人たちが決算書を見る。
●税務署職員
会社は、事業で得られた利益に応じて税金を納めている。
納税の際に義務付けられているのが、税務署への決算書の提出。
税務署では、提出された決算書を見て、税金の計算に間違いがないかどうかを確認する。
間違いがあった場合には税務署からの求めに応じて会社の決算書を修正し、正しく計算された納税額を納めなければならない。

会社は、事業を運営していくためには資金が必要。
時には銀行に「お金を貸してください」と、お願いしなければならないこともある。そうした場合、銀行がお金を貸すかどうかを決める重要な書類になるのが決算書。
銀行では、「お金を貸しても、返してもらえるだけの利益を出せる会社なのか、財産がある会社なのか」を、決算書を見て判断する。
●取引先企業の社員
決算書は、取引先企業にとっても、相手の経営状態を知ることができる重要な書類。決算書を確認することで、その会社と取引を続けても大丈夫かどうかを判断する。
決算書を見ると、「今年は利益を出せずに赤字になってしまっている」などといった実情がわかる。
簿記の資格
事業活動で欠かすことのできない簿記のスキルを身につけている証になるのが、資格を取得すること。簿記に興味がわいてきた人は、資格取得を目標にしながら勉強するといいだろう。
簿記の資格にはいくつかの種類があり、いずれも必要な知識と技能をはかる検定試験に合格すると、資格を得ることができる。
私が主宰する簿記教室の生徒さんは小学生から社会人まで幅広く、高校生も商業高校だけではなく、普通科の生徒さんも大勢、学んでいます」

簿記資格はどんな種類があるの?
簿記資格の種類は複数ある。主な簿記検定には全商簿記、全経簿記、日商簿記の3種類があり、主催団体や対象などが異なっている。
それぞれの概要と特徴を解説しよう。

全商簿記
全商簿記は簿記実務検定試験が正式名称で、全国商業高等学校協会が主催していることから全商簿記とよばれている。主に商業高校の生徒を対象にした試験で、1級・2級・3級の3ランクがある。
商業高校で使用している教科書にもとづいて基礎を重視し、学習内容を網羅する試験内容となっている。
全経簿記
全経簿記は簿記能力検定試験が正式名称で、全国経理教育協会が主催していることから全経簿記とよばれている。上級・1級・2級・3級・基礎簿記会計の5つのランクに分かれて実施。
上級に合格すると、税理士試験のうち、税法に属する科目についての受験資格が得られることから、主には経理・会計専門学校で学ぶ学生が受験している。
日商簿記
日商簿記は、正式名称は商工会議所簿記検定試験だが、一般的には日商簿記検定試験の名称が使われている。日本商工会議所と各地の商工会議所が主催する検定。
出題内容がビジネスとのかかわりが深く、多くの社会人が受験しており、簿記検定のなかでもよく知られている。 年間の受験者数は約50万人(2023年度)。
1級・2級・3級・簿記初級・原価計算初級の5つのランクがあり、1級に合格すると、税理士試験のうち、税法に属する科目についての受験資格が得られる。
☆参考
全国商業高等学校協会(全商) 全商:検定規則 全国経理教育協会(全経) 2024年度 簿記能力検定試験受験要項(全経) 日本商工会議所(日商)簿記検定
───────────────────
簿記の資格をもっていることは、会社の経理業務に必要な知識とスキルだけではなく、会社の経営状態を理解する力や、コストを意識して仕事ができる力が身についている証になる。
コストを意識するということは、仕事をするうえでそれぞれの業務や工程にどのような経費が発生しているかを考え、無駄な経費をどうやって減らすかを常日頃から意識して働くことができるということ。
そのため、就職活動の際、履歴書に書けば、アピールすることができる。
「特に日商簿記は受験者数も多く、ビジネスの世界でよく知られているので、取得すれば就職活動で役に立つでしょう。
一般的には履歴書に書けるのは日商簿記の場合だと、3級以上とされています」
全商・全経・日商簿記検定の難易度
全商簿記には1級・2級・3級、全経簿記には上級・1級・2級・3級・基礎簿記会計、日商簿記ならば1級・2級・3級・簿記初級・原価計算初級と、各検定で級が設定されている。なかでも難易度が高いのが日商簿記といわれ、ビジネスの実践に即した出題内容となっている。
日商簿記の3級は、全商簿記2級、全経簿記2級とほぼ同等のレベルとされ、日商簿記2級は全商簿記1級、全経簿記1級とほぼ同等レベルとされている。
日商簿記1級と全経簿記上級はほぼ同等レベル。
それぞれの簿記検定について、以下に各級の試験内容やレベル、合格率をまとめたので、参考にしてほしい。
全商簿記の合格率

☆参考
簿記実務検定試験(全国商業高等学校協会) 2023年度 各種検定試験申込者・受験者・合格者数集(全国商業高等学校協会)
全経簿記の合格率


☆参考
簿記能力検定試験(全経)受験データ・合格率
日商簿記の合格率

☆参考
日本商工会議所 簿記検定 日商簿記 受験者データ
────────────────
簿記の手法には建設業簿記、農業簿記など、事業の業種に応じて複数あり、代表的なものが商業簿記と工業簿記。
商業簿記は主に商品の売買やサービスを提供する会社が採用している簿記で、小売業、卸売業、サービス業などで用いられている。
工業簿記は、メーカーなど、製造業を行う会社が用いている簿記。
製品を作るためにかかった原価(材料費や人件費、光熱費など)の記録・計算をし、正しく利益を算出する。
商業簿記と工業簿記は、簿記の基本で簿記検定でも出題されているので、興味のある人は調べてみよう。
初心者は何級を目指せる?
全商簿記、全経簿記、日商簿記は、いずれの検定試験もすべての級で受験資格の制限はない。どの級からでも受験できるが、簿記を初めて学ぶ初心者は日商簿記検定の3級から目指すのがおすすめという。
日商簿記には、入門レベルの原価計算初級、簿記初級がありますが、一般的には3級から始める人がほとんどです。
3級は、簿記の基礎知識を試す出題内容となっていますので、初心者でも目指せます。
普通科の高校生でも簿記の初歩から学んで、日商3級に合格した人は少なくありません。
まず3級を目指して勉強することで簿記の基本が身につき、3級合格後も勉強を続けて2級を受験。
簿記への理解度が深まってくると、問題を解くのがおもしろくなってきて、2級に受かったら1級にも挑戦するというパターンが多いです」
簿記資格を取得するための勉強法
簿記資格を取得するための勉強法はいろいろある。参考書籍、問題集など、さまざまな教材がそろっているので、独学でも合格を目指すことができる。
高校生も自分に合った勉強法で、簿記資格の取得が可能。
どんな勉強法があるのか、合格するために高校生はどのように対策を立てるのがいいのか、主に日商簿記検定について、南先生に教えていただいた。
独学でも合格できる?
受験対策テキストや参考書籍、過去問、予想問題集など教材がたくさんあります。
また、ネット上でも受験対策講座があったり、YouTubeでも日商簿記検定対策としてさまざまな動画がアップされているので、独学でも受験対策が可能です。
日商3級と2級の場合、ネット受験の試験方式もあり、全国各地のテストセンター(※)でほぼ毎日実施されているので、思い立ったらいつでもチャレンジできます。
一度不合格でも、同じ年度の別の日に再度、受験することができます。
極端な言い方になりますが、その年度中に合格したければ受かるまで何回でも受験できます。
つまり、日商3級と2級は、チャレンジのチャンスがたくさんあるので、独学でも目指しやすいと言えるでしょう」
(※)試験日程はテストセンターによって異なる。
☆参考 日商簿記検定 ネット試験テストセンター
受験対策テキストと過去問題集を繰り返し学習することで、出題パターンをつかむことができたので、3級、2級に合格できたと思います。
ただ日商1級となると、例年合格率が約10%という難関です。
簿記のしくみをしっかりわかっていないと合格するのは難しいと思い、独学ではなく、簿記検定の受験対策スクールで学びました。
大学とのダブルスクールです。
スクールで簿記の理論を体系的に学ぶことができて、簿記の理解を深めることができ、『簿記の勉強はおもしろい!』と確信しました。
1級は初チャレンジでは不合格だったのですが、大学3年の秋、2度めの受験で合格できました」

高校生が簿記資格を取得するためにできることは?
全商簿記に加えて日商簿記合格を目指す場合でも、授業の予習・復習をしっかりやることが、基本の対策になるでしょう。
普通高校の生徒さんの場合は簿記の授業はないのですが、簿記検定受験対策テキストや問題集、参考書籍、YouTubeの動画など、自分に合ったツールで、独学で日商簿記3級、2級合格を目指せると思います。
一方、簿記をまったく知らない初心者にとってはどの教材がいいのか、自分に合うツール選びで迷ってしまうこともあります。
その場合、お金がかかるかもしれませんが、受験対策スクールに通ったり、通信講座を利用するという方法も検討してみるといいでしょう。
スクールでは基礎から体系的に知識が身につくので、検定合格への早道とも言えます。
高校生は、普段は定期テストや部活、大学受験の勉強などで忙しいでしょうから、夏休みや春休みなどを利用して集中的に簿記を勉強するといいと思います。
大学受験が終わったあとに、簿記を集中して学ぶ人も多いようです」
簿記に向くのは理系の人?
私のスクールでは大学生も学んでいますが、日商簿記1級合格者の所属学部で一番多いのは、外国語学部の学生です。
簿記には専門用語がたくさんあるので、勉強を始めたころはなかなか理解できなくて悩むこともありますが、語学が得意な学生は、難解な簿記用語をわかりやすい言葉に置き換えることが比較的たやすくできるので、知識がスムーズに頭の中に入ってくるようです。
翻訳に近い感覚があるのでしょう」
簿記はゲーム感覚で楽しく学習できる
計算が合わない時は、どこかが間違えているので、取引の記録の漏れやミスがないかを見直すなどして修正し、最終的に計算が合うと、パズルを完成させたような達成感があると言うのです。
私も簿記はひたすら数字を追うだけの作業ではなくて、ゲーム感覚で学習できるものだと思っているので、楽しく学べますよ」
簿記資格を取るメリット
簿記資格を取ることでさまざまなメリットがある。高校生でもメリットがあり、大学受験の推薦入試や総合選抜型入試などで出願要件の1つにしている大学がある。
大学受験以外にも、将来的にも就職活動や転職、キャリアアップ、自分の店や事業の開業する際など、いろいろと役に立つ。
また、簿記の資格取得を足がかりに、難関国家資格へのステップアップも可能になる。
具体的にどのようなメリットがあるのか、解説していこう。
大学受験に役に立つ
簿記の資格をもっていると、大学受験でもメリットがある。推薦入試や総合選抜型入試などで簿記資格の取得を出願要件の中に組み込んでいたり、選考時に評価の対象にしている大学がある。
下記で紹介する事例は、いずれも2025年度の入試制度の中から簿記資格にかかわる情報のみを抜粋。
簿記資格の取得以外に、ほかにも学業成績などの出願要件が決められており、選考方法も大学により異なっている。 制度の詳細は各大学の入試要項を確認してほしい。
──────────────────
<一橋大学>
☆学校推薦型選抜
・簿記資格取得で受験可能になる学部(学科)
商学部(経営学科・商学科)
・対象になっている簿記資格・級
学校長の推薦を受けて受験する入試方式。
出願要件の中に「大学が指定する資格を取得していること」という条件があり、複数の指定資格の1つに日商簿記検定1級がある。
☆参考 2025年度 一橋大学 学校推薦型選抜募集要項
<東洋大学>
☆学校推薦型選抜(学校推薦入試総合評価型~プレゼンテーション型~)
・簿記資格取得で受験可能になる学部(学科)
第1部(昼)国際観光学部(国際観光学科)
・対象になっている簿記資格・級
学校長の推薦を受けて受験する入試方式。
出願要件の中に、大学が指定する複数の資格の中から1つ以上取得するという項目がある。
その指定資格には、日商簿記検定3級
・2級・1級、全経簿記能力検定2級・1級・上級、全商簿記2級・1級が含まれている。
☆参考 2025年度 東洋大学 総合型選抜・学校推薦型 入学試験要項
<中央大学>
☆高大接続入学試験(資格・実績評価型)
・簿記資格取得で受験可能になる学部(学科)
経済学部(経営学科・経済情報システム学科・国際経済学科・公共・環境経済学科)
・対象になっている簿記資格・級
入学後の学習計画や将来の構想が明確にあり、大学での学びやその後の進路で、高校時代に取得した資格や活動を活用していきたいという意欲のある学生を選抜する制度。
出願要件として、「大学が指定する資格の中のいずれかを取得していること」というた項目がある。
複数の資格が指定されており、それらの中に日商簿記検定2級・1級、全商簿記検定1級が含まれている。
☆参考 2025年度 中央大学 経済学部 高大接続入学試験要項
<京都産業大学>
☆公募推薦入試(総合評価型)
・簿記資格取得で受験可能になる学部(学科)
全学部(全学科)
・対象になっている簿記資格・級
学校長の推薦を受けて受験する入試方式で、試験や調査書に加えて取得資格や部活動なども総合して合否を判定する。
選考時に加点の評価対象として指定されている資格の中に、日商簿記検定2級、全商簿記検定1級がある。
☆参考 2025年度 京都産業大学 入学試験要項
<大分大学>
☆総合型選抜(英語資格・簿記資格に基づく選抜制度)
・簿記資格取得で受験可能になる学部(学科)
経済学部(総合経済学科)
・対象になっている簿記資格・級
英語または簿記の能力が高く、そのうえで経済学・経営学を学び、能力を高めようとする学生を選抜することを目的とする入試方式。
対象の簿記資格は日商簿記検定2級・1級。
☆参考 2025年度 大分大学 総合型選抜学生募集要項
☆参考
日商簿記検定 入試で優遇される大学(2024年7月現在:日本商工会議所) 資格取得で優遇される学校(2024年12月現在:全経ブログ)
ちなみに簿記資格を取得することで、大学入学後もメリットがある場合がある。
商学部、経済学部などに進学した場合、簿記資格取得で身につけたスキルがあるので、簿記や会計の授業内容がスムーズに理解でき、楽しく学ぶことができるだろう。
また、大学在学中に簿記検定に合格すると、申請により単位として認めてもらえたり、難関の日商簿記1級合格で合格報奨金を支給してくれる大学もある。
就職に役に立つ
就職先選びでは、その会社の業績がアップしているかどうかを確認することが大切です。
一般的には売り上げが増え続けていて儲かっている会社のほうが、従業員の給料が高かったり、福利厚生が充実している傾向にあると思います。
簿記検定合格を目指して勉強したことで、企業の決算書を読みこなす力がついているので、自分が興味をもつ会社が利益を上げていて本当に儲かっている企業なのかどうかを見極めることができます。
上場企業の決算書は、企業のホームページで公開されているので、いつでも見ることができます」
多くの企業では、簿記はビジネスを行ううえで必要なスキルととらえており、社員に簿記資格の取得を義務付けている企業も少なくありません。
社員教育の研修プログラムの1つに日商簿記検定取得講座を組み込んでいる企業も多いです。
私が開いている簿記スクールでも、毎年4月ごろは、生徒さんのなかに企業の新入社員が増える時期で、『仕事に欠かせないから」『会社の上司から簿記検定を受けるようにと言われたから』といった理由で、学びにきています」

簿記の資格はさまざまな仕事で生きる
簿記の資格は、会計・経理の仕事はもちろんのこと、さまざまな仕事で生かされる。どのような仕事で生かされるのか、見ていこう。
●会計・経理職
簿記の資格が生かせる仕事の代表的な職種。
事業の日々の取引を記録したり、財務書類など経営管理のための資料作成、決算書の作成など、簿記検定の受験勉強を通して身につけたスキルを生かすことができる。
☆会計・経理の仕事を詳しく知る
●コンサルタント
企業の経営や事業展開などの相談に対応し、コンサルティングを行う専門家。
顧客である企業の財務・会計状況をつかむことが必須なので、簿記の知識が必要とされる。
☆コンサルタントの仕事を詳しく知る
●営業職
営業職は、簿記とは関係ない仕事のように思うかもしれないが、「営業職の人も、簿記を勉強して資格を取っておくと、役に立つことがたくさんあると思います」と、南先生。
例えば、『当社のこの製品を購入していただければ、コストはこのぐらい減らすことができて、売り上げをこのぐらい増やすことが可能になります』といった提案です」
●金融機関
銀行などの金融機関で働く際にも簿記の資格が役立つ。
そのため、簿記の知識は欠かせません」
●海外でのビジネス
意外かもしれないが、海外での事業展開の際にも簿記が生かされるという。
14世紀ごろにイタリアの商人が用いた会計手法がルーツといわれ、その後、世界に普及していきました。
簿記の理論と方式は、世界共通になっています。
そうしたことから、海外でビジネスを展開する場合でも、簿記の知識を身につけておく必要があり、海外での事業を順調に運営するための必須スキルとなっています。
実際、世界を舞台に事業展開をしている企業の中には、海外の支店に赴任するための条件の1つに日商簿記検定3級以上としているところもあります。
グローバルに活躍するためには語学のスキルも必要ですが、それと並んで簿記の知識を身につけることも必要とされています」
弁護士、検察官など法律家の仕事でも、簿記の知識があると役立つ場面があるという。
例えば、企業の顧問弁護士として活動する場合、顧問先企業が何らかの損害をこうむって損害賠償を請求するというケース。
損害賠償として請求する金額は、その損害のために得ることができなかった利益、減少してしまった財産の額などをもとに算出されるため、決算書や財務資料を読み込むなど、簿記のスキルが求められる。
☆弁護士の仕事を詳しく知る
☆検察官の仕事を詳しく知る
キャリアアップや転職に役立つ
簿記はビジネスを理解するうえで欠かせないものなので、社員に簿記資格の取得を奨励していたり、必須としている会社もあり、そうしたことからも簿記資格はキャリアアップや転職に役立つと言える。日商簿記2級以上の取得を必須としている会社もあります」
資格手当の支給額は会社により異なり、日商簿記2級で月に5000円前後~、1級の場合は月に1万円前後~となっている(※)。
(※)資格手当の金額は編集部の調査による。目安として参考にしていただきたい。

自分の店や事業を開業する時に役立つ
自分の店を開いたり、自分の会社を開業する時も、簿記の資格取得で身につけたスキルが役に立つ。自分自身が経営者になるわけですから、取引を記録して決算書を作成したり、決算書を読みこなせるようにならなければいけません。
また、店や事業の規模を大きくする、あるいは事業の継続のために、銀行から資金を借りて調達しなければならないケースも出てくると思いますが、そうした場合には、銀行の担当者に自分の店や事業の決算書を提出し、その決算書を踏まえて店などの売り上げや経営状況を説明することが求められます」

難関資格へのステップアップに役に立つ
簿記資格の中でも、合格率は例年10%前後と難しく、取得者への評価が高いのが日商簿記1級。日商簿記1級を取得すると、税理士、公認会計士、中小企業診断士といった税務・会計・経営関連の国家資格取得の足がかりになる。
●税理士
日商簿記1級取得で、税理士試験の税法に属する科目の受験資格が得られる。
※税理士試験は2023年度から受験資格が緩和されており、会計に属する科目については受験資格の制限がなくなっている。
●公認会計士
公認会計士試験には財務会計論、会計学といった科目が課せられ、日商簿記1級の勉強で身につけた知識が生かされる。
そのため、日商簿記1級は、公認会計士の登竜門とも言われている。
●中小企業診断士
中小企業診断士試験には「財務・会計」の科目があり、日商簿記1級の学習内容と重複する部分があるので、挑戦しやすくなる。
高校生の皆さんへ
大学に入学したころ、公認会計士の仕事に興味をもち、足がかりとして簿記を勉強したのです。
日商簿記3級から受験し、大学3年の時に1級に受かった時は『すごいね!』と、友人知人、親戚の人たちにもほめられてうれしかったし、何より、自信がつきました。
それまでは、周りから優秀な学生と認識されていなくて、今いち自信をもてずにいた私ですが、日商簿記1級に合格して『やればできるんだ!』と思いました。
『公認会計士も合格できるかも!』と気持ちが上がり、勉強を続けて大学卒業後の24歳の時に公認会計士試験に合格。
ますます自信がわいてきて、プライベートでもマラソンを始めたり、トライアスロンや登山にチャレンジするなど、趣味が増えて、毎日が楽しくなりました。
簿記に生きる力を与えてもらった…そう思っています。
そんな私の経験から言えるのは、簿記の資格は将来の可能性を広げてくれる1つの選択肢になり得るということです。
高校生の皆さん、進路について考える時、簿記の学習にも目を向けてみてください。
皆さんの未来のために、頑張ってくださいね!」
簿記の資格に興味がわいてきた人は、さっそく、調べてみてほしい!

構成・取材・文/小林裕子 取材協力・監修/南伸一
※2024年12月現在の取材に基づく情報になります。
☆監修者著書紹介

『イチバンやさしい簿記入門』(西東社)
☆簿記の教室メイプル
☆簿記の教室メイプル YouTubeチャンネル
☆関連記事をチェック
【法学・政治学部、経済学・経営学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
【経済学・経営学分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
企業の成長を支援する「コンサル」とは?東大・京大生になぜ人気?仕事内容とやりがいに迫る!
勉強に集中する方法とは?今すぐできる14のコツ、専門家に聞きました!
勉強のモチベーションを爆上げする方法16。5秒で勉強モード!受験勉強やる気キープのコツは?