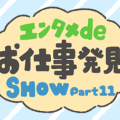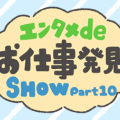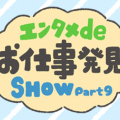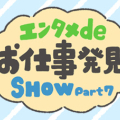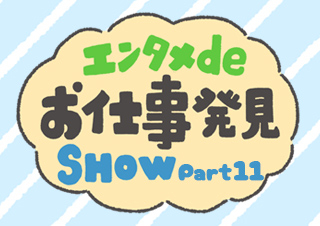クリエイターとは?デザイナー、イラストレーター、動画クリエイターetc.23職種を徹底解説
クリエイターとは、企業や個人のニーズにこたえて、創造的な作品や企画を生み出すプロフェッショナルのことだ。映像、音楽、文章、イラスト、デザインなど、ジャンルを問わず自らのアイデアやスキルをもとに新たな価値を生み出す人を指す。
この記事では、実際に業界で働くプロフェッショナルからのアドバイスも交えながら、さまざまなジャンルのクリエイターを紹介し、スキル、年収などを詳しく解説する。
将来クリエイターを目指している高校生はもちろん、「どんな職種があるのかな?」と興味をもっている人も、ぜひ参考にしてみて。
あなたの「好き」や「得意」を仕事にする第一歩になるかも!
目次
クリエイターの就職・転職支援を全国で展開する株式会社フェローズのエージェント、田原さん、志賀さん、名波谷さん
フェローズは「世界に誇れる日本のクリエイティブ産業の発展に貢献する」をミッションに掲げ、クリエイター人材と企業をつなぐだけでなく、スキルアップセミナーの開催や業界の最新情報の提供、充実した福利厚生など、クリエイターが安心して働ける環境づくりに力を入れている。
日々クリエイターと向き合い、彼らの悩みや成長を間近で見守ってきた経験から、次世代のクリエイターを目指す高校生の君たちへ、貴重なアドバイスを提供してくれた。
クリエイターとは?

君たちが日々見ているテレビ番組、楽しんでいるゲーム、目にする広告やポスターなどには、クリエイターの手が加わっている。
単なる「ものづくり」ではなく、人々の心を動かし、新しい価値を提供するのがクリエイターの使命といえるだろう。
クリエイターとアーティストの違いは?
「クリエイター」と「アーティスト」の違いは目的と立ち位置にある。クリエイターは、クライアント(依頼主)の要望にこたえるために作品を制作するのに対し、アーティストは自分自身の表現のために作品を生み出す。
クリエイターは、予算や納期、ターゲット層などさまざまな制約の中で最大限の創造性を発揮するが、アーティストは自分の感性や思想を優先させる。
簡単に言えば、クリエイターは「依頼者の課題を解決するものを創る専門家」、アーティストは「自分の表現を追求する表現者」というわけだ。
しかし、境界線はあいまいで、クリエイターがアーティスト的な活動をすることも、アーティストがクリエイターとして働くこともある。
クリエイターの仕事

例えば君たちが遊ぶゲームを考えてみよう。
ゲームが完成するまでには、さまざまな工程があり、多くのクリエイターがかかわっているんだ。
企画~運営まで、それぞれの主な役割
ここではクリエイターの仕事を上流・中流・下流の3つの工程と、全体管理にかかわるものに分けて紹介していく。まずは「何を作るか」を決める段階だ。
プロデューサーやディレクター、マーケターなどが中心となって、コンセプトや予算を決め、スケジュールを立てる。
この段階では発想力や企画力、市場を読む目、プレゼン力、長期的な視点が重要になる。
【中流工程】制作・開発
次に実際に形にしていく段階だ。
デザイナーやエンジニア、ライターなどが中心となって、デザイン、コード、シナリオなどを制作する。
この段階では技術力や表現力、チームワーク、コミュニケーション力が求められる。
【下流工程】チェック・リリース・運営
完成した作品をチェックし、修正して、世に出す段階だ。
品質管理スタッフやマーケター、運営スタッフなどが中心となる。
リリース後もアップデートや管理が必要で、ユーザーの反応を見ながら改善していく。
この段階でも、細部へのこだわりや長期的な視点は欠かせない。
【全体管理】
そして、これら全体を統括するのがプロデューサーやディレクターの役割だ。
企画から運営まで一貫してかかわり、チーム全体の方向性を決めていく。
それぞれの分野によって細かい違いはあるけれど、基本的な流れは同じだ。
それでは、クリエイターが活躍する各分野の職種を見ていこう。
映像制作・技術にかかわる職種

ディレクターとして全体を統括する仕事、監督として自分の名の下に作品を完成させる仕事、動画クリエイターとして映像コンテンツを制作する仕事のほか、カメラマンとして映像を撮影する仕事、大道具・小道具として撮影現場の空間を作る仕事、音響効果として音で映像を彩る仕事など、映像の世界を作り上げる職種に注目してみよう!
ディレクター・アシスタントディレクター
映像制作の現場で指揮を執るのがディレクターだ。テレビ番組やCM、PVなどの映像制作の総指揮官として、企画から撮影、編集、演出まで、作品全体の方向性を決める重要な役割を担っている。
一方、アシスタントディレクター(AD)はディレクターの右腕として、撮影スケジュールの管理や出演者との調整、小道具の手配など、現場の進行をサポートする。
いわば「縁の下の力持ち」だ。
同じシーンを撮るにしても、カメラアングルや照明、音楽などでまったく違う印象に見せることができる。
それが「演出」であり、そんな「見せ方」のセンスが問われる仕事だ。
ディレクターになるためには、まずはADとしての経験を積むのが一般的。
現場でたくさんの経験を積み、自分なりの演出手法を身につけていくことが大切だ。
特別な資格は必要ないけれど、視聴者の心を掴む感性と、チームを統率するリーダーシップは欠かせない。
ディレクター・アシスタントディレクターを目指すには
監督・助監督
映画やドラマなどの監督は、作品全体の世界観や表現方法を決定する最高責任者だ。ディレクターと似た役割だけれど、監督は「作家性」や「芸術性」が強く求められる。
自分の視点で物語を表現し、観客に何を伝えたいかを明確にもっている必要がある。
助監督は、監督の右腕として撮影スケジュールの管理や演出の補助を行う。
監督の「よーい、スタート!」の声に合わせてカチンコを鳴らすあのポジションといえば、わかりやすいかもしれない。
映画の世界では第1助監督(チーフ助監督)、第2助監督(セカンド助監督)といった階層があり、経験を積みながらステップアップしていく。
監督になる道は一筋縄ではいかないけれど、映画学校で学んだり、アシスタントや助監督として経験を積んだりするのが一般的。
何より「伝えたいこと」をもっていることが重要だね。
監督・助監督を目指すには
動画クリエイター
動画クリエイターは、YouTubeやSNSでの動画コンテンツの普及に伴って注目されるようになった職種だ。企業のプロモーション動画や広告、WebコンテンツなどのあらゆるジャンルのPR動画を制作する。
最近では、一人で企画から撮影、編集まで行う「ビデオグラファー(映像作家)」的な立ち位置の動画クリエイターが増えてきている。
もちろん、チームで分担して制作することもあるけれど、マルチに活躍できるスキルが求められる職種といえるだろう。
動画クリエイターには、Adobe Premiere Pro(アドビプレミアプロ)やAdobe After Effects(アドビアフターエフェクト)といった動画編集ソフトを使う技術はもちろん、企画力やストーリーテリング能力も重要だ。
視聴者の心を掴む「伝え方」のセンスも必要になるね。
カメラマン(男女)
カメラマンは映像作品の「目」ともいえる存在だ。単にカメラを回すだけでなく、どのアングルから撮影するか、どんなレンズを使うか、どう光を取り入れるかなどの判断で、作品の印象がガラッと変わる。
特に映画やドラマでは「撮影監督」として作品全体の映像表現を担当することもある。
監督のビジョンを理解し、それを視覚的に表現する技術とセンスが求められるんだ。
映像のカメラマンのほかに、スチールカメラマンという職種もある。
こちらは映画やドラマの宣伝用の写真を撮影する専門職だ。
ポスターやチラシに使われる写真を撮るんだね。
カメラマンになるには、映像制作会社に就職したり、フリーランスとして活動したりする道がある。
特別な資格は必要ないけれど、専門学校や大学で学んだり、実践を通じた経験を積み重ねたりすることが重要だ。
カメラマンを目指すには
大道具・小道具
大道具は、テレビ番組や映画、舞台などのセットを制作する仕事だ。視聴者が目にするカラフルなスタジオセットや映画のロケセットは、すべて大道具スタッフの手によって作られている。
セットデザイナーやアートディレクターが考えた設計図をもとに、実際に木材や金属、布などを使って形にしていく。
そして、撮影や公演が終われば、それらを解体する作業も担当する。
小道具は、名前のとおり小さな道具を担当する職種だ。
俳優が使う小物や、部屋に置かれる装飾品などを準備する。
一見地味な仕事に思えるかもしれないけれど、物語の世界観や雰囲気づくりに欠かせない存在なんだ。
大道具や小道具になるには、美術系の学校で学んだり、現場でアシスタントとして経験を積んだりする道がある。
手先の器用さや空間把握能力が求められるよ。
音響効果
音響効果(音効)は、映像に効果音や環境音、BGMなどを付け加え、作品の雰囲気を豊かにする仕事だ。君たちが見ているテレビ番組やアニメ、映画には、セリフ以外にもたくさんの音が使われている。
それらの音を選び、適切なタイミングで入れていくのが音響効果の仕事だ。
例えば、感動的なシーンには心に響くBGMを、緊張感のあるシーンにはドキドキする効果音を。
音一つで作品の印象がガラリと変わるから、センスが問われる仕事といえるだろう。
音響効果になるには、専門学校や大学で音響について学び、テレビ局や制作会社に就職するのが一般的。
音楽の知識はもちろん、映像と音の関係性を理解する感性も大切だね。
音響効果を目指すには
Web制作にかかわる職種

Webデザイナーとしてサイトの見た目を整える仕事、エンジニアとして機能を実装する仕事、SNS運用としてSNSを活用する仕事など、デジタル時代の新しいクリエイティブ職に迫ってみよう。
Webデザイナー
Webデザイナーは、Webサイトのデザインや構成を考える職種だ。単にカッコいいデザインを作るだけでなく、ユーザーが使いやすく、新商品の発信や事業紹介などの、クライアントの要望を実現するサイト設計が求められる。
具体的な仕事内容としては、クライアントのヒアリングからワイヤーフレーム(設計図)の作成、デザインカンプ(完成見本)の制作、設計書をもとにホームページやプログラムを作るコーディングまで幅広く担当することもある。
規模の大きな会社だと役割分担がはっきりしていて、デザインのみを担当することも多いよ。
Webデザイナーに必要なスキルは、Adobe Photoshop(アドビフォトショップ)やAdobe Illustrator(アドビイラストレーター)などのデザインソフトの操作技術や、HTML/CSSといったプログラミング言語を使ったコーディング知識だけではない。
製品やサービスの見た目や操作性であるUI(ユーザーインターフェース)、それらを使用することで得られる体験のUX(ユーザーエクスペリエンス)の考え方も知っておきたい。
スポンシブデザイン(スマホ対応)のスキルも必須だ。
クライアントの前でプレゼンテーションをすることもあるので、コミュニケーション力も必要だよ。
Webデザイナーになるには、専門学校や独学でスキルを身につけ、制作会社や自社サイトをもつ企業に就職するのが一般的。
フリーランスとして独立する道もあるよ。
Webデザイナーを目指すには
エンジニア
Webサイトやアプリケーションの裏側で、技術的な部分を担当するのがエンジニアだ。コードや技術を使って「何かを生み出す人」という意味では、エンジニアもクリエイターであるといえる。
最近では、設計・企画・改善に関わりながら、自らアイデアや仕組みを生み出すエンジニアも増えている。
見えないところで動いているからこそ、サービスの根幹を支える重要な存在といえるだろう。
代表的なのがフロントエンドエンジニア。
彼らはWebサイトやアプリのユーザーが直接触れる部分(フロントエンド)の開発を担当する。
HTML、CSS、JavaScriptなどのプログラミング言語を駆使して、Webデザイナーが作ったデザインを忠実に再現しつつ、動きや機能を実装していくんだ。
一方、バックエンドエンジニアは、サーバー側のプログラミングやデータベース管理を担当する。
ユーザーからは見えない部分だけれど、Webサイトの動作や情報処理の要となる部分を担っている。
エンジニアになるには、プログラミングスキルを習得することが必須。
専門学校や独学で学び、実務経験を積んでいくのが一般的な道筋だ。
論理的思考力や問題解決能力が求められる職種といえるだろう。
SNS・YouTube企画・制作・運用
SNS・YouTube企画・制作・運用は、企業や団体のSNSアカウントを管理し、投稿やフォロワーとの交流を行う仕事だ。Instagram、X(旧Twitter)、Facebook、YouTube、TikTokなど、さまざまなプラットフォームで活動する。
単に投稿をするだけではなく、アカウントのコンセプトや目標設定、ターゲットの分析、投稿内容の企画、効果測定など、マーケティングの視点も重要になってくる。
投稿後の反応を分析し、より効果的な発信方法を模索する改善サイクルを回していく。
SNS・YouTube企画・制作・運用に求められるスキルは、SNSの特性理解はもちろん、ライティング力、画像・動画編集スキル、コミュニケーション能力、データ分析力などだ。
また、世の中のトレンドへのアンテナを常に張り巡らせておく必要もある。
SNS・YouTube企画・制作・運用の担当者になるには、マーケティング部門や広報部門でキャリアをスタートさせるのが一般的。
最近ではSNS・YouTube企画・制作・運用に特化した代行会社も増えてきている。
インフルエンサーマーケティングなど、新しい分野にも挑戦できるおもしろい職種だ!
グラフィック・DTPにかかわる職種

グラフィックデザイナーとして平面デザインを手掛ける仕事、イラストレーターとして絵で表現する仕事、フォトグラファーとして写真を撮影する仕事、コピーライターとして言葉で伝える仕事と、視覚と言葉で人々の心を動かすプロフェッショナルたちだ。
グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナーは、ポスターや書籍、商品パッケージなど、平面のデザインを手掛ける職種だ。印刷物からデジタルコンテンツまで、さまざまな媒体でのデザインを担当する。
仕事の流れは、クライアントからの依頼内容をヒアリングし、コンセプトを決め、実際にデザインを制作し、修正を重ねて完成させる。
単に「かっこいい」「かわいい」だけでなく、伝えたいメッセージが的確に伝わるかどうかが重要なポイントになる。
グラフィックデザイナーに必要なスキルは、Adobe Photoshop(アドビフォトショップ)、Adobe Illustrator(アドビイラストレーター)などのデザインソフトの操作技術、色彩感覚、レイアウト力などだ。
最近ではデジタルでの発信も増えているため、Web知識も求められることが多い。
分業していることも多いが、少数精鋭の企業では、ライティングもまかされることふぁあるよ。
グラフィックデザイナーになるには、美術系の学校でデザインを学ぶか、独学でスキルを身につけてポートフォリオ(作品集)を作ってアピールし、デザイン事務所や広告代理店などに就職するのが一般的な道筋だ。
もちろん、フリーランスとして独立する道もあるよ!
グラフィックデザイナーを目指すには
イラストレーター
イラストレーターは、イラストを描くことを専門とする職種だ。書籍や雑誌の挿絵、広告のビジュアル、キャラクターデザインなど、さまざまな場面でイラストが使われている。
クライアントの依頼に応じて、コンセプトに合ったイラストを制作するのが主な仕事。
アーティストとの違いは、自己表現というよりは「依頼内容に沿った作品を制作する」点にある。
クライアントの意図を汲み取る力が必要なんだ。
イラストレーターに必要なスキルは、まず何より描画技術。
手描きでもデジタルでも、表現したいものを紙やスクリーン上に再現できる技術が必須だ。
加えて、クライアントとのコミュニケーション能力や、締め切りを守る責任感、また知的財産権によって保護された独自の「IPコンテンツ」に関連する著作権の知識などももっておきたい。
イラストレーターになるには、美術系の学校でイラストについて学ぶか、独学で技術を磨いてポートフォリオ(作品集)を作り、出版社やデザイン事務所などに売り込むのが一般的。
最近ではSNSで作品を発表したり、コンテストや公式ファンアート企画へ参加したりして、仕事につなげるケースも増えているね。
イラストレーターを目指すには
フォトグラファー
フォトグラファー(写真家)は、カメラを使って被写体を撮影する職種だ。広告、雑誌、書籍、Webサイトなど、さまざまな媒体で写真が使われている。
商業写真の場合、クライアントの要望に沿った写真を撮影するのが主な仕事。
人物、風景、料理、商品など、専門分野をもつフォトグラファーも多い。
単に「きれいな写真」ではなく、伝えたいメッセージや魅力が伝わる写真を撮ることが求められるんだ。
フォトグラファーに必要なスキルは、まず何よりカメラの操作技術。
光や構図、タイミングなど、瞬間を切り取るための技術と感性が不可欠だ。
また、撮影後の画像編集技術も重要になってきている。
フォトグラファーになるには、写真の専門学校で学ぶか、プロのフォトグラファーのアシスタントとして経験を積むのが一般的だが、最
終的に独立して、フリーランスとして活動する人が多い。
ほかの職種と同じく、最近ではSNSで作品を発表し、仕事につなげるケースも増えている。
コピーライター
コピーライターは、広告や宣伝のための文章(コピー)を書く職種だ。テレビCMのナレーション原稿、ポスターのキャッチコピー、Webサイトの文章など、商品やサービスの魅力を伝える言葉を考える。
単なる説明文ではなく、人の心を動かす、記憶に残る言葉を生み出すのがコピーライターの役割。
「一度見たら忘れられない」キャッチコピーは、商品の認知度や印象を大きく左右する。
コピーライターに必要なスキルは、言語感覚はもちろん、世の中のトレンドや心理学の知識、マーケティング的な視点も重要だ。
限られた文字数・時間の中で、最大のインパクトを与える言葉を生み出す創造力が試されるんだ。
コピーライターになるには、広告代理店や制作会社に就職するのが一般的。
最初はアシスタントとして経験を積み、徐々に自分の担当案件をもつようになる。
文学部や広告学科出身者が多いけれど、学歴は問われないことも多い。
コピーライターは「人の記憶に残る言葉」を生み出す仕事。
君も知っているコピーが、なぜ君の心に残ったのか、考えてみるとおもしろいかも。
コピーライターを目指すには
ゲームにかかわる職種

3DCGデザイナーとして立体的な世界を作る仕事、シナリオライターとして物語を紡ぐ仕事、背景美術デザイナーとして舞台を描く仕事など、ゲームという大きな作品を作り上げるチームの一員たちだ!
3DCGデザイナー
3DCGデザイナーは、ゲーム内の3Dグラフィックを制作する専門家だ。キャラクターや背景、アイテムなどを立体的にデザインし、ゲームの世界観を視覚的に表現する。
3DCGデザインの工程は大きく分けて、モデリング(形を作る)→リギング(動かせるように骨組みを入れる)→テクスチャリング(色や質感をつける)→アニメーション(動きをつける)→ライティング(光と影をつける)→レンダリング(映像として出力する)となる。
規模の大きな会社では、これらの工程ごとに専門のデザイナーがいることも多い。
3DCGデザイナーに必要なスキルは、Maya(マヤ)、Blender(ブレンダー)、3ds Max(スリーディーエスマックス)など3DCGを扱うソフトの操作技術はもちろん、立体感覚や空間把握能力、アートセンスなども重要だ。
3DCGデザイナーになるには、専門学校や大学でCGについて学び、ゲーム会社やCG制作会社に就職するのが一般的。
ポートフォリオ(作品集)が重視されるから、学生のうちからしっかり作品を作っておくといい。
メタバース、AR(拡張現実)/VR(仮想現実)などの新しい分野でも需要が高まっているから、将来性も期待できる職種だ!
テクニカルアーティスト
テクニカルアーティストは、アーティストとエンジニアの橋渡し役として、ゲーム開発現場の潤滑油となる存在だ。アートの知識とプログラミングのスキルを併せもち、開発チームのクリエイティビティーを最大化するための環境づくりや高品質な表現をかなえる。
デザイナーが作った素材データが、スムーズにゲーム内に実装できるよう作業フローを設計したり、作業効率化のためのツール開発を行ったりする。
例えば「このクオリティーのグラフィックを、動作遅延させずに表示できる技術は何か」を考え、検証を行って最適解をみつけ出すなどだ。
テクニカルアーティストに必要なのは、アーティストが使うDCCツール(Adobe Photoshopや3DCGソフトなど)の知識と、エンジニアがもつプログラミング知識の両方だ。
アーティストの立場、現場の要望、どちらも理解・分析し、改善する提案力も重要になる。
そして何より新しい技術への好奇心と探究心も外せない。
以前はアーティストやエンジニアからの転身が多かったが、最近は専門の養成学校も増え、新卒からテクニカルアーティストとしてキャリアをスタートさせる人も増えている。
技術の進化とともに、需要が高まっている職種といえるだろう。
シナリオライター
ゲームのシナリオライターは、ゲームの物語やキャラクターのセリフ、世界観などを書く仕事だ。特にRPGやアドベンチャーゲームなど、ストーリー性の強いゲームでは重要な役割を担っている。
ただ物語を書くだけでなく、選択肢による分岐や、マルチエンディングなど、ゲームならではの特性を考慮したシナリオを構築する必要がある。
また、ゲームの世界観に合った用語やキャラクターの口調なども設定するんだ。
シナリオライターに必要なスキルは、ストーリーテリング能力、キャラクター造形力、世界観構築力などが挙げられる。
また、ゲームという媒体の特性を理解し、プレイヤーが楽しめる要素を盛り込む力も重要だ。
シナリオライターになるには、ゲーム制作会社に就職するか、シナリオコンテストに応募して実績を作るのが一般的。
小説やシナリオの執筆経験があると有利だろう。
ゲームだけでなく、小説やアニメなど関連メディアでも活躍できる可能性がある。
背景美術デザイナー
ゲームの背景美術デザイナーは、ゲームの舞台となる背景や環境を作り上げる仕事。プレイヤーがゲームの世界に没入できるよう、コンセプトに合った魅力的な背景を描く。
地味な存在に思えるかもしれないけれど、ゲームの世界観を支える大切な仕事だ。
2Dゲームではイラストとして背景を描くことが多いけれど、3Dゲームでは3DCGで立体的な空間を構築する。
モデリングだけでなく、テクスチャ(質感)やライティング(光の当て方)、エフェクト(特殊効果)などで雰囲気を作り込んでいく。
背景美術デザイナーに必要なスキルは、デッサン力や画力、空間把握能力、グラフィックソフトや3DCGソフトの操作技術などだ。
また、建築や自然科学の知識があると、よりリアルな背景が描ける。
背景美術デザイナーになるには、美術系の専門学校や大学で学び、ゲーム会社や映像制作会社に就職するのが一般的。
ポートフォリオ(作品集)が重視されるから、学生のうちからたくさん作品を作っておくといいね。
アニメにかかわる職種

制作進行として全体の進行を管理する仕事、アニメーターとしてキャラクターに命を吹き込む仕事、アニメ監督として作品全体をまとめる仕事と、一つのアニメ作品を完成させるために欠かせない職種をチェック!
制作進行
アニメの制作進行は、アニメ制作のスケジュール管理や、各部署間の連携を図る役割を担う。監督やプロデューサーの指示の下、制作全体がスムーズに進むよう調整するのが主な仕事だ。
具体的には、スケジュール作成や進捗管理、スタッフへの指示伝達、素材の受け渡しなどを行う。
アニメーターや背景美術デザイナーなど、各部署の作業状況を常に把握し、遅れが生じたときは解決策を考える。
いわば「アニメ制作の現場監督」ともいえるポジションだ。
制作進行に必要なスキルは、スケジュール管理能力やコミュニケーション能力、問題解決能力などが挙げられる。
アニメの制作工程についての知識も必要だ。
画力などのクリエイティブなスキルは必須ではないから、「アニメ業界で働きたいけれど絵は苦手…」という人にもおすすめの職種といえるだろう。
制作進行になるには、アニメ制作会社に就職するのが一般的。
新人はまず制作進行として現場を経験することが多い。
実際の仕事を通じてアニメ制作全体の流れを学ぶことができるよ。
アニメーター(動画・原画マン)(男女)
アニメーションを作るうえで欠かせないのが、アニメーターである動画マンと原画マンだ。これらはアニメーターのなかでも専門分野が分かれている職種といえる。
原画マンは、キーとなる絵(原画)を描く役割を担う。
絵コンテをもとに、キャラクターの動きの要となるポーズや表情を描いていく。
例えば「走る」動作なら、足を上げた状態、着地した状態など、動きの節目となる絵を描くんだ。
原画マンの腕前でアニメのクオリティーが大きく左右されるため、高い画力が求められる。
一方、動画マンは原画と原画の間を埋める「中割り」と呼ばれる絵を描く役割を担う。
原画があっても、そのままでは動きがぎこちなくなってしまう。
そこで間の動きを補完する絵を描くことで、滑らかな動きを表現するんだ。
アニメーターとしてのキャリアは、まずは動画マンからスタートすることが多い。
アニメーターに必要なスキルは、なんといっても画力だ。
キャラクターをさまざまな角度・表情で描く技術、動きを表現する技術などが求められる。
最近ではデジタル作画も増えてきているから、PCでの作画スキルも重要になっているよ。
アニメーターになるには、専門学校や大学で学び、アニメ制作会社に就職するのが一般的。学生のうちから絵をたくさん描いておこう。
アニメーターを目指すには
アニメ監督
アニメ監督は、アニメ作品全体の方向性を決める責任者だ。作品のテーマや世界観、演出方法など、クリエイティブ面での最終決定権をもっている。
具体的な仕事内容は、シナリオの構成チェック、絵コンテの制作・確認、声優のキャスティングや演技指導、音楽や効果音の選定など多岐にわたる。
アニメーション制作の全工程にかかわり、チーム全体をリードしていく役割を担う。
アニメ監督に必要なスキルは、映像表現力、ストーリーテリング能力、キャラクター造形力などのクリエイティブスキルはもちろん、チームをまとめるリーダーシップやコミュニケーション能力も重要だ。
幅広い知識と経験が求められる職種と言えるだろう。
アニメ監督になるには、まずはアニメーターや演出家、脚本家など関連職種でキャリアを積み、実力と実績を認められる必要がある。
一朝一夕でなれる職種ではないけれど、「自分の世界観を形にする」というやりがいは格別。
ヒット作を生み出せば評価も高まり、新しい仕事のオファーにつながっていく。
空間・プロダクトデザインにかかわる仕事

CADオペレーターとして図面を作成する仕事、プロダクトデザイナーとして製品をデザインする仕事、空間デザイナーとして快適な空間を設計する仕事と、形のあるものづくりの世界で活躍するクリエイターたちだ。
CADオペレーター
CADオペレーターは、CAD(Computer Aided Design)というソフトを使って設計図や製図を作成する職種だ。設計者のアイデアや意図をくみ取り、最適なレイアウトを提案する、施工しやすさや美しさを考えて図面の見せ方を工夫するなど、クリエイティブなスキルが求められることが増えている。
いわば、技術職とクリエイティブの融合タイプ的な働き方をしているのが、CADオペレーターだ。
建築物や工業製品、家具など、さまざまな分野で活躍している。
手描きの図面とは違い、CADを使えば正確な設計図を短時間で作成できる。
また、修正や複製も容易なため、現代の設計・製造現場では必須のツールだ。
CADオペレーターの仕事内容は、設計者や建築士からの指示をもとに、CADソフトを使って図面を作成すること。
2Dの平面図だけでなく、3Dの立体モデルを作ることもある。
完成した図面は製造現場に送られ、実際の製品づくりに活用される。
CADオペレーターに必要なスキルは、CADソフトの操作技術、図面の読み描きの知識、空間把握能力など。
また、製造や建築に関する基礎知識があると、より高品質な図面が作れるだろう。
CADオペレーターになるには、専門学校や大学でCADについて学び、建築会社やメーカー、設計事務所などに就職するのが一般的。
未経験からでも比較的チャレンジしやすく、デスクワークが中心なので、安定した環境で働きたい人におすすめの職種だ。
CADオペレーターを目指すには
プロダクトデザイナー
プロダクトデザイナーは、家具や家電、文具、玩具など、私たちの身の回りにある「もの」のデザインを手掛ける職種だ。見た目の美しさだけでなく、使いやすさや機能性、安全性なども考慮してデザインする。
仕事の流れとしては、企画・コンセプト立案→スケッチやラフデザイン→3Dモデリングやプロトタイプづくり→テスト・評価→量産化への調整といった工程がある。
ユーザーの立場に立って、使いやすく魅力的な製品を考えるのがプロダクトデザイナーの腕の見せどころだ。
プロダクトデザイナーに必要なのは、デザイン力はもちろん、製品の機能や構造を理解する技術的知識、素材や製造方法についての知識なども重要だ。
最近では3DCADや3Dプリンタの技術も求められることが多い。
プロダクトデザイナーになるには、美術系や工学系の大学・専門学校でプロダクトデザインを学び、メーカーやデザイン事務所に就職するのが一般的。
自分がデザインした製品が実際に店頭に並び、人々に使われる喜びを味わえる、やりがいのある仕事だ。
空間デザイナー
空間デザイナーは、オフィスや店舗、ホテル、住宅などの空間をデザインする職種だ。内装や照明、家具などを適切に配置し、その空間の目的に合った快適で機能的な環境を作り出す。
仕事の流れとしては、クライアントとの打ち合せ→コンセプト立案→レイアウト設計→素材や色彩の選定→施工管理→完成といった工程がある。
単に「おしゃれな空間」を作るだけでなく、その場所をどう使うか、どんな体験を提供するかを考えてデザインする。
空間デザイナーに必要なのは、空間把握能力、色彩感覚、素材や照明についての知識、CADやパースの技術などだ。
また、建築や設備に関する基礎知識、予算管理能力なども重要になってくる。
空間デザイナーになるには、建築やインテリアデザインを学べる大学・専門学校に進み、内装会社やデザイン事務所に就職するのが一般的。
実務経験が重視される職種なので、学生時代からインターンなどで経験を積むのが近道。人々の生活や仕事の場を創造する、社会的意義の大きい仕事といえるね!
空間デザイナーを目指すには
ここで紹介した職種以外にも、まだまだたくさんのクリエイティブな仕事がある。
もっと詳しく知りたい君は、フェローズのお仕事図鑑 をチェックしてみて!
クリエイターの年収は?

ここでは各ジャンルの代表的な職種の年収例を紹介しよう!
• ディレクター: 400万〜700万円(キャリア次第で1000万円超も)
• カメラマン: 460万〜470万円
• 音響効果: 350万〜450万円
Web制作分野
• Webデザイナー: 480万円
• フロントエンドエンジニア: 400万〜600万円
• SNS・YouTube企画・制作・運用: 350万〜500万円
グラフィック・DTP分野
• グラフィックデザイナー: 478万円
• イラストレーター: 466万円
• コピーライター: 570万円
ゲーム分野
• 3DCGデザイナー: 509万円
• テクニカルアーティスト:400万~600万円
• シナリオライター: 300万〜500万円
アニメ分野
• 制作進行: 285万円
• 動画マン: 125万円
• 原画マン: 334万円
• アニメ監督: 787万円
空間・プロダクトデザイン分野
• CADオペレーター: 300万〜400万円
• プロダクトデザイナー: 600万〜700万円
• 空間デザイナー: 400万〜450万円
フリーランスで活躍する道もあるし、独立して事務所や会社を興す道もある。
ただし、初任給は他業界に比べて低めなことが多いから、覚悟も必要だ。
「好きなことを仕事にできる」「自分の作品が世に出る喜び」など、お金以外のやりがいが大きな魅力だともいえる。
クリエイターに向いている人は?

ここでは、クリエイティブ業界で働く人に共通して大切なことを紹介しよう。
上流工程(企画・構想)で大切なこと
上流工程では、何よりもまず発想力が求められる。新しいアイデアを次々と生み出せる力は、クリエイターの基本スキルだ。
また、頭の中にあるイメージを言葉にして他者に伝えられる言語化能力も重要。
さらに、好奇心旺盛に新しいものに興味をもち、「おもしろい!」と感じる感性も大切にしたい。
そして、さまざまな分野の知識を吸収し、それらを組み合わせて新しい価値を生み出せる視野の広さも、企画段階では欠かせない要素となる。
中流工程(制作・開発)で大切なこと
実際に形にしていく中流工程では、まず自分の専門分野での確かな技術力が必要だ。基礎をしっかり身につけ、応用できる力があってこそ、クオリティーの高い作品が生まれる。
また、納得いくまで試行錯誤できる粘り強さも重要。
思いどおりにいかないことも多いけれど、あきらめずに取り組み続ける姿勢が成功へとつながる。
さらに、常に新しい技術やトレンドを学び続ける向上心も必要。
クリエイティブの世界は日々進化しているから、学びを止めた瞬間に時代に取り残されてしまう。
そして、一人では作れない大きな作品も多いから、チームの中で自分の役割を果たせるコラボレーション力も欠かせないスキルだ。
下流工程(チェック・リリース・運営)で大切なこと
作品を世に送り出す段階の下流工程では、まず最後まで品質にこだわる責任感が大切だ。
「これでいい」と妥協せず、最高のクオリティーを追求する姿勢が良い作品を生む。
また、小さなミスも見逃さない細部への注意力も必要。
些細なエラーや不具合が、作品全体の評価を下げてしまうこともある。
さらに、チェックや修正といった地道な作業をていねいにこなせる粘り強さも重要。
そして何より、その作品を使う人の立場に立って考えられるユーザー目線があってこそ、人々に愛される作品が完成するんだ。
すべての工程に共通して大切なこと
どの工程にも共通して、さまざまなことに興味をもち、学び続けられる好奇心が大切だ。また、自分の考えを伝え、他者の意見も受け入れられるコミュニケーション能力も必須。
さらに、時間内に成果物を納品できる締切意識や時間管理能力も重要。
そして何より、お金をもらって仕事をするというプロ意識をもち、責任をもって最後までやり遂げる覚悟が必要だね。
クリエイターの仕事は、一見「自由に好きなことをやれる」と思われがちだけれど、実際には、予算、納期、クライアントの要望などさまざまな制約の中で最大限のクリエイティビティーを発揮する仕事だ。
その制約をむしろチャンスととらえ、創造性を発揮できる人が、クリエイターに向いている。
つまり、技術力だけでなく、コミュニケーション能力や粘り強さなど、さまざまなスキルが必要なんだ。
どのスキルも大切だけれど、自分の強みを生かせる分野をみつけるのが、成功へのカギかもしれないね!
クリエイターを目指す高校生へアドバイス

進学先の選び方や、今のうちからやっておくべきことなど、参考にしてほしい。
進学先の選択肢
クリエイターを目指すうえで、どの学校に進むかは大きな選択肢だ。それぞれの特徴を理解して、自分に合った道を選ぼう。
メリットは、実践的な技術や知識を集中的に学べること。
業界とのつながりも強く、就職に直結しやすい。
卒業制作などを通じてポートフォリオ(作品集)の内容も充実させられるよ。
デメリットは、幅広い教養が身につきにくいこと。
技術は身につくけれど、その技術を生かすための発想力や視野の広さは自分で培う必要があるかも。
美大・芸大
メリットは、基礎からしっかり学べること。
デッサンや色彩などの基礎技術から、美術史や芸術論などの教養まで広く深く学べる。
仲間との切磋琢磨も魅力だ。
デメリットは、実践的なスキルよりも表現力や芸術性を重視する傾向があること。
就職に直結するスキルは自分で補う必要があるかもしれない。
総合大学
メリットは、幅広い知識と教養が身につくこと。
デザインや映像だけでなく、心理学や社会学などの知識も吸収できれば、クリエイティブの幅が広がるよ。
デメリットは、専門的な技術の習得には自分の努力が必要なこと。
サークルなどでの自主的な活動が重要になってくる。
今からやっておくべきこと
進学先を考えるのと同時に、高校生のうちからできることもたくさんある。今から始めることで、将来のクリエイターとしての可能性がぐんと広がるはず!
美術館や映画館に行ったり、さまざまな本を読んだり、旅行に出かけたり。
インプットの量がアウトプットの質に直結する。
好きなものだけでなく、興味のない分野にも積極的に触れてみよう!
手を動かし続ける
絵を描く、写真を撮る、文章を書く、プログラミングを学ぶ…とにかく自分の興味ある分野で実践あるのみ。
コンペティションに挑戦したり、SNSで発信したりすると、自分の今の実力を把握しやすい。
たくさん失敗を重ねても、継続的に実践することで、スキルアップやポートフォリオ(作品集)の充実につながり、確実に成長できるよ。
仲間をみつける
同じ志をもつ仲間と切磋琢磨することで、一人では気づけない視点や成長が得られる。
SNSでの交流も良いけれど、できれば実際に会える仲間がいると心強いね。
好きなことを深掘りする
今の時代、「少しずついろいろなことができる人」より「一つのことを極めた人」のほうが評価されることも多い。
自分が本当に好きなこと、得意なことをみつけて、とことん追求してみよう。
プロからのメッセージ

田原さんは全国の支社統括として幅広い地域、幅広い領域を担当し、志賀さん、名波谷さんは、それぞれ東日本・西日本地域でクリエイティブ業界の就職を目指す学生の支援を専門とし支援を専門とし多くのクリエイターの就活を支援してきた。
業界の第一線で活躍するクリエイターたちと日々向き合い、彼らの成長を見守ってきた3人から、クリエイターを目指す高校生の君たちへ、アドバイスとエールをもらったよ。
正直な話、技術はあとからでも身につけられるんです。
まずはさまざまな経験をして、自分だけの視点を養うことが大切です。
旅行や読書、美術館巡り、さまざまな人との出会い…これらすべてが、あなたにしか生み出せない表現につながります。
高校生のうちは、技術ばかりに囚われず、好奇心の赴くままにいろいろなことに挑戦してみてください。
志賀さん
クリエイティブな仕事は、常に変化し続けるのが特徴です。
特に今の時代は技術革新のスピードが速く、10年前とは仕事の形も大きく変わっています。
今学んでいることが将来そのまま役立つとは限りません。
でも学ぶ姿勢そのものが、どんな変化にも対応できる力になるんです。
常に新しいことへの興味をもち続けてください。
名波谷さん
自分の作品に誇りをもち、自信をもって発信できる人が最終的に成功します。
最初からうまくいくことはほとんどないですが、批判を恐れずに作品を公開し続けることが成長につながるんです。
思い切って作品を公開してみてください。
予想もしなかった場所からチャンスが生まれることも多いんですよ。
田原さん
クリエイターの道は一本道ではありません。
回り道も寄り道も、すべて自分のオリジナリティーにつながる財産になります。
例えば、進路だって、国内の学校に行くと限られてはいないはず。
海外の学校への進学やワーキングホリデーに出かけるなど、すべてがクリエイター人生の糧になります。
若いうちのさまざまな経験が、ほかの誰にもできない表現を生み出す原動力になるんです。
他人と比べるのではなく、自分だけの表現方法をみつけ、それを磨き続けることこそが、クリエイターとして成功する秘訣だ。
世界はこれからも、新しい表現やアイデアをもつクリエイターを必要としている。
「あなたたちのなかから、次世代を代表するクリエイターが生まれることを、心から楽しみにしています」と笑顔で話してくれた。
まとめ

クリエイティブな仕事は実に多様で、それぞれに魅力があることがわかったのでは。
クリエイターの仕事に共通しているのは、「0から1を生み出す」という創造性と、「人の心を動かす」という目的。
技術やツールは時代とともに変わっていくけれど、人の心を理解し、感動させる力は普遍的な価値をもち続ける。
高校生のみんなは、可能性に満ちあふれている。
今は「どの職種が自分に合っているか」を決めるよりも、さまざまなことに挑戦して、自分の興味や適性を探る時期かもしれない。
気になる分野があれば、とにかく手を動かして実践してみよう。
うまくいかなくても、その経験はきっと将来に生きてくる。
クリエイティブな仕事は、決して楽な道ではない。
納期に追われたり、クライアントとの調整や、技術の変化についていくのに苦労したり…。
でも、自分の作品が世に出て、誰かの心を動かすことができたときの喜びは何物にも代えがたい。
その喜びを知ってしまうと、もうクリエイターの道から抜け出せなくなる魅力がある。
どの道を選んでも、自分らしさを大切に生きていこう。
君たちの未来に幸あれ。
応援しているよ!
取材・文/二階堂ねこ 取材協力・監修/株式会社フェローズ 構成/寺崎彩乃(本誌)
★関連記事をチェック
Webライターとは?仕事内容・年収・向いている人・なり方を完全解説!
Webデザイナーとは?現代社会に必須の仕事の詳細、必要なスキル、向いている人などを解説!