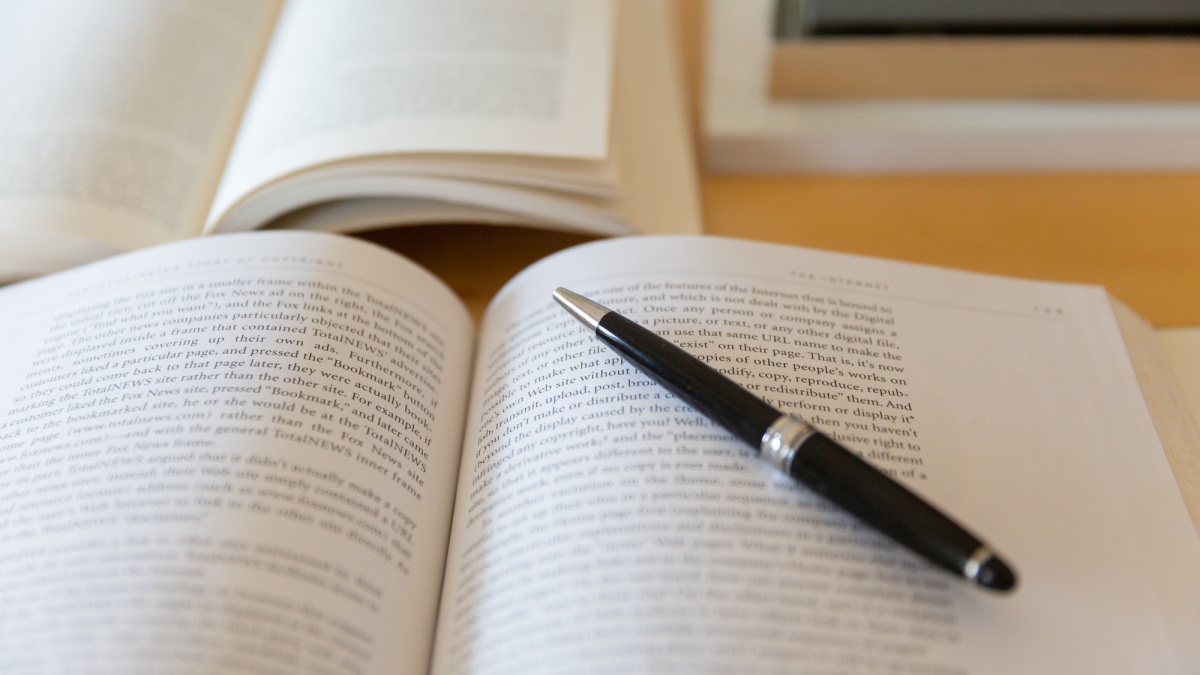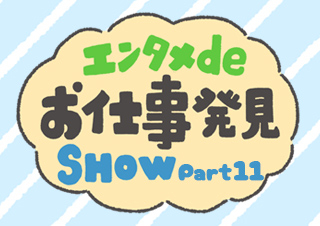MBAの受験準備の期間は?合格にむけた試験対策や提出書類のポイントも解説
ビジネススクールの入学を視野に入れている人向けに、受験までの段取りや主な提出書類、入試の攻略法について解説します。目次

監修者プロフィール
乾 喜一郎 リクルート進学総研主任研究員(社会人領域)
資格や社会人大学院など専門誌の編集長を長く務め、これまで取り上げてきた。
3000人以上の事例をもとに学習者の立場から提言。
文部科学省等の各種事業で有識者委員を歴任。
ビジネススクール受験までのダンドリ
入試対策はどのくらい前から取り組むべきか?
大学院入試では、志望校の入試科目によって必要な準備期間は大きく異なります。そのため、志望校に関する情報収集はできるだけ早めにしておくのがベター。
入試の時期は大学院によってまちまち。
秋と年明け1~2月ごろにピークがありますが、複数回入試を実施する大学院では3月に入試を行うところもあります。
前年のうちには情報収集をし、志望校のメドをつけ、入試日程を把握しておきましょう。
そのうえで、受験する入試方式(社会人入試か一般入試か)を決め、入試科目を調べます。
英語や専門科目試験が課される場合は、遅くとも入試の半年程度前には入試対策を始めておきたいところ。
ただし、これはあくまで学部レベルの基礎があることが前提なので、自信がない場合は、さらに早めの準備が必要になります。
特に実務経験を重視する社会人向け大学院では、入試が書類選考と面接のみという場合が一般的。
この場合はそれほど長期間の準備期間を必要とするわけではありませんが、遅くても入試の3カ月前には研究計画書、志望理由書対策に取り組むようにしましょう。
なお、入学前に科目等履修制度を活用して学び始めることができる大学院もあります。
特に進学に迷っている場合には、入試前に"お試し"として受講しておくのもよいでしょう。
周囲から入試に関するアドバイスも受けられます。
入試日の1カ月程度前から出願受付が始まるので、それまでには書類をそろえておき、期間中の早めの段階で出願しましょう。
いよいよ受験となったとき、英語や専門科目試験がある場合は直前対策も入念にしましょう。
秋入試で不合格だった場合でも、その後の入試を行っている大学院があります。
同じ大学院に再度チャレンジするか、第二志望に切り替えるかの判断をして、弱点の補強や研究計画書の見直しに取り組むなどして目標とする入試に備えましょう。
ビジネススクール出願の際の主な提出書類
志望理由書、エッセイ
それまでの職業経験(社会人の場合)、ビジネススクールに進学する理由、そのビジネススクールを志望する理由などをまとめた書類のこと。通常の大学院の場合は必須となることが多い「研究計画書」(後述)の提出が必要ない場合に課されます。
書式や文字数は大学院によって異なり、自由に記述するタイプもあれば、質問に答える形式もあります。
志望理由書自体が書類選考の材料となるほか、面接も志望理由書の内容に沿って行われることが多いため、重要な書類です。
研究計画書
大学院で研究したいテーマ、研究の目的、進め方、スケジュールなどをまとめた書類のこと。ビジネススクールの場合、研究計画書を課す大学院もあれば、研究計画書ではなく、志望理由書やエッセイの提出を求める大学院もあります。
大学卒業(見込)証明書、成績証明書
いずれも出身大学で発行してもらいます。書類の作成・発行に数日を要する場合もあるので早めに手配しておくことが大切です。各種語学検定のスコア
英語での授業を行う大学院のなかには、英語の試験の代わりに、語学検定のスコアの提出を求めるところもあります。複数回受験して、スコアアップを図っておきましょう。
志願票、大学の成績証明書、履歴書、職務経歴書、推薦書など
志願票以外は、大学院によって提出の必要があるものもないものもあるので、事前にチェックしておきましょう。職場の上司などに書いてもらう推薦書は提出を求める大学院もあれば、不要の大学院もあります。
ビジネススクールの試験攻略法
「志望理由書」「エッセイ」の攻略法
志望動機、仕事経験から感じたこと、研究したい課題などを記載するという点では、志望理由書もエッセイも基本的に大きな違いはありません。記述のしかたに関しては、志望理由書は自由に記述できる場合が多く、エッセイは、「大学院での学習を今後のキャリアにどのように活用したいか」「職場でリーダーシップを発揮した経験について述べてください」「あなたの価値観や倫理観に最も影響を与えたことは何か」などの設問(課題)に答える形式になっていることが多いです。
ともに、学習・研究への意欲、大学院での研究に必要な経験と能力の有無、文章構成力などが問われているので、その点を意識してまとめることが必要となります。
ポイントは抽象的、理念的になりすぎないこと。
特に研究したい課題や今後のキャリアなどは、読む側がイメージしやすいよう、できるだけ具体的に記述することが求められます。
そのほか、ダラダラとまとまりのない文章を書くこともNG。
志望理由書やエッセイは書いて終わりではありません。
面接試験が課される場合には、志望理由書の内容に基づいて質問をされるので、自分が書いた内容について、しっかりと頭に入れておくことも忘れないようにしましょう。
「研究計画書」の攻略法
研究計画書は、提出が求められる場合には、合否に大きく影響する書類です。合格に近づく研究計画書を作成するポイントは、先行研究を踏まえたうえで、実際に研究したいテーマやコンセプトを明確にすること。
業務に関連して進学を目指すのであれば、実務経験と関連のある研究テーマを設定するといいでしょう。
まずは、興味のあるテーマに関して先行研究の文献をリサーチするところから対策を始める必要があります。
ただし、学術系の論文などを書き慣れていない人の場合、適切な文献探しから苦労することも多いので、早い段階から予備校などで指導を受けたほうがベター。構成のポイントなども指導してもらえます。
合格した研究計画書の例などを参考にして書いたものを、繰り返し添削指導を受けてブラッシュアップしていきましょう。
「小論文」の攻略法
まず取り上げられるテーマについて知見がないと対応できないので、『日本の論点』など時事問題をコンパクトにまとめた書籍を読み、何が課題なのかということに加え、賛否両方の意見を理解し、自分なりの考えをまとめてみましょう。また、実際に書くトレーニングも重要です。
前述の書籍からテーマをピックアップし、賛成・反対の意見をそれぞれ60分、1500字でまとめるのがオススメ。
その後、改めて書籍の該当項目を読んでみると、より理解も深まります。
なお、小論文は、「結論→理由→(反対意見)→まとめ」という構成が一般的。
あまり細かい点にとらわれずに論旨の明快さを意識して書くことがポイントです。
また、書いた文章は人に読んでもらうことも重要。予備校の講師などにチェックしてもらうことも大切ですが、その分野に詳しくない知人・友人・家族などに読んでもらい、わかりにくい点などを指摘してもらうのも有効です。
「面接試験」の攻略法
研究計画書や志望理由書に基づいて質問されるので、提出書類の内容はしっかり頭に入れておくことが大切です。もちろん、書類に書いていないことも聞かれるので、自分の職業経験やリーダーシップを発揮した経験、今後のキャリアの展望などに関しては、しっかりと考えをまとめておくようにしましょう。
与えられたテーマに関して受験生数人でディスカッションをするなどの集団面接を行う大学院もあり、この場合は、臨機応変に効果的な発言をする必要があるので、普段から仕事の中でもディスカッションを重ね、創造的な発言ができるようトレーニングしておくことが大切です。
経済・経営・商学の学部学科がある大学・短期大学を探す