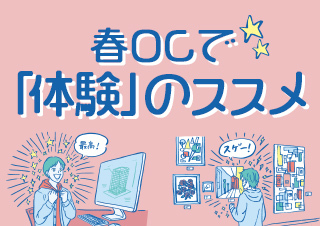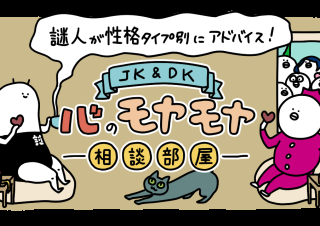法科大学院(ロースクール)の学費はいくら?働きながら通える?奨学金についても解説
法曹になるための主要ステップである法科大学院の学費や奨学金について解説します。
監修者プロフィール
乾 喜一郎 リクルート進学総研主任研究員(社会人領域)
元『法科大学院入試ガイド』編集長。資格や社会人大学院など専門誌の編集長を長く務め、これまで取り上げてきた。
3000人以上の事例をもとに学習者の立場から提言。
文部科学省等の各種事業で有識者委員を歴任。
法科大学院選びのポイント
裁判官・検察官・弁護士(=法曹三者)を養成するための専門職大学院
どの法科大学院に進学するかを検討する際に、一般的に目安とされやすいのが法科大学院別の司法試験合格率です。ただし、法科大学院には一学年20人程度の小規模校から、200人を超える大規模校まであり、小規模校の場合は、数人の合否で合格率は大きく変動するので、単年度の数字にあまりこだわっても意味はありません。
合格率で比較検討する場合は、過去数年間の推移や平均を見るようにしましょう。また、その場合も、数ポイント程度の差にとらわれないほうがいいでしょう。
また、司法試験は法科大学院修了後、または在学中から5回まで受験できます。
法科大学院修了生全体の単年度の合格率は20-40%と年度によって幅がありますが、最近のデータでは既修者コースの場合、大学院修了後2年めまでの累積合格率は7割を超えています。
個人にとってより重要なのは「累積合格率」と言えるでしょう。
なお、合格率上位校にはもともと優秀な学生が集まっているから合格率が高いという側面もあります。
その意味でも、合格率がダイレクトに教育の質や内容を反映しているとは言い切れません。
法科大学院選びは、「自分が合格できるかどうか」を第一に考える必要があるのです。
また、法務省から法科大学院等別合格者数(https://www.moj.go.jp/content/001427119.pdf)も発表されており、参考にするとよいでしょう。
自分の目標がかなうカリキュラムか確認する
志望校選びで忘れてはならないのは、合格後自分自身がどのような法曹を目指したいかをイメージし、それに合致したカリキュラムをもつ大学院を探すことです。大学によって「市民法務に強い」「金融法務に強い」「渉外法務に強い」といった特徴があります。
該当する分野を専門とする教員や各校が開設している「展開・先端科目」の内容などはしっかりチェックしておきたいところです。
大学院の規模によるメリットを考慮する
また、大規模校か小規模校かという点も重要なポイント。大規模校は同級生の人数が多く、法曹になってからも生かせる幅広い人的ネットワークを構築できるといったメリットがありますが、小規模校には教員とのコミュニケーションが密になり、よりきめの細かいていねいな指導が受けられるといったメリットが。
それぞれに良さがあるので、どちらが自分に合っているかを十分検討しましょう。
司法試験対策では自習が重要
司法試験対策では自習が非常に重要になります。そのため、学生同士が自主的に組んでいる自主ゼミの活発さや、自主的な学習をサポートするチューター(補助教員)の充実度もチェックポイントの一つ。
その法科大学院出身の先輩弁護士がチューターとなっていることも多く、学習に行き詰まったときには非常に頼りになります。
説明会などの機会ではぜひ確認しておきましょう。
法科大学院の学費と奨学金
国公立、私立の法科大学院の学費
国立大学の多くは、入学金が28万2000円、年間の授業料が80万4000円で、初年度納入金は108万6000円です(2025年現在)。国立大学の中でも、福岡大学では2024年度入学者の授業料が60万円で同大学の大学卒業者は入学金等をあわせて77万8000円(他大学の場合、84万8100円)となっています。
公立大学は、大学がある自治体の住民は入学金が安くなり、例えば東京都立大学では東京都の住民の場合、入学金が141,000円(それ以外282,000円)です(2025年現在)。
授業料は年額663,000円と抑えていることもあって、初年度納入金が最も安いカテゴリーとなっています。
私立大学の入学金、授業料は幅があります。入学金は10万~30万円ですが、その大学の卒業生に関しては入学金を免除または半額にする制度を導入している大学も。
授業料は、90万~130万円程度の大学が多いようです。
その他の費用も合わせると、私立大学の初年度納入金は、130万~160万円程度が目安といえるでしょう。
奨学金&授業料減免制度が充実
各法科大学院が独自に実施する奨学金制度や授業料減免制度は年々充実傾向にあります。以前から経済的に苦しい成績優秀者若干名を対象に授業料を減免する制度はありましたが、現在では、収入面での制限を設けず、かつ入学者の大半が該当する規模で、授業料の全額・半額免除制度を導入する法科大学院や、奨学生枠の入試で選抜された学生を対象に授業料全額免除に加えて毎月の奨学金を給付する法科大学院も。
これに準ずるような制度も含め、奨学金・授業料減免制度拡充の取り組みは広がりを見せています。
法科大学院に関するQ&A
予備試験のほうが効率的なルートに思えますが、法科大学院に進学するメリットはありますか?
そもそも予備試験は例年合格率3-4%と非常に狭き門なので合格は至難の業。また実際の受験者には、法科大学院に在籍している学生も含まれています。法曹になることを目標としているなら、予備試験のみを目標に据えるのはリスキーです。そして何より、法科大学院には、司法試験受験に向けて同じ目標をもった仲間が集まっています。
試験範囲の幅広い司法試験ですべての科目に一人で精通するのは大変なので、勉強会を開き担当科目を分け、お互いに教え合うことができる点が大きなメリットです。
教員や勉強仲間などの人脈は、就職活動や就職後にも生きてきます。
加えて、インターンシップ、エクスターンシップなどを通して、法曹になったあとで役立つコンサルテーション能力などを磨くことができるのも魅力。
企業とのやりとりや、依頼人の信頼を得るコミュニケーションなども実地で身につけられます。
なお、予備試験対策と法科大学院既修者コースへの入学対策は、並行して行うことができます。
今は法律知識ゼロですが、既修者コースに合格することは可能ですか?
法学部出身者でなくても既修者コース合格ラインの知識を習得することは決して不可能ではありません。予備校などで効率的に勉強することが条件ですが、勉強に専念できる環境であれば半年程度、働きながら学ぶ社会人であれば1年程度学ぶことで知識の習得が可能です。
既修者コースの法律科目試験は難度が全体的に下がっている傾向にあり、対策の期間が短いからといってあきらめる必要はありません。
もちろん、上記は最短期間の目安なので、余裕があるなら1年半~2年半程度じっくりと準備をするのが理想的ではあります。
一時期司法修習終了後の就職難が話題になりましたが、やはり厳しいのですか?
法科大学院スタート以前と比較すると司法試験の合格者数は増えているので、たしかに、大手法律事務所への就職時の競争は激しくなっています。一方で、経済環境の変化に伴い、企業内弁護士の募集は増加。人材不足の傾向が高まっているのも事実。
エクスターンシップなど在学中の活動を通じて自分がどのような分野で活躍したいのかを考え、それにかなう進路を幅広く探していくことが大切です。
法科大学院修了後、司法試験に合格できなかった場合の進路は?
残念ながら司法試験に合格できなかったとしても、法科大学院で習得した法律知識や法律的な思考力を一般企業などで生かすチャンスはあります。例えば、弁護士の資格を有しているかどうかを問わず、「法律に詳しい人材が欲しい」というスタンスの企業も、大手・中小といった規模にかかわらず少なくありません。
このような企業と司法試験に不合格だった法科大学院修了生をマッチングする人材エージェントもあります。
法科大学院進学後に予備試験を受験することはできますか?
在学中の司法試験受験が可能になり以前より減少しているものの、法科大学院在学中に予備試験を受験することは可能で、実際に受験している人も少なくありません。法科大学院進学が難しい人のための救済措置という予備試験の当初の趣旨からずれているのはたしかですが、ルール上は問題ないのです。
ただし、法科大学院で思考力や実務能力を養い、司法試験にチャレンジする仲間と切磋琢磨することの意義は入学すれば実感できるもの。
そのため、あくまで力試しとして予備試験を受験し、合格しても修了まで法科大学院を辞めずに学び続ける人もいます。
法律の勉強ができる大学・短大を探す 弁護士を目指せる大学・短期大学を探す 裁判官を目指せる大学・短期大学を探す 検察官を目指せる大学・短期大学を探す