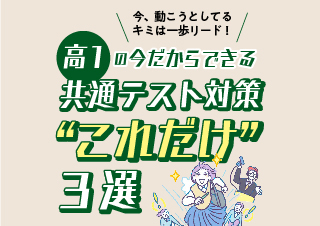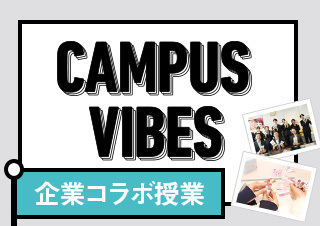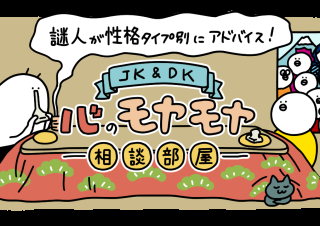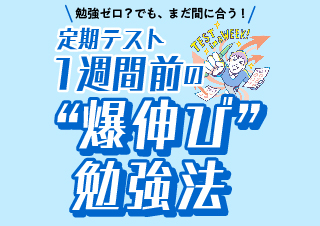交換留学との違いは?海外大学の学位や単位が取得できる「ダブルディグリー」を解説!
教育のグローバル化が進み、留学の種類や海外での学び方も多様化している。一口に「海外で学ぶ」「留学する」といっても、様々なシステムが生まれていることを知っているだろうか?
中でも特に最近注目されているのが、「ダブルディグリー」「ジョイントディグリー」という、留学とは違う国際展開の学位プログラム。
海外でチャレンジしたい、グローバルな仕事に就きたいと考えているなら、選択肢に入れておくべき制度だ。
そこで、「ダブルディグリー」「ジョイントディグリー」の詳細とポイントを、リクルート進学総研の小林 浩所長に聞いてみた!
留学といっても種類はいろいろ、主流は「語学留学」
「ダブルディグリー」「ジョイントディグリー」を説明する前に、「留学」「交換留学」の復習から始めよう。文部科学省では、グローバル化の最初の一歩として「パスポートを持つ」ことから勧めている。
これは、「留学」をより身近にするための方法だ。
訪日外国人が増えても、日常で接したり、話をする機会はまだまだ少ないのが現状。
また親世代では、「留学」というと全て同じという認識であることも多いが、自分にあった留学の種類を見極めることが大事だ。
「パスポートを持つこと」は、次のステップである「留学」へのキーワードなのだ。

※「パスポートを持つこと」は留学への大事な一歩
さて、パスポートを取得したら、次はいよいよ海外へ学びに行くというステップへ進む。
留学の種類としては、目的や期間に応じて主に下記がある。
留学の種類
2週間や1カ月の短期間の留学。
主に語学留学が多く、語学学校等で外国語を学ぶ。
クウォーター制のカリキュラムに合わせて、学校の寮が空いている8~9月の間だけ生活しながら学ぶという、新しいスタイルの留学もある。
大学が提携している海外の大学で単位を取得する。
半期~1年などの長期となる場合が多い。交換留学は留学先の学費を払う必要がないため、金銭的な負担は少ない。
海外の大学に進学し、単位と学位を取得する長期留学。
日本にはない専攻やプロフェッショナルな分野を学ぶことが可能。
ただし、大学在学中であれば休学、または卒業後に留学することとなるため、学費・時間共に負担が大きい。
また、入学審査や語学力などのハードルが高い。

※留学は目的や期間によって選択肢が異なる
留学は目的や期間によって、大きく分けて「自費で負担をして留学する」「交換留学として無料で行く」「休学して留学する」の3通りの選択肢があります。
大学がどの留学制度を導入しているのか、事前に調べたほうが良いですね。
交換留学を希望する場合は、交換留学制度の確認が必須。
交換制ではない場合、別途休学中の学費に加えて、留学先の学費が必要となることもあります。
期間や単位、費用などを、オープンキャンパスや学校ホームページパンフレットでしっかり調べることが重要です。
交換留学とどう違う?ダブルディグリーとジョイントディグリー
これらの留学とは別に、海外の大学の学位や単位を取得する新しい方法として注目されているのが、「ダブルディグリー」と「ジョイントディグリー」というプログラムだ。一般的な大学では、ひとつの学部を修了したら、その学部の学位しか取得することはできない。複数の大学の学位が欲しければ、卒業後に別の大学へ入学する必要がある。
しかし、ダブルディグリー、ジョイントディグリーは、2つの大学、または複数大学共同の学位の取得が可能だ。それぞれの定義とシステムをみてみよう。

※ジョイントディグリー・ダブルディグリーの仕組みを解説!
ダブルディグリーとは
文部科学省によると「複数の連携する大学間で開設された同じ学位レベルの共同プログラムを修了した際に、各大学がそれぞれ学位を授与するもの」と定義している。つまり、日本の大学に入学し、4年間の間にその大学が提携している海外の大学へ1年間以上留学すれば、卒業時に日本の大学と留学先の大学それぞれから学位が授与されるシステムだ。

※ダブルディグリーの仕組み
例えば、日本の大学の専攻が経営学なら、その大学の学位と連携先の大学の経営学の学位、2つ以上の大学の学位が取得できる。通常、2つの大学の学位を取得する場合、どちらかの大学を卒業してから他の国の大学にもう一度入学しなければならない。
ダブルディグリーであれば、4年間の間に2つの学位を取得することが可能だ。
再度海外の大学に留学するよりは費用や修業年限、習得単位数の負担が少ないと言えるだろう。
2つの学位が取得できることは大きな魅力だが、デメリットもある。
例えば、両方の単位を取らなくてはならないので、もう一度海外の大学に留学するほどではないとしても授業数の負担が大きい。
互換共有できる単位があればその分軽減ができるとしても、単位の互換は年々厳しくなっているという。
日本と海外の基準の差が大きいためだ。
このため、学ぶ科目や課題が増える場合がある。
ダブルディグリーは、立命館大学の「立命館大学・アメリカン大学学部共同学位プログラム」をはじめ、国際関係の学部をもつ非常に多くの大学が取り入れています(平成27年度実績では351件)。
4年間で2つの学位が取れるということは、大きなメリット。
どこの国のどの大学の学位が取れるのか、授業数や修業年数、費用を十分に確認することが必要です。
・立命館大学 「立命館大学・アメリカン大学学部共同学位プログラム」
・早稲田大学 「Double Degree Programs(DD)」
・慶應義塾大学(商学部)「エセック経済商科大学院大学とのダブルディグリープログラム」
・横浜国立大学(経済学部)「華東師範大学経済与管理学部ダブルディグリープログラム」
ジョイントディグリーとは
ダブルディグリーが2つ以上の学位が取得できるプログラムであることに対し、「連携する大学間で開設された共同プログラムを修了した際に、複数の大学が共同で単一の学位を授与するもの」と定義されているのがジョイントディグリーだ。日本のA大学と、海外のB大学が共同で独自のプログラムを形成し、その単位を修得するシステム。
ダブルディグリーと違い1つの学位しか取得できないが、海外の大学と共同の学位を取得できる。

※ジョイントディグリーの仕組み
ジョイントディグリーの開設状況は、現在「名古屋大学大学院・アデレード大学国際総合医学専攻」など下記で開設されている。学部では「立命館大学・アメリカン大学国際関係学部」しかなく、他は国立の大学院だ。
・立命館大学国際関係学部 - アメリカン大学(アメリカ)
・名古屋大学大学院医学系研究科 - アデレード大学(オーストラリア)
・東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究所 - チリ大学(チリ)
・京都大学大学院医学研究科 - マギル大学(カナダ)
など
共同プログラムを開設している大学へ留学を義務づけている場合もあるが、基本的に日本で取得できる。
日本にいて、海外の学生と一緒にひとつのプログラムを学ぶことができるわけだ。
必要取得単位はダブルディグリーよりも少なく、費用の負担も軽減できる。

※ジョイントディグリーを実施しているのは主に大学院
しかし、ジョイントディグリーのハードルは、現在非常に高い。
学力はもちろん、海外の学生と共に学ぶことができる語学力も必要だからだ。
学部からジョイントディグリーを選択しようとするなら、今のところ立命館大学しかありません。
ハードルは非常に高いですが、海外の大学の学生と一緒に学べる貴重な機会です。新しいチャレンジをしたい人には、チャンスだと思います。
国際力を身につけて何をしたいのかを見極めて選択しよう
留学にするか、ダブルディグリーやジョイントディグリーにするのか。自分が何をしたいのか、そのために何を身につけるべきなのかを見極めて、選択する必要があるだろう。
また、ダブルディグリーやジョイントディグリーがプログラムではなく、学部や専攻そのものになっている場合は、受験時に選択しなければならない。
これは、大学によって異なるので事前に調査が必要だ。
さらに、取得できる学位やプログラムのある国は、欧米やアジア圏など大学によってさまざま。
何をどこの国で勉強したいのか、どんな単位が取れるのか、授業料はどうなっているのか、大学によって大きく異なる。
オープンキャンパスで確認するのはもちろん、わからなければその大学に直接問い合わせすることを勧める。
海外で学びたい、専門分野を学びたい、グローバルな仕事をしたいと考えている高校生にとって、良い制度がたくさん生まれている。
将来を見据え、なりたい自分へ向かう道を選択しよう。
※記事内の情報は2019年8月時点のものです。
★ほかの記事もCHECK!
●これで怖くない! 海外留学前の不安を解消するための極意
●『トビタテ!留学JAPAN』応援ソングのSHE’Sに聞く 一歩踏み出した瞬間とは?
●18歳で世界一周! 吉野くんが思う国際協力に必要なこと【前編】