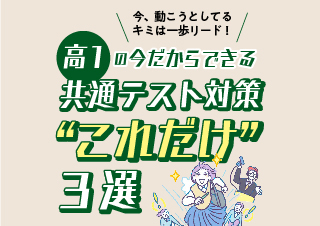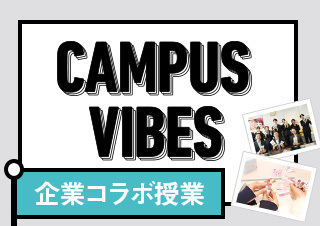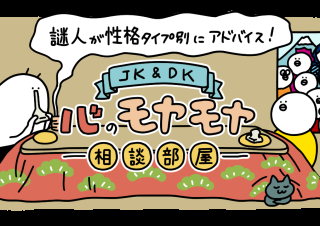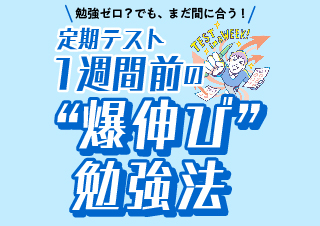将来何がしたいかわからない高校生へ!やりたいことのみつけ方【適職診断付き】
「将来何がしたいかわからない」「やりたいことなんて正直ないかも…」そんなふうにモヤモヤしている高校生は、きっとキミだけじゃない。
この記事では、進路指導・キャリア教育の専門家・浦部ひとみ先生に、やりたいことのみつけ方、さまざまな進路のメリット・デメリット、進路を選ぶときのポイントなどを教えてもらった。
進路に迷っている人は、ぜひ参考にしてみてほしい。
目次

浦部ひとみ先生
東京都高等学校進路指導協議会前事務局長。東京都立晴海総合高等学校勤務。進路指導・キャリア教育の専門家。
進路多様校を中心に、教育委員会や各種の行政機関、NPOなどと連携しながら、都立高校で進路指導・キャリア教育の充実に取り組んでいる。
「将来何がしたいかわからない」は、実はみんな同じ!

なかでも多かったのが、「将来やりたいことがわからない」という悩み。
その背景には、「そもそもどんな選択肢があるのかわからない」「自分に合う進学先や職業がイメージできない」など、さまざまな理由があったが、将来がはっきりしないことへの不安は多くの高校生が感じているようだ。(※)
やりたいことをみつけるにはどうすればいいのか、考え方や行動のヒントを見ていこう。
※2023年6月スタディサプリ進路編集部調べ
高校生がやりたいことをみつけるには?
やりたいことをみつけるには、「考える時間をしっかりとることが重要」と浦部先生。やりたいことがわからない高校生の多くは、そもそも考える時間が足りていないことが多い。
また、何となく向き合っているだけで、真剣に自分の進路と向き合えていないケースもある。
とはいえ、やみくもに考えるのはつらいもの。
そんなときは、考えるヒントになる“材料”を集めることから始めよう。
例えば
・オープンキャンパスに参加する
・進路相談会で情報収集する
・まわりの人たちの意見を聞く
・適職診断ツールで自分の傾向を知る など。
「動きながら考える」ことが、高校生活のなかでやりたいことをみつけるポイントになる。
具体的にどのようにすればよいのか、ひとつずつ詳しく解説していこう。
オープンキャンパスに参加する

高校1年生の夏休みに、オープンキャンパスのレポートを提出する、という宿題が出される高校は多いと思います。
明確な学部・学科が決まっていなくても、ちょっと興味がある分野、気になるジャンルがあったら、オープンキャンパスで先生や在学生の話を聞いて、自分がこれから考えていかなければならないことはどんなことか、イメージを作っていくのです。
いろいろな人と出会うことで、やりたいことをみつけるきっかけがもらえますよ。(浦部先生)
進路相談会で情報収集する
さまざまな大学や専門学校のブースがたくさんある会場ガイダンスでは、自分が知らなかった学校と出合ったり、一日で複数の学校や学部学科の話を聞くことができたり、いろいろな発見があると思います。
特に高校1年生はまだ視野が狭く、自分では気がついていないことも多いでしょう。
スマホでネット検索をしても情報収集できますが、検索ワードを入力するだけでは自分が知っている方向にしかいきません。
どの学校のオープンキャンパスに行けばいいか選べない人は、まず合同説明会で、いろいろな方向に目を向けて比較検討してみるといいですね。(浦部先生)
まわりの人たちの意見を聞く

一番身近で頼りになりそうな存在が担任の先生です。
担任の先生が自分のことをわかってくれていて適切なアドバイスをしてもらえるなら、まずは自分が考えていることを話してみましょう。
もし自分の考えとは合わないかもと感じたら、進路指導の先生や部活動の顧問の先生、さらには塾の先生に相談することもできます。
また、保護者の場合は、自分の経験をもとにアドバイスをくれることが多いかもしれません。
しかし、今と昔では受験制度や社会の状況が変わっていますので、その違いをふまえたうえで、参考にすることが大切です。
年齢の近い卒業生や部活動の先輩など、自分の状況に近い人の経験談は、参考になることも多いでしょう。
特定の人からだけの情報だと偏りがあるかもしれないので、いろいろな人の話を聞いてみるのがおすすめ。
相手に自分の考えをしっかり伝え、また相手の意見に耳を傾けるなど、コミュニケーションがスムーズに行える相談相手をみつけてください。(浦部先生)
適職診断ツールで自分の傾向を知る
そのために利用できるのが適職診断ツールです。
ただし、診断結果をうのみにすることはありません。
あくまで参考程度に留め、担任の先生や保護者との話のきっかけとして活用するといいでしょう。
やりたいことをみつけるためには、まずそれを考えるための材料を準備します。
そして相談を重ねながら、その材料を増やしていきましょう。(浦部先生)
高校生が選ぶ進路の例
高校生が選べる進路は、大学・短大・専門学校といった進学だけではない。海外留学や就職、起業やフリーランスといった選択肢もある。
進路を考えるうえで大切なのは、こうした多様な選択肢を知ったうえで、自分に合った道をみつけること。
どの進路を選ぶかによって、経験できること、身につくこと、そしてその後の生き方が大きく変わってくる。
自分の可能性を広げるためにも、「いろいろな選び方がある」という前提を知っておくことが大切だ。
大学へ進学する

多くの高校生が選ぶ進路のひとつが、大学進学。
幅広い教養と専門分野の知識などが身について視野が広がり、その分、出会いの場も増えることで人間関係が豊かになる。
その分、時間と金銭面の負担が大きく、ミスマッチがあると大きなロスになってしまう。
大学へ進学するメリット
一般的には4年間かけて学ぶことで専門知識や幅広い教養を身につけることができて、視野が広がり、社会に出たときの発展性につながっていきます。
総合大学では、行事やサークル活動などを通して、さまざまな学部・学科に所属する自分の知らない分野の学生たちと出会うチャンスがあり、交友関係が広がっていきます。
学生時代に築いたネットワークは、その後の人生の大切な財産になるでしょう。(浦部先生)
大学へ進学するデメリット
総合型選抜や学校推薦型選抜で学力試験を受けずに入学して大学の勉強についていけなくなったり、将来の夢につながる学びがかなわずに目的を見失ってしまったり、こんなはずじゃなかったと後悔することもあります。
大学は時間も学費もかかるだけに、ミスマッチがあると大きな負担になってしまうのです。
(浦部先生)
短大へ進学する
2年または3年で修了する短期大学は、4年制大学よりも早く社会に出ることができる。その分、学費も抑えて学位を取得できるが、学べる内容が限られるデメリットもある。
短大へ進学するメリット
2年間で修了すれば、学費は大学の約半額で済みます。
幼児教育・保育・食物栄養・歯科衛生など、実践的なスキルを習得できる学科が多く、卒業と同時に保育士・幼稚園教諭、栄養士などの資格を取得することも可能になります。(浦部先生)
短大へ進学するデメリット
大卒と比べて学歴が評価されにくいこともあって、短大へ進学する学生は減少傾向で、募集停止をする短大が増えているのが現状です。(浦部先生)
専門学校へ進学する

学べるジャンルが幅広く、その道のスペシャリストを目指せるが、入学後の進路変更は難しい。
専門学校へ進学するメリット
語学・法律・ビジネス・不動産・医療・福祉・保育・栄養・調理・美容・コンピュータ・建築・デザイン・音楽など、幅広いジャンルのスペシャリストを目指すことができて、資格取得も可能です。(浦部先生)
専門学校へ進学するデメリット
似たような分野の学校でも学べる内容が異なる場合があり、あこがれや雰囲気だけで決めてしまうと、自分が目指している職業に直結した専門知識やスキルが磨けないケースもでてくるので、しっかり調べることが肝心です。(浦部先生)
海外へ留学する
海外の大学や語学学校に入学して、語学力を磨きつつ、国際的な視野を広げていく。将来的に海外で活躍する、国際的な仕事に就く、といった明確な目標がないと、時間とお金をかけたことが浪費で終わってしまうこともある。
海外へ留学するメリット
実際に海外へ出て、自分で見聞きして、肌で感じることは、貴重な経験となって、グローバルな視野が広がっていきます。(浦部先生)
海外へ留学するデメリット
帰国後の進路が不透明になりがちなデメリットもあるので、自分は海外で学んで何をしたいのか、将来のことまで考えておくことが大切になります。(浦部先生)
就職する

それとは逆に、学歴がスキルアップに影響したり、キャリアチェンジが難しかったりすることも考えておきたい。
就職するメリット
大学の指定校推薦のように、就職には「指定求人」として、なかには大学や専門学校へ進学していたら就職が難しい企業からの求人が含まれている場合もあるのです。
大卒と比べて初任給は低いものの、昇進や給与アップに学歴は関係なく実力次第という会社もあります。(浦部先生)
就職するデメリット
また、どうしても就職した特定分野の知識や経験が中心となるため、視野を広げにくい点から、キャリアチェンジが難しいというデメリットもあるのです。
会社によっては、管理職は大卒中心、給与も大卒と高卒とで明確に分けられているというケースもでてきます。(浦部先生)
起業する・個人事業主になる
ベンチャー企業が認知されるようになったこともあって、高卒で起業したり、個人事業主になったり、自分の力で挑戦する人もいる。得意分野を最大限に生かすことができるが、失敗したときのダメージも大きく、相当な覚悟が必要。
起業する・個人事業主になるメリット
稼いだ分だけ自分の収入になるので、成功すれば大きなリターンが得られます。(浦部先生)
起業する・個人事業主になるデメリット
起業に失敗した場合、高卒で中途採用にチャレンジすることになり、スキルや経験の面からも希望職種への就職が難しく、大きなダメージとなる可能性があります。(浦部先生)
進路を決めるときにやってはいけないこと
進路を決めるとき、自分が知っている狭い世界の中だけで完結するのはNG!ネームバリューがあるから、SNSで高評価されているから、保護者が勧めるからなど、それだけで選んでしまったり、自分が進路活動にしっかりと向き合えていなかったりすると、いつの間にか偏った方向に向かってしまっていることもあるので注意しよう。
ネームバリュー・ブランド力だけで選ぶ
高校生はまだ視野が狭いこともあり、知っている大学も多くはないと思います。
ネームバリューやブランド力がある大学だからといって、自分が学びたいことがかなうとは限りません。
大学の名前だけで選ばず、どんなことが学べるのか、将来どんな道に進めるのか、しっかりと調べて、自分に合った学校を探すことが大切です。(浦部先生)
情報収集をスマホのみに頼る

「自分が知っていること」だけで完結してしまうことにもつながりかねないのです。
自分にとって都合の良い情報ばかりを集めていても、新しい発見は期待できません。
オープンキャンパスや進路相談会に参加したり、まわりの大人の意見を聞いたり、幅広い情報を比較検討して判断するようにしましょう。(浦部先生)
SNSの情報を信じ込んでしまう
誤った情報が広まっていたり、場合によっては口コミサイトが操作されていたりすることもあるでしょう。
SNSの情報だけを信じ込んでしまい、他の人の意見に耳を貸さなくなるケースもあります。
あくまで参考程度にしておきましょう。(浦部先生)
保護者の意見だけで進路を決める
ただ、保護者が高校生だったころと今とでは、大学の難易度や受験制度、就職事情などが大きく変わっています。
過去の経験だけで「こうするべき」と言われると、少し戸惑ってしまうこともあるかもしれません。
そんなときは、保護者にしっかりと自分の意見を伝えて理解を求めるとともに、担任の先生など信頼できる人にどんどん相談してみましょう。
大切なのは、誰かの意見をそのまま受け入れるのではなく、自分の考えで選ぶことです。(浦部先生)
自分自身と向き合い、じっくり考えてみよう
浦部先生のアドバイスには、「将来についてしっかりと考え、自分で決断することの大切さ」が込められていた。もし今キミが迷ったり悩んだりしていたとしても、決して悪いことではない。むしろ、自分と向き合うチャンスでもある。
「大学か専門学校か迷っている」「第一志望が決められない」「進学費用が不安」など、進路について気になることがある人は、ぜひこの記事を読んでほしい。
迷っている気持ちを、前に進む力に変えるヒントがきっとみつかるはずだ。
気になる学校の資料を取り寄せる
取材・文/やまだみちこ 監修/浦部ひとみ 構成/寺崎彩乃(編集部)
\関連記事をチェック/
先輩たちはどう選んだ?行きたい大学&学部・学科の選び方
どんな学部・学科を専攻すればいい? 公務員の種類、職種を徹底解剖!
大学、短大、専門学校の違いは?先輩たちにメリット・デメリットを聞いた!