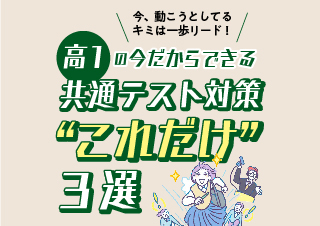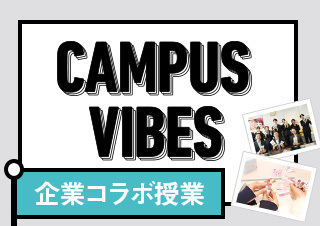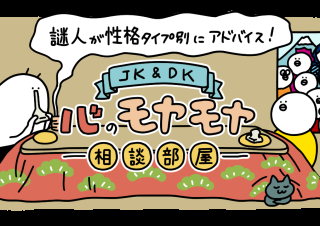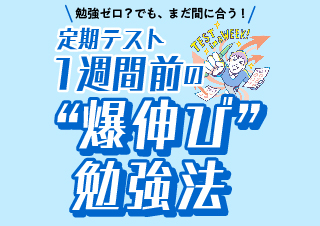高校の科目選択で後悔しない方法!文系理系別の選び方、決定前の最終チェックリストつき
高校の「科目選択」とは、高校3年生で履修する科目を選択すること。多くの学校では、高校2年生の12月ごろまでに科目選択を行うことになる。
選択した科目によっては受験できる大学・学部が限られる…というケースもあり、「何となく」の感覚で決めてしまうと、後悔することになりかねない。
そこで今回は、受験指導のプロに高校の科目選択のポイントを教わった。
目次

スタディサプリ講師。私立学校研究家。高大接続・教育コンサルタント。
大学卒業後、大学受験予備校において小論文講師として活動する一方、通信教育会社や教科書会社にて小論文・志望理由書・自己アピール文の模擬試験作成および評価基準策定を担当。
のべ6万人以上の受験生と向き合うなかで得た経験や知見をもとに、小論文・志望理由・自己アピール・面接の指導法「カンザキメソッド」を開発する。
現在までに刊行した参考書は26冊(改訂版含む)、販売部数はのべ25万冊、指導した生徒は10万人以上にのぼる。
高校の科目選択とは?
高校の科目選択とは、高校3年生で履修する科目を選択すること。多くの学校では、高校2年生の12月ごろまでに選択する。
一方、学校によっては文系・理系を決める高校1年生のタイミングで理科や社会の科目選択を行うケースもあり、自分の学校がどうなっているか早めの確認が必要だ 。
科目選択は大学入試に直結する重要な決断
科目選択が重要なのは、大学受験に影響があるから。科目によって希望する大学・学部を受験できないケースもあれば、科目の組み合せによって受験勉強の負担が大きくなるケースもある。
「ラクそうだから、教科書が薄いから、周囲がみんな選ぶから…といった安易な選択は禁物」と神崎先生は注意を喚起する。
高校の科目選択の基本
神﨑先生によると、高校の科目選択の基本ルールは、次の3つ。①志望大学・学部の受験科目と合っている科目
②大学で学びたいことや将来なりたい職業との関連性が高い科目
③興味をもって勉強ができそうと思える科目
志望大学・学部がすでに決まっている人は①を優先、まだ決まっていない人は②や③を意識して、科目を選んでいこう。
文系・理系や教科により大きく変わる
科目選択は、「文系か理系かによっても教科によっても、ポイントが変わってくる」と神崎先生。英語については、文系・理系とも入試でも将来的にも必須なので、悩むことは少ないはず。
文系の数学、理系の国語については、「どこまでやるか」という範囲を選ぶことになる。
そして、文系・理系にかかわらず高校生を悩ませるのが、理科と社会の選び方。
いずれも科目数が多く、組み合わせも多様だ。
詳しくは後述するが、どの科目を選ぶか、組み合せるかによって、負担感も変わってくる。
志望大学・学部(学科)が決まっているかどうかが分かれ道
科目選択においては、志望大学や学部(学科)が決まっているかどうかで、選択基準が大きく変わる。「志望大学・学部のいずれも決まっている場合は、その大学・学部の最新の受験科目を調べて、それに合った科目を選択するのが王道」(神﨑先生)
一方、興味のある学部・学科や学問系統は決まっているものの、大学までは絞り込めていない人もいるだろう。
「進路の方向性が決まっている場合は、複数の大学の志望学部・学科の受験科目をリサーチしてみると、その学部や学問における傾向が見えてくるはず」(神﨑先生)
また、志望が国公立大学か私立大学か、一般選抜か総合型選抜・学校推薦型選抜かによっても大きく変わってくる。
「一般選抜の場合、国公立大学では6教科8科目(共通テスト含む)、私立大学では3教科3科目の受験が主流。特に共通テストについては、受験可能な理科・社会の科目の組み合せに目を通しておきたい」(神﨑先生)
では、まだ進路を決めかねている人、見当もつかないという人は、どうしたらいいのだろうか。
「科目選択こそ進路について考える好機ととらえ、自分はどんなことに興味・関心があるのか、将来どうなりたいのか…といったことを掘り下げよう。
そして、先に挙げた2点、大学で学びたいことや将来なりたい職業との関連性が高い科目、興味をもって勉強ができそうと思える科目を選ぶのが良いだろう。
興味をもって勉強ができる科目というのは、自分にとって勉強の負荷が少ない科目と言い換えることもできる。
なぜなら負担が多いとモチベーションが下がってしまう人が多いから。周囲の人の選択に流されないことが大切だ」(神﨑先生)
文系の科目選択の選び方

文系の科目選択においては、
①志望大学・学部の受験科目と合っている科目
②大学で学びたいことや将来なりたい職業との関連性が高い科目
③興味をもって勉強ができそうと思える科目
を基本に、以下のような点に考慮して選択しよう。
社会は負担の少ない組み合せを考える

文系の社会では、「日本史探究」「世界史探究」「地理探究」「倫理」「政治・経済」から1〜2科目を選ぶ(これとは別に「歴史総合」「地理総合」「公共」は全員が必修)。
日本史や世界史を選択する人が多いが、いずれも範囲が広く覚えるべきことも多いので、勉強の負担は比較的大きいといえるだろう。
一方、一部の大学などでは、地理や倫理、政治・経済などでは受験ができないケースがあるので気をつけたい。
「社会については、自分が興味のある科目を選んで勉強し、その科目で受験できる大学を探す…という方法もある」と神﨑先生はアドバイスする。
国公立大学の文系学部では、共通テストで社会の2科目受験が求められるケースも少なくない。
その際、「日本史・世界史」の組み合せは負担が大きいので、避けたほうが良いだろう。
共通テストの社会科目については、「地理総合・地理探究」「歴史総合・日本史探究」「歴史総合・世界史探究」「公共・倫理」「公共・政治経済」「地理総合・歴史総合・公共(うち2つを選択)」の6科目から1ないし2科目を選択する。
2科目受ける場合は、科目ごとに可能・不可能な組み合せや、大学によっては認めていない組み合わせなどがあるので、下記を参考に志望校の受験科目を確認しておこう。

理科は基礎科目から選ぶ
文系で理科が必要になるのは、一般選抜で国公立大学を受けるケース(共通テストでの受験)。文系の理科は、「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」の4つの基礎科目から2つを選択する。
文系の場合は「化学基礎・生物基礎」を選択するケースが比較的多いが、いずれを選択しても受験には大きな影響はない。
なお、「地学基礎」は開講されない学校も多いが、計算などが少ないため、穴場な科目ともいえるだろう。
国語は「古典」まで選択を
国語の選択科目は、「論理国語」「文学国語」「古典探究」「国語表現」(それとは別に「現代の国語」と「言語文化」は1年次に必修)。ここから3~4科目を選択する(学校によって異なる)が、「論理国語」「文学国語」「古典探求」を必修とし、「国語表現」を選択とする学校も多い。
小論文、国公立二次試験の論述などが控えているのであれば、「国語表現」を選択しておきたい。
また、数学については、国公立大学の2次試験では文系でも「数学Ⅱ」「数学B」「数学C」まで必要になるケースがあるため、国公立大学への進学を考えている人は選択しよう。
理系の科目選択の選び方論理国語・文学国語・古典探究

理系の科目選択においては、
①志望大学・学部の受験科目と合っている科目
②大学で学びたいことや将来なりたい職業との関連性が高い科目
③興味をもって勉強ができそう(勉強の負荷が少ない)と思える科目
を基本に、以下のような点に考慮して選択しよう。
理科は大学での学びに必要な科目を選ぶ
理系の場合、理科は1・2年次に基礎科目(「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」)を受講したうえで、「物理」「化学」「生物」「地学」の専門から2科目を選ぶことになる(それぞれ「基礎」を付した科目を履修後に履修)。基礎科目では受験に太刀打ちできない大学・学部が多いので注意が必要だ。
2科目の最も一般的な組み合せは「物理・化学」だが、医学系、農学系、生物学系などの学部では「生物」の知識が不可欠になる。
大学入学後の学びを視野に入れたうえで、科目を選択することが重要だ。
社会は負担が少ないor興味のある科目を選ぶ
理系で社会が必要になるのは、一般選抜で国公立大学を受けるケース(共通テストでの受験)。理系の場合は、覚えるべきことが比較的少ない地理や公民を選択する人が多い。
日本史や世界史は覚えるべきことが多く負担はあるが、歴史が好きだという人は選択しても良いだろう。
数学は「数学Ⅲ」「数学C」まで選択を

数学については、「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学A」「数学B」「数学C」の6科目があり、学習指導要領上の必修科目は「数学Ⅰ」のみだが、理系の場合は「数学Ⅱ」「数学B」までは必修としている学校がほとんど。
理系の大学入試では「数学C」に加えて「数学Ⅲ」までが出題範囲となるケースが多く、選択しておくと進路選択の幅が広がる。
一方、理系でも「数学Ⅲ」が不要な学部・学科もあるため、数学が苦手な人はあらかじめ大学の情報を集めておくと良いだろう。
先輩の体験からわかる!科目選択の教訓

実際に科目選択をした先輩たちに、ヒアリング調査※を実施。
「後悔している」という先輩たちのエピソードに対して、神﨑先生からコメントをもらった。
先輩たちの体験から教訓を得て、失敗のない科目選択につなげてほしい。
※現役大学生・専門学校生25名にヒアリングを実施。
先輩体験談に基づく教訓①
迷ったら、独学では難しそうな科目の選択を!
「文系コース国際系志望だったが、国公立大学を受験するかも…と考えて数学を選択。しかし、その後、私立大学を第一志望としたため数学は必要なく、歴史を独学でやらなければいけないことになり、後悔した。
科目選択は、受験に必要な科目を確認してからするべき。
もし必要な科目が決まっていない、もしくは迷う場合は、独学では補えなさそうな科目を選択すべき」。
(大学1年生・千葉県)
国公立志望ということであれば社会は選択していたはずなので、きっと地理など、私立で受験できない科目を選択してしまったのでしょうね。
一般選抜の場合、国公立大学と私立大学では受験科目数が大きく異なり、勉強法も変わってきます。
志望校、特に国公立大学か私立大学かはなるべく早く決め、そこから逆算して科目選択をするのが王道です。
独学については、世界史は混乱しやすく、日本史はより深い知識が問われるため敬遠されがち。
昨今は動画などもあるので比較的やりやすくなっているとは思いますが、勉強の負担が大きいのは否めないでしょう。
先輩体験談に基づく教訓②
数学が得意なら、数学で受験できる文系学部で勝負するのもあり!
「私立大学志望だったため受験できる大学や学科が多く、参考書なども充実している安定の日本史を選択した。しかし、文系でも数学で受験できる学部・学科もあり、数学選択はボーダーが低いということも聞いたので、数学を選んでおけば、もっと勉強しておけば…と後悔した」。
(大学2年生・千葉県)
「数学選択はボーダーが低い」というのは正確ではなく、「(文系において)数学が得意な数学選択者は有利になりやすい」という意味合いでしょう。
というのも、文系の学部・学科で出題されるのは数学Ⅰ・Aの範囲であることがほとんどで、日本史などに比べると覚える量も少なく、数学が得意な文系の受験生にとっては「おトクな科目」といえるから。
しかし、「おトクらしい」と聞いて自分の得意・不得意を考慮せず科目を選ぶのはNGですよ。
先輩体験談に基づく教訓③
先生が合う合わないよりも、興味をもてるかが大事!
「志望の学部から物理を選択したものの、高校の物理の先生が自分に合わなかったため、最後まであまり理解できなかった。最後まであまり理解ができず、復習不足もあるだろうが、先生を見て決めることも大事だと感じた」。
(大学1年生・埼玉県)
「この先生とは合わない」と思うと、授業がおもしろくなくなるのは当然のこと。
とはいえ、学校の先生はなかなか自分では選べないので、先生と合わないことを理由にその科目を選択肢から外すのはもったいないと思います。
授業がおもしろくなくても、ネットで解説動画を探すなど、工夫して勉強に励むことはできるはずです。
先生と合うかどうかよりも、その科目の内容が自分に合っているのかどうか(興味をもって取り組めるかどうか)を見極めることが大切です。
もう迷わない!疑問点をプロが解決

実際に科目選択をした先輩たちと、神﨑先生がこれまで指導した生徒が抱いた悩みを紹介。
それぞれのお悩みに対して、神崎先生からアドバイスをいただいた。
悩み①
国公立大と私立大、どちらを目指すかまだ決められていない。
「文系です。国公立大学を受験する場合には理系科目を選択する必要がありますが、数学や理科は苦手です。私立大学のみ受験する場合は、英語や歴史を履修したほうが良いと思うのですが、どちらを重視すべきですか?」
(大学1年生・千葉県)
一般選抜で国公立大学を受ける場合は受験科目が多く(最大6教科8科目)、3科目受験が基本の私立大学とは対策法も大きく変わってきます。
文系の場合、英語や歴史はいずれの場合も必要になるので履修すべきでしょう。
理系科目については、履修しても私立大学を受けることになった場合、「受験では不要だが、授業には出席して定期試験も受けなければならない」ということになり、かえって負担が大きくなりかねません。
科目選択のしかたも変わってくるので、国公立大学を目指すつもりがあるなら、できるだけ早く決断しましょう。
また、国公立大学か私立大学かを決めることも大切ですが、そもそも大学で何を学びたいのか、まずはそこをしっかりと詰めて学部系統を絞り込む必要があります。
科目選択は進路について考えるチャンスですので、これを機に自分が何をしたいのかを深掘りしてみましょう。
悩み②
大学で数学が必要そうだけど、数学が超ニガテ!
「心理学が学べる学部を志望しています。心理学では数学を使うと聞いているのですが、数学で学年最下位や赤点を取ってしまう自分は、数学の受験勉強は頑張れないと思います。
どうすればいいでしょうか?」
(大学2年生・千葉県)
文系の数学の場合、「受験で必要」と「大学で必要」を分けて考えたほうが良いでしょう。
数学が苦手なのであれば、受験に数学が必要のない心理系の大学・学部を探すことは十分に可能です。
一方、「大学に入ってから数学の知識・技能が必要」というのは、高校で学ぶ数学のすべての範囲が必要という意味ではありません。
例えば、統計やデータの扱い方、計算方法など一部ですので、そこは気持ちを新たに学び直せば良いのではないでしょうか。
悩み③
理工学部志望で物理が必須だけど、苦手…。
「理工学部を志望しています。物理は必須ですが苦手なので、物理を選択すべきか悩んでいます。」
(大学1年生・埼玉県)
理工学部といっても多様な分野が含まれますので一概には言えませんが、物理が苦手だと苦労すると思います。
「苦手だ」と思っているだけで、実はまだしっかりと勉強をしていないだけ、授業におもしろみを感じられないだけ…というケースもあります。
物理に関する書籍を読んだり動画を視聴したりして、自分なりに物理の世界を探ってみてはいかがでしょうか。
悩み④
総合型選抜・学校推薦型選抜の場合、科目の選び方にコツはある?
「総合型選抜・学校推薦型選抜での受験を考えています。いわゆる学力試験はないのですが、その場合にも科目の選び方にコツはあるのでしょうか?」
(神﨑先生より)
総合型選抜・学校推薦型選抜では、調査書で科目の履修状況が確認できるはずです。
例えば、志望理由書には「宇宙の研究がしたい」と書いているのに物理を履修していなかったり、「DNAを解明したい」と書いているのに生物を履修していなかったりすると、説得力がなくなってしまいます。
「なぜこの学問を学びたいと思ったのか」というストーリーと整合性のある科目選択をすることが大切になるでしょう。
悩み⑤
文理選択と同時に科目選択が…どう選べばいい?
「高校1年生の時に文系・理系を選択するタイミングで、理科と社会の科目選択をしなければなりません。自分の得意・不得意もまだわからないのですが、どうすればいいでしょうか?」
(神﨑先生より)
得意・不得意がまだわからないのであれば、「好き」を優先してしまってよいと思います。
可能なら学校の科目担当の先生に話を聞き、どんなことを学ぶのかを教えてもらうといいでしょう。
自分から聞きに行くのが苦手なら、教科書を素読みしてみる、動画で探してみるなどしてみるのもおすすめ。
「何となくこんなことやるんだな」という概要を掴み、「おもしろそう!」と心が動いたものを選ぶと良いでしょう。
これで完璧!科目選択のポイントチェックリスト
最後に、科目選択のポイントをチェックリストとして再掲する。すべてを網羅するのは難しいかもしれないが、できるだけ多くの項目にチェックが入る科目を選ぶよう心がけてほしい。

\共通テストってどんなテストだっけ?という人はこちら/
共通テストの基礎知識!一般入試と何が違うの?
\「科目選択の落とし穴」について知りたい人はこちら/
【高2向け】8つの性格タイプ別に謎人が解説!科目選択の落とし穴