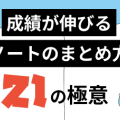小論文の書き方完全マニュアル!構成、ルール、注意点とは?模範解答&減点対象ダメ答案例文つき
小論文とは、与えらえたテーマに対して自分の意見・主張を論理的に述べた文章のこと。大学入試でも出題される小論文だが、苦手意識を持っている人もいるのでは?
しかし、基本とルールをきちんと理解すれば、どんな人でも小論文攻略は可能なのだ。
それでは、スタディサプリの現代文・小論文講師を務める小柴大輔先生に、基礎から教えてもらおう。
目次
小柴大輔先生

東京巣鴨にある大学受験専門塾ワークショップで講師を務めるほか、ロースクール(法科大学院)受験の予備校においても一般教養小論文を指導。
感覚ではなく論理的に答えを導く指導に定評があり、「現代文に対するイメージが変わった」と受験生から圧倒的な支持を集めている。
スタディサプリでは、現代文の他、小論文やAO・推薦対策講座を担当。
小論文の基本
小論文とは?
小論文とは、一つの模範解答があらかじめ用意されていない問いに対して、自分の意見を仮説として600~1000字程度で提示する文章のこと。大学入試では、一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜のいずれでも課されることがある。
一般選抜では、試験会場で60分、90分などの制限時間内に書き上げる必要があるが、総合型選抜や学校推薦型選抜の場合、書類選考の段階で提出を求められることが多い。
小論文と作文・感想文はどう違う?
作文・感想文は、感情や印象など自分の思ったことを思ったように書いてOK。
これに対して、小論文は、設問に対して、根拠を示して自分の意見を論じ、論理的に相手を説得することが求められる。
独りよがりな思いだけを書いても誰も説得することはできず、それでは小論文として成立しないのだ。
以下の違いをよく理解しておこう。
小論文と作文の違い比較表
| 小論文 | 項目 | 作文 |
| 自分の意見や主張。 | 伝える 内容 |
自分の体験やそれを通して感じたこと。 |
| 根拠や理由を示し、論理的、客観的に 伝えることが求められる。 |
求められる 要素 |
一般論ではなく、自分の気持ち、 感想を伝えることが求められる。 |
| 基本的には使用しない (多少の比喩表現などであればOK)。 |
文学的な 表現技法 |
効果的であれば使用してOK。 |
| 序論・本論・結論で構成する。 | 文章の 構成 |
読みやすさが第一。細かな制限はない。 |
| 「だ・である」が基本。 | 文体 | 「だ・である」でも「です・ます」でもOK。 どちらかに統一すること。 |
実は、小論文の試験であるにもかかわらず、作文や感想文のような文章を書いてしまう受験生は少なくありません。
この違いを正しく理解することで、求められる考え方や書き方が明確になり、対策の精度もぐっと上がります」(小柴先生)
小論文は序論→本論→結論の3部構成
小論文を書くうえで必ず理解しておきたいのが「構成」だ。小論文の基本的な構成は、序論→本論→結論となる。
序論では、設問に対して、自分なりの方向性(賛否やどういう立場からテーマを論じていくか、どんな例を出すつもりかなど)を設定する。
続く本論では、意見の裏付けとなる理由・根拠を記述。
そして、結論で全体を締めくくる(ここで意見を記述する場合もある)。
序論では、自分の立場・関心・目の付け所を明らかにするのがポイント。
2~3行の序論形成がしっかりできていると、小論文の方向性が決まりますから、書く側も書き進めやすいし、読む側にとってもわかりやすい文章になります」
本論はそれを裏付ける理由や根拠を中心に展開する。
小柴先生によれば、意外にも「結論」はそこまで重視しなくてもいいのだとか。
結論は省いて、序論→本論という構成にしてしまっても、実は問題ないんです」
小論文で求められる「意見」は持論や思想とは違う
では、小論文で求められる「意見」とはどのようなものなのだろうか。そもそも、課題文に対して賛成・反対の両方の立場から論じさせる設問だってありますから。
自分の考えとは違う意見を書くことだってあるのです」
要するに、問われているのは、その人の本質的な考え方や思想(そうしたものは大学での専門の学びの中で徐々に形成したらよい)ではなく、初めて見るテーマについても臨機応変に論理展開できる柔軟な思考力というわけだ。
仮説の提示、言葉のパフォーマンスと言ってもよい。
ちなみに、意見と感想の違いがよくわからないという人も多いかもしれない。
わかりやすく言えば、自分の中の「好き/嫌い」で終わってしまうのが感想、一方、自分の感情とは別に、論理的な根拠とともに主張されるのが意見。
例えば、「とてもおいしいから納豆が大好きだ。だから毎日食べたい」は感想(あるいは自分の感情・感覚だけに基づいた考え)。
これに対して、「納豆には必須アミノ酸がバランス良く含まれており、人々の健康増進に貢献するとの科学的実証データが示されている。
だから、積極的に摂取すべき食物の一つである」は意見。
なお、後者の「意見」は、実は納豆が嫌いな人が書いている場合だってあるし、それでもまったく問題ないというわけ。

また、一口に「意見」といってもいくつか種類がある。
分類すると次の通り。
①問題発見、問題の指摘
②問題の分析
③問題解決、対策案の提示
④希望や価値、可能性、重要性の指摘
例えば、少子高齢化や地球温暖化などの社会問題について意見を述べる場合、受験生は、つい対策まで書かなければいけないと考えがちだ。
しかし、このような複雑な問題に対して、限られた時間、文字量で説得力があるレベルの対策を提案するのは、受験生にとっては至難の業。
そのような場合は、無理をせず、問題の指摘や分析に止めても十分意見として成立する。
①~④のうちのどれかに該当していれば大丈夫(もちろん複数を組み合わせてもOK)。
理由・根拠がなぜ重要か?
次に、「理由・根拠」についても説明しておこう。根拠として使えるのが統計データだ。
数字で裏付けることにより、意見の説得力はグンと高まる。
ただし、課題文や図表から引用する場合を除けば、数字を覚えておく必要があるので、受験生にとってややハードルは高め。
あくまでできる範囲で盛り込めばOKだ。
.jpg?20260203) より意識してほしいのが、文中で自分の意見に対する反論を示して、それを乗り越えること。
より意識してほしいのが、文中で自分の意見に対する反論を示して、それを乗り越えること。
どんな意見にも反対意見はあります。
文中で反対意見を明示し、比較上自分側の意見の方がより重要である、あるいは反論側にはこんな大きな問題があるなどを指摘することで、説得力が大きくアップします。
もう一人の自分とディベートするイメージですね」
小論文の種類、出題形式
ひとくちに小論文と言っても、その出題形式にはいくつかのパターンがある。大きく分類すると、課題文型、図表型、(課題文+図表の)ミックス型、テーマ型の4つ。
小論文を課す大学・学部では、例年同じタイプの出題をしてくることが多く(突然タイプを変えてくることもなくはないので油断は禁物だが)、志望校・志望学部の出題パターンは過去問でしっかりチェックしておくことが必須だ。
では、それぞれどのような特徴があるのかを解説していこう。
文章資料を読んで回答する「課題文型」
特定のテーマに関する評論などの課題文が資料として提示され、それを読んでそのテーマに対する自分の意見を論じるタイプ。文章資料は1つの場合が多いが、複数提示される場合もある。
課題文型の場合、意見を論じさせるだけでなく、合わせて要約問題が出題されるのが定番で、要約には、全文要約と、指定されたキーワードや傍線部分を要約する部分要約とがある。
小論文試験では、このタイプの出題が最も多い。
グラフや統計資料を踏まえて回答する「図表型」
特定のテーマに関するグラフや統計資料が提示され、それを分析して自分の意見を論じるタイプ。グラフや統計資料は1つの場合もあるが、複数提示され、比較したり、照らし合わせたりして分析するパターンのほうが多い。
図表型の場合、意見を論じさせるだけでなく、「この資料からわかることは何か」という分析問題がセットで出題されるのが定番。
ただし、純粋に図表だけを提示して論じさせるこのタイプの出題はあまり多くはない。
課題文と図表がセットで提示される「ミックス型」
ミックス型は、特定のテーマに関する文章と、そのテーマに関するグラフや統計資料がセットで提示され、そのテーマに対する自分の意見を論じるタイプ。文章は課題文型と比べると短めで、新聞記事のような事実を記述する内容が一般的。
資料分析問題がセットで出題されることが多いのは図表型と同様だ。
小論文試験では、課題文型に次いでこのタイプの出題が多い。
シンプルな問題文のみが提示される「テーマ型」
課題文や図表は一切なく、短めの問題文のみが提示され、そのテーマに対する自分の意見を論じるタイプ。例えば、「グローバリゼーションに関してあなたの意見を述べなさい」「少子高齢化についてあなたの考えを論じなさい」といった出題がされる。
上記のように、いろいろな角度から論じることが可能な大きなテーマが出題されることが多いので、とりとめなく論点を広げすぎず、できるだけ受験する学部に関連する切り口から意見を展開するのがポイント。
小論文の書き方

小論文を書き始める前に大事なことをおさえよう
小論文を書くうえで、重要な手順は以下の通り。
まず出題の趣旨を理解し、自分の意見を決める
小論文を書き始める前に、まず出題の趣旨をしっかり理解することが重要だ。例えば、「環境問題に関して先進国が抱える課題について論じなさい」という出題に対して、「先進国が抱える」という記述を無視して、「自分が個人的に抱えている課題」について論じるといったように、出題の趣旨を理解していない解答は、どんなに構成がしっかりしていてもNGだ。
合わせて、出題の条件を踏まえることも大切。
小論文全体を出題の趣旨・条件に沿った内容にまとめることを意識して、構成を考えよう。
序論・本論・結論に何を書くかを考え、設計図を作る
出題の趣旨・条件を理解したら、次のステップは意見を決めること。その際に、明確な理由や根拠が示せるかどうかをしっかり考えることもポイントだ。
小論文で示される意見とは、論理やデータで組み立てていくものなのです」
序論をどう書くか、本論をどう展開するか、結論をどうまとめるかをイメージし、小論文の設計図を作っていこう。
論点や意見の整理にはメモを活用
なお、意見を決め、構成を考えるときにはメモを取るのがおすすめ。
頭の中で考えているだけだと、最初に考えたことを忘れてしまったり、アイデアが整理しきれずに混乱してしまったりすることもある。
メモを取る時間が無駄に思えるかもしれないが、キーワードを書き出したり、序論・本論・結論それぞれのポイントを簡単に書き出したりするだけでも、頭の整理につながり、文章を書き進めやすくなる。
小論文のOK例・NG例

小論文の答案サンプル集を参考に小論文の書き方をマスターしよう
小論文の基本的な書き方を押さえたら、具体的な例文に触れて理解を深めよう。
OK例とNG例を比較することで、評価される小論文のポイントがより明確になるはずだ。
反論を乗り越える「根拠」や「具体例」はこう書く!
私は①国際化が進み、国内的には少子化・人口減が進む現代社会という視点から、多彩な人材をワールドワイドに集めるためにも、②年功制から能力給への移行は重要だと考える。
以下詳しく論じる。
③年功制は、新卒一括採用・終身制・定年制などとセットで「日本的経営」と呼ばれてきた。なるほど集団や組織を重視する「日本人のメンタリティ」に適しているともいわれる。
④しかし、年功制は戦後日本の人口増加という状況で生まれたという事実がある。
100年200年続いた「不動の伝統」ではなく、ある歴史的・社会的な条件下で形成されたものだ。
すなわち、「国内の人口増加=労働力人口増・消費人口増」の中で生まれ定着したという背景がある。したがって、歴史的社会的状況が変化すれば(国際化・少子化・人口減少)、給与の仕組みや働き方も変化することは必然である。
加えて、商品やサービスを売る消費市場は海外に広がっている。
そうした視野の拡大のためにも、人材・労働力の市場を得るためにも「日本的経営」で国内人材を囲い込むのではなく、国際社会から多彩な人材を獲得することが重要であろう。
統計によれば、⑤日本のGDPの総額は米中独に続く世界第4位であるが、人口で割った「一人当たりGDP」も働く人の数で割った「労働生産性」でも先進国(OECD)中、平均以下の下位グループである。
この点でも国内人口増とは相性のよかった「日本的経営」には限界がきている。ゆえに能力給への移行がこれからの日本には必要であろう。
① 大切なのはやっぱり序論。最初に明確に視点を提示することで小論文全体の切り口が絞られ、読みやすい構成になる。これだけで加点対象。
② 序論でこの小論文の結論(=自分の意見)を書いている。この構成は非常に読みやすい。
③ 自分とは異なる意見(反論)にも触れている。ここでのポイントは自分の意見とは違う立場だとわかるように書くこと。「一般的には~と言われているが」「~という面では評価されているが」といった書き方をすると立場の違いは明確になる。なお、反論はあくまで脇役なのでボリュームが増えすぎないように注意。
④ ここから反論を乗り越えて、自分の意見の強調(再反論)に入っている。再反論は大事なところなので分厚く。続く文章では言い換えや根拠の説明、具体例を重ねて意見に説得力が加えられている。
⑤ このように統計を出すと説得力アップ。加点要素になる。OECDの統計など、使えるデータはしっかり頭に入れておきたい。なお、ハッキリ覚えていない場合は無理して使わなくてもOK。
序論になっていない序論は大きな減点対象!
①給与の仕組みについて、年功制に代わり能力給(成果主義)を導入することについて、私の意見を述べる。
②そもそも給与の仕組みなど、人間が働く動機としては二次的で重要ではない。
むしろ、自らの適性にあった仕事かどうかが重要であると私は思う。
そのために学校教育を通じて自己の適性を知ること③が重要であるとは私は思う。
能力給(成果主義)は④日本人の性格に合っていないため導入しても長く続かないだろう。
④能力給の長所もあるので、それを十分に踏まえる必要がある。
① この序論は、設問の内容を繰り返しているだけで自分なりの視点や切り口がまったく示されていない。序論としての役割を果たしていない「あってもなくてもいい文章」になってしまっている。これは減点対象。とりあえず導入っぽいことを何か書けばいいというものではないのだ。
② 設問は給与の仕組みについて尋ねているのに、この内容はまったく設問に答えていない。これは大きな減点対象。0点でも文句は言えない。
③ 「~が重要であると私は思う」という表現は直前にも使っている。同じ表現の繰り返しは避けたい。日本語にはさまざまな表現があるのだから言い換えよう。
④ 理由や根拠がない横暴な断定になっている。この場合なら、「日本人の性格」とはどのようなもので、なぜ合わないのか、言葉を尽くすべき。ここをしっかり書かないと意見に説得力が生まれない。
⑤ この締めは、何が言いたいのか不明。能力給の問題点を重視して書くのか、可能性を重視して書くのか、序論で明記していないから、自分でも最後に来て混乱してしまっている(実はよくあるケース)。
また、この一文が自分の意見なのか他者の意見なのかもよくわからない。これも小論文における表現としては大きなマイナス材料。
そのうえ「長所である」ことの根拠も示されていない。
図表分析は「点」ではなく「線」を読み取ろう!
続いては苦手な人も多い図表分析の模範答案とダメ答案。
こちらはポイントとなる部分を抜き出した答案サンプルを紹介しよう。
①年少人口比も生産年齢人口比も下降傾向である。
一方、老人人口比は上昇傾向で、②90年代後半以降、年少人口比を上回っている。
いわゆる③少子高齢化を示している。
図表2によれば、④社会保障費はほぼ一貫して増加傾向であり、人口に占める高齢者比率が高まるにつれて、上昇していると言える。
また、図表1の将来予測から、今後も社会保障費が増加していくと推測される。
したがって、⑤働く世代の税負担などが増すことが考えられる。
① グラフなどの数字は、「点」でとらえるのではなく「線」でとらえるのがポイント。この文章は「下降傾向」という「線」を説明しているのでグッド。
② 流れの中の転換点、難しい言い方をすると「線の中の特異点」を指摘できている。「線」が読み取れたら次のステップはこれ。どの点を境に傾向が変化しているのかなどを説明できると分析に厚みが生まれる。
③ 図表にも設問にも「少子高齢化」という言葉は出てきていない。図表が示していることを自分の知識と関連付けて表現できている。これも図表分析では大事なポイント。
④ このように複数の図表が示された場合、その関連性が問われていることがほとんど。図1と図2を関連付けた分析はグッド。
⑤ 単に数字が示されただけのグラフから、その意味することを概念化し、まとまった言葉を与えている。この場合は将来どんな問題が起こりうるかと言うことをしっかり記述できている。ここまでできれば図表分析問題の解答としてはハイレベル。
図表分析でありがちなミスはこれだ!
図表1によれば、2015年の年少人口比率はおよそ13%とわかる。
図表2によれば、2015年の社会保障費はおよそ120兆円だとわかる。
見たままを書いただけ。数字の棒読みで分析になっていない。
しかも、数字の推移がグラフで示されているのに、「点」の指摘しかしていない。これでは得点は期待できない。
図表1によれば、老人人口は増加傾向である。
こちらは一見「線」を読み取れているように思えるが、実は図表を読み間違えている。
図表1は「人口構成比」、つまり割合を示しているだけ。高齢者人口そのものが増えていることを示しているわけではない。
実際には日本の総人口はすでに減少が始まっている。
割合と実数を取り違えて解釈してしまうのも実はよくあるミス。
要約は「対立構造」をしっかり抜き出そう
続いては、小論文につきものの要約問題の模範答案&ダメ答案も見ておこう。
心と体が二つの異なる実体とみなす心身二元論には、長い伝統がある。
古代ギリシャのプラトンの哲学や近代のデカルトの哲学が代表である。
もっと素朴な感覚からも、たとえば、生きて活動していた人間が死んでしまうと体だけ残して活動を停止するところから、魂・心と身体が別物で分離可能なものと見えることも、心身二元論をもっともらしいものとしてきた。
こうした心身二元論は、ちょうどアニメにあるような乗り込み型のロボットのようなものとして、人間というものを捉えている。
乗り込む人間が魂や心に相当する部分で、一方それに操られるロボットが身体に相当する。
『マジンガーZ』でも『ガンダム』でも『マクロス』でも『エヴァンゲリオン』でも、お望みのロボットアニメを思い浮かべていただきたい。
この意味でも、ロボット的心身二元論モデルは、私たちになじみ深い。
これまで実に多くのロボットアニメが作られ、またこれらを違和感なく見てこられたのも、心身二元的な自分自身と乗り込み型ロボットとの間にアナロジー=類比を見ているからだろう。
だが、このような心身二元論的モデル、乗り込み型ロボットモデルは、身体というものを、なにかしら「外部」的なものとして捉えていることが分かる。
つまり、自分という人間の核は心・魂・精神と呼ばれるところにあり、身体はそれから区別された周辺的なものと見なされている。
しかしながら、よく考えてみれば、身体が「自分」というものから「外」にあるという感覚、身体がよそよそしく感じられる時というのは、骨折などして体の自由が効かない場合や緊張のあまり体がぎくしゃくしている場合など、むしろ特殊な場合である。つまり、通常の日常活動しているとき、私たちは身体の「外部性」など感じたりはしない。
あるいは、身体というものの存在をとりわけて意識したりはしないのだ。ことさらに身体を意識しているようでは、日常の行動はうまくいかない。例えば、体重を前方に傾けながら右足を一歩前に出し、そのとき左足は軽く地面をけってそのまま前方に送る、などと意識していては、走ることも歩くこともろくにできはしない。
むしろ、身体がほんとうに身体として機能しているときには、身体はその「外部性」を消失している。
心と身体との一体感こそ私たちにとって常態なのである。そしてこの心身の一元的な感覚を幸福な一体感と私は呼びたい。
だが、先にも触れたように、通常の日常生活が行われているとき、身体はその「外部性」「存在感」を消失しているために、人々はこの幸福な一体感に気付かない。
ところが、柱の角に足の指をしたたかぶつけたとき、自分が身体なのだと、ありありと感じる。
骨折治療用のギプスをはずされ、リハビリテーションで苦痛のうめき声をたてながら、自分の身体性を取り戻す。歯科医の椅子で呻吟(しんぎん)しているとき、これ以上に、自分が他ならない身体であり、自分の外に身体はなく、身体の外に自分はないということを切実に感じることはない。私たちが苦痛を被(こうむ)ったとき以上には心身の幸福な一体感を感じられないとは、いかにも皮肉だ。
(小柴 大輔 『心と体の哲学』)
プラトンやデカルトの哲学を代表に、①心身二元論 には長い伝統がある。
②また一般的にも心体は別とされがちだ。
ここではアニメの乗り込み型ロボットのように身体は心に対して「外部」とみなされる。
②だが、 身体を外部と感じるのは体がうまく機能しない特殊な場合である。
②むしろ 身体が真に機能するとき心身は一体である。
②ただし、 この状態が常態であるために、苦痛を感じた時にしか心身の幸福な一体感を感じられないことは、皮肉だ。
① 文章の主役は「心身一元論」だが、敵役(=乗り越えるべき反論)である「心身二元論」について触れている。要約ではこの対立構造を抜き出すことがポイント。
② 要約の文章はとにかく短文で切って、適切な接続詞でつないでいくこと。こうすると簡明で論理的な文章になる。
ダラダラと一文が長い要約は減点される!
プラトンやデカルトの哲学を代表に、心身二元論には長い伝統があり、一般的にも心体は別とされがちで、アニメの乗り込み型ロボットのように身体は心に対して「外部」とみなされ、身体を外部と感じるのは体がうまく機能しない特殊な場合で、身体が真に機能するとき心身は一体であり、この状態が常態で、苦痛を感じた時にしか心身の幸福な一体感を感じられないことは、皮肉だ。
これは要約問題でありがちなミス。「要約=まとめ」だから一文で書くものと勘違いして、約200字を句点なしで書き切ってしまっている。取り上げている重要語句は模範答案と同じでも、非常に読みにくく減点される答案。
身体が真に機能するとき①心身は一体である。この状態が常態で、通常の日常生活が行われているとき、身体はその「外部性」「存在感」を消失している。
これを幸福な一体感というが人々はこれに気付かない。
ところが、②柱の角に足をぶつけたときや骨折治療用のリハビリテーションで苦痛のうめき声をたてるとき歯科で呻吟(しんぎん)しているとき、身体の外に自分はないということを切実に感じる。
① 課題文の主役である「心身一元論」にはもちろん言及すべきだが、この要約では敵役の「心身二元論」が抜けている。
② 具体例を書きすぎ。要約では具体例はカットするのがセオリー。
原稿用紙の使い方&小論文のルール
小論文では、記述上のルールや原稿用紙の使い方を正しく守ることが求められる。正しい形式を理解し、基本的な減点を防ごう。
●適切な段落分けを意識しよう
小論文をわかりやすく展開するには、適切な段落分けがポイントになる。
段落分けをどのようにしていいのかわからないという人も多いかもしれないが、それほど難しくはない。
典型的には、まず〈課題文要約〉〈序論〉〈本論〉〈結論〉で分ける。
また、本論は長いので、内容のまとまりで段落分けすることを意識しよう。
●倒置法や比喩などの文学的表現は使わない
小論文は小説や随筆などの文学ではなく、説明文。
そのため、文学作品やエッセイなどで頻繁に用いられる倒置法や比喩、体言止めなどの技法は使わないのが基本的なルールだ。
●促音、拗音、句読点、かっこなどは1マス使う
原稿用紙の基本的なルールとして、「っ」などの促音、「ゃ」、「ょ」などの拗音、「、」などの句読点、かぎかっこなどは1マスを使って書かなければならない。
ただし、例外は、句読点や閉じかっこが原稿用紙のいちばん上のマスに来てしまう場合。
句読点や閉じかっこはいちばん上のマスにもってくることができないため、この場合に限り、前の行の最後のマスに記入してもOKとされている。
●小論文として適切な日本語を使う
小論文の文章は「だ」「である」調で記述するのがルール。
丁寧な印象を与えようと「です」「ます」調で書いてしまう人もいるが、小論文のルールからは外れている。
●カタカナ語の使い方に注意
日常的な文章や会話では、「リスペクト」「インパクト」などのカタカナ語がよく使われるが、日本語で置き換えられる表現がある場合、小論文では、これらのカタカナ語の連発は避けよう。
もちろん、「ビジネス」「マーケティング」「コンプライアンス」などのように日本語として定着している表現ならOKだが、意味をよくわかったうえで使っていることを示すため、文章全体のどこかで、別の日本語表現で言い換えるとかっこいい。
●略語は基本的に使用NG
小論文では略語は使わないのがルール。
「スマホ」「コンビニ」「就活」など日常語として定着している言葉は、ついそのまま書いてしまいがちだが、「スマートフォン」「コンビニエンスストア」「就職活動」と書くのが正しい。
また、「WHO」「UN」など公的機関名も「世界保健機関」「国際連合」と正式な日本語名で書くのが原則。
ただし、問題文に略語で記載されている場合は、略語で表現しても大丈夫。
その場合は、文中で表記を統一するように注意しよう。
●口語体(話し言葉)は使わない
「だから~」「(接続語としての)あと~」「~なのに」「いろんな」といった口語体(話し言葉)は小論文にはそぐわないので使わないようにしよう。
これらの表現はすべて、「したがって~」「また~」「~だが」「様々な」といった文語体に置き換えられる。
●擬態語や擬音語を使わない
「ギリギリ」「コツコツ」「イライラ」「テキパキ」などの擬態語や擬音語は小論文では使わないのがルール。
それぞれ「直前まで(限界まで)」「堅実に」「苛立つ」「迅速に」などの表現に置き換えることが可能だ。
●重複表現に注意しよう
「違和感を感じる」「すべてを一任する」などの重複表現はつい無意識に使ってしまいがちなので注意が必要(「違和感を覚える」「一任する」が正しい)。
日常会話で使う表現としても間違っているので、普段から気をつけよう。
●同じ言葉の多用に注意しよう
あるテーマについて論じる文章中では、意識していないとつい同じ言葉やほぼ同じ意味の言葉(近接同語)を多用してしまいがち。
しかし、一文のなかに同じ言葉が何度も出てくると、文章が不必要に長くなるうえ、単調な印象を与える。
なるべく、言葉が重ならないように工夫して文章をまとめよう。
小論文の評価基準
小論文で高得点をねらうには、どのような観点で評価されるのかを知っておくことが重要だ。
小論文の評価は、通常、「理解力」「構成力」「発想力」「表現力」の4つが重視される。
理解力とは、設問や課題文、資料の内容を正しく理解できているかどうか、構成力とは、序論→本論→結論の構成がしっかりとできているかどうか、発想力とは自分なりの意見がしっかりと示されているか、表現力とは、正しい日本語表現で記述されているかどうかということだ。
それらを踏まえ、重要な評価基準となるものを3つ紹介しよう。
序論→本論→結論の構成がしっかりとできているか
「構成力」「発想力」にかかわるポイントとしては、以下のようなものがある。前述のように鍵を握るのは序論。
序論でその小論文の方向性をしっかり提示できているかが問われることを意識しよう。
なお、序論で結論まで言ってしまっている場合は、最後の結論がなくても減点にはならない。
設問の趣旨にしっかりと答えているか
「理解力」にかかわるポイントと重要なのは、設問の趣旨にしっかりと答えているかどうか。例えば、『Aという問題について、賛成の立場から論じなさい』という設問条件に対して、『いや、自分は反対なので、その立場から論じたい』というのはNG。
問われているのは、自分の持論や思想ではなく、あくまで設問条件に応える柔軟な思考力なのです」
誤字・脱字、表現の誤用などがないか
「表現力」にかかわる部分では、誤字・脱字や表現の誤用などは一つ一つが減点対象になる。例えば、本来は否定的な表現で使う「美辞麗句」という言葉を肯定的な意味で使う、あるいは、「汚名挽回」(正しくは汚名返上)など間違った表現を使うといったミスで減点を重ねるのは避けたいところ。
自信がなければ無理して難しい表現を使わないほうが無難だ。
小論文の評価基準チェックリスト
小論文の評価基準について、主なものは前述した通りであるが、それ以外にも細かな評価基準が存在する。
ここでは、それらをまとめて紹介するので、推敲の際になどに活用してほしい。
|
表記・表現に関する評価基準 |
文字量 |
・規定の文字量を満たしているか。 規定の8割以上を満たしていれば問題なし。 |
| 文体 |
・「だ・である」に統一されているか。 「です・ます」が混在していると小幅減点。 |
|
| 表現 |
・「話し言葉」「略字」「漢字間違い」「誤字・脱字」「ら抜き言葉」などがないか。 それぞれ小幅減点の対象となる。 |
|
| 文字の 丁寧さ |
・読みやすいきれいな文字で書かれているか。 判読が難しいほど極端に汚い字などは大幅減点の可能性あり。 |
|
| 主語 ・ 述語 |
・文章の主語・述語が明確か。 主語・述語が不明確な文が多いと、トータルな表現力の評価で大幅減点の可能性あり。 |
|
| 文の長さ |
・一文が長すぎないか。 読みにくさや主語・述語関係の不明確さにつながる場合、大幅減点の可能性あり。 |
|
| 原稿用紙の 使い方 |
・段落の冒頭で一マス空けるなど、基本ルールが守られているか。 小幅減点の可能性あり。 |
|
| 指定外の記述 |
・指定されていないのに本文スペースにタイトルや名前を記入していないか。 小幅減点の可能性あり。 |
|
|
全体に関する評価基準 |
答案の 趣旨 |
・設問の趣旨にきちんと応えているか。 例えば、「課題文に対して反論しなさい」という出題に対して、答案が反論になっていない場合などは大幅減点。 |
| 意見 |
・全体を通して一貫した自分の意見・主張を展開できているか。 何が言いたいのかわからない場合、一般論なのか自分の意見なのかが不明瞭な場合、論文としての妥当性を欠く暴論などは大幅減点。 |
|
| 構成 |
・序論・本論・結論が明確に段落分けされているか。 各段落の役割が不明瞭な場合、序論が明確でない場合などは大幅減点。 |
|
| 論理性 ・ 客観性 |
・意見・主張に対する根拠や理由が示されているか。 意見・主張だけで裏付けとなる客観的事実や統計データ、または考えられる反論などが盛り込まれていない場合は大幅減点。 |
|
| 基礎教養 |
・受験する学部の学問に関する基礎教養があるか。 その学部を志望するなら当然知っているべき基礎知識、あるいは社会常識と言えるレベルの知識がないことが読み取れてしまうと減点対象。 |
|
小論文の得点アップのコツ
評価基準を理解したうえで、得点につながる具体的な工夫を知っておこう。対策から本番まで活用できる、小柴先生直伝の得点アップのコツを紹介する。
小論文は満点を目指さなくてもいい
小論文は、ほかの試験科目と比較しても、相対的に高得点をねらうのが難しい。一つの正解があるわけではないから、上記のような評価基準に十分注意を払ったとしても、必ずしも完璧に到達できるとは限らない。
だから「あえて満点を目指さない」というのが実は大事になるポイントだ。
例えば60分以内に2000字の課題文を読んで、要約もして、800字の意見論述もするとなると、まったく時間に余裕はありません。
それだけに、満点を取ろう!と力が入りすぎると、時間配分を誤って、意見論述を書き切れないで終わってしまい、大幅減点になってしまうということにもなりかねません。
小論文は100点満点で50点以上取れれば平均点を上回り、ギリギリ合格ラインを越えられることが多い科目。
少なくともそのラインを越えることを目標にすれば、落ち着いて臨めるはずです」
要約に十分な時間をとる
上で説明したように時間に余裕はないから、どのように時間配分するかは非常に重要になる。制限時間のうち、要約に何分かけられるか、意見論述に何分かけられるかはあらかじめイメージして臨むようにしたい。
一般的に意見陳述がメインで要約はサブという先入観があるので、要約はできるだけ早く終わらそうと焦ってしまいがちですが、課題文を読んで要約するのはどうしても時間を要する作業。
だから実は時間をかけていいんです。
要約に制限時間の半分、場合によっては6割の時間を割いても大丈夫。
要約自体が、意見論述の準備にもなっているので、残り4割で意見論述をまとめることは十分可能です」
課題文では結論部分を先読みする
時間配分を意識しながら課題文を読んで内容を理解するのは大変なこと。だからこそコツを押さえて効率的に読むことがポイントだ。
次に、課題文を頭から読むのではなく、本文ラストの結論から読むのも有効な方法です。
そこが一番大事なポイントであることが多いですから。
そして、要約問題があるなら、その結論をまとめたものを先に書いてしまうのも効率的です。
要約は課題文の流れに合わせて頭から書いていくと、つい長くなって、最後に一番大事な結論を書くのに文字数の余裕がなくなってしまうことがあります。
要約は課題文の流れとは異なって結論を最初にもってきてもまったく問題ありません。
ですから、結論を先読みして、先にそこだけ要約してしまうのはおすすめの作戦です」
小論文の対策、練習方法
小論文は一朝一夕で書けるようになるものではなく、計画的な対策と反復練習が重要。ここでは、基礎力を養いながら実践力を高めていくための効果的な学習法を紹介する。
志望校の過去問をチェックする
小論文は、すでに説明したように、大学・学部によって出題形式が分かれる。だから、志望校の過去問は可能な範囲でさかのぼって、課題文型なのか図表型なのかミックス型なのかテーマ型なのか、文字数や制限時間はどうなのかをしっかりチェックするのは必須だ。
メモの取り方を練習する
過去問や問題集を使って小論文のトレーニングをする際には、しっかり制限時間を設定して取り組むことが大切。その際、効率的なメモの取り方もしっかり練習しておくようにしよう。
本番でメモを丁寧に書きすぎて、時間をムダにしてしまう失敗例も意外と多いからだ。
メモはあくまでメモ。
後から見て、内容が思い出せるようキーワードだけ記しておけばいい。
例えば、
「序論 国際化 人口減 年功給→能力給必須」
「本論 年功制の背景 新卒一括採用・終身制・定年制 日本的経営 人口増加=労働力人口増・消費人口増→国際化・少子化・人口減少 国際社会からの人材獲得 変化は必然」
「データ GDP世界3位 1人あたりGDP OECD下位」
こんな具合で十分だ。
書いたものは第三者に見てもらう
小論文は、問題集の模範解答と自分の答案とを比較しても、自分の答案のどこが改善すべきポイントなのかはよくわからない。自分一人では対策が難しい試験科目だ。
だから、書いたら第三者に評価してもらうことが大切。
一番いいのは学校または予備校の国語の先生に添削してもらうこと。
それが難しくても、書きっぱなしにはせず、少なくとも保護者や国語の得意な友だちなどに見てもらうと、何かしらのフィードバックは得られるはず。
「話が入り組んでて何が言いたいのかよくわからない」
「結論が唐突な感じがする」
「ここはさすがに漢字で書きなよ」
「ここの文章長すぎて読みにくい」
「すごくわかりやすくなった」
といった反応が返ってくるだけでも、気づきにつながることがよくある。
小論文対策におすすめの記事をピックアップ!
この記事では、小論文の大事なポイントを総ざらいしてみた。
知らなかった、意識していなかったことが見つかった人も多いのでは?そうなれば、あとは、トレーニングあるのみ!
最後に、小論文対策に本腰を入れていきたいキミのために、役に立つ記事をまとめて紹介しよう。
序論の書き方をマスターしたいなら
小論文の序論、本論、結論の中でも、重要な役割を果たす序論。小柴先生も「最も重視して対策を行うべき」と話す序論の書き方について、より詳しく解説されているのがこちらの「書き方マニュアルⅡ・Ⅲ」だ。
序論がうまく書ければ加点が得られる可能性もぐんと高まる。
小柴先生直伝の書き方のポイントと例文をチェックしよう!

大学入試での出題傾向をチェックしたいなら
小論文の基本を理解したら、次に、志望する大学でどのような形式の小論文が出題されるのか確認し、対策を進めていく必要がある。大学入試での小論文の出題傾向、テーマ型小論文、課題文読解型小論文、資料分析型小論文の違いから、それぞれの対策方法まで、詳しく解説されている。

学部ごとの対策を強化したいなら
大学入試の小論文では、学部の内容に関するテーマが出題されることも多い。
志望学部・学科に関連する基礎的な教養や時事的な知識はしっかり身につけておこう。
過去の出題傾向や話題の出来事などから、学部・学科ごとにねらわれやすい頻出テーマを小柴先生が解説。
さらに、それらのテーマの理解を深めるのに役立つおすすめ本も紹介されている。
●文学部、国際・外国語学部
【文学部、国際・外国語学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
【心理学系分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
【外国語分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
●法学・政治学部、経済学・経営学部
【法学・政治学部、経済学・経営学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
【法学政治学分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
時事問題を1冊でおさえる!小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
●理学・工学部、農学・水産学・畜産学部
【理学・工学部、農学・水産学・畜産学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
●医学部、看護・医療系学部、スポーツ学部
【医学部、看護・医療系学部、スポーツ学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
【医学系分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
.gif?20260203)
取材・文/伊藤敬太郎 監修/小柴大輔 構成/寺崎彩乃(本誌)※2025年7月更新 \この分野の推薦入試を受ける人必見!/
【文学部・芸術学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【法学部・政治学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【家政学部・栄養学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【社会学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【教育学部・児童教育学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【国際学部・外国語学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【家政学部・栄養学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【医学部・薬学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き >
【農学部・生物学部・水産学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【情報・データサイエンス・IT系学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【獣医学部・動物看護学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【建築学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
※無料会員登録で読めます