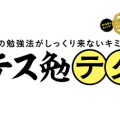高校生の読書感想文おすすめ本52選│書きやすい、短い、おもしろい!本の選び方【2025年】
読書が苦手な人でも、サクサク読める!楽しく読める!すぐに読める!そして、読書感想文が書きやすい!そんな選りすぐりの本を、一挙52冊紹介しよう。
さらに、読書感想文が書きやすい本の選び方や書き方のポイントを、スタディサプリ講師で小論文のプロ、小柴大輔先生が解説。
読書感想文の宿題に困っている高校生に役立つ内容が満載なので、今すぐチェックしよう。
目次
小柴大輔先生
.jpg?20260203)
Z会東大進学教室で講師を務めるほか、ロースクール(法科大学院)受験の予備校においても一般教養小論文を指導している。
感覚ではなく論理的に答えを導く指導に定評があり、「現代文に対するイメージが変わった」と受験生から圧倒的な支持を集めている。
スタディサプリでは、現代文のほか、小論文や総合型選抜・学校推薦型選抜対策講座を担当。
読書感想文が書きやすい本とは?

短ければ「全部読めるのだろうか」と心配する必要がなく、興味があれば「これならわかるかも」「これ、知りたかったんだ」などと手に取りやすい。
境遇が近ければ、主人公や作者に共感しやすく、あるいは「自分だったらどうする」など、感想文に書ける意見が出てきやすくなるはず。
また、本屋大賞や直木賞などの受賞した本、映画やアニメの原作などの有名な本は、あらすじや書評などの情報がネット上にもたくさんある。
こういった情報を参考にすることで自分の意見がまとまり、感想文が書きやすくなるだろう。
短編集なら読書が苦手でも読みやすい
「本を1冊読むなんて無理!」ということなら、短編集のなかの1作だけ読むという方法もある。短編といえども、起承転結があり深いテーマを描いているものもあり楽しく読める。
恋愛やSF、ミステリーなど、想像がふくらむものなら、さらに読みやすく感想も書きやすいのではないだろうか。
「星新一のショートショートを超える短編集『100文字SF』(北野勇作/早川書房)もおすすめです。
また、どうしても本が読めない、読む時間がないという人は、朗読CDやオーディオブックを利用するという手も!
星新一の『ひらめきの法則』(新潮社)の朗読CDは50分。
朗読だけではなく小説をラジオドラマ風にしているものもよいでしょう。
知っている映画や芝居のノベライズや脚本もありです」(小柴先生)
自分の興味関心がある本を選ぶ
趣味や部活動、これからかかわってみたいことなど、自分が好きなことなら本の内容も理解しやすく自分の考えと比較して書けるのではないだろうか。自分の興味関心が何か明確ではない人は、幼少期からどんなものに興味をもってきたか思い出しながら書き出してみよう。
家族に、自分が小さいころの話を聞いてみるのもよい方法だ。
「趣味、興味関心を明確にしておくことは、学校推薦型選抜の面接や志望動機書を書くうえで非常に大切です。
面接では、読んできた本の内容や感想を聞かれることがあります。
また、最近は猫など動物やペットの話題も多いので、好きな動物をテーマにした本も読みやすいのでは。
夏目漱石の『吾輩は猫である』は名作ですが、小説だけではなくさまざまなパロディや論文なども出ています」(小柴先生)
「愛」は人が生きるうえで必要不可欠なものだ。
愛はよろこびを与え、時には欲するあまりエゴが働き苦しめることも。
そんな「愛」をテーマにした小説や評論はたくさんあり、共感することも多いだろう。
「人は愛されることで、愛することを学ぶ」はアシュリー・モンタギューの名言ですが、『「愛」という名の優しい暴力』(斎藤学/扶桑社ブックス)というドキッとするタイトルの本もあります。斎藤さんは精神科医です。
慶應大学文学部の総合型選抜公募制の試験で、この言葉に対して自分はどう考えるかを記述する小論文課題が出題されています。
自分の考えと比較しながら書くとよいでしょう」(小柴先生)
自分と同じ環境や境遇なら共感することも多く、主人公に自身を投影しやすい。知っているから感想も書きやすいだろう。
「自分の境遇とは反対、または遠いテーマの本を読んで、共感できる可能性を探るのも方法です。
自分だったらどんな行動をするだろうか、自分だったらどんな感情だろうか、など、こちらも比較を書くことで深みのある感想文となります」(小柴先生)
日本のアニメは世界に誇る文化であり、日本の漫画のクオリティーは非常に高い。
このアニメや漫画の歴史や文化の研究書は多く、精神分析やマーケティングなどテーマもさまざまだ。
「なぜあの漫画はおもしろいのか」など、自分流に解析してみるのもおすすめだ。
「特撮ヒーローや妖怪などの研究書もあるので、自分が好きなアニメや漫画をテーマにしている本を読みながら、自分なりの考察を書くのも楽しいのでは」(小柴先生)
迷ったら課題図書から選ぶ
課題図書とは、読書感想文コンクールの主催団体などが、学年ごとに選定した推薦図書のこと。「高校生が今、向き合っておくとよいテーマ」が意識されて選ばれており、内容の深さと読みやすさのバランスがとれているものが多くそろっている。
「課題図書は、読みやすくて高校生が興味が持ちやすく、意見を出しやすい内容のものが多いです。
『何を読んだらいいかわからない』という人には、入り口としておすすめ。
興味のあるものがあれば、ぜひ手にとってみましょう」(小柴先生)
高校生が読みたい!読書感想文おすすめ本52選
では、読書感想文のおすすめ本を紹介しよう。今話題の本、現代社会を論じた本、スタディサプリLIBRARYなどのなかから、高校生の読書感想文におすすめの本を、小柴先生とスタディサプリ進路編集部が厳選。
ぜひ参考にして「これぞ!」と思える自分の本をみつけよう。
時間がない時におすすめ!短い、すぐに読める本 5選
読書感想文の宿題を後回しにしてしまい「もう時間がない!」という人もいるかもしれない。そんな高校生の救世主! 短い本や一部だけ読んでも読書感想文が書けそうな本など、すぐに読める本を紹介しよう。
また、過去に「読んだことがある」「聞いたことがある」ものであれば、なおさら内容を理解しやすいので、試験や模試で出題されたことがある文章もおすすめだ。
小論文対策にもなるので一石二鳥と言えるだろう。
『100文字SF』北野勇作/著(早川書房)

たった100字で無限の時間と空間を創造する、まったく新しいSF。
「Twitterよりも短文ですので、本が苦手で読めないという人でもサクサク読めます」(小柴先生)
『ラ・ロシュフコー箴言(しんげん)集』ラ・ロシュフコー,F./著 二宮フサ/翻訳

「恋は燃える火と同じで、絶えずかき立てられていないと持続できない。だから希望を持ったり不安になったりすることがなくなると、たちまち恋は息絶えるのである」
など、愛・友情・勇気など美名の下にひそむ打算・自己愛を1、2行の断言であばき、読者を挑発する。
人間の真実を追求するフランス・モラリスト文学の最高峰。
★Amazonで詳細を見る
「『100文字SF』よりもさらに短い文章。
全て読むのではなくどれかひとつの言葉を選んで、自分ならどう考えるのか、賛成でも反対でも自分の意見を述べるとおもしろいでしょう」(小柴先生)
赤ずきんちゃんの比較『グリム』と『ペロー』
『完訳 ペロー童話集』新倉朗子/訳(岩波文庫)
★Amazonで詳細を見る
『完訳 グリム童話集1』 金田鬼一/訳(岩波文庫)

「誰もがよく知っている赤ずきんの童話には、グリム版とペロー版があります。
この二つを比較して、何が違うのか、なぜ違うのか、自分だったらどんな話にするのか、などを書いてみましょう。
巻末の解説も参考になります」(小柴先生)
『友だち地獄 ─「空気を読む」世代のサバイバル』土井隆義/著(筑摩書房)

「空気を読む」という高度で繊細な気配りの人間関係を解説。
「『次の文章を読んで、「集団の中で独りでいること」の積極的な意味について論じなさい。(320字以上400字以内)』と本文の一節が小論文で出題されました。
この出題の解答として、文章を書いてみましょう。毎日の学校生活の中で感じていることなので、共感しやすく、考えを言語化しやすいでしょう」(小柴先生
読書が苦手でもおもしろく読める本5選
本を読むのはちょっと苦手…そんな人にこそ手に取ってほしい、おもしろく読める本を紹介しよう。
文章がやさしい、テーマが身近、思わず続きが気になる、など、ストレスなく読み進められるものばかり。
感想文の題材としてはもちろん、ちょっとした息抜きの読書にもぴったりだ。
『読みたい心に火をつけろ!学校図書館大活用術』木下通子/著(岩波ジュニア新書)

そんな生徒の「読みたい」「知りたい」に応える様子を具体的なエピソードとともに紹介。
同時に,長年学校司書として活躍してきた著者が本を読む楽しさや意義をビブリオバトル等、豊富な実践をもとに語っている。
「筆者は東洋大学国文学科卒、埼玉県立春日部女子高校司書から浦和女子高校司書となった著者は、知的書評合戦『ビブリオバトル』の普及活動にも取り組んでいます。
2020年から制度がスタートした社会教育士でもあり、地域、特に子ども食堂など子どもの居場所への本の普及にも尽力。
ネットで公立図書館や国会図書館の図書が検索できるという情報は貴重。
岩波ジュニア新書は中学生でも読みやすい新書で、本が苦手でも読み進められます」(小柴先生)
『言語学バーリ・トゥード: Round 1 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか 』川添 愛/著(東京大学出版会)

曖昧さや冗談、遠回しな言い方、婉曲表現など、私たちが日常で無意識に使っている言葉の“空気”を、AIや言語学の視点からユーモラスに掘り下げていく。
かの東京大学出版会のPR誌『UP』の人気連載を書籍化。これほど笑える言語学エッセイはなかなかありません。
タイトルの「バーリ・トゥード」はポルトガル語で「なんでもあり」を意味し、著者はコアなプロレスファンとしても知られています。
ユーモアたっぷりでありながら内容は模試や入試にも頻出。読んでおけば、思わぬ場面で役立つかもしれません。
扱うテーマが日常に身近なので、感想文も書きやすいはずです。(小柴先生)
『読んでいない本について堂々と語る方法』ピエール・バイヤール /著 大浦 康介 /訳( 筑摩書房)

“完全な読書”という幻想を疑い、読書そのものの意味を問い直す内容となっている。
著者はフランスの大学教授・精神分析学者であり、本書は慶應SFCの小論文でも取り上げられました。
「そもそも“完全な読書”など存在しない」と説く本書は、読書そのものに対する見方が変わる、非常に刺激的な読書論です。
“読まないで語ることこそ教養”という大胆な主張は、30以上の言語に翻訳されたことからも世界的な注目度がうかがえます。
読書感想文でもそのまま活用しやすく、読んでいなくても、あるいは少し読んだだけでも、どこまで書けるかチャレンジしてみてください。
読書が苦手な人にこそ、気軽に手に取ってほしい一冊です。(小柴先生)
『社会学が面白いほどわかる本 大学一冊目の教科書』大野哲也/著(KADOKAWA)

身近なテーマを通じて、社会のしくみや考え方を自然に理解できるよう構成されている。
「大学で社会学を学ぶ前の“最初の一歩”のような内容なので、社会学に興味があるならぜひ読んでおきたい一冊です。
筆者は体育学部卒、中学校教諭を経て、青年海外協力隊に参加、大学院で社会学と文化人類学を専攻。
文章もやわらかく図も多いため、読書が苦手な人にもおすすめ」(小柴先生)
『牛車で行こう!─平安貴族と乗り物文化』京樂真帆子/著(吉川弘文館)

牛車の構造やマナー、階級ごとの乗り分けまで、当時の“乗り物文化”を通して、平安貴族の価値観や日常生活が見えてくる。
「実は、牛車の中にもちゃんと序列があり、それを現代の車にたとえて紹介しているので、とてもイメージしやすく、おもしろく読めます。
例えば、最上位の唐車はベンツ、檳榔毛車はクラウン、網代車はアクアといった具合です。
牛車のマナーや乗り降りの作法などもわかりやすく解説されていて、歴史が苦手な人でも気軽に楽しめます」(小柴先生)
小柴先生厳選!最新本8選
小論文の神、年間100冊以上読む読書のプロである小柴先生。そんな先生が、今年読んだ本のなかで「本当におもしろい!」と感じただけを厳選して紹介する。
高校生が読書感想文に書くなら、どんなところに注目して読んだらいいのか、アドバイスをもらった。
「難しいと感じるかもしれないけれども、全部読み切らなくても、理解しきれなくても、本文の1行だけでも読んだのなら、それが読書です。
わからなかった、自分とは相容れない、自分だったらこう考える、というのも立派な感想です。
また、読書は先人の意見に触れる体験でもあります。
意見から自分の考えを発展させることが大切です」(小柴先生)
『やんごとなき読者』アラン ベネット/著 市川 恵里/訳(白水社 )

読書がもたらす気づきと変化を、ユーモアたっぷりに描いた英国のベストセラー。
「女王エリザベス二世が齢70を過ぎて読書に熱中し始めるフィクション。
宮廷の人々がその読書熱を嫌がる様子や、イギリス首相・フランス大統領への風刺もユーモアたっぷりで楽しく読むことができます。
しかし物語の根底には、女王を通して「読むこと」の意味を問いかけられるような、読書の本質的な意義が流れています。
2007年に原書が英米で出版されると、『タイムズ』『オブザーヴァー』『ニューヨーク・タイムズ』などで絶賛され、ベストセラーに。
読書感想文としては、女王と自分との“本との向き合い方”を比較する切り口で書くのもおすすめです」(小柴先生)
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』三宅 香帆/著 ( 集英社)
.jpg?20260203)
本を読むとはどういうことか、働くことと読むことの関係を静かに問い直す一冊。
新書大賞2025受賞、第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞2024 受賞の話題作。
「著者の三宅香帆さんは、京都大学文学部卒業後、同大学院人間環境学研究科を修了し、IT企業勤務を経て文芸批評家として活動されています。
本書は、日本における労働と読書の歴史を接続しようとする意欲的な一冊。
「なぜ本が読めなくなるのか」という問いに、著者自身の経験を交えて迫っており、自分自身の「読めなさ」と比較しながら読書感想文を書くこともできる内容になっています」(小柴先生)
『積ん読の本』石井千湖 /著 (主婦と生活社 )

作家、翻訳家、研究者、辞書編纂者など12人の本との付き合い方が、写真とともに紹介されている。
「著者は、早稲田大学文学部美術史専修卒。書店員を経て、現在は書評家として活躍する石井千湖さんです。
“読んでいない本がたくさんある”という状態が、罪悪感ではなく、むしろ豊かさに思えてくるような一冊です。
積ん読に悩む人ほど、気が楽になるヒントが見つかるかもしれません」(小柴先生)
『毎日読みます』ファン・ボルム /著 牧野 美加 /訳(集英社)

本を通じて人とつながるよろこびや、読書がもたらすささやかな変化が丁寧に描かれている。
「タイトルからして印象的な読書エッセイで、130冊近くの本が紹介されており、ブックガイドとしても楽しめます。
たとえば村上春樹について「小説よりエッセイの方が好き」と語るくだりがあり、私自身も同じなので思わず頷きました。
本を読むこと、そして本をきっかけに人とつながることのよろこびが全体ににじみ出ています。
また、本の内容を語るだけでなく、読書によって自分の内面がどう変化したかを言葉にしていく方法も紹介されており、感想文を書く上でも大いに参考になる一冊です」(小柴先生)
『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです─村上春樹インタビュー集1997~2011』村上春樹/著(文春文庫)

公の場に出ないという印象を与える村上春樹。
1997年から2011年までの19本のインタビューで知る作家の素顔と思想。
「筆者は早大文学部卒の、ノーベル文学賞に一番近い作家です。
海外メディアからの取材多数収録し、日本と海外における村上春樹の評価の違いを比較できます。
文藝春秋社の『猫を棄てる─父について語るとき』もおすすめです。
半端な自伝エッセイではありません。村上文学のルーツを知ることができます」(小柴先生)
『あらゆることは今起こる 』柴崎友香/著( 医学書院 )

40歳でADHDと診断された作家・柴崎友香が、自身の違和感や困りごとをたどりながら、その正体に向き合っていくエッセイ。
「目が覚めた」と感じた診断後の日々を通して、発達障害の理解と、自分自身を知ることの大切さが描かれている。
「著者は、2014年に『春の庭』で芥川賞を受賞した柴崎友香さんです。
本書では、40歳でADHDと診断された自身の経験をもとに、子どものころから感じていた違和感や生きづらさを丁寧に振り返っています。
処方薬によって「36年ぶりに目が覚めた」と語るくだりも印象的で、注意欠陥多動性障害(ADHD)についての理解を深めるきっかけにもなります。
少しずつ自分を知っていく過程をたどるこの作品は、特別な世界をもつ人のまなざしを通して、自分ならどう感じるかを考える手がかりにもなります」(小柴先生)
『みんな水の中-「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか 』横道 誠/著( 医学書院 )

「発達障害」のラベルの向こうにある、脳神経の多様性=ニューロダイバーシティのリアルな内側を描き出す。
「著者は、京都府立大学准教授として比較文化・西洋思想を専門に教える横道誠さんです。
40歳でASDとADHDの診断を受け、本書ではその経験を起点に、自身の内面や社会との関わりをとことん正直に綴っています。
『そこまで書かなくても』と思うほどの赤裸々な告白が続きますが、それこそがこの本の魅力でもあり、これまでにない当事者研究としての意義を持っています。
特別な世界観をもつ人の語りを通して、自分はどう感じたか、何を考えたかを書きやすく、読書感想文にも向いています」(小柴先生)
『バカロレアの哲学 「思考の型」で自ら考え、書く 』坂本 尚志 /著(日本実業出版社)

「芸術はわれわれに何を教えるのか」などの問いに対し、自分の考えを言葉にするためのヒントが詰まっている。
「フランスの大学入試(バカロレア)では、『哲学』という教科で小論文が課されます。
たとえば『仕事・職業は人々を分断するか』『芸術はわれわれに何を教えるのか』『自然は人間に対して敵対的であるか』など、お題はさまざま。
本書は、こうしたテーマに対して、どのように思考を組み立て、どう書き進めるかを丁寧にガイドしています。
読書感想文にも応用できるので、読んだあとに自分でも文章を書いてみるのもおすすめです」(小柴先生)
時事問題、社会課題について考える本 16選
時事や社会問題をテーマにした本は、タイムリーな話題でもあり、またネット上でも議論が繰り広げられているなど、読書感想文に必要な素材は多い。自分だったらどう考えるのか、ネット上にあった意見などを本文と比較しながら読み進めてみよう。
vol.1 ジェンダーについて考える
令和では、性差による差別はタブーであることが当たり前の認識だが、ジェンダーをテーマにしたドラマが国営放送で放送されるなど、解決されていない課題があるからこその現象だろう。読書感想文のテーマにするのなら、こうしたドラマでのシーンや、実際に自分が経験したことなどを交えると書きやすい。
『少女マンガジェンダー表象論〈男装の少女〉の造形とアイデンティティ 新増補版』押山美知子/著(アルファーベータブックス)

新増補版として電子版『RE:BORN ~仮面の男とリボンの騎士』(集英社ホームコミックス)を取り上げ、〈男装の少女〉サファイアの表象の変容について論じる。
「著者は東京女子大日本文学科卒、専修大大学院日本語日本文学専攻博士課程修了。本書で第3回女性史学賞。
手塚治虫の『リボンの騎士』、池田理代子の『ベルサイユのばら』を中心にした、日本における女性性・男性性の描かれ方の分析をしています。
図版多数で楽しく読めます」(小柴先生)
『虹色チェンジメーカーLGBTQ視点が職場と社会を変える』村木真紀/著(小学館新書)

「企業や自治体での性的マイノリティへの施策を先導してきた事例のまとめとレズビアンとしての自身の半生の記録。
この分野での先進的で企業の社会的責任を果たす事例として、野村證券、ゴールドマンサックス、ソニー、ライフネット生命、資生堂、楽天、みずほ銀行、、LIXIL、オムロンなどが掲載されています。
自分が気になる企業の事例について、自分の考えを書いてみては」(小柴先生)
『トランスジェンダー入門』周司 あきら・高井 ゆと里/(集英社新書)

トランスジェンダーについて知りたい当事者およびその力になりたい人が、最初に手にしたい一冊。
「本書はこの分野の日本初の入門書。
単に性的マイノリティの問題ではなく、この社会を知的に捉え直し、すべての人が人生の納得いく選択ができるための、すべての人の人権上の問題として読んでほしいと思います」(小柴先生)
『女の子はどう生きるか─教えて、上野先生』上野千鶴子/著(岩波ジュニア新書)

社会に潜む差別や刷りこまれた価値観を洗い出し、ひとりひとりが自分らしい選択をする力、知恵や感性を磨くための1冊。
「著者は、1948年生、京大文学部卒、同大学院社会学専攻博士課程修了。
東大教授、東大副学長。日本におけるフェミニズムのリーダー的な社会学者です。
ベストセラーで映画化もされた吉野源三郎『君たちはどう生きるか』が結局のところ、男子の生き方を問うているのにすぎないことへの抵抗から生まれた本で、約50の女子中高生の質問に応える形式となっています。
同じ筆者の本では『上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください!』(大和書房)があり、こちらもおすすめです」(小柴先生)
vol.2 AI・技術革新、教育について考える
ネットでも話題になっている生成AIの問題や、理系vs文系の話題など、世論が政府を動かし始め、ジワジワと私たちの生活に影響を及ぼしている。読書感想文は生成AIで書く方法はあるのだろうか?と少しでも思ったのなら、読んでみてほしい。
『AI vs 教科書が読めない子どもたち』新井紀子/著(東洋経済新報社)

しかし、"彼"はある一定のレベルの大学の合格水準には達していた。
これが意味することとはなにか? AIは何を得意とし、何を苦手とするのか?
「AIにできない種類の仕事をすれば人間は生き残れる」の幻想を打ち砕く内容。
「著者は、一橋大学法学部卒、イリノイ大学数学科卒、同大学院単位取得退学、理学博士、国立情報学研究所教授。
専門は数理論理学。パターンの抽出と確率統計によるAIは言葉の意味を理解できないとしています。
東ロボくんのマーク模試・東大模試の講評があり興味深い内容です。
カーツワイルのシンギュラリティ予測には懐疑的」(小柴先生)
『AIに負けない子どもを育てる』新井紀子/著(東洋経済新報社)

日本中で騒然の書『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』、待望の続編。
AIが苦手とする読解力を人間が身につけるにはどうしたらいいのか?
★Amazonで詳細を見る
『ロボットは東大に入れるか 改訂新版』新井紀子/著(新曜社)

「天声人語」ほかで紹介された、人工知能「東ロボ」くんのその後のすべて。
ベネッセ模試、代ゼミの「東大プレ」における成績の最新データから、AIの最新技術とその得意不得意も明らかに。
そして、はたして私たち人間の能力とは?
★Amazonで詳細を見る
『科学者はなぜウソをつくのか─捏造と撤回の科学史』小谷太郎/著(インプレス)

科学史に残る「過ちの瞬間」を「撤回論文」を軸に振り返り、「科学者の夢」に迫る。
「筆者は東京大学物理学科卒、理化学研究所勤務、NASA研究員を経て、大学教授。
2014年の小保方晴子氏によるSTAP細胞作成の論文ねつ造事件や、論文撤回本数が現在世界第1位の東邦大准教授藤井善孝の医学論文ねつ造などが事例として掲載されています」(小柴先生)
『サイエンス・フィクションズ─あなたが知らない科学の真実』スチュアート・リッチー/著(ダイヤモンド社)

「著者はキングス・カレッジ・オブ・ロンドン講師、専門は心理学。
過去の有名な研究不正の紹介だけでなく、不正につながりうる論文発表のプロセスにも注目し、再現性の危機、バイアス、誇張、瑕疵などについて述べています。
さらに科学性を救い出すための提言もあります」(小柴先生)
『「文系学部廃止」の衝撃』吉見俊哉/著(集英社新書)

理系偏重の学部再編を推し進める「官僚の暴走」により、近代日本の教養の精神はここに潰えてしまうのか?
大学論の第一人者が驚愕の舞台裏を語る。
「『役立つ学問』偏重の文部科学省や政治家への反論。
文系学部は『役立たないが重要』どころか『長期的本質的レベルではっきり役立つ』と提言しています。
慶応大学文学部の推薦入試の小論文で登場しました」(小柴先生)
vol.3 戦争と平和について考える
日本は今のところ憲法9条により「戦争を放棄」する形になっているが、世界では戦争を外交の課題解決の手段として用いる国が存在する。ウクライナ侵攻など、最近にわかに身近な問題としてニュースで語られる戦争。
「終戦記念日」がある夏休みは、戦争についての解説番組も多い。
本と同時にそうした番組を見ることで、理解が深まるだろう。
『職業は武装解除』瀬谷ルミ子/著(朝日文庫)

「武装解除」のプロとして、24歳で国連ボランティアに抜擢、30代で各界の注目を集めるに至るまで、いくつもの組織を渡り歩いてきた著者が、その半生をつづる。
「筆者は1977年生、中大総合政策学部卒、英国ブラッドフォード大紛争解決学修士課程修了。
NPO法人日本紛争予防センター理事で、「世界が尊敬する日本人25人」に選出されています」(小柴先生)
『戦争はいかに終結したか 二度の大戦からベトナム、イラクまで』千々和泰明/著(中公新書)

戦争はいかに収拾できるのだろうか。
第一次世界大戦、第二次世界大戦から戦後の朝鮮戦争とベトナム戦争、さらに近年の湾岸戦争やイラク戦争まで20世紀以降の主要な戦争の終結過程を分析。
「筆者は広大法学部卒、阪大大学院国際公共政策研究科博士課程修了、ジョージ・ワシントン大留学。
「紛争原因の根本的解決」と「妥協的和平」、「将来の危険」と「現在の犠牲」、これらの葛藤、ディレンマが主要テーマであり、歴史から学ぶ未来の奮闘解決と予防の知恵を伝えています」(小柴先生)
『空爆論 メディアと戦争』吉見俊哉/著(岩波書店)

ウクライナ侵攻まで一貫してつながる「メディア技術としての戦争」を問い直す。
「著者は東大大学院情報学環教授、東大副学長。空爆には植民地主義のイデオロギーが潜伏していたと書かれています。
空爆の最先端ともいえるドローンの研究が1930年代にまで遡れるのも驚き。
同じ筆者の本として、『トランプのアメリカに住む』(岩波新書)があります。
就任2年間でトランプが発したウソは、ファクトチェックによれば8000件、全発言のうちファクトの裏付けのあるものはわずか4%。
いかなる背景からトランプが大統領に就任でき、今どんな影響を与え、どんなカウンターが出ているか。
なおハーバードと東大の比較も興味を惹かれます」(小柴先生)
『戦争とデータ 死者はいかに数値となったか』五十嵐元道/著(中央公論新社)

その過程で国際的な人道ネットワークが、統計学や法医学の知見を取り入れ、どのように戦争データを算出するようになったか、特に民間人死者数に注目する。
また、データをめぐる人々の苦闘にも光を当てる。
「筆者はサセックス大学大学院国際関係学博士課程修了、関西大学教授。
本書で大佛次郎賞を受賞しました。
戦争での死者(特に文民)数と死因を明らかにする種々の取り組みを解説した本です。
調査結果を真か偽かの二分法でかたづけない〝批判的機能主義〟によりデータの科学的耐久性や社会的信頼性とその機能で評価しています」(小柴先生)
vol.4 環境問題について考える
大地震などの災害や異常気象など、環境問題は私たちの暮らしにも影響を与えており、今世界中が解決に向かい行動しなければならないとされている。テレビの広告や企業説明でよく聞くSDGsなど、環境問題はタイムリーな話題。
自分たちができることは何か、正しい情報を選択するにはどうしたらよいかなど、自分ごととして考えながら読んでみよう。
『新・環境倫理学のすすめ【増補新版】』加藤尚武/著(丸善出版)

環境問題を総合的視点で考察するうえで重要な考え方がよくわかる。
「増補新版」では各章末に新たに「補遺」を加え、現代人が深く考えるためのヒントも提示。
「著者は、東京大学哲学科卒で、千葉大学教授、京都大学教授、鳥取環境大学学長を歴任した環境倫理学や生命倫理学における日本の権威。
この分野の最新のデータと理論をわかりやすくまとめています」(小柴先生)
『災害論 安全性工学への疑問』加藤尚武/著(世界思想社)

「絶対安全」と言われたフクシマ原発事故の原因は、技術体系と責任制度のミスマッチにあった。技術の暴走はなぜ起こり、どうすれば止められるのか。
原発事故の原因究明から復興の倫理まで、未来世代への責任という視点から原発問題を考える。
「3.11の震災と原発事故を踏まえ従来型のリスク論を問い直した、『新・環境倫理学のすすめ』の加藤尚武の本。
この分野の基本文献です」(小柴先生)
スタディサプリLIBRARYのおすすめ本 9選
スタディサプリLIBRARYは、今高校生に読んでほしい本をテーマごとに掲載。未来の「好き」につながるヒントを27カテゴリーに分けて、関連する本を紹介している。
1000冊以上のおすすめ本があるので、自分にぴったりの1冊がきっと見つかるはずだ。
『サピエンス全史』(上・下)ユヴァル・ノア・ハラリ/著、柴田裕之/訳(河出書房新社)

『サピエンス全史』(上・下)ユヴァル・ノア・ハラリ/著、柴田裕之/訳(河出書房新社)
国家、貨幣、企業…虚構が他人との協力を可能にし、文明をもたらした。ではその文明は、人類を幸福にしたのだろうか?
現代世界を鋭くえぐる、40カ国で刊行の世界的ベストセラー。
「20万年分のホモサピエンスの歴史をイッキ読み。
ピュリッツァー賞を受賞した、ジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原体・鉄』(草思社)と併せて読むと、なお理解が深まります」(小柴先生)
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
『せいめいのはなし』福岡伸一/著(新潮社)

『せいめいのはなし』 福岡伸一/著(新潮社)
内田樹、川上弘美、朝吹真理子、養老孟司。好奇心あふれる4名との縦横無尽な会話が到達する、生命の不思議の豊かな深部。
気鋭の分子生物学者にして名文家の筆者。
『生物と無生物の間』(講談社)、『もう牛を食べても安心か』(文藝春秋・狂牛病についての本)『できそこないの男たち』(光文社)など興味深い本をたくさん出している。
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
『ソロモンの指環─「動物行動学入門」』コンラート・ローレンツ/著、日高敏隆/訳(早川書房)

『ソロモンの指環─「動物行動学入門」』 コンラート・ローレンツ/著、日高敏隆/訳(早川書房)
“刷り込み”などの理論で著名であり、「動物行動学」というジャンルをメジャーにしたノーベル医学生理学賞受賞者である動物行動学者・ローレンツが、けものや鳥、魚たちの生態をユーモアとシンパシーあふれる筆致で描いた、永遠の名作。「動物まみれのドタバタ愉快な生活。
動物好きなら読まないわけにはいかないでしょう。
同じ筆者の『攻撃─悪の自然誌』(みすず書房)も近年、復刻版が出版されています」(小柴先生)
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
『世界を、こんなふうに見てごらん』日高敏隆/著(集英社)

『世界を、こんなふうに見てごらん』日高敏隆/著(集英社)
動物行動学者が、生きものと自然のユニークで新鮮な見方を、子どもでもわかる言葉でシンプルに伝える。21世紀に生きるすべての人々に贈る、やさしい自然の魅力発見の書。
「著者はコンラート・ローレンツの『ソロモンの指環─「動物行動学入門」』の翻訳者であり、日本を代表する昆虫学、動物行動学の偉人。
弟子にあたる竹内久美子氏の『女は男の指を見る』(新潮社)、『指からわかる男の能力と病』(講談社)も、目の付けどころが興味深い本でおすすめです」(小柴先生)
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
『ボタニカム─ようこそ、植物の博物館へ』キャシー・ウィリス/著、ケイティ・スコット/絵、多田多恵子/訳(汐文社)

『ボタニカム─ようこそ、植物の博物館へ』 キャシー・ウィリス/著、ケイティ・スコット/絵、多田多恵子/訳(汐文社)
美しいイラスト(ボタニカルアート)と説明文からなる本。細部まで正確な絵と、地球史と暮らしを織り込んだ説明文には、どの展示室でも思わず足を止めてしまうはず。
「私が所有するすべての書物のうち、一番美しい本です」(小柴先生)
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
『ご冗談でしょう、ファインマンさん』(上・下)R.P.ファインマン/著、大貫昌子/訳(岩波書店)

『ご冗談でしょう、ファインマンさん』(上・下)R.P.ファインマン/著、大貫昌子/訳(岩波書店)
日本の朝永振一郎さんと同じ年にノーベル物理学賞を受賞したファインマンの科学エッセイ。「良質な科学論」として、これまでにも多くの人が推薦してきた本。
続編も多数。
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
『コミュニティデザイン 人がつながるしくみをつくる』 山崎亮/著(学芸出版社)

『コミュニティデザイン 人がつながるしくみをつくる』 山崎亮/著(学芸出版社)
行政まかせでも巨大企業の誘致でもない、住民主体のまちづくり・まちの再生の先駆者の本。続編や類書も多数。
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
『ウラからのぞけばオモテが見える 佐藤オオキnendo・10の思考法と行動術』 佐藤オオキ/著 川上典李子/著 日経デザイン/編(日経BP)

『ウラからのぞけばオモテが見える 佐藤オオキnendo・10の思考法と行動術』 佐藤オオキ/著、川上典李子/著、日経デザイン/編(日経BP)
デザイン設計事務所nendoを主宰する、今や世界的デザイナーによるアイデア発想法の本。同じ筆者の本『問題解決ラボ』(ダイヤモンド社)がある。
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
『最強の女 ニーチェ、サン=テグジュペリ、ダリ…天才たちを虜にした5人の女神』鹿島茂/著(祥伝社)

『最強の女 ニーチェ、サン=テグジュペリ、ダリ…天才たちを虜にした5人の女神』鹿島茂/著(祥伝社)
『ツァラトゥストラはかく語りき』『星の王子さま』…歴史に残る傑作誕生の背後には彼女たちの存在があった。世紀末から20世紀のパリ。有名文化人のミューズとなり、自らも燦然と輝いた女たちの壮絶な人生。
「19世紀フランス文学を専門としつつ、博覧強記で知られる筆者の本。
同じ筆者の本としては、タイトルからしてわくわくする『馬車が買いたい』(白水社)、『明日は舞踏会』(中公文庫)などがあります」(小柴先生)
★スタディサプリLIBRARYで詳細を見る
★Amazonで詳細を見る
スタディサプリ講師の著書 9選
「スタディサプリ」にはわかりやすくておもしろい講義をしている講師陣がたくさん。受講生のなかには「○○先生のファン!」という人もいるのではないだろうか。
そんな講師が書いたおすすめの1冊を紹介する。
『暴虐と虐殺の世界史─人類を恐怖と絶望の底に突き落とした英傑ワーストイレブン』村山秀太郎/著(二見書房)

社会思想史と世界史上の事件のつながりがよくわかる。
マルクス、ダーウィン、ルソー、ハイエク、聖書の入門書にもなっている。
★Amazonで詳細を見る
『「世界史と日本史」同時授業─「世界と日本」つなぐとわかる歴史の本質!』村山秀太郎・伊藤賀一/著(アーク出版)

『「世界史と日本史」同時授業─「世界と日本」つなぐとわかる歴史の本質!』村山秀太郎・伊藤賀一/著(アーク出版)
日本の古代から近現代まで、歴史上エポックメイキングとなった事件・紛争・対立を取り上げ、その原因、背景と経緯、後世にもたらした影響などを政治・経済・宗教など多方向から考察。世界史と日本史が絡まる歴史の醍醐味が味わえる本。「膨大な知識と語りの高度な技量をもつ二人による掛け合いの書籍化。
歴史の教養があると現代社会を見る目も研ぎ澄まされるということがよくわかります」(小柴先生)
★Amazonで詳細を見る
『ツムグ日本文学─未来に残したい文学の名著』小柴大輔 /著 岡本梨奈 /著(リベラル社)

各作品は約300字でコンパクトにまとめられ、芥川賞・直木賞・本屋大賞・ミステリー大賞など話題作も網羅。
美しいイラストや写真も魅力で、読みものとしても資料としても活用できる構成。
「文学にあまりなじみのない人でも、ページをめくるうちに自然と興味がわいてきます。
紹介されている作品から読書感想文用の本を選んでもいいですし、この本そのものを読んでの感想を書くこともできます。
さらに、各ページに添えられた美しいイラストに着目して、ビジュアルに対する感想を書くというアプローチも可能です。
読書感想文のヒントを探したい人や、文学の世界に気軽に触れてみたい人にぴったりです」(小柴先生)
『読み解くための現代文単語 改訂版』小柴大輔/著(文英堂)

『読み解くための現代文単語 改訂版』小柴大輔/著(文英堂)
大学入試の評論・小論文・小説・エッセイに必須の語句・語彙を、見出し語800語、関連語を合わせると1600語以上収録。これ1冊で大学入試に対応できる必要十分な語数を習得。
「2022年11月に発刊された改訂版では新規に現代語を100加えたほか、3つのエッセイを書き下ろし。
「1.仕事の道具、2.本の街、神保町、3.仕事の流儀、このほか、科学、近代、異文化理解、言語・文学、情報、倫理・SDGs、心理、芸術などのテーマ理解文章を8本収録しています」(小柴先生)
★Amazonで詳細を見る
『ざんねんな万葉集』岡本梨奈/著(飛鳥新社)
.jpg?20260203)
『ざんねんな万葉集』岡本梨奈/著(飛鳥新社)
日本人は1300年前からダメダメで美しかった!4516首からよりぬき51首、驚愕の万葉集逆ベスト版。
超美麗なイラストとセットで、1300年前のダメダメな男女のせきららな歌をわかりやすくおもしろく案内している。
スタディサプリで古文と漢文を担当している岡本莉奈先生の著書。
★Amazonで詳細を見る
『眠れないほど面白い枕草子─みやびな宮廷生活と驚くべき「闇」』岡本梨奈/著(三笠書房)

『眠れないほど面白い枕草子─みやびな宮廷生活と驚くべき「闇」』岡本梨奈/著(三笠書房)
清少納言と「ガールズトーク」をしているかのように『枕草子』を超訳&解説。現代のTwitterやブログのつぶやきととらえて、なじみやすく紹介している。
こちらも、スタディサプリで古文と漢文を担当している岡本莉奈先生の著書。
★Amazonで詳細を見る
『ニュースの「なぜ?」は日本史に学べ─日本人が知らない76の疑問』伊藤賀一/著(SBクリエイティブ)

『ニュースの「なぜ?」は日本史に学べ─日本人が知らない76の疑問』伊藤賀一/著(SBクリエイティブ)
スタディサプリ日本史の伊藤賀一先生の著書。授業と同様に、テンポ良く歯切れ良く、ユーモア満載で、時事ネタを歴史視点から読み解く本。
★Amazonで詳細を見る
『47都道府県の歴史と地理がわかる事典』伊藤賀一/著(幻冬舎)

『47都道府県の歴史と地理がわかる事典』伊藤賀一/著(幻冬舎)
全都道府県に足を運んで集めた「鉄板ネタ」「地雷ネタ」まで盛り込んだ、読んで楽しく役に立つ画期的な事典。スタディサプリの日本史講師、伊藤賀一先生の著書。
「自分の住んでいる県の再発見に、次の旅行先の予習に、クイズ番組対策にと、ためになっておもしろい本です」(小柴先生)
★Amazonで詳細を見る
『絵本のようにめくる世界遺産の物語』村山秀太郎 、本田陽子/監修(昭文社)
.jpg?20260203)
『絵本のようにめくる世界遺産の物語』村山秀太郎 、本田陽子/監修(昭文社)
スタディサプリの世界史講師・村山秀太郎先生が監修している、美しい写真と含蓄のある文章から成る本。シンプルな解説と選りすぐりの絶景を見ているだけで、世界旅行をしている気分になれる。
『絵本のようにめくる世界遺産の物語─地球の記憶編』『絵本のようにめくる世界遺産の物語─色彩の魔術編』『絵本のようにめくる世界遺産の物語─城と宮殿』などのシリーズがある。
★Amazonで詳細を見る
読んでみたい本は見つかっただろうか。
最後に、この記事の監修者の小柴先生の最新著書を紹介しよう。
『話し方のコツがよくわかる人文・教育系面接 頻出質問・回答パターン25』小柴大輔/著(KADOKAWA)

主に推薦入試用対策本だが、以下のテーマでの質疑応答と解説があり、小論文のコンテンツとしても有益。
テーマは、日本語と英語公用語化・リベラルアーツ・AI・日本文化・異文化理解・ストレスと現代人のメンタリティ・コミュニケーション・いじめ・学校教育の課題・感染症対策・リバタリアニズム・ボランティア・日本社会の格差問題など。
★Amazonで詳細を見る
『話し方のコツがよくわかる社会科学系面接 頻出質問・回答パターン25』小柴大輔/著(KADOKAWA)

主なテーマは、ポピュリズム・ヘイトスピーチ・憲法改正論・裁判員制度・平和構築・国連・環境問題・格差社会・日本的経営・自由と人権の普遍性・地域と高齢社会・資本主義・感染症など。
★Amazonで詳細を見る
読書感想文が書きやすくなる5つの方法
読む本が決まったとしても、感想文に何を書いたらよいのかわからないという人もいるかもしれない。ここからは、感想を文にしやすくなる読み方と書き方を解説していく。
この感想を誰に伝えたいのかを想像してみよう。
高校の課題として提出するとしても、希望校の面接を想定したり先生や友達に伝えたりなど、「誰か」を想像することで言葉が出てくるものだ。
2、自分と比較して書く
自分の考えや行動と比較すると深く読み取り書くことができる。
「一般的には〇〇だが私は~」「以前の私なら〇〇だが、今の私は~」に当てはめながら読み進めてみよう。
3、過去に読んだ本との比較
同じテーマについて書いた本を過去に読んだことがあるのなら、その本と今読んでいる本を比較してみよう。
作者の考えの違いや書かれた時代の違いなど、比較対象はたくさんある。
前に読んだ本と同じテーマの本なら、予備知識があるので読みやすいだろう。
4、自分が続編を書くならどう書くか
創作をする人におすすめの書き方。
パロディやパスティーシュでもよい。
自分ならどんな続編を書くか、その理由やキャラクター設定の考察も含めて書くと、注目される感想文になる。
想像力を発揮して、楽しんで書いてみよう。
5、内容の一部だけ読んで書く
読書感想文を書くだけなら、本1冊すべて読まなくても大丈夫。
書くテーマを決めたら、関連する箇所だけ読んで、そこから自身の考察や見解を書くことが可能だ。
また、名作の読み方やあらすじをまとめた本やサイトがあるので、参考にしてもよいだろう。
読書感想文の基本的な書き方の手順から、内容をさらに充実させる方法まで丸ごとわかる!
感想文を書くのが得意でなくても、すらすら書けるようになるコツを小柴先生が解説している。
.jpg?20260203)
読書感想文の書き方|構成・書き出し・すぐ使える例文まで完全ガイド!
読書感想文は自分自身を磨くチャンス
大学受験を考える高校生にとって、読書感想文は自分をアピールできるツールでもあることを知っているだろうか。読書感想文に挑むことは、自分自身を磨くチャンスなのだ。
次の効果効能を読んで、ぜひ前向きに挑んでもらいたい。
自分がどんな言葉に感銘を受けるのか、どんなストーリーに共感し反発するのか。
これらを読書は教えてくれる。名言から人生観が変わるということも多い。
2、内面を言葉にすることで癒しの効果と語彙力の向上
心の声をあえて言葉にすることで癒しが得られるという。
言葉にならないと安易に断念してはいけない。
心の叫びは、言葉にすることでより理解でき、通じるものだ。
3、学校推薦型選抜の志望理由書や面接対策
受験生なら読書は必修科目。
学びたいくらい興味があるのに、その分野の本を1冊も読んでいないのでは話にならない。
反対に、本を読んで受けた影響や感想を話せることで、本気度を伝えられる。
読書感想文は小論文対策にも有効だ。
本との出合いは一期一会。
この記事を参考に、自分だけの感動を見つけにいこう!
取材・文/編集部 監修/小柴大輔 ※2025年7月更新