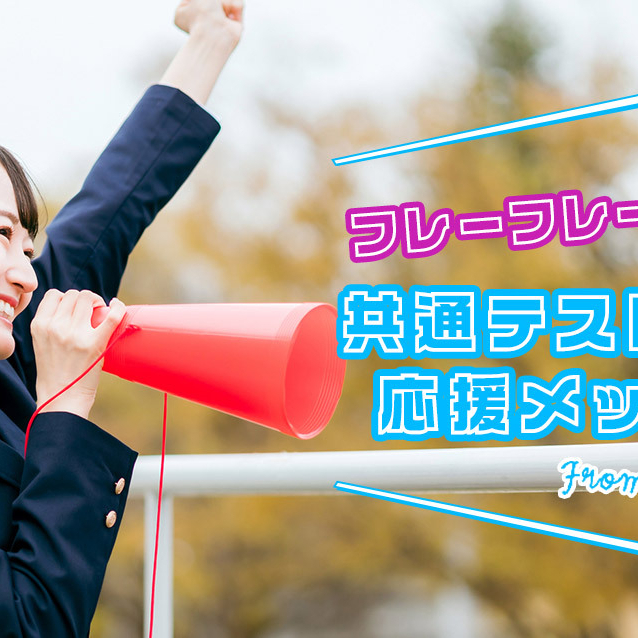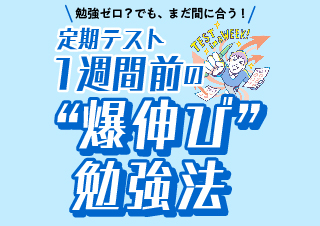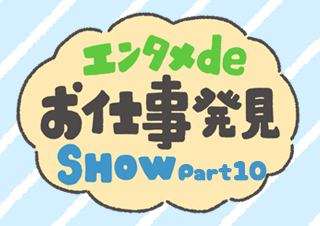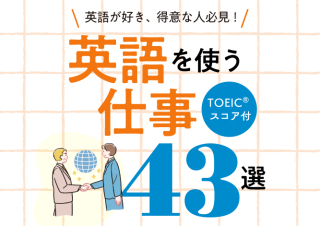共通テストとは?一般入試との違いを簡単に解説!2026年度最新版
大学入学共通テストとは、国公立大学を目指している人にとって必須ともいえる入学試験。大学入学共通テストと一般入試との違いは、受験する科目数の差が大きく、国公立大学を受験する場合、6教科8科目が必要となる。「私立大学志望の私には関係ない」「たくさん科目があって、全部勉強するのは無理!」と最初からあきらめている高校生もいるのでは?実は、大学入学共通テストを受験すると、国公立大学だけでなく、私立大学の一般選抜に利用することもできて、3教科3科目が多い私立大学受験が、1教科や2教科で受験できることもある。
そこで、大学入学共通テストについて、私立大学の一般選抜との違いをふまえながら、基礎知識から受験するメリット・デメリットまでをスタディサプリ講師で、カンザキメソッド代表の神﨑史彦先生に教えてもらった。
神﨑史彦先生

株式会社カンザキメソッド代表取締役。
スタディサプリ講師。私立学校研究家。高大接続・教育コンサルタント。
大学卒業後、大学受験予備校において小論文講師として活動する一方、通信教育会社や教科書会社にて小論文・志望理由書・自己アピール文の模擬試験作成および評価基準策定を担当。
のべ6万人以上の受験生と向き合うなかで得た経験や知見をもとに、小論文・志望理由・自己アピール・面接の指導法「カンザキメソッド」を開発する。
現在までに刊行した参考書は26冊(改訂版含む)、販売部数はのべ25万冊、指導した学生は10万人以上にのぼる。
目次
大学入学共通テストとは?

※大学入学共通テストの概要や科目をおさえよう
大学入学共通テストとは、大学入学を目指す高校生などを対象に、主に高校までの基礎的な学習の到達度を判定するため、毎年1月中旬に行われる日本最大規模の大学入学試験。日本最大規模の試験で毎年、約50万人が志願
大学入学共通テストは、国公立大学を目指す人にとって必須の大学入学試験。2019年度まで「大学入試センター試験」として実施されていた試験が、2020年度(2021年1月実施)より「大学入学共通テスト」として新たに始まった。国公立大学の一般選抜の1次試験であると同時に、私立大学でも選抜方法の一つとして利用されていて、2025年度入試では、全国で838大学・専門職大学・短期大学が大学入学共通テストを利用した。総合型選抜や学校推薦型選抜でも、大学入学共通テストの受験が必要となるケースもあるため、毎年、約50万人が志願。2025年度入試では、前年より約4500人多い46万2066人が受験している。
────────────────────
大学入学共通テストは、大学入試改革の一つで、「高校教育」と「大学教育」、そしてそれらをつなぐ「大学入試」の3つを一体化させる「高大接続改革」の要として導入された。それまで行われていた大学入試センター試験は、「知識・技能」を問う問題が中心でパターン化されていたため、より「思考力・判断力・表現力」を重視する出題内容へと見直されている。
マークシート方式で思考力や判断力が求められる
大学入学共通テストとは、全問マークシート方式で、記述式問題は出題されない。しかし、選択式だからといって知識さえあれば解けるシンプルな問題は少なく、知識・技能を活用する思考力や判断力が求められ、「知識の理解の質」が問われている。問題文だけでなく選択肢の文章も長く、読み解かなければならない文章量、理解・考察すべき情報量が多いことが、大学入学共通テストの試験内容の最大の特徴。
出題科目は7教科21科目
大学入学共通テストの出題教科・科目は、7教科(国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報)21科目。「国語」と「情報」以外の教科は、志望する大学が指定する科目を選択して受験する。受験する科目は試験当日に選択することが可能だが、受験する科目数や科目の選択方法、配布を希望する冊子を出願時に申し出ることが必須の教科もあるので、出願前に試験要項を確認しておこう。

2025年度大学入学共通テスト(共通テスト)の日程は?時間割、当日の注意事項も紹介!
大学入学共通テストと一般選抜試験との違いは?

※大学入学共通テストとは?一般受験と何が違うの?
大学入学共通テストと私立大学の一般選抜試験との一番の大きな違いは、受験する科目数。国公立大学を受験する場合、文系学部でも数学や理科、理系学部なら国語や地理歴史・公民を受験する必要がある。受験する科目数が一番大きな違い
国公立大学の受験では、多くの場合は6教科8科目が必要です。国公立大学の文系学部は、英語+国語+数学2科目+情報+基礎がついた理科+地理歴史・公民から2科目で合計8科目。

国公立大学の理系学部では、英語+国語+数学2科目+情報+理科2科目+地理歴史・公民から1科目で合計8科目。

私立大学の一般選抜試験は3科目が基本となり、文系の場合、英語+国語+数学・地理歴史・公民から1科目、理系の場合、英語+数学+理科が一般的。2教科や1教科で受験できる私立大学もあります。


『情報』を必須で課す私立大学は少なく、他教科との選択として利用するケースが多いといわれています。そのため、私立大学の『大学入学共通テスト利用入試』を受験する場合は、大学入学共通テストで『情報』を受験しなくてもよい私立大学が多いでしょう。私立大学の一般選抜の出題傾向は、過去数年間の試験問題を比べる限りでは、あまり大きな変化は見られません。
しかし、大学入学共通テストは、2019年度までの大学入試センター試験と比べて、知識理解・思考力・判断力が問われる内容に変わっています。過去の大学入試センター試験では、豊富な知識があれば問題を解くことができましたが、大学入学共通テストは、学んだ知識を組み合せて、論理的に考えられなければ正答するのは難しいでしょう。
暗記科目といわれる世界史や生物などでも、受験生は『現代文のような問題が出題された』と述べるほど、読解力が求められているのです」(神﨑先生)
国公立大学志望の人は受験すべき?私立大学志望なら受けなくてもいい?
また、国公立大学のなかには、たとえ総合型選抜または学校推薦型選抜で合格しても、大学入学共通テストの受験も必須で、規定の点数が取れなければ入学が認められないというケースがあるので、総合型選抜または学校推薦型選抜の受験要項をしっかりとチェックしておきましょう。
私立大学には、大学入学共通テストの得点で合否が決まる『大学入学共通テスト利用入試』があるので、それを視野に入れている人は受験すべきです」(神﨑先生)

大学入学共通テストの受験科目はどう決める?
大学入学共通テストは1科目単位で受験することができ、7教科を全部受験する必要はなく、自分の志望大学で指定されている科目を選択して受験すればよい。国公立大学を受験する場合は、6教科8科目が基本。 私立大学の「大学入学共通テスト利用入試」を受験する場合は、1教科~3教科で、1科目~6科目を選択する。ただし、『地理歴史』『公民』は組み合せ不可の科目があるので注意が必要。
国公立大学では多くの大学が6教科8科目
大学入学共通テストの受験科目は、国公立大学を受験する場合は6教科8科目、私立大学の「大学入学共通テスト利用入試」を受験する場合は1教科~3教科で1科目~6科目を選択する。私立大学であれば一般選抜を受験する道がありますが、国公立大学はその学部・学科を受験することが不可能になってしまうので、特に国公立大学が第一志望の人は、選択ミスのないよう、志望大学の試験要項をしっかりチェックしておきましょう」(神﨑先生)
理科の基礎がついた科目は4つの出題範囲から選択
理科は『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』『物理』『化学』『生物』『地学』の5科目から最大2科目を選択する。『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』は、4つの出題範囲から2つを選択して解答。受験する科目は、大学入学共通テスト当日に試験問題を見てから決めることが可能だが、受験する科目数は出願時に申し出る必要がある。
第1解答科目とは?
理科と地理歴史・公民で2科目を受験した場合、②2科目のうち高得点の科目を合否判定に利用
③第1解答科目を合否判定に利用
「第1解答科目」とは、理科、地理歴史・公民で、1科目めに受験した科目。国公立大学や私立大学でも、1科目のみを合否判定に利用する大学は第1解答科目を指定するケースが多くみられ、いくら2科目めに受験した科目のほうが高得点でも採用されない。
2科目のうち、どちらを第1解答科目にするかは大学入学共通テスト当日に試験問題を見てから決めることができるが、第1解答科目を指定している大学もあるので注意しよう。
.gif?20260118)
地理歴史・公民は科目選択の組み合せに注意
大学入学共通テストの科目選択で特に注意が必要なのは、地理歴史・公民。(a)『地理総合、歴史総合、公共』、(b)『地理総合、地理探究』『歴史総合、日本史探究』『歴史総合、世界史探究』『公共、倫理』『公共、政治・経済』の6科目から最大2科目を選択できるが、組み合せ不可となるバターンがある。ただし、2科目を選択する場合、同一名称を含む科目の組み合せができません。例えば1科目めに(b)の『地理総合、地理探究』を選択したら、2科目めで(a)の『地理総合、歴史総合、公共』を選択した場合に3つの出題範囲から『地理総合』が選べなくなります。
また、『公共、倫理』と『公共、政治・経済』の2科目を選択するパターンも、両方に『公共』が入っているため、不可です。下記の組み合せパターンを参考にして、選択ミスをしないように気をつけましょう」(神﨑先生)

.gif?20260118)
大学入学共通テスト利用入試とは?
大学入学共通テストを受験した後、私立大学の「一般選抜(大学入学共通テスト利用)」に出願すると、大学入学共通テストの成績だけで複数の私立大学を受験することが可能になる。これを大学入学共通テスト利用入試という。大学入学共通テスト利用入試には「単独型」と「併用型」がある
大学入学共通テストを受験して、その成績のみで出願した私立大学の合否が決まるのは「単独型」。大学によっては「併用型」もあり、大学入学共通テストの成績だけでなく、その大学独自の個別試験や小論文、適性検査、調査書などが評価される。大学入学共通テストの受験科目は、1科目~6科目まで大学によって大きく異なり、複数の科目から選択できる場合もあるが、必須の受験科目が決められていることも。併用型の場合の配点なども大学独自の判定基準があるので、注意しよう。
大学入学共通テストの日程は?

※受験科目はしっかり事前チェック!
大学入学共通テストは毎年1月の中旬ごろに行われている。2026年度大学入学者対象の試験実施期日は、2026年1月17日(土)・18日(日)。試験は2日間に分けて行われ、前述の7教科21科目の中から、志望する大学が指定するものを選択して受験することになる。2026年度から出願手続きが電子化
2026年度大学入学共通テストの出願期間は、2025年9月16日(火)10時~10月3日(金)17時(予定)。出願方法は、2025年度まで現役生は在学する学校を経由して郵送で提出していたが、2026年度から出願手続きが電子化され、現役生、既卒生共にすべての受験生が個人でオンライン出願をする。出願にあたり、大学入試センターのホームページ上から大学入学共通テスト出願サイトにアクセスして、受験生自身がアカウントを登録のうえ、マイページを作成する必要がある。
マイページ作成期間は、2025年7月1日から10月3日まで。大学入学共通テストの出願にかかわるすべての手続き(出願内容の登録や訂正、受験票の取得、成績の閲覧など)は、受験生がマイページで行う。
2025年度までは、現役生の場合、高校の担任の先生に大学入学共通テストの出願書類を提出すればよかったので、内容などをチェックしてもらえたが、2026年度からは、私立大学の一般選抜と同様に、受験生自身が出願手続きをしなくてはならないので要注意。
大学入学共通テストを受験するメリット・デメリットは?

※大学入学共通テストは自分の住んでいる地域で受験することができる!
大学入学共通テストは、1回の受験で複数の私立大学にも出願できて、受験できる大学の選択肢が広がり、受験料が安くなることがメリット。ただし、一発勝負なので失敗した場合にリカバリーできないというデメリットもある。メリットは大学の選択肢が広がること
大学入学共通テストは自分たちの住んでいる地域で受験することができますから、大学入学共通テスト利用入試の単独型なら出願のみで、実際に大学へ行って試験を受ける必要がないため、日本全国どこの私立大学でも受験できます。
また、一般選抜の個別学力試験よりも大学入学共通テスト利用入試のほうが、受験料が安いというメリットもあります」(神﨑先生)
デメリットは失敗した場合のリスクが高い
私立大学の一般選抜では3科目前後にしぼることができますが、国公立大学の場合、6教科8科目がほぼ必須になり、その分、受験勉強をする時間が分散してしまいます。
また、私立大学の一般選抜(大学入学共通テスト利用)は、一般選抜(個別学力試験)よりも募集定員が少ないことが多いため、必然的に高倍率になります。個別学力試験なら60~70%程度の得点率で合格可能ですが、大学入学共通テスト利用では、85%以上の高得点が求められる学校もあります」(神﨑先生)
共通テストに失敗したらどうする?5つの選択肢【先輩たちの体験談つき】
共通テストの失敗をばん回!現役合格をかなえる「追い出願校」の選び方
大学入学共通テスト利用入試とは? 個別入試との違い、メリット・デメリットを詳しく解説!
大学入学共通テストの勉強方法は?

※大学入学共通テストの問題形式はマークシート方式のみ!
大学入学共通テストの受験勉強では、まず過去問題をくり返し解いて、出題傾向を把握し、予想問題集や模擬試験に取り組んでいく。そして模擬試験を受けたら必ず復習することが重要になる。過去問題をくり返し解いて出題傾向を把握
まずは、2025年度以降の過去問題をくり返し解いてみて、出題傾向を把握しましょう」(神﨑先生)
予想問題集や模擬試験にも取り組む
模擬試験は、回数を重ねれば重ねるほど、試験問題を解くテクニックが上がっていくと思います。ただし、模擬試験を受けたら、必ず復習すること。
間違った問題を解き直すのはもちろん、正解した問題でも、どういう論理で解答を導いたのか、どの知識を当て込んで応用したから解けたのか、きちんと整理しておくと着実に身についていきます。スタディサプリ講師による教科別の対策方法も参考にしてみてください」(神﨑先生)
大学入学共通テスト対策はいつまでに何をすればいい?

※大学入学共通テストの学年ごとの対策とは?
大学入学共通テスト対策は、高校1年生からコツコツと知識を積み重ねていくことが大事。まずは授業をしっかり受けて、教科書の内容を理解してから、問題集や過去問題に取り組み、本番に向けてレベルアップしていこう。高校1年生は基礎固め
高校2年生で問題集をくり返し解く
高校2年生の3学期は、高校3年生の0学期ともいわれていて、この時期までに国公立大学を第一志望にするのか、学部はどうするのか、ある程度の方向性を決めて、受験する科目を考える必要があります」(神﨑先生)
高校3年生は過去問題に取り組む
大学入学共通テストの対策法。背景や基礎知識から各教科のコツまで網羅!
不安になったら受験のプロに相談しよう
2025年度の過去問題を解いてみれば、どんな問題が出るのか、今の自分の学力で解けるのか、体感することができます。
過去問題が解けなければ、なぜ解けないのだろう、どうすれば解けるようになるのか、身近な信頼できる受験のプロに相談してみてください。
受験のプロとは、高校の進路の先生、高校の教科の先生、高校の担任の先生、塾や予備校の講師、スタディサプリ講師、大学入試を研究しているところのメンバーなど。君たちの保護者が大学入試を受けた時代とは、入試形態も出題方法も問題の作り方も変わっているので、保護者の意見は参考程度に留めておくといいでしょう。
SNSなどの情報に頼る人もいますが、信頼できるプロに相談することが安心だと思います」(神﨑先生)
.gif?20260118)
また、当日は思わぬアクシデントが起こる場合も!そんな時も慌てず対処できるように、事前にどこへ連絡すればいいのかをチェックしておこう!
【2025年度版】共通テストに遅刻!試験は受けられる?大学受験トラブル対処法
取材・文/やまだみちこ 監修/神﨑史彦 構成/スタサプ編集部(2025年8月更新)
★【共通テスト】関連記事をチェック!
●【2025年度】大学入学共通テスト、試験日程・出願期間・教科・時間割・当日の注意事項は?
●大学入学共通テスト利用入試とは? 個別入試との違い、メリット・デメリットを詳しく解説!
●大学入学共通テストの対策法。背景や基礎知識から各教科のコツまで網羅!
●【2025年度版】共通テストに遅刻!試験は受けられる?大学入試トラブル対処法
●共通テストに失敗したらどうする?5つの選択肢【先輩たちの体験談つき】