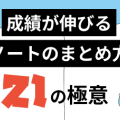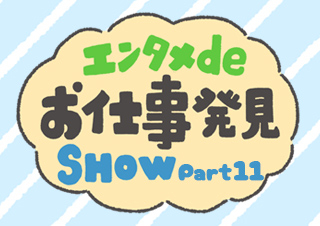勉強が楽しくなる方法とは?“ビリギャル”小林さやかさん&先輩200人が本音で回答!
みんなは「勉強が楽しい」と思う?「勉強が楽しい!」と心から思って、毎日、授業や自習に取り組んでいる高校生は、どれくらいいるのかな?
勉強が楽しくない、つまらないと思ってしまう理由は、「勉強がわからない」から。
勉強が楽しくなるには、「勉強がわかる」「勉強をする意味がわかる」ことが大事。
そこで、「勉強が楽しい」と思える効果絶大な方法を、偏差値を40上げて慶應義塾大学に合格したビリギャルこと小林さやかさんに教えてもらったよ。
さらに、先輩たちはどうやって「勉強が楽しい」と思えるようになったのか、リアルな声を聞いてみた。
目次
 小林さやかさん
小林さやかさん坪田信貴著『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』の主人公ビリギャル本人。
中高大学⼀貫の私立中学に入学してすぐ勉強することをやめ、学力がみるみる低下し学年ビリに。
高校2年生の夏、塾の面談で恩師坪田信貴先生と出会い、先生と二人三脚での1年半猛勉強のすえ、慶應義塾大学 総合政策学部入学。
卒業後、ウエディングプランナーとして仕事をし、フリーランスに転身。
講演、学生・親向けのイベントやセミナーの企画運営など、幅広い分野で活動中。
YouTube『ビリギャルチャンネル』にて、学生・先生・親、すべての人に送るエンタメ教育番組を配信中。
現在は、アメリカ・コロンビア教育大学院に留学し、認知科学を学んでいる。
最新書籍『ビリギャルがまたビリになった日-勉強が大嫌いだった私が、34歳で米国名門大学院に行くまで』。
どうすれば勉強が楽しくなる?

※勉強が楽しくない理由から、勉強が楽しくする方法が見えてくる
勉強が楽しくなるには、「勉強がわかる」ようにならなくてはいけない。先生の言っていることが難しくてわからない、どうしたらテストで結果を出せるのかわからない、そもそも勉強する意味がわからない…。
わからないことだらけで勉強していては、楽しくなるわけがない。
そこで、なぜ勉強が楽しくないのか、どのようにすれば変えられるのか、小林さやかさんと先輩たちのリアルな意見を聞いてみた。
そもそも勉強が楽しくないのはなぜ?
勉強が楽しくない、勉強がつまらない、と思うのは、●勉強がわからないから
●勉強しても結果が出ないから
●勉強する意味がわからないから
といった理由が多い。
具体的にどんなときに勉強が楽しくないと思ったのか、聞いてみた。
自分のレベルに合わない勉強をやらされるから
「ほとんどの高校生に当てはまると思うのですが、勉強が楽しくないのは、やっていることが難しすぎるから。自分の能力に合っていないことをやらされているから、勉強がつまらないのです。
これは、まさに私が中学入学後にまったく勉強をしなくなった理由でもあります。
高校では1クラス30~40人で、一人ひとり学習速度も理解度も違うのに、みんな一緒に授業を受けていますよね。
あるところでつまずいてしまっても、どんどん授業は進んでいきます。
すると、新しく入ってくる知識はさらに難しく感じてしまう。
先生の言っていることが理解できていないけど、テストがあるから、とりあえず暗記しなくてはいけない。
理解ができていない丸暗記の勉強は、すごくつまらないし、この勉強は何のためにやっているのか、わからなくなりますよね。
レベルに合っていない勉強を、テストのために無理矢理覚えようとするから、難しいし、つらいし、どんどん負のサイクルになって、勉強が楽しいと思えなくなるのです」(小林さん)
さらに、先輩たちは、どんなときに勉強が楽しくない、つまらないと思ったのか聞いてみると、大きく分けて3つの理由があった。
勉強をしても期待した結果が出ない

※勉強をしても思うような結果が出ないと意欲を失ってしまう
先輩たちの声で一番多かったのが、一生懸命に勉強しても成績が上がらなかった、テストで高得点を取れなかったとき、勉強をする意欲を失って、勉強が楽しくないと思ってしまうようだ。「自分なりに頑張ったと思っても成績が少ししか上がらなかったときや、周りの人がどんどん成績をあげているとき」(大学2年生・看護福祉学部・秋田)
「英語がなかなか上達せず、どう勉強すればどう成績が上がるのか、ビジョンが見えなかった」(大学1年生・経済学部・東京)
勉強をする意味がわからない
自分は何のために勉強をしているのか、勉強をする意味がわからなくなると、モチベーションが下がってしまいがち。「勉強をやる気が起きず、前へ進めてないことに不安を覚えて、またやる気を失う負の連鎖から逃れられずにいた」(大学4年生・文学部・大阪)
「自分が何のために勉強をしているのかわからなくなってしまったとき、自分で計画を立てて勉強をしていくことに不安を感じた」(大学3年生・心理学部・神奈川)
勉強以外のことに興味がある
勉強よりも楽しいことがあるのに、やりたいことをガマンして勉強しなくてはいけないと思うと、当然、勉強はつまらなくなってしまうのだ。「部活との両立がうまくいかず、自分が行きたい学部の理系科目の成績があまりふるわず、モチベーション維持が大変だった」(大学4年生・医学部・北海道)
「今したいことを優先してしまい、勉強に手がつかなかった」(大学2年生・医学部・神奈川)
次は、先輩たちに勉強が楽しくなったきっかけを聞いてみた。
先輩たちに聞いた!勉強が楽しくなった「きっかけ」は?
先輩たちの勉強が楽しいと思うようになったきっかけは、達成感を得られたり、プラスαのメリットを感じたり、仲間の存在も大きいようだ。わからなかった問題ができるようになった

※問題が解けるようになるとモチベーションも上がりやすい
できなかった問題がスラスラと解けたり、テストの成績がアップして勉強した成果が目に見えたりすると、勉強が楽しくなって、モチベーションが上がること間違いなし。「校内テストの点が上がって、自分の努力が可視化されたとき。自分には解けないと感じていた問題を誰かに説明できるくらいになったとき」(大学2年生・理工学部・北海道)
「得意分野をきわめたことで、各分野の先生にほめていただけたとき、自信がついて楽しくなった」(大学4年生・農学部・愛知)
新しい知識が増えて自分の生活に役立った
知らなかったことを知ることがおもしろく感じたり、学んでいることが自分の生活にもつながっているとわかったり、知識が増えていくと、自然に楽しくなるのだ。「自分の生活に深く結びついている物事のしくみや原理を知ったとき」(大学1年生・工学部・東京)
「世界史の勉強をしているときに、それぞれの裏話や逸話を調べていくとワクワクした」(大学4年生・社会学部・兵庫)
「わからないことがわかるようになる瞬間。日常の疑問が勉強することで解消した瞬間」(大学1年生・看護栄養学部・北海道)
友達と一緒に勉強を頑張っているとき

※友達と一緒に勉強することでやる気がアップすることも
友達と一緒に教えあったり、競い合ったりして、成長していける。そんな仲間の存在を感じられると、勉強を頑張ろうという気持ちにつながっていくはず。
「友達と勉強しているときは楽しかった。特に好きな人の隣で一緒にテストの点を競ったり、教えあったりしてるときは幸せだった」(大学4年生・文学部・北海道)
「勉強ができるようになると、自分に自信がつき、楽しくなった。また、友達に教えることも多く、その分、多くの友達とかかわることができて、楽しいと感じていた」(大学5年生・薬学部・兵庫)
勉強が楽しいと感じる理由は?どんなとき?
先輩たちのアンケートによると、「勉強ができるようになる」「自分の生活につながる」ということが、勉強が楽しいと感じるためのポイントになるようだ。小林さんに体験談もふまえて解説してもらった。
「達成感」と「学ぶ意味」が楽しさにつながる
この小さな『できる』が、大きな『やる気』に変わっていく感覚は、勉強にはすごく大事で、これを続けていくことで『勉強も悪くないな』という気持ちにつながっていくのではないかと思います。
もう一つ、この勉強は何のためにやっているんだろうと疑問を感じることがありますよね。
大人になってわかったのは、学校で学んでいたことは、全部、私たちの日常生活につながっていたということ。
例えば、科学を知らなくても生きていけるって自信満々に思っていたけど、大学時代にガスボンベをセットしたカセットコンロをオーブントースターの上に置いたまま、長時間かけてグラタンを焼いていたら、突然、ガスボンベが爆発して、キッチンの天井に穴が空いてしまったんです。
奇跡的に無傷だったけれど、空気が温まると膨張するという理科の勉強をしていれば、いかに危険なことだったか、わかりますよね。
今なぜ戦争が起こっているかは、その国の歴史を知っていれば、ある程度、理解ができます。
国語が苦手な人は、他人の気持ちが理解できないと思うので、対人関係で苦労するかもしれませんよ。
物語の作者の気持ちとか、いろいろな視点で解釈しようとすることは、相手からのメールに、これはどういう意味なんだろうと想像することに似ていると思いませんか?
学校の授業で学ぶことを、日常生活とリンクさせて、どこにつながっているのだろうと考えてみると、途端に勉強がおもしろくなると思います」(小林さん)
勉強が楽しくなるための考え方とは?

※勉強が楽しくなるためにはどんな考え方をしたらいいのか、心理学から見てみよう
勉強が楽しくなるためには、努力やトレーニングによって、できないことができるようになると信じる気持ちが大切だと小林さん。心理学でも、それを信じている人のほうが成長できるのだといわれているそう。
努力によって変えられると信じることが大事
グロースマインドセットとは、努力やトレーニングによって能力は発展するし、才能が育って、できないことができるようになるという信念。
フィックストマインドセットは、その逆で、成功する人はそういう才能があったからで、生まれもった才能や能力を変えることはできないという信念。
努力によって才能が変えられると信じている人のほうが、失敗したり、挫折したりしたときに立ち上がる力が強いといわれています。
失敗から学ぶことができて、どんどんパフォーマンスが良くなっていく傾向があるのです。
例えば、100点満点のテストで30点だったとき、グロースマインドセットだと、何がいけなかったのかを考え、そこから学びをしぼり出して次のテストに生かすことができるでしょう。
ところが、フィックストマインドセットだと、やっぱり自分は地頭が悪いから、どんなに頑張っても30点以上は取れない、と努力することをやめてしまい、当然、パフォーマンスは上がりません。
もちろん、そんな勉強は楽しくないですよね。
人間の能力は、生まれもった才能やDNAですべてが決まっているわけではなく、努力やトレーニングによって大きく変わる可能性があると科学的にも証明されています。
楽しく勉強するためにも、『どうせ私は地頭が悪いから』という気持ちは捨ててほしいと思います」(小林さん)
「各教科を勉強する意味を、小さいことでもいいから1つ以上考える」(大学1年生・法学部・静岡)
「勉強内容だけでなく、努力していることや理解できていること自体に楽しみを感じることができるといいと思う」(大学4年生・地域系学部・福岡)
「できなかったことを悪いと思うのではなく、新しい知識を得たとプラスにとらえること」(大学4年生・音楽学部・東京)
「やらなければいけないこと、という感覚ではなく、調べたいことや知りたいことを学ぶ感覚で勉強するといいと思う」(大学4年生・社会学部・兵庫)
「知らなかったことを知ることはよろこびだと感じられるようにするといいと思う。問題を解いて正解したり、点数が上がったりすることを楽しみととらえる」(大学4年生・看護学部・福岡)
勉強が楽しくなる方法6選

※勉強が楽しくなる具体的な方法を見ていこう
勉強が楽しくなるには、●自分のレベルに合った勉強をする
●仲間を作る
●すぐ達成できる目標を作る
●日常生活に役立つと考える
●勉強しやすい環境を整える
●モチベーションを上げる
といった方法がある。
具体的にどうすればいいのか、小林さんや先輩の体験談も参考にしてみよう。
6割できるレベルに戻って勉強する
私が今、大学院で研究している認知科学でも、自分の能力よりちょっと難しいことをやると、人間のパフォーマンスが最大化するといわれています。
6割以上できると簡単すぎて退屈しますが、6割を切るとストレスを感じ、やっぱり自分は地頭が悪いのかな、と、やる気がなくなってしまいます。
100点満点中60点を取れるくらいのレベルが、学び直しにはちょうどいいのです。
私の場合、高校2年生の夏に大学受験をしようと決めて、塾で学力テストを受けたら小学4年生レベルだと評価され、小学4年生のドリルから勉強を始めました。
そのレベルから勉強したことがビリギャルストーリーのキーポイントで、もし高校2年生レベルの難しい勉強をやらされたら、どんどん勉強が嫌いになって、速攻で塾をやめていましたね。
自分の能力に合った戦略を立てて、地道に道筋をたどっていくことが重要。
楽しく勉強するためには、思いきって学び直す勇気が欲しいと思います。
一番良いのは、勉強のプロである高校の先生や塾の先生に相談すること。
それができなければ、薄い参考書や問題集を1冊ひととおり勉強してみて、6割できるレベルを探してみましょう。
自分はいつごろ、勉強が楽しくない、つまらないと感じるようになったのかを思い出してみると、つまづいたところをみつけるヒントになるかもしれませんよ」(小林さん)
勉強仲間を作る

※仲間の存在がモチベーションアップにつながる
一人で勉強するときより誰かと一緒のほうがスマホを触っている時間が短いな、と思ったら、友達と一緒に勉強するといいですね。
もちろん、一人のほうが集中できるという人は一緒に勉強しなくてもよいのですが、仲間の存在はモチベーションアップにつながるでしょう」(小林さん)
「同じ目標をもつ友達と声をかけ合って、励まし合った」(大学3年生・現代社会学部・奈良)
「ライバルをみつけると、目標に向かっている感があってよかった」(大学2年生・公益学部・山形)
小さな目標を作ってクリアしていく

※短期的で実現可能な目標を立てよう
大きな目標とは別に、そこへ向かうために短期間で到達しやすい小さな目標を定期的に設けておくことが重要。
私も、1年半後に慶應義塾大学に合格するという大きな目標に向けて、○月までに中学生レベルの復習を終えておこう、○月までに高校レベルの問題集で9割取れるまで頑張ろう、入試の2カ月前までには過去問で手ごたえを感じられる学力をつけよう、といった具体的な小さな目標をたくさん作って、それを一つひとつクリアしていきました。
まさにゲームのように、1ステージずつクリアしていって、気づいたら合格できるレベルまで登ってこられた、というほうがモチベーションは維持しやすいと思うので、短期的な実現可能な目標を作ることが必要だと思います」(小林さん)
「ポイントカードを作り、一日の勉強目標をクリアしたらポイントをつける。ポイントがたまったら、ごほうびに何か買う」(大学3年生・心理学部・長野)
「簡単な問題を1問解いてから勉強を始める」(大学1年生・経済学部・福岡)
「わからないことを放置せず、自分で調べたり、友達や先生に聞いたりして解決に向かうようにする。『わからない』から『わかる』になったときの達成感はとても気持ちがいい」(大学3年生・薬学部・福岡)
日常生活とリンクさせる
どんな科目でも、日常生活につながっている部分があるはずなので、それを考えてみると、丸暗記するよりも自然に頭に入ってきて、勉強が楽しくなると思いますよ。
さらに、身につけた知識が日常生活に役立つとイメージしたら、頑張って勉強しようという気持ちになりますよね」(小林さん)
「身のまわりのものに常に好奇心をもち、なぜ?どうして?と思うようにする」(大学1年生・工学部・東京)
「英語の場合、洋画やスポーツ観戦などの趣味と結びつける」(大学2年生・人文学部・三重)
「内容を理解して、その先にある深い世界に興味をもつ」(大学3年生・工学部・大分)
「勉強を好きな物事に結びつけると、楽しく感じられると思う」(大学4年生・芸術学部・神奈川)
勉強しやすく集中できる環境をみつける

※自分に合った集中できる場所をみつけられるとよい
音楽を聴きながら勉強するほうが楽しいという人は、思考力の邪魔をしない程度のBGMをかけてもいいと思います。
勉強する環境は人それぞれなので、自分が一番集中できる場所をみつけてください」(小林さん)
「勉強場所を変える、お気に入りの場所をみつける」(大学2年生・環境情報学部・神奈川)
「音楽聴きながらノリノリでやる」(大学1年生・保健医療福祉学部・埼玉)
好きなことでモチベーションを上げる
先輩たちの体験談を聞いてみると、自分の好きなこと、テンションが上がることを目の前にぶらさげて、勉強するモチベーションを上げていた。「勉強が終わったらしたいことを紙に書いて、壁に貼る」(大学3年生・人文社会学部・愛知)
「ごほうびの食べ物を用意して勉強する」(大学1年生・理工学部・神奈川)
「お菓子を食べながら勉強する」(大学4年生・文学部・北海道)
【番外編】ほかにもあるこんな方法
そのほかにも、先輩たちは勉強が楽しくなるために、いろいろな工夫をしているようだ。「大学受験をしない友達にグチを聞いてもらう」(大学3年生・農学部・秋田)
「たまに基礎の簡単な問題を解いて自信をつける」(大学3年生・文学部・神奈川)
「ゲーム感覚で問題を解いたり、友達とテストの点数を競い合うといいと思う」(大学3年生・経済学部・群馬)
「勉強時間と内容をノートにまとめて、努力が見えるようにする」(大学4年生・芸術学部・愛知)
勉強が楽しくなるメリットは?
勉強が楽しくなると、成績が上がるだけでなく、自分の人生の選択肢が増えるし、大人になったときに「勉強しておいてよかった」と思うときが必ずくると、小林さん。楽しく勉強することは、楽しい将来につながっていくのだ。
人生の選択肢が増えて、将来の自分の投資になる
この感覚がもてると、人生は勝ちだと思います。
勉強はテストで良い点を取るためだと思いがちですが、それに惑わされず、この勉強は、自分の人生、これから生きていくうえで、将来により多くの選択肢をもつために必要なことなのだと考えてほしいのです。
勉強が楽しいとか楽しくないという次元の問題ではなくて、学べば学ぶほど、いろいろなことが将来できるようになると思います。
例えば、お金を稼ぐことができる可能性が高くなるし、モテるだろうし、大事な人を守ってあげられる知識が身につきます。
自分だけじゃなく、自分の命をかけても守りたいと思う人ができたときに、勉強しておいてよかった、もっと勉強をしておけばよかったと思うことがあるから、勉強は自分のためじゃなくて、いつか大切な人を守るツールにもなる、と考えてもらえると、勉強する意義がわかるのではないでしょうか。
私も、坪田先生と出会って、勉強をしたことで、すごく彩り豊かに人生の可能性が広がったと実感しています」(小林さん)
勉強のやる気が出ないときはどうする?
勉強のやる気が出なかったとき、小林さんは慶應義塾大学へ行ってみて、そこに通っている自分の姿をイメージして、モチベーションを上げたそう。オープンキャンパスへ行ったり、大学の先生や先輩の話を聞くことで、頑張って勉強しようというやる気がわいてくるのだ。
自分が目標とする大学へ行ってみる

※実際に大学に行って将来の自分の姿をイメージしてみよう
そのころ、スランプに陥って、もうこれ以上勉強はできないと泣き叫んでいたら、坪田先生に『1回、慶應義塾大学へ行ってきなさい』と言われたので、母と慶應義塾大学の三田キャンパスへ行ってみました。
そのほかに受験する予定の大学も全部見ましたが、『どうしても私は慶應義塾大学じゃないとダメだ』と、何か感じるものがあったのです。
そこに通っている学生を見たり、そのキャンパスに通っている自分を想像したりすると、すごくモチベーションが上がります。
オープンキャンパスでもいいし、そのほかのときでも大学のキャンパスに入ることができると思うので、学生食堂でランチを食べてみてもいいかもしれないですね。
あとは、こういう人になりたいという人をみつけて、その人に話を聞く。
私にとっては坪田先生があこがれの人。
坪田先生と毎日会って、会話できたことが、やる気アップにつながりました。
学校や塾の先生、先輩でもいいし、身近にいなかったら、YouTuberを探してもいいでしょう。
あこがれの人をみつけて、実際に会えたら話をして、会えなければその人が書いた本を読んだり、動画を見たりすると、こういう人になれるよう勉強を頑張ろう、とモチベーションが上がると思いますよ」(小林さん)
志望校のオープンキャンパスをチェックしよう
小さなきっかけから勉強が楽しくなることもある!
勉強が楽しくなるには、ちょっとしたきっかけが大切。意識を変えてみたり、環境を整えてみたりして、モチベーションを上げて、維持し続けることができるよう、まずは、身近なところから見直してみよう。
文/やまだみちこ 取材協力・監修/小林さやか 構成/寺崎彩乃(本誌)
※2023年10月取材時の情報になります。
※記事内のデータ及びコメントは2023年10月に大学生206名が回答したアンケートによるものです。
【監修者著書紹介】

『ビリギャルがまたビリになった日-勉強が大嫌いだった私が、34歳で米国名門大学院に行くまで』
小林さやか著
★関連記事をチェック!
勉強のモチベーションを爆上げする方法16。5秒で勉強モード!受験勉強やる気キープのコツは?
「受験勉強がつらい」は甘えじゃない!勉強がつらい時の乗り越え方&心に効く名言集
勉強スケジュールの立て方。すらすら進む、挫折しないコツは?【スケジュール書き方例付き】
勉強に集中する方法とは?今すぐできる14のコツ、専門家に聞きました!
一夜漬けの暗記のコツは?東大生がテスト前の効果的な勉強法を伝授!