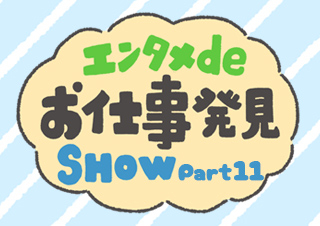十訓抄「大江山」原文と現代語訳・テスト対策のポイントをわかりやすく解説!
十訓抄は鎌倉時代に作られた説話集で、定期テストでもよく出題される。特に、文章の読解や教訓が問われることが多いので、内容や意味をしっかり押さえておこう!
そこで今回は、十訓抄「大江山」について、スタディサプリの古文・漢文講師 岡本梨奈先生に解説してもらった。
目次
- 『十訓抄』とは?
- 漫画でわかる!十訓抄「大江山」のあらすじ
- 十訓抄「大江山」の登場人物は?
- 十訓抄「大江山」の原文と現代語訳を読んでみよう
- 十訓抄「大江山」の定期テスト対策!ポイントをチェック!
- 「歌合」とは何ですか。
- 「丹後へ遣はしける人」とは、何のために遣わしていると言いたいのですか。
- 「心もとなく」のここでの意味を答えなさい。
- 「局」「御簾」「直衣」の読みを、それぞれ現代仮名遣いで答えなさい。
- 「袖を控へて」は、誰が誰の袖を控えるのですか。
- 「大江山」の和歌には掛詞が二つあります。抜き出して、それぞれ何と何の掛詞かわかるように説明しなさい。
- この「大江山」の和歌で、詠者が一番伝えたかったことは何ですか。
- 「あさまし」の意味を答えなさい。
- 「かかるやうやはある」を現代語訳しなさい。
- 「覚え」の意味を答えなさい。
- 古文の関連記事や学問をチェック!

岡本梨奈先生
古文・漢文講師
スタディサプリの古文・漢文すべての講座を担当。
自身が受験時代に、それまで苦手だった古文を克服して一番の得点源の科目に変えられたからこそ伝えられる「わかりやすい解説」で、全国から感動・感謝の声が続出。
著書に『岡本梨奈の1冊読むだけで古文の読み方&解き方が面白いほど身につく本』『岡本梨奈の1冊読むだけで漢文の読み方&解き方が面白いほど身につく本』『古文ポラリス[1基礎レベル][2標準レベル]』(以上、KADOKAWA)、『古文単語キャラ図鑑』(新星出版社)などがある。
『十訓抄』とは?
鎌倉時代中期の説話集で、若者のための教訓書です。十個の教訓を掲げて、具体的な話として約280話集められています。
『古今著聞集』と重複している話も多く、今回の「大江山」も(少しだけ原文の違いはありますが)同じ話が収録されています。
漫画でわかる!十訓抄「大江山」のあらすじ

十訓抄「大江山」の登場人物は?
●小式部内侍(和泉式部の娘)●定頼中納言
●和泉式部
●(藤原)保昌
十訓抄「大江山」の原文と現代語訳を読んでみよう
和泉式部が、(藤原)保昌の妻として、丹後の国に下向した頃に、京都で歌合わせがあったところ、小式部内侍が、歌詠みに選ばれて、(歌を)詠んだのを、定頼中納言がふざけて、小式部内侍が(局に)いた時に、
「(あなたのお母さんがいる)丹後へおやりになった人は帰参したか。どれほど待ち遠しくお思いになっているだろう。」と言って、局の前を通り過ぎられたところ、
御簾より半(なか)らばかり出でて、わづかに直衣の袖を控へて、
(小式部内侍が)御簾から半分ほど(身を)乗り出して、少し(定頼の)直衣の袖を引っぱって、
と詠みかけた。
(定頼中納言は)思いがけないことに、驚きあきれて、
「こはいかに、かかるやうやはある。」とばかり言ひて、返歌にも及ばず、袖を引き放ちて、逃げられけり。
「これはどういうことか。このようなことがあろうか、いや、ない。」とだけ言って、返歌もできずに、袖を引っ張って離して、逃げなさった。
小式部(内侍)は、この時から歌詠みの世界で評判が出てきた。
これはうちまかせての理運のことなれども、かの卿の心には、これほどの歌、ただいま詠み出だすべしとは、知られざりけるにや。
これは普通の道理にかなっていることであるが、あの卿〔=定頼中納言〕の心には、(和泉式部の娘である小式部内侍が)これほどの歌を、すぐに詠んで披露することができるとは、おわかりにならなかったのだろうか。
掛詞の意味をしっかり理解して、和歌の内容を正しく読み取れるようにしましょう。
また、和泉式部がとても優れた歌人であったことも知っておきたいポイントです。
この作品からは、娘の小式部内侍にもその才能が受け継がれていることがよくわかります。
当意即妙なやりとりで、定頼の言葉にさらりと反撃している場面に注目してみてください。(岡本先生)
十訓抄「大江山」の定期テスト対策!ポイントをチェック!
「歌合」とは何ですか。
左組と右組に分かれて和歌の優劣を競う遊び。「丹後へ遣はしける人」とは、何のために遣わしていると言いたいのですか。
歌合で披露する歌を母親の和泉式部に代作してもらうため。「心もとなく」のここでの意味を答えなさい。
「待ち遠しい」の意味です。「心もとなし」には「はっきりしない」「気がかりだ」「待ち遠しい」の意味があるので、前後の文脈を踏まえて、一番しっくりと訳せるものを選ぶとよいです。
「局」「御簾」「直衣」の読みを、それぞれ現代仮名遣いで答えなさい。
「つぼね」「みす」「のうし」と読みます。「直衣」は歴史的仮名遣いだと「なほし」です。
「袖を控へて」は、誰が誰の袖を控えるのですか。
「小式部内侍が定頼中納言の」です。「直衣」とは、貴族男性の平常服です。よって、ここでは「定頼中納言の服の袖」だとわかります。
その袖を控えた〔=引っ張った〕のは「小式部内侍」です。
「大江山」の和歌には掛詞が二つあります。抜き出して、それぞれ何と何の掛詞かわかるように説明しなさい。
「いく」が「生野(地名)」と「行く」の掛詞。/「ふみ」が「文〔=手紙〕)」と「踏み」の掛詞。この「大江山」の和歌で、詠者が一番伝えたかったことは何ですか。
母からの手紙なんて見ておらず、母に代作など頼んでもいないということ。「あさまし」の意味を答えなさい。
「驚きあきれる」の意味で、入試頻出単語です。「あきれる」はマイナス要素を強く感じる言葉ですが、なかには「プラス過ぎて驚きあきれる」の場合もあるので気をつけましょう。
「かかるやうやはある」を現代語訳しなさい。
「かかる」は、指示副詞「かく」に「あり」がついた「かかり」が活用したもので、「このような」と訳します。係助詞「や」は疑問と反語の意味がありますが、「やは」の場合は反語になりやすいです。
これらを踏まえて訳すと、「このようなことがあろうか、いや、ない」となります。
「覚え」の意味を答えなさい。
この「覚え」は名詞です。名詞「覚え」は、「評判」の意味です。古文の関連記事や学問をチェック!

定期テストに出やすい古文の単元はほかにもたくさんある。
岡本先生が現代語訳とポイントを解説してくれているので、テスト勉強に役立てよう。
●伊勢物語「初冠(ういこうぶり)」
●伊勢物語「筒井筒(つついづつ)」
●枕草子「中納言参り給ひて」
●大鏡「花山院の出家」 前編
●大鏡「花山院の出家」 後編
●平家物語「木曾の最期」
\古文に興味をもったキミへおすすめの学問/
●日本文学
古代から現代まで、あらゆる日本の文学作品を学ぶ学問。
日本文学の作品を読み、テーマや文体などの研究を通して、作品の背景となる歴史や文化、社会、人間そのものを研究する。
日本文学を学べる学校を探す
●日本文化学
日本独自の文化について研究する学問。
文学、芸術、民族、思想、日本語など、日本文化の特色をとらえ、日本の風土、歴史、社会などとの関連性を研究する。
日本文化学を学べる学校を探す
●歴史学
日本や世界各国の歴史と文化を研究する学問。
人間の文化、政治、経済などの歴史上のテーマを、それがどのように起こり、どんな意味をもつのか、資料や原典にあたり、実証的に研究、現代に生かしていく。
歴史学を学べる学校を探す
文・監修/岡本梨奈 イラスト/梶浦ゆみこ 構成/寺崎彩乃(本誌)