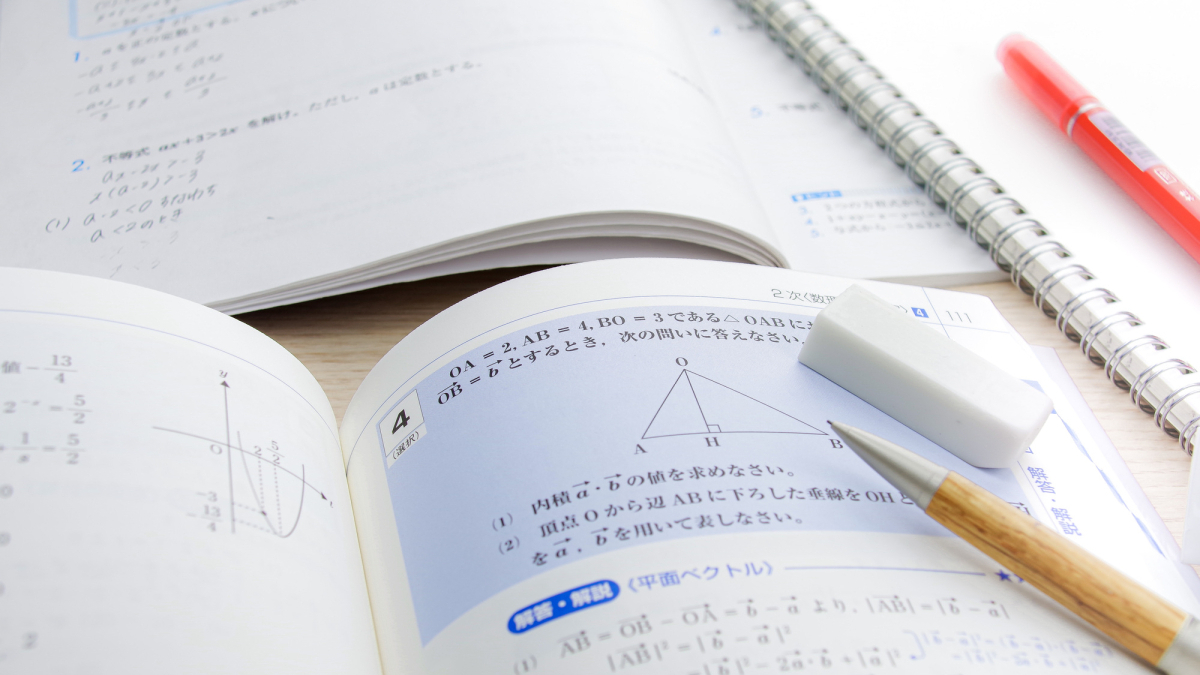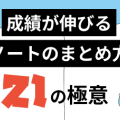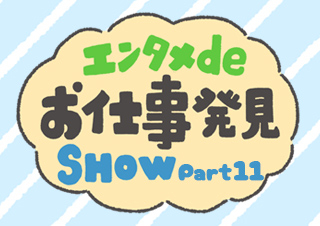【2025年最新!】共通テスト数学の時間配分方法を伝授!出題傾向から対策法まで徹底解説
「共通テストの数学の時間配分はどうすればいいの?」「時間切れになったらどうしよう」と思っている高校生も多いかもしれません。今回はスタサプ数学講師の山内先生に、共通テストの数学の時間配分とテストを受ける時に気をつけることを聞いてきました。
時間が足りなくなってしまって最後まで解けなかった!
実力を出せなかったということがないように共通テストを受ける高校生はぜひ、チェックしてみてくださいね。
目次
スタディサプリ高校講座の数学講師 山内恵介先生
 上位を目指す生徒のみならず、数学が苦手な生徒からの人気も高い数学講師。
上位を目指す生徒のみならず、数学が苦手な生徒からの人気も高い数学講師。数多くの数学アレルギー者の蘇生に成功。緻密に計算された授業構成と熱意のある本気の授業で受講者の数学力を育てる。
厳しい授業の先にある達成感・感動を毎年数多くの生徒が体験!
著書に、『「カゲロウデイズ」で中学数学が面白いほどわかる本』、『「カゲロウデイズ」で中学数学が面白いほどわかる本[高校入試対策編]』、『ゼッタイわかる 中1数学』、『ゼッタイわかる 中2数学』、『ゼッタイわかる 中3数学』(以上、KADOKAWA)監修。
共通テスト数学の特徴は?
どんな力が問われる?
文章や会話で与えられる設定を高速に、正確に読み解く力と、そこから得た情報を 数式に落とし込み、計算を着実に実行する力が問われます。日常生活に基づく設定や、会話文、条件を変化させるとどのようにグラフや図が変化するかを とらえる力が求められます。
試験時間は?
科目「数学Ⅰ、数学A」、「数学Ⅱ、数学B、数学C」ともに70分です。共通テスト 「数学Ⅰ、数学A」とは?
問題構成および配点例(令和7年度大学入学共通テストより)
| 選択方法 | 問題番号 | 出題内容 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 必答 | 第1問〔1〕 | 数学Ⅰ「数と式」 | 10 |
| 第1問〔2〕 | 数学Ⅰ「図形と計量」 | 20 | |
| 必答 | 第2問〔1〕 | 数学Ⅰ「二次関数」 | 15 |
| 第2問〔2〕 | 数学Ⅰ「データの分析」 | 15 | |
| 必答 | 第3問 | 数学A「図形の性質」 | 20 |
| 必答 | 第4問 | 数学A「場合の数と確率」 | 20 |
数学Ⅰ、数学Aの特徴や注意点

数学Ⅰ、数学A共に全問必答となります。 前課程で出題されていた数学A「整数の性質」に関する問題は、出題範囲から外れています。
また数学Ⅰ「データの分析」に「外れ値」「仮説検定の考え方」が追加され、数学A「場合の数と 確率」に「期待値」が追加されました。
前課程やそれ以前の課程の共通テストやセンター試験の 過去問に取り組む際には注意が必要です。
共通テスト 「数学Ⅱ、数学B、数学C」とは?
問題構成および配点例(令和7年度大学入学共通テストより)
| 選択方法 | 問題番号 | 出題内容 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 必答 | 第1問 | 数学Ⅱ「三角関数」 | 15 |
| 必答 | 第2問 | 数学Ⅱ「指数・対数関数」 | 15 |
| 必答 | 第3問 | 数学Ⅱ「微分・積分」 | 22 |
| いずれか 3問を 選択 |
第4問 | 数学B「数列」 | 16 |
| 第5問 | 数学B「統計的な推測」 | 16 | |
| 第6問 | 数学C「ベクトル」 | 16 | |
| 第7問 | 数学C「平面上の曲線と複素数平面」 | 16 |
数学Ⅱ、数学B、数学Cの特徴や注意点

数学Ⅱは全問必答、数学B、数学Cは大問4問中3問の選択となります。
数学B「統計的な推測」に「仮説検定」が追加されました。また「ベクトル」は前課程では数学B、でしたが、現課程では数学Cとなります。さらに、数学C「平面上の曲線と複素数平面」が出題範 囲に追加されました。
前課程やそれ以前の課程の共通テストやセンター試験の過去問に取り組む際 には注意が必要です。 \この分野の推薦入試を受ける人必見!/
【医学部・薬学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【建築学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【農学部・生物学部・水産学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【情報・データサイエンス・IT系学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
共通テストの数学「数学Ⅰ、数学A」おすすめの時間配分とポイントは?
| 大問 | 単元 | 内容・特徴 | 目安時間 | アドバイス |
|---|---|---|---|---|
| 大問1 | 数と式 | 展開・因数分解・方程式・不等式・集合など短時間で正確に解こう | 約7分 | 大問1を20分前後で解く |
| 図形と計量 or 2次関数 | 会話文・日常設定を数学的に読み解く力が必要 | 約12分 | ||
| 大問2 | データの分析 | 図・グラフ・文章の読み取りが多く時間を要する | 約11分 | 大問2を20分前後で解く |
| 残りの単元(図形or関数) | 大問1で出ていない単元が出題される | 約9分 | ||
| 大問3 | 図形の性質 | 中学内容(円・相似)も復習を図形条件から定理・知識を引き出す問題 | 約14分 | 大問3と4を28分で解く 後半で落ち着いて取り組むこと! |
| 大問4 | 場合の数と確率 | 期待値など段階的に解く途中の結果が後問に影響する構成も多い | 約14分 |
それぞれ詳しく設問ごとに見ていきましょう。
大問1、大問2はそれぞれ約20分前後で解こう!
データの分析に時間をかけ過ぎないように。数学Ⅰ「数と式」「図形と計量」「2次関数」「データの分析」が大問1、大問2に2つずつ振り分 けられて出題されることが予想されます。
「数と式」は、展開、因数分解、方程式、不等式、集合などの知識が問われます。7分前後で解きましょう。
「図形と計量」(三角比)、「2次関数」は、各単元ごとの学習で身につけた数学の問題を解く力に 加え、日常生活に基づく設定を数学的に読み解く力、太郎さんと花子さんの会話を理解して 数学の課題に落とし込む力などが求められます。
文章量や会話量にもよりますが、12分前後で解き ましょう。 「データの分析」は、設定や問われていることを文章やデータ、図から理解し読み解くのに時間が 比較的かかります。
11分前後で解きましょう。
大問1を20分前後、大問2を20分前後、大問1と大問2が終了した時点で試験開始から40分前後、残りの大問2つに30分前後を残すことを目標にするとよいでしょう。
大問3は14分で解こう!
図形の特徴から使う知識を引き出す力が求められる。大問3は「図形の性質」からの出題です。与えられた図形において、長さや角度、位置関係などの 条件から、問題を解くために必要な知識や定理などを引き出す力が求められます。
高校の範囲のみならず、中学範囲の図形の知識も活躍します。
特に、円の性質や相似について振り 返っておくとよいでしょう。
14分前後で解き終えることを目標にし、大問4を解く時間として15分程度を残しておくとよいでしょう。
大問4は14分で解こう!
期待値は確率の集大成 !大問4は「場合の数と確率」からの出題です。
苦手にしている人が比較的多い分野ですが、適切な誘導や、ある問題の答えが次の問題を解くために必要なものの一部になっているケースがあります ので、自分が出したものを整理しながら進めていくとよいでしょう。
特に、期待値を出すためには、すべての場合が整理され、その確率が求められている必要があります。
共通テストの数学「数学Ⅱ、数学B、数学C」おすすめの時間配分とポイントは?
| 大問 | 単元 | 内容・特徴 | 目安時間 | アドバイス |
|---|---|---|---|---|
| 大問1 | 三角関数 | 会話文による誘導あり。変域や関数の値の範囲に注目。読み解き力が必要 | 約10分 | 大問1と2を20分前後で解く |
| 大問2 | 指数・対数関数 | 日常設定ベースの問題が多い。グラフや条件整理に注意 | 約10分 | |
| 大問3 | 微分・積分 | 最大級の配点。変化の割合・接線・面積などを読み解く力が問われる | 約15分 | 大問1〜3を約35分で解く。基礎3題を確実に、35分以内を目安に処理 |
| 大問4 | 数列 | 漸化式・Σ計算など、数式処理力を要する | 約11分 | 約33分で解く!選択3問なので得意分野を3つ選ぼう! 迷う場合は“解きやすそうなもの”を選ぶのも有効 |
| 大問5 | 統計的な推測 | 新傾向。統計量・母集団・標本など、分布や推測に関する理解が必要 | 約11分 | |
| 大問6 | ベクトル | 平面図形の位置関係に注目。内積・成分表示・図形的意味の理解がカギ | 約11分 | |
| 大問7 | 平面上の曲線と複素数平面 | 新範囲。複素数平面や軌跡に関する出題あり。過去のセンター試験(1997〜2005年)も参考になる | 約11分 |
それぞれ詳しく設問ごとに見ていきましょう。
大問1、2はそれぞれ10分で解こう!
三角、指数、対数関数は範囲に注目!大問1、大問2は「三角関数」「指数・対数関数」が大問1、大問2に振り分けられて出題される ことが予想されます。
それぞれ、10分前後で解くとよいでしょう。
三角関数は、会話による気づきや誘導、指数・対数関数は、日常生活に基づく設定などが出題され、いずれも読み解くのに時間が必要です。
変域や関数のとり得る値の範囲に注目して問題を解き進めましょう。
大問3は15分で解こう!
微分・積分は、山場の一つ 。大問3は「微分・積分」からの出題となります。
配点が、前課程までの30点から、およそ27%減 の22点に減少しましたが、それでも、単一分野としては、共通テストの数学の大問で最大級の 配点であることに変わりはありません。
重点的に演習を積んでおきましょう。解く時間の目安は 15分前後となります。大問3を解き終えた時点で、試験開始から35分が経過しているのが理想です。
大問4、5、6、7はそれぞれ11分で解こう!
選択する大問を3つ決めておこう 。大問4、5、6、7は「数列」「統計的な推測」「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」が各大問に振り分けられ、大問4問から3問選択する形式です。それぞれ、11分前後で解くとよいでしょう。
「数列」「統計的な推測」「ベクトル」は、前課程までの20点から、およそ20%減の16点に減少 しました。
また、前課程は選択する問題数が2問でしたが、3問選択する形になったため、問題の 設定を読み解くための時間がより求められます。
「数列」「統計的な推測」「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」をすべて学んでいる人は、 自分の得意分野の上位3つを選ぶことになるでしょう。
余裕がある人は、本番、選択問題を眺めて、 ぱっと見で解きやすそうなものを選ぶとよいでしょう。
「平面上の曲線と複素数平面」は、新たに共通テストに加わった範囲です。
このうち、複素数平面 は、1997年~2005年のセンター試験「数学Ⅱ・数学B」にて出題されていますので、参考にする とよいでしょう。
時間切れを防ぐための対策6選

時間配分のイメージをもつ
共通テストの数学は、時間との闘いです。そのためは、大問すべてを70分で解く時間的感覚が必要です。ご紹介した時間配分を参考に、11月ごろを目処に、すべての大問を通して70分で解く感覚を体に覚え込ませていきましょう。
1つの問題にこだわりすぎない
数学は、ある問題の結果が次に影響することが多い教科です。よって、ある問題で詰まったときの焦 りが、こだわりにつながり、その結果、ほかの大問にかけるべき時間を奪ってしまいます。
詰まってしまったら、そこまでに費やした時間と、その大問にあと何分つぎ込めるのかを記録したうえで、思い切 って次の大問に進んでみましょう。
流れを把握する
共通テストの問題は、単問の集合ではなく、一連の流れを作っています。与えられた1つひとつの問題をこなすだけでなく、自分が出したものが、その流れの中でどういう意味をもつのか、を常に意識することで、次の問題を解くときの鍵になったり、足りない部分を自分で埋める必要性に気づいたりします。
典型的な解法を身につけておく
すべての問題について、どう解くのかを考えながら進めると、確実に時間が足りなくなります。参考書に掲載されている問題のうち、中程度の難易度の問題について、見た瞬間に解法の方針が 浮かぶかをチェックし、似たような場面に出会ったときに思考をスキップできるようにしておくと よいでしょう。
普段から高速に計算しミスを洗い出す
プレッシャーの中では、今までやったことのないミスをする可能性があります。普段の演習のときに 自分の中のトップスピードで計算してみると、思わぬミスをするかもしれません。
どういうときにそのミスが起こるのかを自覚すれば、それに近しい場面で意図的にスピードを落とす、といった工夫ができるようになります。
普段から対話を大切にする
友人との対話を通じ、相手が何を言いたいのかを理解する練習とともに、「今、言いたかったことは こういうこと?」といったように、相手の言った内容のサマリー(要約)を整理し、言語化する練習をしておくとよいでしょう。共通テスト数学の試験対策は何をすればいいの?

一連の流れで形成される問題に慣れるためには、共通テストの過去問が有効です。
範囲外の問題に 注意しながら、誘導に乗る、行間を埋める、今までやったことを整理しながら進める、といった訓練 をするとよいでしょう。
\過去問を解く時のアドバイス/
共通テストの過去問は、まずは大問別に時間制限なく取り組むとよいでしょう。
解き終わったら、解答解説を最後までじっくり読み、解けなかった部分も含めて理解した後、再度、その大問を最後 まで自力で解き、流れを自分の中に作ることを心がけましょう。時間を測ってすべての大問を通すの は、直前期で構いません。
共通テスト模試およびその改題を集めた問題集が、予備校各社から出版されています。
共通テストの 形式に慣れるために利用するとよいでしょう。
共通テストを受験する高校生へメッセージ

共通テストは、過去問を何年分も行ってパターンに慣れれば解ける、といった、いわゆる「対策」が 通用するテストではありません。
いま目の前にある場面は、今までに経験したことのないものである 可能性が高いと思ってください。
そこで起こっていることを、限られた時間で理解し、流れを損なわない形で、最も適した数学的ソリューションを採用し、実行する力が求められています。
普段の学習から、パターンマッチングや解法の丸暗記ではなく、他者理解や、自分の言葉でアウトプットする練習を心がければ、数学的に難しいテストではありません。
この共通テストに向けた学習が、自分の将来に必要なスキルアップにつながります。
過去問や模試で時間配分を意識した実戦練習を重ねることが大切!
今回は、共通テスト数学(数学Ⅰ・A、数学Ⅱ・B・C)のおすすめの時間配分から問題の出題傾向、対策まで詳しく山内先生に教えていただきました。共通テスト数学では、限られた時間内で効率よく解き進めるために、戦略的な時間配分が不可欠です。
数学Ⅱ・B・Cでは、得意分野を見極めて選択する判断力も求められます。 いずれの科目も、問題文の読解・条件整理・計算処理を効率よく進める力がカギとなるため、過去問や模試で時間配分を意識した実戦練習を重ねておくことが、高得点への最短ルートです。
ぜひ、共通テストの数学の時間配分を参考に自分にあった時間配分を見つけてみてくださいね。
文・監修/山内恵介 構成/スタサプ編集部 \この分野の推薦入試を受ける人必見!/
【医学部・薬学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【建築学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【農学部・生物学部・水産学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【情報・データサイエンス・IT系学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き