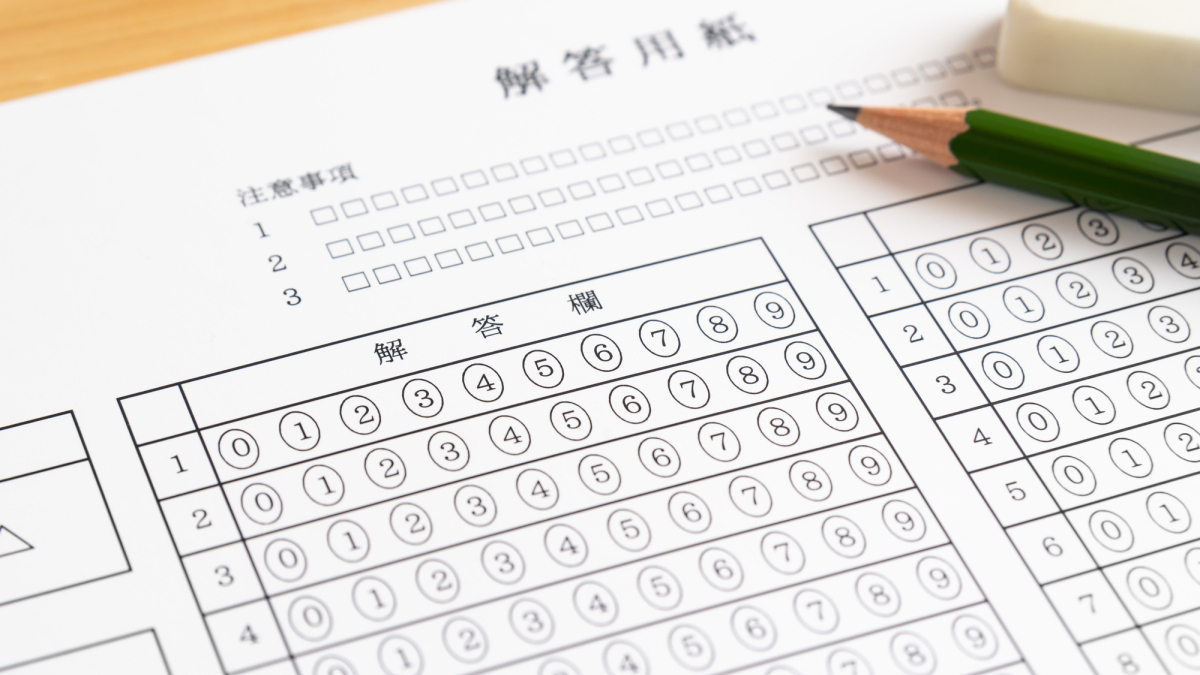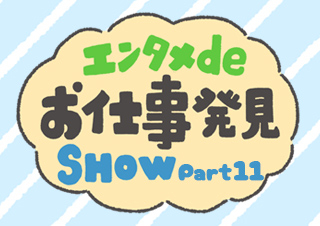共通テスト理科の時間配分を伝授!出題傾向と対策を把握して得点源に
「共通テストの理科の時間配分はどうすればいいの?」「時間切れになったらどうしよう」と思っている高校生も多いかもしれません。今回は、スタディサプリの理科各分野の担当講師の先生方に、共通テストの理科の時間配分とテストを受ける時に気をつけるポイントを聞いてきました。
時間が足りなくなってしまって最後まで解けなかった、実力を出せなかったということがないように共通テストを受ける予定の高校生はぜひ、チェックしてみてくださいね。
今回教えてくれたのは…
【物理担当】中野喜充先生

スタディサプリ「共通テスト対策講座 物理」「共通テスト対策講座 物理基礎」を担当。
【化学担当】坂田薫先生

スタディサプリ「共通テスト対策講座 化学」「共通テスト対策講座 化学基礎」を担当。
【生物担当】牧島央武先生

スタディサプリ「共通テスト対策講座 生物」「共通テスト対策講座 生物基礎」を担当。
【地学担当】野津太一先生

スタディサプリ「共通テスト対策講座 地学基礎」を担当。
目次
- 2025年度共通テスト理科の変更点
- 近年の共通テスト理科の傾向は?
- 共通テスト理科の時間配分の重要性
- 共通テスト理科の試験時間と配点
- 理科の先生から科目別におすすめ時間配分のアドバイス!
- 物理基礎のおすすめの時間配分
- 化学基礎のおすすめの時間配分
- 生物基礎のおすすめの時間配分
- 地学基礎のおすすめの時間配分
- 物理のおすすめの時間配分
- 化学のおすすめの時間配分
- 生物のおすすめの時間配分
- 地学のおすすめの時間配分
- 理科の先生から時間切れを防ぐためのアドバイス
- 物理基礎の時間切れを防ぐアドバイス
- 化学基礎の時間切れを防ぐアドバイス
- 生物基礎の時間切れを防ぐアドバイス
- 地学基礎の時間切れを防ぐアドバイス
- 物理の時間切れを防ぐアドバイス
- 化学の時間切れを防ぐアドバイス
- 生物の時間切れを防ぐアドバイス
- 地学の時間切れを防ぐアドバイス
- 共通テスト理科の対策法
- 共通テストを受験する高校生へのメッセージ
- 共通テスト理科で得点するために大切なこと
2025年度共通テスト理科の変更点
.jpg?20260210)
2025年度の共通テスト理科では、大問数や試験時間、出題傾向にいくつかの変更がありました。
理科の受験科目数に応じた試験時間は、1科目受験で60分、こちらは変更なしです。
2科目受験では120分が10分追加されて実施方式に変更があり、130分(解答時間120分)に設定されています。
生物は大問数が6題から5題に減少しました。
これは近年の減少傾向の延長であり、これ以上の減少は考えにくいものの、今後も5~6題の構成が続くと予想されます。
文章量や処理すべき情報量は減りましたが、考察重視の傾向が強まり、全体の難易度は大きくは変わっていません。
2025年度の生物は、共通テスト開始以来の乱高下を経て、最もバランスが取れた標準的な難易度と言えるため、今後の試験対策の指標として適しています。
生物基礎では大問3題の構成やテーマに大きな変化はありませんが、第1問で仮説検証を問う新傾向の問題が登場しました。
どの大問でも初見の情報を提供し、知識を単に問うのではなく、知識を運用し、グラフや図から情報を読み取って根拠を導く力がより重視されています。
物理分野では力学が必須となり、熱や電気の融合問題も増加しました。
地学では、実験や観察データを活用する問題が多く、資料読み取りや考察力が一層求められます。
全体的に、基礎知識だけでなく、資料やグラフを正確に読み取り、考察・応用する力を鍛えることが重要になっています。
近年の共通テスト理科の傾向は?

各科目とも日常生活や資料に基づく応用力が求められる。知識だけでなく、グラフや実験データの読解力、考察力、全体を俯瞰して解く力が重要です。
各先生方に共通テスト理科の傾向を単元ごとにうかがいました。
物理基礎の傾向は?
基本的な知識問題や計算問題だけでなく、日常生活や実際の技術と関連した問題も出題されます。この場合、資料やグラフから情報を読み取り、物理の基本法則を理解し適用する力が求められます。
力学・電気・波動・熱量のうち、力学は必須です。また、熱と電気に関してはジュール熱の計算など、融合問題も出題されます。
さらに、放射線やエネルギー資源およびその変換に関する知識問題も出題されるため、注意が必要です。
化学基礎の傾向は?
第1問は基礎的な知識や計算に関する小問集合です。各単元で正しい知識が身についているか、モルや濃度の基本的な計算ができるかが問われます。基本的なグラフなど、一度は見たことのあるものが出題されることもあります。
第2問は新しい実験などを題材にした総合問題で、比較的長い問題文から要点を読み取り、グラフや資料のデータと合わせて解答する力が求められます。
いずれもすべての単元から幅広く出題されます。
生物基礎の傾向は?
生物基礎では、大問3題のテーマが固定化されています。第1問:細胞・代謝・遺伝子
第2問:恒常性・免疫
第3問:生態系
第1問は、実験考察や仮説検証などやや難しい内容になりやすい傾向があります。
一方、第2問と第3問は身近な題材を扱い、生物基礎の内容を問う問題が多いが、いずれの大問でもグラフや図の読み取りが求められます。
地学基礎の傾向は?
地学基礎では、基本的に全単元からまんべんなく出題され、知識問題が中心で、・地球環境の変化(地球温暖化など)
・日本の自然環境(各種の災害など)
については特に頻出です。
また、過去のできごとを推定する方法や、物事の原因に関する理解を問う問題も多く出題されています。
物理の傾向は?
基本的な知識問題や計算問題、そしてセンター試験の時と同様の問題だけでなく、日常生活や実際の技術と関連した問題も出題されます。この場合、資料やグラフから情報を読み取り、物理の基本法則を理解し適用する力が求められます。
化学の傾向は?
全単元から幅広く出題されます。基礎知識や簡単な計算に関する問題だけでなく、教科書に載っていない物質や反応を扱う問題もあり、問題文で与えられた情報を正確に読み取る力が求められます。
また、実験に関する問題も出題されるため、学校での実験に真剣に取り組んだり、資料集などで実験関連の内容を確認しているかどうかも問われます。
生物の傾向は?
生物では考察を重視する姿勢は変わらないが、知識を駆使して与えられたデータを正確に読み取り、それに基づいて解答することが王道の出題形式となっています。リード文や設問文、図の中に情報が凝縮されているため、生物で高得点を狙うにはまず「読解力」が必要だと言えます。
また、標準的な難易度であるからこそ、取りこぼしなく全問にしっかり解答することが求められます。
ひとつの問題に固執せず、全体を俯瞰しながら解答する力も重要です。
地学の傾向は?
地学では、知識問題を中心に基本的に全単元からまんべんなく出題されます。これらを含め、問題文や図表で示された情報と自分の知識を組み合わせ、その場で計算や考察を行う問題が多く出題されています。
なお、「地学」の教科書で説明されていない「地学基礎」範囲の知識を用いて解答する問題も、一定数出題されています。
共通テスト理科の時間配分の重要性

共通テスト理科は、各大問に「易→難」の傾斜がついています。
科目により違いはありますが、初めの問題は比較的解きやすい問題が多いため、ここで確実に得点を積み重ねることが重要です。
しかし、後半の難問に時間をかけすぎると、ほかの問題を解く時間が足りなくなり、得点機会を逃してしまうことにもなりかねません。
時間配分を意識して、全体を俯瞰しながら解答を進めることで、効率的に得点を最大化できるでしょう。
特に、時間切れを防ぎ、得点を落とさないためにも、見切りの判断と見直し時間の確保がカギとなります。
共通テスト理科の試験時間と配点
理科1科目受験の場合
【選択肢①】発展科目(物理・化学・生物・地学)を1科目選択
試験時間:60分配点:100点
理系学部を受験する場合でも、私立大学では理科1科目だけで良いこともあります。
【選択肢②】基礎科目(物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎)から2科目選択
試験時間:60分(2科目合わせて)配点:100点(各科目50点ずつ)
基礎科目は、文系学部や看護・教育・福祉系などを志望する受験生によく選ばれます。
※どの2科目を選ぶか、またどの順に解くか、時間配分もすべて受験生の自由です。
理科2科目受験の場合(発展科目×2)
試験時間:130分(うち解答時間は120分)配点:200点(各科目100点)
理系の国公立大学を志望する場合、多くがこのパターンです。
試験時間130分のうち、間の10分間は答案回収などの時間であり、実際の解答時間は120分。
各科目60分間で、選択した2科目(例:物理+化学、生物+地学など)を解いていきます。
解答の順番は受験生の裁量に委ねられています。
★受験パターン別まとめ表★
| 受験方式 | 科目数 | 科目の種類 | 試験時間 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 理科1科目 | 発展科目ひとつ | 物理・化学・生物・地学 | 60分 | 100点 |
| 理科1科目 | 基礎科目ふたつ | 物理基礎+化学基礎など | 60分(2科目合計) | 100点(各50点) |
| 理科2科目 | 発展科目ふたつ | 物理+化学など | 130分(解答時間120分) | 200点(各100点) |
───────
各大学により出願条件や科目指定は異なります。大学によっては「第1解答科目を利用する」などの指定がある場合があるので、志望校の入試要項を必ず確認してください。
特に基礎科目については、解答順や時間配分を工夫することで、得点効率が大きく変わることがあります。
──────────
共通テストの理科は、「受験する科目」と「科目数」によって、試験時間や配点、難易度が大きく異なります。
基礎科目は広く浅い知識を求められ、発展科目はより専門的な内容が問われます。
自分の志望校や得意分野に応じて、最適な受験パターンを選びましょう。
そして、試験本番では限られた時間の中で実力を発揮できるよう、時間配分の練習も忘れずに!
理科の先生から科目別におすすめ時間配分のアドバイス!
| 教科 | 大問数 | 目安時間(分) | コメント |
|---|---|---|---|
| 物理基礎 | 3問 | 各10分以内 | 基礎問題はすばやく解き、計算や考察に時間を残す |
| 化学基礎 | 2問 | 第1問:15分、第2問:15分 | 知識問題はスピーディーに、総合問題は落ち着いて解答 |
| 生物基礎 | 3問 | 各10分以内 | 知識問題は迅速に解き、考察問題に十分な時間を割く |
| 地学基礎 | 3~4問 | 第1問:10分、第2~4問:各5分 | 知識問題は悩まずに解き、計算・考察問題に時間を残す |
| 物理 | 5問 | 各10分程度 | 知識問題は1分以内で解き、計算・考察問題はじっくりと |
| 化学 | 5問 | 各10分程度 | 得意分野は確実に得点、難問は後回しにする戦略を |
| 生物 | 5問 | 各10分程度 | 全体を俯瞰し、解ける問題から確実に得点を取る |
| 地学 | 5問 | 各10分程度 | 難問で時間を浪費せず、全体のバランスを重視 |
物理基礎のおすすめの時間配分
大問3題のうち、第1問は知識を問う問題が多い。簡単な問題ばかりではないが、ここは手早く解いて第2問と第3問に時間をかけたいですね。また、第2問以降は、身のまわりのものに関する問題や実験問題、データを読み取って考える問題が出題されることが多いです。
はじめに問題文をしっかりと読み、多少時間をかけても何の話題で何を問われているのかをていねいに把握しましょう。
そのうえで、データの読み取りや考察には時間をかけ、計算は手早く済ませるよう心がけることが重要です。
化学基礎のおすすめの時間配分
第1問の知識問題や基本的な計算については、スピーディーに解答しましょう。第2問では、落ち着いてリード文を読み、与えられたグラフなどのデータと合わせて解答していくことが大切です。
生物基礎のおすすめの時間配分
各大問には10分以内(理想は8分)で解答する必要があります。知識のみで対応できる大問内の前半の問題は、できるだけ迅速に解きましょう。ただし、正誤判断の根拠となった情報には「印」をつけておくことです。それが見直しの精度と速度を高めます。
残り時間は考察問題にあてるが、必ず5分程度は見直しの時間を確保しましょう。
その時間を有効に使うためにも、見直すべき大問や小問、選択肢には事前に「印」を付けておくことが大切です。
地学基礎のおすすめの時間配分
第1問に10分、第2問から第4問までは各5分(第3問までの場合は第1問に15分、それ以外は同じ)を目安です。単純な知識問題は悩みすぎず、1問あたり1分以内、4文から正文や誤文を選ぶ問題でも約2分程度を目安に解いていきましょう。
自信のない問題にはあとで確認できるよう印をつけておくと良いですね。
図表の読み取りや計算・考察を要する問題は、焦らずじっくり考えることが重要です。
ただし、難しすぎて上記の大問ごとの目安時間を超えそうな場合は、一旦飛ばして次の問題に進むことも大切です。
物理のおすすめの時間配分
第1問は知識を問う問題が多いです。簡単な問題ばかりではないが、ここは手早く解いて第2問以降に時間をかけたいですね。
また、第2問以降では、身のまわりのものに関する問題や実験問題、データを見て考察する問題が出題されることがあります。
その際は、まず問題文をていねいに読み、多少時間をかけても何の話題で何を問われているのかを正確に把握しましょう。
そして、データの読み取りや考察には時間をかけ、計算は手早く済ませるように心がけることが重要です。
化学のおすすめの時間配分
知識を問われる正誤問題や、簡単な計算問題についてはスピーディーに解答しましょう。そして、見たことのない物質や反応を扱う問題や、実験のデータから必要な情報を読み取る問題などは、落ち着いてゆっくりと問題文を読んでいきましょう。
生物のおすすめの時間配分
各大問には10分程度で解答する必要があります。知識のみで対応できる大問内の前半の問題は、できるだけ迅速に解きましょう。それでも、正誤判断の根拠となった情報には「印」を付けておくことが大切です。これが見直しの精度と速度を高めてくれます。
残り時間は考察問題にあてるが、必ず5分以上は見直しの時間を確保しましょう。
その時間を有効に使うためにも、見直すべき大問や小問、選択肢には事前に「印」を付けておくようにしよう。
地学のおすすめの時間配分
第1問から第5問まで、各10分程度を目安としましょう。各大問には5~6問程度の小問があるので、知識や単純な図表の読み取りで解ける問題は各1分程度で解き、複雑な図表の読み取りや計算・考察問題に時間を確保するイメージをもつとよいでしょう。単純な知識問題は悩みすぎないことが大切であり、自信のない問題にはあとで確認できるよう印をつけておくと良いですね。
図表の読み取りや計算・考察を要する問題は、焦らずじっくり考えることが重要です。
ただし、難しすぎて上記の大問ごとの目安時間を超えそうな場合は、一旦とばして次の問題に進むことも大切です。
理科の先生から時間切れを防ぐためのアドバイス

時間切れを防ぐには、問題ごとの目安時間を意識し、難しい問題は一旦飛ばすことが重要です。
確実に得点できる問題を優先し、全体を見渡す力と見切りの判断がカギとなるようです。
各先生方にアドバイスをもらいました。
物理基礎の時間切れを防ぐアドバイス
ひとつの目安としては、第1問に8分、第2問に10分、第3問に10分を目標としましょう。もしどこかでつまずいて考え込んでしまい、この時間を超えそうな場合は、一旦その問題を切り上げて次の問題に進むのが効果的です。
化学基礎の時間切れを防ぐアドバイス
第1問の小問集合をなるべく短い時間で解くようにしましょう。また、第2問に関してはざっと全体を確認し、化学反応式の係数を埋める問題など、確実に点数を取れる部分については優先して解答していきましょう。
生物基礎の時間切れを防ぐアドバイス
時間切れを防ぐためには、読み取れないグラフや図にいかに見切りをつけるかが重要です。グラフの意図がまったく理解できない場合は、次の大問に移るのが良いでしょう。
特に生物基礎では、それぞれの大問がA問題・B問題に分かれており、次に移ってもリスクはそれほど大きくないでしょう。
まずはとばしてでも、一とおり問題に目を通すことを目標にしましょう。
地学基礎の時間切れを防ぐアドバイス
地学基礎は、試験時間に対する問題量がそれほど多くなく、無理なく解答できる受験生が多いでしょう。ただし、年度によっては後半にやや難しい考察問題が配置されていることがあり、残り時間が少ないと解答が厳しくなる場合があります。
知識問題に時間をかけすぎず、考察問題に十分な時間を割けるよう、試験の受け方をあらかじめ練習しておくと良いでしょう。
物理の時間切れを防ぐアドバイス
第1問は8分、そのほかはそれぞれ10分程度を目安とするが、何よりも一とおり全問題に目を通せるよう時間を意識して進めましょう。どこかでつまずいて時間がかかりそうになったら、一旦その問題を飛ばして先に進み、時間に余裕があれば最後に戻って再度考える方法が効果的です。
化学の時間切れを防ぐアドバイス
第1問から順に解いていくのではなく、自分の得意な分野から解いていき、得意分野は確実に得点を取るようにしましょう。また、知識を問われる正誤問題や簡単な計算問題を優先して解き、残った時間で見たことのない物質や反応を扱う問題や、実験のデータから必要な情報を読み取る問題を解いていくと良いですね。
とにかく、確実に点数が取れる問題が時間切れで解答できなくならないよう、優先して解くべき問題を判断して解いていくことが重要です。
生物の時間切れを防ぐアドバイス
時間切れを防ぐためには、読み取れないグラフや図にいかに見切りをつけるかが重要です。グラフについて1点でも納得できるポイントがあれば、そこにこだわってみるのも良いです。
しかし、グラフの意図がまったく読めない場合は、次の大問に移るほうが良いかもしれません。
その際は戻るための「印」を付けておき、一とおり問題に目を通したあとで優先的に戻るようにしましょう。
地学の時間切れを防ぐアドバイス
地学では、時間をかけて考察することが必要な難問が所々に存在します。これらに時間を取られすぎると、本来解けるはずの知識問題にも十分な検討時間がなくなり、解答が厳しくなってしまいます。
途中で難しい問題に当たった場合は、一度飛ばしてそれ以外の問題に十分な時間を割き、確実に得点するという練習を積んでおくと良いでしょう。
共通テスト理科の対策法
物理基礎の共通テスト対策
実験タイプの問題では「何を測定したいのか」、そして、そのために「どのようなデータが示されているのか」をしっかり確認しましょう。問題を解くために必要な知識は、教科書などで通常の学習を通じて身につけてきたものだけです。不安にならずに落ち着いて取り組みましょう。
化学基礎の共通テスト対策
第1問の基礎的な知識や計算は悩むことなく解けるように「正確な知識を頭に入れること」「モルや濃度の計算はスムーズに立式すること」を、日頃からトレーニングしておきましょう。第2問の総合問題はグラフや資料からデータを読み取る練習をしっかりしましょう。
生物基礎の共通テスト対策
まずは知識を盤石にしましょう。知識問題の演習では、選択肢の一つひとつについて正誤の根拠を明確にし、ていねいに理解することが大切です。知識問題を安定して解けるようになると、考察問題に挑戦するための下準備となり、考察問題に割く時間も確保できるため、良いことずくめです。
地学基礎の共通テスト対策
まずは正確な知識を自分のものにすることが大切です。その際、教科書やスタディサプリの講座で図表を用いて、図表の意味を説明されている部分は意識的に確認しておくと良いでしょう。
ただし、知らない、あるいは忘れてしまった知識に関する問題でも、問題文や図表をヒントにして正答できる場合があります。
落ち着いて問題文や図表と向き合えるよう、基本知識のインプットが終わったあとは、過去問や本番形式の問題集で練習することが重要です。
物理の共通テスト対策
実験タイプの問題では、「何を測定したいのか」、そのために「どのような量のデータが示されているのか」をしっかり確認しましょう。問題を解くために使う知識は、教科書などを通じて普通に学習して身につけてきたものです。不安がらず、自信をもって取り組みましょう。
化学の共通テスト対策
正確な知識を頭に入れること、そして単純暗記ではなく理解する習慣をつけておくことが重要です。また、見たことのない物質や反応に関しては問題文で必ずヒントが与えられるため、落ち着いてしっかりと情報を読み取ることができるよう、普段から二次化学の問題なども利用して向き合っておきましょう。
生物の共通テスト対策
共通テスト形式の演習を大量にこなしましょう。共通テストの生物では、初見の設定をいかに正確に読み取れるかが重要です。
同じ問題を繰り返すのではなく、初見の問題に多く触れることで、その力を養っていきましょう。
また、解説もていねいに読むことが大切です。読解力の向上と知識の補充につながるはずです。
地学の共通テスト対策
まずは教科書の全範囲について、正確な知識を自分のものにしておくことが大切です。教科書の語句が多すぎて、どれを覚えるべきか判断が難しい場合は、スタディサプリの「ベーシックレベル地学」を参考にすると良いでしょう。この講座で扱われている知識は、共通テスト受験に向けて覚えておくべき内容です。
また、「地学基礎」を学習してから時間が経っている場合は、教科書やスタディサプリの講座を使って復習しておくと安心です。
さらに、考察や計算問題への対策には、共通テスト対策の問題集がおすすめです。
一とおりの学習が終わったら、過去問を活用して時間配分も含めた実践的な練習を行いましょう。
共通テストを受験する高校生へのメッセージ
物理担当 中野喜充先生のメッセージ
勉強をいくら重ねても不安が残るのは、誰もが経験することだ。ただ、そこで焦っても良い結果は生まれない。
必要な知識をしっかり頭に入れ、典型的な解き方を100%マスターし、十分な演習を積むことが大切だ。
不断の努力こそが、あなたの最大の武器である。自信をもって目の前の問題に冷静に対処できる力を身につけられるよう、着実に進めていこう。
化学担当 坂田薫先生のメッセージ
一つひとつの単元をしっかり理解することを継続していけば、必ず目標点を取ることができます。苦手意識のある単元はスタサプの授業を何度も見て、克服しておきましょう。皆さんが第一志望に合格できるよう、応援しています。
生物担当 牧島央武先生のメッセージ
今の君の努力は、必ず血となり肉となり、君を支えるものになります。自分の可能性を自分で切り開いていることを自覚してください。それはすばらしいことです。
地学担当 野津太一先生のメッセージ
共通テストの地学基礎や地学は、しっかりとした基礎知識と、共通テストそのものへの対策の掛け合わせで得点を伸ばすことができます。共通テスト本番まで、こつこつと努力を積み重ねていきましょう。応援しています!
共通テスト理科で得点するために大切なこと
共通テスト理科は、単なる知識の暗記だけでなく、与えられた資料やグラフを読み取り、考察力を働かせる力が求められます。2025年度の試験でも、基礎的な知識問題から応用的な考察問題まで幅広く出題されており、時間配分の工夫が合否を大きく左右します。
特に理科基礎科目では、2科目を60分で解く必要があり、問題の優先順位を見極めて解答を進めることが重要です。
また、どの科目も問題文や図表で与えられた情報を正確に読み取る力が不可欠です。難しい問題に固執せず、まずは確実に得点できる問題を確保し、時間をうまく使いながら見直しの時間も確保することが合格へのカギとなります。
最後に、共通テストは自分の実力を出し切る場です。
日頃の積み重ねを信じて、時間配分や解答順序を自分なりに工夫し、本番では焦らず冷静に問題に向き合うことが得点アップに繋がります。
文・監修/中野喜充・坂田薫・牧島央武・野津太一 構成/スタサプ編集部