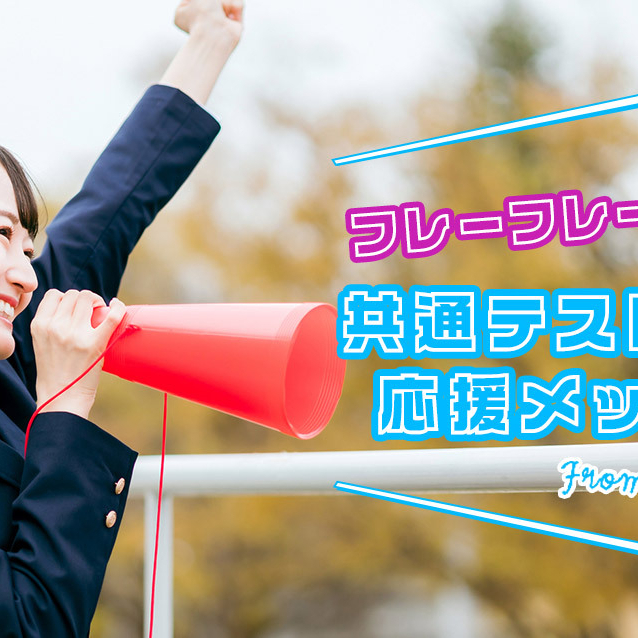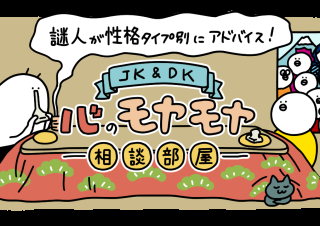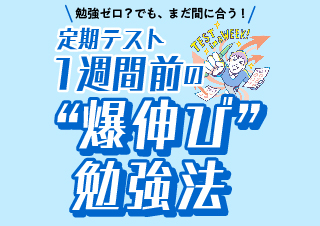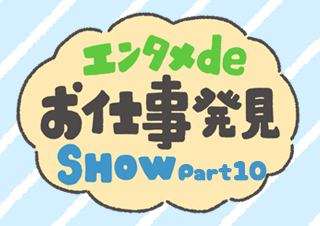志望理由書の書き方|例文15選+NG例・書き出し・ルール・対策まで完全ガイド
志望理由書とは、大学入試の際、志望する大学に提出する、「その大学・学部・学科を志望する理由」などを記述した書類のこと。総合型選抜・学校推薦型選抜で提出が求められるほか、最近では、一般選抜でも提出を求める大学・学部が増えている。書類選考において重要な評価材料とされるため、受験生にとっては対策が必須だ。
それでは、スタディサプリの現代文・小論文講師を務める小柴大輔先生に、基礎から教えてもらおう。
目次
 小柴大輔先生
小柴大輔先生Z会東大進学教室や巣鴨にある大学受験塾ワークショップで講師を務めるほか、司法試験予備校においても一般教養小論文を指導している。感覚ではなく論理的に答えを導く指導に定評があり、「現代文に対するイメージが変わった」と受験生から圧倒的な支持を集めている。スタディサプリでは、現代文のほか、小論文や総合型選抜・学校推薦型選抜対策講座を担当。
志望理由書とは?
志望理由書とは、大学入試の出願の際に、「自分がなぜその大学・学部を志望するか」を800~2000字程度で記述して提出する書類のこと。自分がそれまでに何に関心をもち、どのようにしてその関心を深めてきたか、それが志望学部・学科の学びにどうかかわっているか、大学でどのようなことを学びたいか、大学で学んだことを活かして将来社会でどのように活躍したいかを一連のストーリーとして伝えることが重要になる。分量の指定は大学によって様々で、800~1000字程度が一般的だが、400字など少なめの大学もあれば、2000字など多めの大学も。特に指定がない場合もある。
総合型選抜、学校推薦型選抜の出願の際にはほぼ必ず志望理由書の提出が求められるが、最近では、一般選抜でも志望理由書の提出を求める大学が増えてきている。また、志望理由に関わる内容をまとめる「志望理由書」と入学後の学びに関する内容をまとめる「学修計画書」などを別々に提出させる場合などもある。
なお、名称は「志望理由書」が一般的だが、大学・学部によっては、「自己推薦書」「エントリーシート」といった名称の場合もある。
大学が志望理由書で知りたいポイント

◆ 学部・学科への適性
「それまでにどんなことに関心を持ち、理解を深めてきたか」「将来どんな職業に就きたいか」などを書くことで表現できる。
◆ アドミッションポリシー
その大学・学部が求める人物像のこと。この人物像と本人の関心・希望かけ離れていると、いくら意欲があっても評価が下がる場合がある。例えば、 “経済学の先端的な理論を踏まえ、地域経済の発展に貢献することを目指す人材を求める”というアドミッションポリシーの学部を志望している受験生が、“将来は海外を拠点に国際的な舞台で戦略系コンサルタントとして活動したい”と志望理由書に書いていたら、大学側にとってそのズレは気になるはずだ。このズレを避けるためには、志望大学・学部のアドミッションポリシーをよく読み込んでおくことが大切になる。
◆ 大学で学問する意欲
志望する学部・学科のカリキュラムなどをよく調べ、「そこでどんなことを学び、どんな力を養いたいか」を具体的に書くことで伝えることができる。意欲を見せるといっても、「一生懸命頑張ります」といった単なる気持ち、決意表明では評価の対象にはならない。
志望理由書を書く前に必要な準備は?
いきなり志望理由書を書こうとしても、どう書いていいのかよくわからないという人もきっと多いだろう。書き始める前に、しっかりと準備をしておくことが、説得力のある志望理由書を書くためには欠かせない。事前にやっておくべきことを以下にまとめる。過去の経験を振り返って自己分析する
志望理由書に必ず盛り込まなければならない項目の一つが、「なぜその学問分野に興味を持ち、より深く学びたいと思うに至ったか」だ。「授業で学んでおもしろかったから」「ニュースで社会問題を知り、問題意識を持ったから」といった理由は、すぐに思い浮かびやすいかもしれない。しかし、これだけでは志望動機に深みや説得力に欠けてしまう。そこで必要となるのが、自己分析だ。本当にその学問分野に深い興味があるのか、改めて自分自身に問いかけてみよう。もしかしたら、高校生活や社会での経験の中に、興味をさらに強く引き出すようなできごとが隠れているかもしれない。このように過去の経験を幅広く振り返って自己分析することで、それまで自覚していなかった自分の本当の興味や関心が見えてくることもあるだろう。
また、小学校・中学校の通知表を引っ張り出して、担任の先生のコメントをよく読んでみることで、忘れていた“きっかけ”に改めて気づくこともあります」
なぜその大学、学部・学科を志望したのかを考える
実際には、「自宅から通える範囲で自分の学力で入れそうな国公立大学がそこしかなかった」「偏差値と知名度が高い大学・学部だから」「親に勧められたから」といった理由で志望校を選んでいる人もいるかもしれない。しかし、それだけでは自分が学びたい学問を深めるために大学・学部を選ぶ理由としては弱い。そこで大切なのは、「なぜその大学で学問をしたいのか?」という観点から、志望理由を掘り下げて考えてみること。よく調べてみると、その大学・学部で学びたい深い理由が発見できるかもしれないし、ほかに、より自分に合う大学・学部が見つかるかもしれない。
同じ名称の学部でも、大学によって教育のスタイルや強みが異なる場合もありますし、一見、自分の志望分野とはジャンルが違うように思える学部・学科が、実は自分の希望に合致していたなんてこともあります。ですから、カリキュラムや教育の特色、さらにアドミッションポリシーまでよく読み込んでみましょう」
どんな学校生活を送り、どんな社会人になりたいかを考える

10年後の目標が決まったら、そのためにはその5年前にはどうなっている必要があるか、さらにそのためには卒業直後はどんな仕事に就いている必要があるか、さらにそれを実現するには大学ではどのような学びを経験する必要があるかを逆算して考えていきます。こういったことをしっかり考えておくと、志望大学・学部を最終的に絞り込む際にも生きてくるはずです」
志望理由書に書くべき内容は?
書くべき内容①:大学・学部・学科の志望理由
ポイントは、「なぜその学問分野を学びたいのか」と「なぜその大学を志望するか」がそれぞれわかるように記述すること。その学問分野を志望する理由は、高校までに興味をもっていたこと、関心をもって取り組んできたことから記述することもできるし、将来どんな仕事に就きたいかということから記述することもできる。しかし、例えば、「高校時代から法律に興味があり、将来は弁護士になりたいので法学部法律学科で学びたい」という記述だけでは、「法学部を志望する理由」はわかるが、法学部を擁する大学はほかにもたくさんあるなかで、なぜ「その大学の法学部を志望したのか」がわからない。
書くべき内容②:志望するようになったきっかけと興味を深めた過程
事前準備の段階で、自分がその学問分野に興味をもつようになったきっかけはピックアップできているはず。志望理由書を一つのストーリーと考えると、この「きっかけ」は起点として大切になるので、必ず書くようにしよう。次にポイントになるのが興味を深めた過程だ。例えば、「探究の授業でそのテーマについて取り組んだ」「課外でそのテーマに関連する活動を行い、現場でさまざまな発見をした」といった経験があれば、それを書くことができる。では、該当する経験がない人は何を書いたらいいのだろうか。
そして読んで印象に残った本は、志望理由書に著者名・タイトルを書くようにしましょう。書名が記述されていることで、その分野に興味があるということへの説得力が大きくアップします」
書くべき内容③:入学後にやりたいこと・将来の展望

将来の展望に関しても、できるだけ具体的な業種・職種を書きたいですね。“まだそこまで具体的には決まっていない”という場合でも、あり得る選択肢の一つを具体的に書くことで、説得力がグンと高まりますから。裏を返せば、具体的な選択肢を挙げられるくらい、しっかりリサーチしておくことが大切だということです。なお、その目標が大学で学ぶ過程で変わってもまったく問題はありません」
志望理由書の書き方は?
一つのストーリーとしてまとめることを意識する
志望理由書の書き方で最も大切なのは、「志望するようになったきっかけ」「その学問分野への興味を深めた過程」「志望学部・学科で学びたいこと」「将来の展望」という一連の要素が一つのストーリーとしてまとまっていること。高校時代に関する記述と大学で学びたいことがつながっていない、大学で学びたいことと将来の展望がつながっていないという志望理由書では、それぞれの項目ではいいことが書いてあっても評価が下がってしまう可能性がある(その意味でストーリーにつながらない要素はあえて盛り込まないほうがいい場合も)。ストーリーの展開の仕方は、大きく分けて以下の2つだ。
・その分野に興味を抱くようになったきっかけ
・その分野への興味をどのように深めたか
・それを大学でさらにどのように深めたいか(だから貴学○○学部を志望する)
・将来は、学んだことを活かしてどのような職業に就いてどのように社会に貢献したいか」
〈問題意識から入るパターン〉
・社会課題などへの問題意識
・その問題意識を抱くようになったきっかけ
・その問題への理解をどのように深めたか
・それを大学でさらにどのように深めたいか(だから貴学○○学部を志望する)
・将来は、学んだことを活かして冒頭の社会課題をどのように解決したいか
適切な文字数と分量のバランスのコツ
志望理由書には、大学側から文字数の指定がある場合が多い。小論文試験とは違って、時間制限なく書くことができるので、「○○字以内」という指定であれば、指定された文字数の9割程度にまとめるのが望ましい。「○○字程度」という指定であれば、プラスマイナス1割程度と考えておけばいいだろう。特に文字数の指定がない場合で、記入用の用紙がある場合は、その用紙に無理なく書き込める程度、指定された用紙がなければ、800~1000字程度を目安に考えよう。内容的な分量のバランスは「過去(きっかけ)+現在(深め方)」と「未来(大学での学び、将来像)」に関する記述が、半々程度になるのが理想だ。なお、清書前に盛り込む要素を書き出す際には、文字数は気にせずできるだけ多めに書き出すのがおすすめだ。
また、志望理由書は、面接の際に質問の材料になります。面接担当者は、志望理由書を踏まえつつ、そこからさらに受験生の言葉を引き出そうと聞いてくることが多いので、準備段階でできるだけ多く書き出してそれらも頭に入れておけば、回答の際に使えるストックになります」
志望理由書のOK例文【書き出し・深め方】

「将来の展望」から入る書き出し例文
「問題提起」から入る書き出し例文
説得力のある「興味の深め方」の書き方例文
「大学で学びたいこと」の具体的な書き方例文
志望理由書のありがちなNG例文と改善方法

自己分析ができていない例文
志望校の分析ができていない例文
ストーリーが成立していない例文
入試の形式別 志望理由書の例文とポイント
志望理由書は総合型選抜・学校推薦型選抜では必須の書類。「両者で内容や書き方に違いはあるの?」と思うかもしれないが、本質的な違いはない。ただし、それぞれの選抜方法で特に重視すべきポイントが少し異なるといえる。- 「なぜこの大学・学部でなければならないのか」を自分の言葉で掘り下げる(別の大学でもよいという印象を与えないようにする)
- ありきたりな内容を避け、オリジナリティを重視
〈学校推薦型の志望理由書で意識すること〉
- 推薦書の内容と合わせて書く
- 「高校でがんばってきたこと」と「大学で学びたいこと」をつなげる構成
- 文章のトーンや内容はまじめかつ堅実に
総合型選抜の志望理由書の例文

きっかけは、友人関係に悩んでいた時期に、自分のSNSアカウントに“誰も見ていない前提の裏アカ”を作り、本音だけを投稿するという小さな実験を続けたことです。フォロワー0のそのアカウントに向けて投稿する中で、普段の自分が「他人向けの感情」を演じていたことに気づきました。この体験から、「人はなぜ“見せるための感情”をつくるのか?」という問いが生まれ、より深く知りたくなりました。
そんな中で出会ったのが、○○教授の「デジタルコミュニケーションにおける感情認知」に関する研究論文でした。特に、表情や語調が存在しないSNS上での“共感のズレ”について、文化や年齢層ごとの違いを実証データで読み解いていくというアプローチに強く引き込まれました。実験心理だけでなく、社会心理学やメディア研究と横断的に結びつけて分析していく姿勢に、自分が求めていた「リアルとネットの心理の橋渡し」を試みる研究だと強く関心をひかれました。
貴学でこの分野を深めた上で、将来的には学校現場や自治体と連携して、若者が“顔を出さずに心の声を届けられる”オンライン相談システムの開発に携わりたいと考えています。テクノロジーを通じて「見せかけではない感情」に個々に対応できる仕組みを作ることが、自分の大きな目標です。
「関心をもっているテーマにも、きっかけや深め方にもオリジナリティがあり、まさに総合型向け。また、総合型では特に知的能力や探究心の自己アピールが重要なので、研究論文を読んでいることも高評価につながります」
学校推薦型選抜の志望理由書の例文
高校生活を通して私が特に関心をもったのは、「気持ちをうまく伝えられないときに、どうやって人と信頼関係を築いていくか」ということです。3年間、学級委員としてクラス運営に携わるなかで、意見がぶつかる場面では一人一人の話を聞き、冷静に話し合いを進めることを心がけてきました。その経験から、相手の気持ちを受けとめ、安心して話せる空気をつくる力が自分の長所だと感じています。また、地域の子ども支援ボランティアでは、小学生と遊びや学習を通じて関わるなかで、言葉ではうまく気持ちを伝えられない子どもたちが、表情や行動を通して何かを訴えている姿に多く触れました。そこから、「感情を言葉にするためのサポート」の大切さに気づき、心理学への関心がさらに深まりました。
これらの経験を通して、気持ちをうまく言葉にできない状況でも、相手の思いをくみ取り、信頼関係を築くにはどのような関わりが必要なのかを深く考えるようになりました。そして、その答えを見つけるために、心理学を体系的に学びたいという思いが強くなりました。
大学では、発達心理学や臨床心理学を中心に学び、将来は学校現場で心理的なサポートに関わる仕事に就きたいと考えています。悩みや不安を抱える子どもたちが、安心して話せるような存在になれるよう、貴学で着実に力をつけていきたいです。
「高校生活で感じたこと、学んだことを大学の志望学部の学びとうまく結びつけられています。丁寧でまじめな印象を与える文章であることも含め、特に学校推薦型ではよい書き方です」
学部別 志望理由書の例文とポイント
学部系統別では、それぞれ何かポイントがあるのだろうか。経済学部、法学部、国際系学部、文学部、教育学部、工学部、建築学部、医学部、看護学部の例を紹介しよう。経済学部の志望理由書の例文

きっかけは、高校2年次に取り組んだ探究学習で、地域の商店街の現状、課題、可能性について調べたことでした。実際に商店街を歩いて観察し、空き店舗の増加や客層の変化に注目しながら、商店街の理事・商店主・消費者など現地の方にヒアリングを行いました。そのなかで、「人の流れが変わると、お金の流れも変わる」という実感を持ち、経済が生活と直結していることを身をもって知ることができました。特に、価格や消費税・地域クーポンなどの制度の変化によって「誰が得をして、誰が困っているのか」という視点で考えるようになったことが、自分にとって大きな転機でした。こうした関心を深めるために、大学ではミクロ経済学や行動経済学を中心に、消費や意思決定、地域経済の仕組みについて体系的に学びたいと考えています。
また、ゼミや地域フィールドワークを通して、現場の声に触れながら学びを実社会と結びつける力を身につけたいです。そして、将来は地方自治体や地域金融機関などで、商店街や中小企業が抱える課題に対し、経済の視点から支援策を考える仕事に携わりたいと考えています。現場と数字の両方を見つめながら、持続可能な地域づくりに関われる人材を目指して、貴学での学びを深めていきたいです。
「経済学のテーマ設定として、高校生が国際経済の問題などを取り上げるのはハードルが高いですが、この例のように、商店街など身近な経済活動に焦点を当てているところがグッド。このように世界規模にも通じる問題を、自分の身近な関心に引き寄せてストーリー展開するのが経済学部の志望理由書のポイントの一つ。
将来像については具体的な職種を絞り込みにくい分野ですが、“現場と数字の両方を見つめながら、持続可能な地域づくりに関われる人材”という目標設定は読み手にイメージが伝わります」
法学部の志望理由書の例文
そうした関心をもったきっかけに自閉症の弟の存在がある。私たち家族からすると当たり前のことだとしても、外出先で弟の言動を不思議、あるいは不快に感じる人は少なからずいるだろう。実際、そのような視線で弟が見られていると感じた経験は多々ある。なぜ弟が「普通」と違うだけで軽蔑ともいえる視線を浴びなければならないのかと心が痛んだ。障がいがある人に対する理解や配慮は未だ十分とはいえず、その結果として障がいがある人の自立と社会参加が阻まれており、共生社会とはいえない状態にある。
また、女性の立場として、日本のジェンダーギャップも看過できない。このようにして人権への関心を深めるなかで、法に関する教養として多くの書籍を読んできた。特に『中高生のための憲法教室』(伊藤 真)では、日本国憲法の根本価値が「個人の尊重」にあることが強調されており、誰もが多数派にも少数派にもなりうるからこそ、人権感覚を意識することに深い意義があると知った。また、社会的弱者にとって社会権は個別に恩恵を受ける権利ではなく、社会のバリア自体を排除する権利と捉える考え方を知った。
人権の尊重はすべての人々が身体的・精神的・社会的な不自由さや格差、差別のない状態を実現することにつながる。加えて個々人のウェルビーイングの実現にも大きく寄与する。人権尊重の実現への第一歩として、社会での生きづらさを感じる人々の現状を把握し、地に足のついた理念を提唱することが挙げられる。そのために貴学の法学部で学び、法の専門知識と多岐にわたる教養と想像力を獲得したい。例えば、差別による人権問題の解消のためには社会学や政治経済学、ジェンダー研究など、法学を核としつつ幅広い知識が必要だ。
貴学では学問分野の枠を超えて探究を広げられる「全学副専攻」や「リベラルアーツ」などの仕組みを採っており、物事の本質を見極める洞察力を養うことができる。また、このように他学部・他学科の人々と積極的に関わる機会を通じて多様な価値観に触れることも可能であり、多面的に問題解決へのアプローチを図れると考え、貴学を志望するに至った。
「法学部で学べることは広範囲にわたるため、自分の関心のあるテーマ(人権)に焦点を当ててストーリーを展開するのがポイントです。このように社会正義的な観点から論を進める場合は、深め方が足りないとありきたりな内容に陥りがち。この例のように、自分なりに文献などを調べ、考察を深めるとよいでしょう」
国際系学部の志望理由書の例文

一つは、校内の希望制で募集されていたアメリカ・オレゴン州への留学である。この3カ月の留学では、ホームステイや現地の学校に通い、陸上部のクラブ活動にも参加した。私の背中を押してくれたのが、父や2人の兄の存在であり、その中でも特に長兄に感化された。彼もまた高校生活内で1年留学を経験しており、その経験談を聞いていたからである。実際に私が留学をした際には、兄から聞いていたように、コミュニケーションの際の距離感、自己主張の強さなど、日本との違いや学校等の生活内での違いを体験し、それらを乗り越えることが英語を学ぶ楽しさにもつながっていった。この経験から、大学ではこのような違いをテーマに研究したいと思うようになった。
もう一つの海外経験は、1週間のイギリスへの修学旅行である。その中で現地の高校に行き、パワーポイントを使った日本の文化のプレゼンテーションを行った。グループごとの発表で、私のグループでは、「アニメにおける日本の伝統社会・習慣の表現」をテーマにしたプレゼンテーションを行い、グループ内でのリーダー兼進行役に立候補しその責務を全うした。
これらの経験から、自他の文化を学ぶ意欲がより増して、これまで『異文化コミュニケーション学』(鳥飼玖美子)、『伝統と文化から世界が見える! イギリスを知る教科書』(君塚直隆)などの本を読んできた。
貴学国際教養学部言語文化学科では、特に、○○教授の『比較文化論』、△△教授の『カルチュラルスタディーズ』などの授業を通して、他国の文化を理解し、受け入れるために必要な視点や考え方、自国の文化を発信する際に意識するべきことなどを学び、学問的な裏付けのある異文化コミュニケーションにつなげていきたいと考えている。語学に関しては、英語とは異なる言語として中国語やスペイン語を学ぶことも考えている。また、来年度から始まる全学部で履修が可能な「情報科学教育プログラム」を履修し、世界に目を向け学ぶ力、ITリテラシーやメディアデザインを学びたい。
以上の理由から私は国際教養学部言語文化学科を志望する。卒業後は、貴学で学んだ異文化理解力や国際的発信力を活かし、世界的にサービスを展開しているゲーム会社の国際部門で働きたい。
「国際学部、国際教養学部などは、この例のように、留学や海外研修、海外旅行などの自分自身の異文化体験をきっかけに据えるのがポイント。重要なのは、単に“こんな経験をした”“こんなことを感じた”というだけにとどまらず、関連する本などを読んで、学問的な側面からも関心を深めたことをしっかり書くことです」
文学部の志望理由書の例文
私が英語や国際社会に興味をもったきっかけは、シンガポールを拠点に勤務をしている叔父の影響です。そのため、私も語学学校や観光、叔父の職場見学などをしてきました。英語力を巧みに使い、職業に活かしている叔父を見て、私は憧れを抱きました。シンガポールの語学学校で、様々なバックグラウンドをもつ生徒たちが母国語ではない英語を用いてコミュニケーションをとるなど、英語のアクセス言語としての有用性を痛感しました。その一方で、ニュアンスがうまく伝わらないもどかしさや、理解のズレなど、英語を自由に操ることの難しさも経験しました。この悔しさをバネに、私は高校でオーストラリアに年間留学をしました。多文化国家として世界中の多彩な文化的背景をもつ人々を受け入れるオーストラリアだからこそ、興味をそそられました。私はこの留学により英語力の向上だけでなく、多彩な価値観に出会い、自国文化の再発見をすることができました。さらに失敗を恐れずに主体性を持ち挑戦するチャレンジ精神を身につけることができたと強く感じています。
英語や国際社会、異文化理解への関心から次のような本を読み、自らの学問関心を深めてきました。『異文化理解』(青木保著)では、異文化を理解していくには様々なレベルがあり、「信号」「記号」「象徴」の3レベルで異文化をとらえることを学びました。同書によれば、信号的レベルは自然なこととして、人間ならば誰しも理解できるコミュニケーションの段階のことを指します。2つめの記号的レベルは社会的な習慣や取り決めを知らないと文化を異にする相手も異社会も理解できないということです。しかしこれは、人間が社会で培った常識的なことが習得でき、社会的な規則を学習すればわかるレベルです。3つめの象徴的レベルは文化的な中心部のことで、外部の者にとっては極めて理解が困難な世界です。象徴的レベルの文化はどの社会に行っても必ずあります。これが異文化理解の難しいところであると同時に社会や国の重要な価値を担っています。私はこの意見に対し、異文化理解には教養と共感と許容が必要だと考えました。異文化を理解するのには限界があり、外部からはわからないことも多いです。ならば許容や共感によって理解しようとすることに意味があるのではないかと考えました。
また、今の日本の英語能力指数は非英語圏112カ国中87位という現状にあります。『日本人はなぜ英語ができないのか』の著者である言語学者の鈴木孝夫氏はこの理由を英米文化の紹介とは違う日本自身を発信する英語教育がないからと論じています。つまり、日本人が自国の文化を他国に発信するために日本を扱った英語教材を使うことで英語を学ぶ目的が変わり、日本の英語教育にも変化を示すことができるということです。この問いに対して英米文学研究者や日本における英語教育の教授の視点からはどのように考えるかを調査してまとめてみたいと考えています。
貴学の英米文学専修を志望した理由は、貴学全体が日本における英語教育の分野で屈指の伝統を誇ること、しかもその中心が文学部英米文学専修であることです。また、オープンキャンパスで○○教授の英語史の模擬授業を受講した際、短い時間でしたが内容が濃く、話に引き込まれました。一口に英語とは言っても、複数のルーツをもち、混交しながら時代ごとに変化してきたことを学びました。貴学科では英古典を学び、英語学を深く学ぶことができます。この講義を聞いて、私は○○教授の授業を貴学で受けたいと感じました。もし貴学に入学することができたら必修科目の第二外国語選択をフランス語にし、英語との比較言語的教養を得たいと考えています。フランス語を含め培った学びで、卒業論文では、ノルマン・コンクエストでの二重言語社会の構造について研究したいと考えています。この卒業論文のテーマに沿って、△△教授のイギリス文学の授業を受講し、文学からも研究テーマにアプローチしたいと考えています。
以上のことより、私は将来につながる学びを○○大学文学部文学科英米文学専修で励みたいと強く希望します。
「文学部はまさに“文章でものごとを伝える”ことを学ぶ学部ですから、志望理由書でも書く力を問う比重が高いといえます。指定される文字量が多い場合もあり、それだけの分量を使って中身のある論を展開できるかが大きなポイントです。この例のように、読んだ本の主張を要約し、それに対して自分の意見をしっかりと展開するのも、文学部の志望理由書では評価されるところでしょう」
教育学部の志望理由書の例文

私は日本の児童・生徒の「自己肯定感」の低さを問題と考え、教育学を大学で学ぶことを目指すようになりました。そこで、『ベーシック発達心理学』(開一夫、齋藤慈子)、『子どもの自己効力感を育む本』(松村亜里)などの本を読み、教育への学問関心を深めていきました。私はただ単に勉強を教えるだけでなく、「幸せを育む心」を育てたいです。それが貴学の学長の言葉と重なっていたことが、私が貴学教育学部を志望した最大の理由でもあります。
私はこれまでの学習においても受動的に先生の話を聞くだけでなく、たくさん質問したり、発言を積極的に行ったりしてきましたので、1年生から少人数のゼミがあり、担当の先生や他の学生たちと対話・議論のできる環境に魅力を感じています。また、私は、世界の平和構築のために教育者は何ができるのかということを自分のテーマと考えており、海外で教育に携わることも視野に入れています。そのため、以前から留学を希望しており、貴学部に全学科留学制度があることも大きな志望動機の一つです。
●入学後学びたいこと、どのような学生生活を過ごしたいか
貴学の授業で特に注目しているのは、『国際社会理解入門』『異文化コミュニケーション教育』です。これらの科目を通して、海外で教育に取り組むうえでの基礎的な力を養いたいと考えています。また、留学に関しては、教育学で世界から注目を集めるフィンランドに行き、日本とは異なる視点からの「教育」に触れ、自分のなかの「教育」という理念を高めたいです。また、全学共通の○○プログラムには、「幸せの国ブータン」との交流事業があり、ブータンへの教育海外研修もあります。これらの留学制度や海外研修を通して、海外の教育のあり方を自らの目で見つめ、考え、自分なりの教育論を確立したいです。
●将来の目標
単に勉学の教育だけにとどまらず、自分と他者、両方を尊重できる児童を育てるために、私自身に誇りをもち、一人一人の児童に愛情を注ぎ、世界の平和構築に貢献できる人材を育てられる教師を目指したいです。そして、自分の周りの人々を笑顔に、幸せにできるような小学校教師になりたいです。
「教育学部の志望者は、その多くが教師を目指しているので、ただ単に“教師になりたい”“教育に関心がある”という記述にとどまらず、どのような教師になり、どのような教育に携わっていきたいのかを、どれだけ具体的に詳しく記述できるかが大きなポイント。この例では、独自の教師像、教育観がしっかりと示されています」
工学部の志望理由書の例文
現在使われているロケットは、とても高い技術と多額の打ち上げ費用を要しているにも関わらず、使い捨てとなっている問題があります。また、ロケットの打ち上げ時には人に強烈な加速度がかかり、一般市民が訓練を必要とせずに宇宙を往来することはとても困難という問題もあります。そこで、二段式有翼型の再使用宇宙往還機が実現することにより、様々な豊かな可能性が広がります。まず二段式有翼型の再使用宇宙往還機は通常のロケットとは違い打ち上げ時にかかる加速度を小さくできると考えられます。それにより、一般市民が訓練を必要とせずに宇宙を往来でき、宇宙観光業の可能性の幅が広がります。また、次世代のエネルギー源として有力なヘリウム3などの地球にはない資源の回収が可能になると考えています。一方、再使用宇宙往還機は、大気圏突入時に発生する約1万度以上もの熱に繰り返し耐える必要があります。
貴学は再利用宇宙システムの研究をされている○○研究室があり、私は当研究室で、機体の形状や熱に耐えることができる素材についての研究を行い、宇宙事業の発展に貢献したいとの熱意をもっています。また、6年一貫教育と大学院横断コースがあり、4年次から専門的な研究を行うことができることをオープンキャンパスで知りました。私は先の研究を進めるためにも、空気力学や材料力学、熱力学なども積極的に学び、6年一貫教育の制度を通して研究につなげていきたく貴学を志望しました。
「工学部の志望理由書では、この例のように、技術的に踏み込んだ課題に言及することで、この分野への関心がホンモノであることを伝えることができます。大学院修士課程に進学する学生が多い分野なので、入学後の構想を、大学院進学も含めて記述することもポイントです」
建築学部の志望理由書の例文

私が最終的に見通すビジョンは、人々が安心安全に利用できる公共施設を建てることです。なぜなら、近年自然災害が増加するなかで、家を失う人も少なくありません。そんなとき、避難場所にもなりうる公共施設が構造的に安全であることは、地域に安心をもたらすはずです。災害は地震だけではありません。台風や大雨による土砂災害・洪水も多発しています。大震災ごとに見直された建築基準法も、あくまで最小限の基準であり、それを守るだけでは安心を提供することはできません。私は、「防災工学」「建築関連法」などの科目を通して、安全な建築構造や耐震性に関する知識を深めつつ、本当に安心できる公共施設を建てられる建築士になりたいです。
以上のような志望をもつ私は、貴学の学びの場に貢献できると自負しています。
「建築は個人住宅からビル・橋梁など規模も様々なため、志望理由書では、自分が取り組みたいものがどういうものかをしっかりと打ち出すことが大切なポイントです。この例では、それが冒頭でしっかりと打ち出せているのが評価できます。AIとの関わりなど、建築業界の仕事の現状や将来展望についても調べていることがうかがえるところもいいですね」
医学部の志望理由書の例文

父の友人が脳腫瘍で若くして亡くなった話を聞いて、腫瘍内科医としてがん患者に貢献したいと志したからだ。がんについて強く関心をもち、さらに医師である叔母に話を聞き、日本人の2人に1人はがんになること、死亡原因の第1位であることも知った。そして、次第にがんに苦しむ人たちの役に立ちたいという気持ちを深めていった。
また、山岡淳一郎の著書『医療のこと、もっと知ってほしい』を読み、「寄り添う医療」が高度専門化した「治す医療」と連携してこそ患者は安心できるということを学んだ。そのため、貴学ではテュートリアル方式を通して、直接対面の対話力を養いたいと考えている。個々に異なる患者への対応でも、チーム医療での協働のためにも重要だからだ。
貴学は臨床実習の期間が長く、海外での臨床実習にチャレンジできるところに魅力を感じた。研究実績のある海外大学を調べ、海外でもクリニカル・クラークシップを通じて、臨床腫瘍学についてより深く学びたいという熱意も持っている。将来は腫瘍内科医となり、貴学附属病院にて研究と臨床で活躍したい。優れた治療のため、患者のQOL実現に寄与できる人間的器量のある医師になる覚悟である。
「医学部入試では、一般選抜であれ、総合型選抜や学校推薦型選抜であれ、必ず面接が課されます。面接や学力試験の配点の比重が高いため、志望理由書の内容が大きく評価に関わる可能性はそれほど高くありません。ただし、面接対策の意味でも、志望理由書は準備からしっかりやっておくことがおすすめです。この例も、“患者に寄り添う医師”などのありがちで抽象的な表現に留めず、内容を詰めるべく、よく調べ、考えた末にポイントとなる要素を抜き出し、少なめの文字数のなかにうまくまとめています」
看護学部の志望理由書の例文
私が看護師を目指したきっかけは、小学生の頃、両親や親戚に「先々考えていつもてきぱき動いていて看護師さんみたいだね」と言われたことでした。その頃はまだ看護師とはどのような職業なのかよくわからず、いろいろ調べてみた結果、物事を熟慮しつつ、具体的に行動を起こせる、他者を思いやることができるといった特性を知り、私に適性があると考えるようになりました。
その後、私が本格的に看護師になろうと考えたきっかけは、新型コロナウイルス感染拡大に対応する看護師の密着映像でした。患者に優しく接し、迅速・的確に仕事をしている姿を見て、私も看護師になりたいと強い思いをもちました。それからは、『看護師のキャリア論』(勝原裕美子)などの本を読み、看護師の仕事への理解を深めました。その過程で、看護師としてのキャリアアップとして専門看護師というものがあることを知り、なかでも小児看護に関心をもちました。
小児看護を目指したのは私が中学生の時に出会った耳の不自由な親友がきっかけでした。その友人は小学生の頃、たくさんの手術であまり学校に行けず、そんなとき、看護師さんに相手をしてもらって乗り越えられたと話してくれました。私はその話を聞いて、彼のような病気で辛い思いをしている子どもをケアできるようになりたいと強く思いました。この友人の影響もあって、独学で手話を覚えました。こうした経験も、将来の看護師としての仕事に活かしていきたいと考えています。
「看護学部の志望理由書では、自分自身が看護師と接した経験、家族や友人をケアした経験など個人的な体験をきっかけとしてストーリーを展開するパターンが多くなります。そのため、自己分析を通して、その体験をしっかりと掘り下げて、学びたいことや将来の働き方にまでつながる軸を作ることが大きなポイントです。この例では、小学生の頃の経験が、小児看護の専門看護師という目標にうまく結びつけられています」
志望理由書の対策は?
志望理由書の評価基準を理解する
志望理由書で主に評価の対象となるのは、大学側が知りたいと考えている「学部・学科への適性があるか」「大学の採用方針(アドミッションポリシー)に合致しているか」「大学で学問する意欲があるか」といったポイント。これらがしっかり書けていることが前提で、その人なりのオリジナリティも評価の対象となる。一方、そつなくまとまっていても、内容がありきたりで他の受験生との差別化ができていないと、平均点までの評価となってしまうことも。配点は大学によって様々だが、学力試験、面接と同等程度のウェイトを置いている大学もある。一次選考が書類選考の場合、志望理由書が二次選考に進めるかどうかを判定する大きな材料となるので、当たり前だが手を抜くことはできない。
構想段階では付箋メモを活用する
構想段階では、志望校から指定される文字数にかかわらず、「きっかけ」「関心の深め方」「大学で学びたいこと」「将来の展望」それぞれに関して、頭に浮かんだことはすべてメモにまとめていこう。その際、便利なのが5センチ四方くらいの付箋を使ったまとめ方だ。- 頭に浮かんだことは、一項目ごとに付箋に分けて書き込んでいく。
- 書き込んだ付箋を「きっかけ」「関心の深め方」「大学で学びたいこと」「将来の展望」にグループ分けして貼り付けていく。
- ある程度、たまってきたら、それぞれから「いいな」と思うメモ、それぞれが一つのストーリーでつながるメモを拾い出して、時系列に並べていく。
書いたものは第三者に見てもらう

志望理由書対策に役立つコンテンツ
この記事では、志望理由書の大事なポイントを総ざらいで解説してきた。最後に、志望理由書対策に役立つ関連記事を紹介するので、あわせてチェックしておこう。しっかりと準備をして、自分の思いが伝わる、アピール度の高い志望理由書を書き上げよう!合格した先輩の志望理由書をチェック
実際に合格した先輩たちの志望理由書を、学部・学科ごとに掲載。小柴先生の解説つきだから、「なぜこの書き方が評価されたのか」までしっかり理解できる。
※この記事は会員限定です。上記リンクから無料登録できるので、まだの方はぜひ!
目指す学部学科の関連書籍をチェック
志望理由を深めるには、本での知識インプットも有効。小柴先生が学部・学科ごとにおすすめの書籍を紹介してくれているので、ぜひチェックしてみよう。●文学部、国際・外国語学部
【文学部、国際・外国語学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
【心理学系分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
【外国語分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
●法学・政治学部、経済学・経営学部
【法学・政治学部、経済学・経営学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
【法学政治学分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
時事問題を1冊でおさえる!小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
●理学・工学部、農学・水産学・畜産学部
【理学・工学部、農学・水産学・畜産学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
●医学部、看護・医療系学部、スポーツ学部
【医学部、看護・医療系学部、スポーツ学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
【医学系分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
学校情報をチェック
志望理由書がうまく書けないときは、そもそも学校情報の収集が不足している可能性も。大学のパンフレットを取り寄せたり、オープンキャンパスに参加したりして、学びの内容や雰囲気をしっかり把握しておこう。学校の資料を請求するオープンキャンパスを探す
取材・文/伊藤敬太郎 監修/小柴大輔 構成/寺崎彩乃(編集部) \この分野の推薦入試を受ける人必見!/
【文学部・芸術学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【法学部・政治学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【家政学部・栄養学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【社会学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【教育学部・児童教育学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【国際学部・外国語学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【家政学部・栄養学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【医学部・薬学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き >
【農学部・生物学部・水産学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【情報・データサイエンス・IT系学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【獣医学部・動物看護学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
【建築学部】合格者の志望理由書を公開!NG例・プロの解説付き
※無料会員登録で読めます