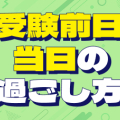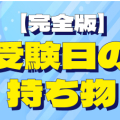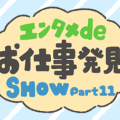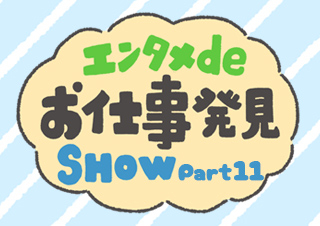リスク分散できてる?偏差値別・出願校マッピングのススメ
そろそろ併願校も固めておけよ~なんて言われる10月。
「本命校のほかに併願校はもう5校選んでるし大丈夫~」と思っているそこのアナタ!
その学校、本当に「併願校」として成立してる?
目次
併願校選びにはリスク分散の意識を!
同じ「5校を併願する」にしても、大事なのはその中身。
知名度重視や高望み、運試し出願校ばかりになっていないかな?
例えば「自分は偏差値55だから本命校はA大学(偏差値55)。残りの併願校は偏差値53のB大学・C大学・D大学・E大学・F大学。
5校も候補があるし、完璧…」なんて思っているそこのキミ、注目ー!

同偏差値帯のみの併願は、「リスク分散」観点だとちょっとキケン。
「チャレンジ校・実力相応校・安全校」なんて言葉があるように、出願では偏差値帯をある程度分散しておいたほうが安心なのはご存じのとおり。
ある程度分散させないと併願校が「保険の役割」を100%果たせないのだっ…!
だからこそ、スタサプ編集部がおすすめしたいのが、「自分が今希望してる志望校を偏差値別にマッピング」すること。
偏りや穴がないかを客観的に確認することで、より堅実な出願戦略を実現できるのです!
マッピングをするに当たっては、進路のプロのスタサプ講師の神﨑先生にもひとことアドバイスをもらってきたよ。
ぜひぜひ参考にしてみてね。

神﨑史彦先生
株式会社カンザキメソッド代表取締役。
スタディサプリ講師。私立学校研究家。高大接続・教育コンサルタント。
大学卒業後、大学受験予備校において小論文講師として活動する一方、通信教育会社や教科書会社にて小論文・志望理由書・自己アピール文の模擬試験作成および評価基準策定を担当。
のべ6万人以上の受験生と向き合うなかで得た経験や知見をもとに、小論文・志望理由・自己アピール・面接の指導法「カンザキメソッド」を開発する。
現在までに刊行した参考書は26冊(改訂版含む)、販売部数は延べ25万冊、指導した学生は10万人以上にのぼる。
本命&併願校は決まってる?まずは現状把握!
出願校マッピングを始める前に、まずは自分の立ち位置を書き出して現状把握から始めよう。
ノートの空きページや裏紙などなんでもOKなのでまずは紙を用意。
併せて、模試などで合格判定を受けている場合は模試結果も手元に置いておこう。
準備ができたら「現状把握リスト」を作って書き出してみて!
◆Action!まずは「現状把握リスト」を作成
必要な情報は(1)志望校の偏差値、(2)志望校の合格判定の2つのみ。
わかるところからリストに書いていこう!
※併願校は何校でもOK!
※まだ出願校が決まっていない人は、もしかして出願することもある…?ぐらいの何となく気になる学校でもいいので、ピックアップしてみよう。
※模試の合格判定に出していない学校は偏差値だけ書いておくのでも大丈夫だよ。
書き出した学校&学部を偏差値別の5つのカテゴリに分けてみよう!
気になる学校の情報を「現状把握リスト」に書き出したら、偏差値別にカテゴリ分けしていくよ。
今回のマッピングの目的は「出願校が極端に偏っていないか」を確認するため。
気になる学校群のバランスを図に落とし込むことで、客観的に把握することが大事なのだ!
◆Action!志望校を偏差値別に5つのカテゴリに分類
現状把握リストの学校を偏差値別に5つのカテゴリに分けしてみよう。
カテゴリ分けの基準は以下のとおり。
①実力相応校…C判定の学校(ここが【基準】になるよ!)
②あと一息校…D判定・E判定の学校 ※基準+偏差値5程度
③ワンチャン憧れ校…D判定・E判定の学校 ※基準+偏差値10程度
④保険校…A判定・B判定の学校 ※基準-偏差値5程度
⑤ほぼ確校…A判定・B判定の学校 ※基準-偏差値10程度
カテゴリ分けは自分がわかれば好きな色でOK!
イメージはこんな感じだよ。
バランスの見直しをしてみよう!
5つのカテゴリ分けが完了したら、バランスを見るためざっくりマッピングしていくよ。
◆Action!5つのカテゴリ別にマッピングしてみよう
マッピングでは偏差値の高い順に書いていくよ。
例えば上の現状把握リストを例に作っていくとこんな感じ。
ざざっと手書きでOKなので、上の記入例を参考に書いてみて!
■ポイント
※同じ大きさの枠を作って、その中に学校名を入れてみよう。
※方眼紙やノートの罫線を使うときれいに書けるかも!
マッピングしてみたみんなの出願予定校はどんな感じ?
図にすることで、まんべんなく分散している、ワンチャン憧れ校に偏っている、ほぼ確校が多いなど自分の傾向が見えてきたんじゃないかな?
【ADVICE】マッピングの基本形は「ひし形」を意識するとGOOD
みんなの出願校マッピングはどんな形になった?
スタサプ講師の神﨑先生に出願のバランスについてのアドバイスをもらったよ。
作ってみたマッピングの図と見比べてみて!
ポイント1:まずはC判定(合格確率40~60%)を基準にする
偏差値を軸に出願校を考えるのであれば、基本的に『ひし形』を意識するとよいでしょう。
まずは「①実力相応校」として、C判定で合格確率40~60%の学校を軸に考えます。
ここは手厚くしておきたいので3校程度あるといいですね。
D判定・E判定の学校は偏差値を見てみましょう。
基準から偏差値+5までの「②あと一息校」、目安は2校。
さらに偏差値+5くらい上の「③憧れ校」は1校選びます。
A判定・B判定の学校も同様です。
「①実力相応校」から偏差値が5くらい低い大学を「④保険校」として2校。
さらに偏差値5くらい低い「⑤ほぼ確校」は1校選ぶとバランスとしては理想的です。

理想のバランスは「ひし形」なんですね!
この図を「出願ダイヤモンド」と名付けたいです。
この形を目指して足りないカテゴリの学校をみつけていくのが理想ではありますが、そんなに出願校数がない場合やひし形にならないときはどうしたらいいですか?
ポイント2:出願校数が少ないときは「縮小版ひし形」に
あくまで基本がひし形というだけで、出願校数や志望度によって形を変えてもOKです。
例えば上の図だと計9校を受験することになりますが、『それでは多すぎる、4~5校に抑えたい』という場合もあるかもしれません。
そのときはひし形を縮小するのもありですね。
ポイント3:ひし形以外にも逆三角形、I型などのパターンもあり
ひし形以外だと、例えば出願校が逆三角形になるパターンもあるでしょう。
その場合はどの層が厚くなっているかをしっかり見ておく必要があります。
例:①実力相応校(C判定)が多いパターン
上図のように①実力相応校(C判定)を固めていくパターンは安全志向ですね。
ただ、受験生は秋から成績が伸びる可能性は十分にあるので、追加の出願候補として少し上の偏差値の学校(②あと一息校、③憧れ校)をいくつか調べておくとよいでしょう。
例:③憧れ校が多いパターン
上図のように、実力に対して「③憧れ校」の出願数が多い、少し強気なパターンの人もいるかもしれません。
(実はこういう強気な出願をする高校生ってけっこういるんです)
本命を出すだけたくさん出してみようというのはありですが、①実力相応校(C判定)が少ない分、現役合格を目指すのであれば少しリスキーではあります。
念のため追加で①実力相応校(C判定)、④保険校なども少し調べておくとよいでしょう。
例:各カテゴリを1校ずつ併願パターン
ほかには各カテゴリを同じ数ずつ併願する「I型」なども考えられますね。
出願にはお金の問題もからんでくるので、保護者の方や先生と相談してみてください。

私、③憧れ校が多いパターンでした…!
同じような偏差値の学校ばかり出願しようとしていて、最後の「あれ、抑え校がないな」って焦ったのを思い出しました。
みんなもバランスには気をつけて…!
出願まであと2~3カ月のこのタイミングは、併願校についてゆっくり考えられるラストチャンス。
悩んでいる人は、マッピングしたリストを三者面談に持ち込んで先生や保護者の方にも相談してみるといいかも。
ぜひみんなトライしてみてね!

気づけばもう10月、そろそろ願書の取り寄せをしよう…と動き始めている人も出てきそうな今日この頃。
どのレベルの併願校に出すか問題は、かなーり難しいところもあるよね。
憧れ校に偏りすぎて全滅するのも怖いし、かといってほぼ確校について調べるのも正直モチベーションが上がらない…。
今回は「偏差値」を軸にマッピングしてみたけど、これに掛け合わせて「その学校でどんなことが学べるか」もしっかりリサーチしてみてね~。
From 「併願校は5校も候補があるし、完璧…」なんて思っていたのは実は私、なスタサプ編集部SENより



.JPG?20260207)

.JPG?20260207)
.JPG?20260207)