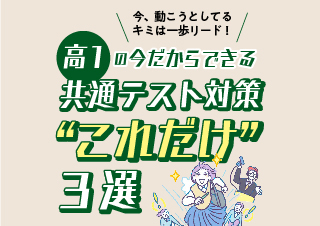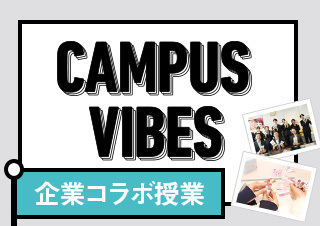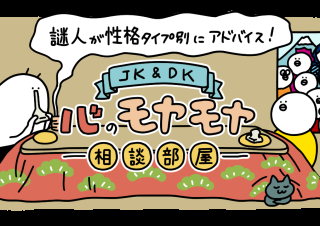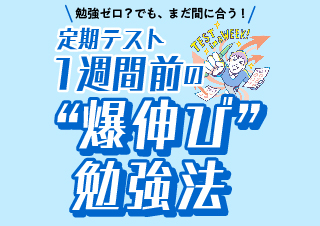バイリンガル講座!今回は【ワニ】
同じ研究対象でも、専門分野によって魅力を感じる部分も気になるところも違う。
そんな学問の奥深い世界を垣間見てみよう。
今回のテーマは、イグノーベル賞でも話題となった「ワニ」。
意外すぎる“ワニへの信仰”&動物の声のディープな世界をご堪能あれ!
ワニ
目次
人文地理学・地域研究ってどんな学問?
人文地理学・地域研究
熊谷圭知先生

お茶の水女子大学名誉教授。都市社会学を学びたくて大学に入ったはずが、専門の先生がいなかったことをきっかけに人文地理学の道へ。パプアニューギニアに通いながら、40年研究を続けている。

フィールドワークで得た疑問を解き明かしていくために、時には文系理系を問わず、違う学問の専門家の手を借りることもあります。
お茶の水女子大学文教育学部の受験科目*
前期:共通テスト利用(5または6教科・7または8科目)、+個別学力検査(外国語および国語または数学の2教科)後期:共通テスト高得点3教科+独自試験、共通テスト5または6教科+小論文
*学科により異なる。
ワニとどんな関係が…?
「ワニを信仰する人々と場所のかかわり」を研究しています。
パプアニューギニアを流れるセピック川の近くに住む人々は、ワニや豚やヒクイドリなど周囲の森や川や湿地に住む動物を、それぞれ自分の氏族(クラン)の祖先と考え信仰しています。ワニはそのなかでも最も存在感のある動物なので、クランを超えて大切にされます。

同じように動物を信仰している文化では、信仰対象の動物は食べられなかったりします。でもセピックの人々は、カヌーの上からモリを投げてワニを狩り、肉は皆で分けます。おいしく食べられること、皮が高く売れることまで含めて、感謝・尊敬しているんですね。

人になつかないワニは、男性の力強さの象徴。セピックの男性たちは成人儀礼で、全身にワニのうろこ模様を彫ります。大変な苦痛に耐えることが一人前の男の証明でもあります。キリスト教の影響で途絶えてしまった地域もありますが、今でも続く文化です。
人文地理学・地域研究は、知らない社会に参加できるからおもしろい!

研究対象の場所に長期間滞在しながら調査を進めるので、相手の社会に溶け込んでいく中で、自分自身も変わっていくのがおもしろさの一つだと思います。昔は好き嫌いも多かったですが、今では虫も食べられるようになりました(笑)。
生物音響学ってどんな学問?
生物音響学・霊長類学
西村剛先生

京都大学霊長類研究所准教授。中高時代は理数系が得意で物理にも関心があったが、理学部の数学の授業の難しさに挫折。数学を避けて選んだ生物学を学ぶなかで、言語やサルの音声に興味を持つ。

「言語」に関わる学問ですが、私たちは喉や舌などの身体の機能の面からアプローチしているので、理系の要素が強いと思います。
京都大学理学部の受験科目*
共通テスト:5教科7科目二次試験:「国語総合・現代文B・古典B」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B(数列、ベクトル)」、「物理・化学・生物・地学」から2科目、英語
*学科により異なる。
ワニとどんな関係が…?
「ワニにヘリウムガスを吸わせた鳴き声」を調べました。
私の専門は霊長類ですが、ほかの動物と比較してみるのも大切。爬虫類の発声を調べるために、ワニにヘリウムガスを吸わせて鳴き声を録音しました。人がヘリウムガスを吸ったときと同じように、ワニの鳴き声も聴いてわかるくらい高くなっていましたよ(笑)。

研究の中で、サル類は感情と連動して声を出しているため、音程の変化はつけられるものの単語を話すことはできないことがわかりました。ではサルからの進化の過程で、人間はどうして「あいうえお」が言えるようになったのかなど、まだまだ謎が残っています。

生物は声帯で振動を作って、その上の空間を共鳴させて「声」を出している場合と、セミのように羽を擦り合わせるなど摩擦・叩くなどの手段で「音」を出している場合があります。「音」はヘリウムガスの影響を受けないので、ワニは「声」を出していることがわかりました。
生物音響学・霊長類学は、思い通りにいかないからおもしろい!

サル類については人間の音声ほど研究が進んでいないこともあり、わかっていないことがまだまだたくさんあります。動物相手の研究なので、思い通りにいかないこと、予想がつかないことも多く、やればやるほど発見に繋がるおもしろさがあります。
※日程や方式によって試験内容が異なる場合もあるので、詳しい情報は必ず各学校のホームページで確認してね。
※この記事は2020/11時点の情報です。

同じ「ワニ」でも“何が知りたいか”で注目するポイントは全然違う!
自分ならワニの何が知りたいか、妄想して自分の興味の方向性を考えてみてー!