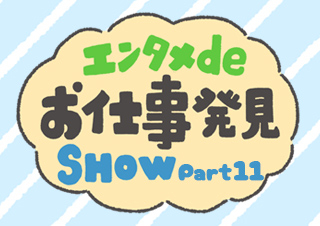「一瞬ですぐ寝る方法」はコレだ!2分で寝られると話題!朝までぐっすり寝る方法22選
一瞬で寝る方法には、SNSで話題になったアリス式睡眠法や米軍式睡眠法、4・7・8呼吸法などの呼吸法に基づく方法のほか、ツボ押しをしたり、頭を真っ白にして何も考えない状況を作ったりと、布団の中で簡単に試せる方法がさまざま。それでも寝れない場合は、アロマをたく、温かい飲み物を飲むなどしてリラックスするほか、生活リズムを整える、部屋の温度や湿度などの寝る環境に注意するなど、寝れない原因を考えて対処することで、ぐっすり寝ることができる。
睡眠医療の専門家・遠藤拓郎先生に一瞬で寝る方法をはじめ、ぐっすり寝る方法を解説してもらったよ。
目次
 遠藤拓郎先生
遠藤拓郎先生スリープクリニック調布 院長
スタンフォード大学 医学部 客員教授
著書『合格を勝ち取る睡眠法』(PHP新書)、『睡眠はコントロールできる』(メディアファクトリー新書)など多数。
監修を手がけた睡眠のための音楽CD『DREAMS~快眠CD』は、日本ゴールドディスク大賞 インストゥルメンタル アルバム・オブ・ザ・イヤー受賞。
一瞬で寝る方法とは?早く寝たいときはどうしたらいい?
一瞬で寝る方法には、SNSで話題になったアリス式睡眠法をはじめ、米軍式睡眠法や4・7・8呼吸法がある。そのほか、ツボ押しも効果的。呼吸法を使ったり、頭を真っ白にして何も考えない状況を作ったりすることで、すぐに寝ることができる。ここでは、一瞬で寝る方法に加えて、メンタル・ライフスタイル・環境といった寝れない原因別に寝る方法を紹介する。人によって効果のある方法は異なるので、いろいろ試してみよう。

※今すぐに寝たいという人は試してみよう
一瞬で寝る方法6選
「テストや受験を控えていて前日ちゃんと寝れるか心配…」という人や、「布団に入ったけどなかなか寝られない…」と今まさに困っている人も必見!準備や道具がなくてもすぐ寝られると話題の方法を紹介するよ。アリス式睡眠法
1:布団の上に座ってあぐらをかくリラックスしてできるだけ体を動かさないように。
2:目を閉じて寝る時のようなゆっくりとした呼吸を意識する
何も考えないようにするのがポイント。
3:頭の中に浮かんできた映像をボーっと見続ける
無意識で頭の中に浮かんできた映像を、目を閉じたまま何も考えずに見続ける。
4:ウトウトと半分寝ているような状況になってきたら横になる
ウトウトとし始めたらゆっくり布団に入る。
布団に入って横になっても寝られない場合は、1~4を繰り返そう。
米軍式睡眠法
1:仰向けに寝て、顔の筋肉の力を抜く布団に仰向けになり、目を閉じて、眉間やこめかみ、目、口など顔の力を抜く。
2:布団に肩と腕を沈めるイメージで片方ずつ力を抜く
うまくできないときは、一度グッと力を入れてから力を抜いてみて。
3:息を吐いて胸の力を抜く
リラックスしてゆっくり行おう。
4:脚の力を抜く
脚の付け根、ひざ、足首、足の指先も力を抜いていく。
5:何も考えずに10秒間、深呼吸をする
全身の力を抜いた状態でゆっくり深呼吸。息を吐くたびに全身が沈んでいくようなイメージで。
無意識に入っている全身の力を徐々にゆるめていき、体と心をリラックスさせよう。
4・7・8呼吸法
1:息をすべて吐き出す座ったり、ベッドや布団に仰向けになったり、ラクな姿勢で体の力を抜いてから始めよう。
2:4秒数えながら、鼻から静かに息を吸い込む
肩を上げるのではなく、お腹を膨らませるのがコツ。
3:7秒間、息を止める
力を抜いたまま息を止めよう。
4:8秒数えながら、口からフーッと吐き切る
お腹がへこんでいくのを感じながら息を吐き出す。
5:1~4を1回のサイクルとして、4回繰り返す
呼吸を意識しながら数を数えることで、自然と無心になって寝られるようになるよ。

※だんだん力が抜けて眠くなってくるはず
ツボ押し
遠藤先生にもすぐ寝られる方法をお聞きしたところ、ツボ押しは効果的な方法の一つだそう。例えば、かかとの真ん中にある「失眠(しつみん)」というツボを両手の親指で押してみよう。かかとは硬いので両手の親指を重ねて押すと効果的。
また、手の甲にある「合谷(ごうこく)」というツボはストレスや緊張を和らげて、眠くなるほか、頭痛や肩こりにも効果があるといわれている。「合谷」の位置は、親指と人差し指の骨が交差する付け根のくぼんでいる部分。
押すと痛気持ちがいいと感じるところがツボの目安なので、実際に押して試してみよう。
早く寝ようと意識することをやめる
『頑張って寝る・努力して寝る』ということは脳が頑張る・努力する状態になるのですが、これは睡眠に対してマイナスな働きなのです。『頑張ることをあきらめる』と脳が働かなくなって寝やすくなるので、寝られないときは『今日寝不足になる分、明日は長く寝られるからいいか』くらいの気持ちで楽しいことでも考えていましょう」
頭の中をからっぽにして何も考えない
ただ、動画や音楽を流しっぱなしで寝るほうが寝やすいという人もいるでしょう。音がなっていると寝つきは悪くなるはずですが、『単調な五感の刺激』が何も考えない状態を作るのに効果的な場合があるのです。
睡眠の一番の邪魔は『記憶』です。布団に入って寝ようとしたときに、今日やった失敗を思い出して目が覚めるという経験はありませんか。人間は五感の刺激がなくなると、自分の記憶の扉を開けて失敗したことや明日の試験のことなどを思い出す特性をもっています。
思い出した記憶によって脳が興奮して寝られなくなるのですが、五感の刺激があるときは、脳が自分の記憶から情報を取り出さないようになり、記憶の扉を閉めたままにできるのです。
つまり、外からの情報や刺激があることで脳の記憶の扉を開けずにいられ、脳をからっぽにできるのです。これが、音楽を聴きながら寝たほうが寝やすいという理由です。
例えば、トイレがくさいと思っても、3分ほどたつとにおいが気にならなくなりますよね。これは『馴化(じゅんか)』という生理現象で、人間は単調な刺激を受け続けるとその刺激を感じなくなります。
繰り返すことで刺激がなくなり、記憶の扉も開けないので、頭が何も考えない真っ白な状態になり、寝られるようになります」
眠れない原因は?
まだ寝られないときはその原因を把握することで解消法や対処法がわかり、ぐっすり寝られるようになる。寝られない原因には3つの要素が考えられるので、当てはまるものがないかチェックしよう。1)メンタル(ストレスや不安感が強い)
2)ライフスタイル(不規則な生活をしている)
3)環境(寝るのに適さない環境で寝ている)
「メンタル」「ライフスタイル」「環境」の3つの原因ごとに、遠藤先生にぐっすり寝る方法を聞いてみたよ。
朝までぐっすり寝る方法11選
【原因別】朝までぐっすり寝る方法~メンタル編3選~
※アロマはぐっすり寝るためのおすすめの方法の一つ
気持ちを落ち着かせて朝までぐっすり寝る方法として、グレープフルーツ系のアロマをたいたり、温かいものを飲んだりしてリラックスする方法のほか、好きなことをして不安やストレスを解消するのもいい方法。ストレスがたまると浅い眠りの時間が多くなり、途中で目が覚めるなど深く寝られない原因になるので、気持ちを落ち着かせる自分なりの方法をみつけておくことが大切だ。遠藤先生が具体的な方法を教えてくれたので、参考にしよう。
寝る前にグレープフルーツ系のアロマをたいてリラックス
特に柑橘系の香りは、褐色脂肪という脂肪を燃やしやすい特徴があり、体温を早く上げてくれる効果をもっています。体温を上げることで眠りにつきやすくなるので、グレープフルーツ系の香りなど柑橘系の香りのアロマを試してみてください」。
温かいものを飲んで気持ちを落ち着かせる
アロマと同様、体温を上げて寝やすくするという観点で、柑橘系の飲み物がおすすめです。ゆず湯のほか、レモン汁とハチミツをお湯で溶かしたホットレモンなどもいいでしょう」。
好きなことをして不安やストレスを解消
例えば、好きな音楽や動画を見る、体を動かすといった方法のほか、苦手教科が心配で不安を感じているなら、100点を取れる簡単な問題集をたくさんやって成功体験を重ね、苦手教科も好きになってみましょう。
何ごとも成功体験がないと好きになれません。簡単な問題集から徐々にランクを上げていくと、最初は解けずに苦しいかもしれませんが、何度もやっていく中で100点を取れるようになり、少しずつ苦手意識を払拭できて自信につながるはずです」

※お風呂に入り、寝る前に体を温める習慣をつけよう
朝までぐっすり寝るために、ライフスタイルを見直してみよう。お風呂に入ったり、夕飯に温かいものを食べたりして寝る前までに体温を上げておく方法のほかに、平日も休日も起きる時間を一定に保つ、夜ふかしはしないといった睡眠リズムを整えて生活することが大切だ。遠藤先生に詳しく解説してもらった。
寝る1時間前に風呂に入る、シャワーをあびる
人間の体は皮膚の下の血管を広げることで体温が下がりますが、血管を広げるのに有効なのがお風呂に入って皮膚を温めることです。湯船につかることができなければ、シャワーをあびるだけでも効果があります」
夕飯は温かいものを食べる
温かいものを食べて、さらにお風呂に入って体の芯まで温めておけば、体温が下がってきたころに眠気が出てくるはずです。生活の中での体温低下をうまく利用しましょう」
平日も休日も起きる時間は一定にする
例えば、週末遅くまで寝ていたら、その日は寝る時間になっても眠くならないですよね。休日に寝だめをしていつもより睡眠時間を長く取る場合でも、就寝時間を早めて、起きる時間は平日と変えないようにしてください。昼過ぎに起きると、長時間寝たとしても、体がだるい、頭痛がする、活力がでないという傾向があります。
できるだけ平日も休日も同じ時間に起きること、もっと積極的にやるなら休日は平日より早く起きるのがおすすめですよ。早起きすればその日の夜にきちんと眠くなり、ぐっすり寝ることができるでしょう」
夜ふかしはしない
夜ふかしをすると、ぐっすり寝たいタイミングで体は起きる準備を始めるため、中途半端な眠りになって翌日の勉強の効率が下がってしまいます。体の自然なリズムを壊さずに勉強をするほうが効率的に勉強できるので、無理に夜ふかしをして勉強するのではなく、朝早く起きて勉強をするほうが効率的です」

※寝室の環境や寝るときの服装も大切
朝までぐっすり寝たいなら、寝る環境も重要。室温は、夏なら27~29度、冬は18~20度を目安とし、湿度のコントロールも行おう。そのほか、部屋はできるだけ暗くする、パジャマに着替えて布団やベッドできちんと寝るといった基本的なことでも睡眠の質を上げることができる。
部屋の温度や湿度をコントロールする
冬の室温の目安は、18~20度です。夏は除湿器を、冬は加湿器をつけることも忘れずに。寝るときに湿度が高いと手足から汗が蒸発せずに、体温が低下していかないので、湿度の管理にも意識を向けてください」
遮光カーテンかブラインドで暗くする
パジャマに着替える
一方でパジャマは基本的に手足が開口されていて、熱が放出されやすいつくりになっています。冷え性の人は手と足の先がつぼまっているタイプでもいいですが、冷え性ではないなら、なるべく手首や足首が広がっているタイプのパジャマがいいですね」
布団やベッドで寝る
朝までぐっすり寝る方法【実例】5選
ここまでは、遠藤先生から教えてもらった「眠れるコツ」を紹介してきた。専門家の視点から、理論的に効果がある方法を教えてもらったが、実際にみんながどうしているかリアルな声も気になるところ。そこで、高校生から大学生までの学生100名に「すぐに寝るためにやっている方法」を聞いてみた。スマホを見ないように工夫したり、音楽を流したり、どれも身近で簡単にできる方法ばかり!自分に合いそうなものを見つけて、気軽に試してみてほしい。
就寝前のルーティンを決める
ベッドに入る前後のルーティンを決めて実践している声が多く見られました。音楽やラジオを聴く
ホワイトノイズやYou Tubeの睡眠用音楽を聴いたり、ラジオなどの人の声を聞いているという意見もありました。「ジャズなどの静かな音楽が良い」(19歳・茨城県)
「ASMRや環境音を聞く。リラックスできる音を聞くことによって眠くなりますし、たとえ寝られなかったとしても体が安心してゆっくり休めることができます」(16歳・東京都)
本や単語帳を読む
「寝る前に読書をするととても集中して本の中身をインプットできるほか、脳を整理でき、とても集中して眠りにつけました」(18歳・東京都)
「単語帳を読むと言葉が単純だからだんだんと頭が疲れて眠くなる」(17歳・東京都)
「紙の漫画を読む。20分ぐらいたつと、自然に寝てしまう。寝る前の時間を楽しみながら、目にも刺激をあまり与えないので、体にやさしい」(19歳・東京都)
就寝前にスマホを見ない
「枕元でスマホを充電しないようにすることにより布団に入ってから後にスマホを触らないようになったので寝れるようになった」(17歳・栃木県)
「スマホを寝る部屋の中に持って入らないようにすると、寝る前のスマホを触る時間がなくなり、ブルーライトを浴びることもないため、眠れるようになる」(17歳・京都府)
「23時ごろ以降に携帯がいじらないように設定することで、いつまでも夜携帯を見て睡眠時間が短くなる問題を解決した」(22歳・愛知県)
楽しいことを考える
「寝られないときに悪いこととか不吉なことを考えて不安で寝られない無限ループに陥ってしまうことが多かったので、好きな人との楽しかった思い出や、これから一緒にやりたい事を考えながら寝るといつの間にか寝られるし、悪夢も見なくなりました」(20歳・島根県)
「寝る前に推しのことを考えて次のライブの予定やテレビ番組の予定など楽しみを考えるだけで寝つきがラクになった」(25歳・北海道)
アプリを使用して睡眠時間を確認する
睡眠時間を計測するアプリを使ってデータを取得することで、客観的に自分の睡眠を把握し、睡眠時間の確保ができるようになっているようです。「睡眠時間を測定できるアプリを使用して、どのくらい眠れているかを日々確認するようにしました。また、このアプリを起動することで他のアプリを使うことがなくなり、自然とスマートフォンから手が離れるようになりました」(25歳・神奈川県)
「睡眠ゲームアプリを入れることで、寝つきが良くなったと感じた」(23歳・愛知県)
寝る前のカフェインを避ける
「寝る前に飲むものをお茶から水に変えたら、寝つきが良くなってトイレに起きることも減った」(25歳・神奈川県)
「コーヒーが大好きだったけど、カフェインレスやデカフェにしてから眠りやすくなった」(22歳・新潟県)
寝る前に温かい飲み物を飲む
「寝る前などに白湯を飲んだら体が少しほてって、体をリラックスしやすくなり、とても深く眠れた」(18歳・東京都)
「冬は特に体が冷えて冷たくなってしまうので、温かいものを飲んで体をポカポカにさせてから布団に寝るようにするといつもよりぐっすり眠れるようになりました」(16歳・東京都)
「温かい甘い飲み物を飲むと、リラックスすることができました」(20歳・沖縄県)
睡眠アイテムを使う
自分のお気に入りのアイテムをみつけて、眠れるようになったという声も。まずは家にあるものから試してみると良い。●アイマスク
「百均で買えるので始めやすいです」(19歳・愛知県)
●ぬいぐるみ
「ぬいぐるみをたくさん置くことで自分が包まれている感覚があるので安心して寝ることができました」(15歳・北海道県)
「ぬいぐるみが背中側にあると守られてる感じがして安心する」(22歳・兵庫県)
●抱き枕
「抱きまくらをつかって、抱っこしているうちに安心して眠れるようになりました」(22歳・山口県)
寝れないときやってはいけないことは?

※寝られないときのNG行動をチェック
では、最後に改めて、遠藤先生に寝られないときにやってはいけないことを聞いてみよう。寝られないときにやってはいけないのは、寝られなかった分、翌朝遅くまで寝ることと、体を冷やしすぎてしまうこと。翌朝遅くまで寝ていると睡眠リズムが崩れて、翌日の寝る時間に影響がでてしまうし、体を冷やしすぎると眠気がおさまってしまう。詳しく遠藤先生の話を聞いてみよう。
遅くまで寝ているのはNG
体を冷やしすぎないように注意
「睡眠」について理解を深めよう
「早く寝なきゃ!」と焦れば焦るほど、寝られなくなるもの。一瞬で寝る方法を試してもなかなか寝られない人や睡眠の質が気になる人は、その原因を探して習慣を見直してみるのもおすすめだ。また、この記事を読んで睡眠のことをもっと知りたい!と興味がわいたなら、これを機会に詳しく知ってみよう。睡眠は私たちの体や頭、心にも大きく関係している。睡眠を見直すことによって、高校生活もガラッと変わるかも!
睡眠とは?役割や意味をわかりやすく解説!

睡眠ってどんな役割があるの?高校生の理想的な睡眠時間は?など、睡眠についてまるっとまとめたので、チェックしてみよう。
\睡眠の関連記事をCHECK/
高校生の理想の睡眠時間を解説!寝不足で成績が下がる?!受験生に最適な睡眠時間とは?
朝パッと目覚める方法14選。朝が苦手、だるいを卒業!スッキリ頭で1日を気持ちよくスタート!
すぐに解消!眠気を覚ます方法【6選】専門家に聞きました
仮眠は何分がベスト?勉強の効率が上がる!理想的な仮眠の取り方
緊張して眠れないときも大丈夫! 眠くなる方法
夕方に眠くなる原因は?すぐできる対策5選!眠気を撃退して勉強効率アップ!
睡眠について深く知るには「睡眠学」を体系的に学ぶ必要がある。「睡眠学」は主に3つの領域の学問から構成されている。まずは治療に直結する「睡眠医学」、さらに社会経済問題からみた「睡眠社会学」、また睡眠の役割やメカニズムを研究する「睡眠科学」だ。
※出典:日本睡眠学会
興味のある人はそれぞれどんな学問なのか見てみよう!
医学について知る科学について知る社会学について知る
取材・文/ミューズ・コミュニティー 監修/遠藤拓郎 構成/スタサプ編集部(2025年9月更新)
※2023年10月取材時の情報をもとに作成しています。
※本記事内の「寝る」という表記は、学術的には「眠る」が正しいですが、高校生に伝わりやすくするため「寝る」という表記を使用しています。
※本記事内の実例ならびにコメントは、2025年7月に学生100人に実施した調査(調査委託先はマクロミル)によるものです。