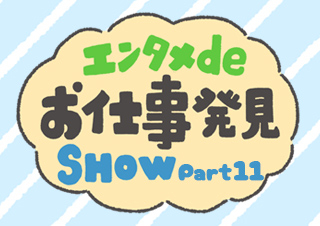朝パッと目覚める方法14選。朝が苦手、だるいを卒業!スッキリ頭で1日を気持ちよくスタート!
朝パッと目覚めるためには、40度のお風呂に入る、呼吸法でリラックスする、寝室の電気を暗くする、など前日にできることから、朝は部屋のカーテンを開ける、ガムを噛む、など朝起きてからやることまで、さまざまな工夫がある。「朝が弱い」「朝起きるのがだるい」という人は必見!
朝パッと目覚めて元気よく1日をスタートするための方法を眠りの専門家に聞いてみた。
パッと起きられない理由や、睡眠の質を高める方法も教えてもらったので、さっそくチェックしていこう。
目次
- 朝パッと起きる、目覚めをよくするには?
- 朝パッと目覚める方法14選
- 1. お風呂:40度のお湯に15分、全身浴をする
- 2. お風呂:炭酸ガスが出る入浴剤を使う
- 3. お風呂後:下着の前にまず靴下を履く
- 4. お風呂後:アロマでリラックス
- 5. お風呂後:呼吸法でリラックス
- 6. 寝る準備:電気を消して寝る
- 7. 寝る準備:寝室のカーテンを少し開けておく
- 8. 寝る準備:アラームはスヌーズ機能をつけない
- 9. 寝る準備:「〇時に起きる」と心の中で唱える
- 10. 朝起きてから:すぐに部屋のすべてのカーテンを開ける
- 11. 朝起きてから:曇りや雨の日はすべての照明を全灯
- 12. 朝起きてから:グレープフルーツの香りをかぐ
- 13. 朝起きてから:ガムを噛む
- 14. 朝起きてから:目覚まし時計を使わず、自力で起きる
- なぜ朝パッと起きられないの?
- 朝パッと目覚めたい!早起きしたい!Q&A
- 最高の朝を迎え、最高の毎日を

眠りとお風呂の専門家 小林麻利子さん
公認心理師。睡眠改善インストラクター、SleepLIVE(株)代表。
JCSP日本睡眠改善カウンセリング主宰。
科学的根拠のある最新研究を基に睡眠個人指導を行う。
第32回日本睡眠環境学会奨励賞受賞。また、企業の睡眠事業のコンサルティングや、マンションやホテルの睡眠空間提案を行う。
近著に『小林式 マインドフルネス入浴法』(MdN)がある。
朝パッと起きる、目覚めをよくするには?
朝パッと起きる、目覚めをよくするには、日頃の生活習慣がとても重要。寝る時間や起きる時間を毎日一定に保ち、規則正しい生活を送って体のリズムを整えることで、睡眠の質が高まり、目覚めもよくなる。
また、睡眠時間が不足すると脳・体・心の疲れが取り切れず、朝起きるのがつらくなってしまうので、自分にとって必要な睡眠時間をしっかりとることも目覚めをよくする大事なポイントだ。
とはいえ、生活習慣を改善するのは少し大変そう、時間がかかりそうと感じてしまう人もいるかもしれない。
そんな高校生のために、前日からできる簡単な方法を紹介していくので、さっそく試してみよう!
朝パッと目覚める方法14選

入浴のしかたを見直してみたり、寝る準備の中でできることがあったりと、前日にできる方法もさまざま。
そのほか、朝起きてからできる工夫にも注目だ。
小林さんに幅広く教えてもらったので、自分に合う方法をみつけてみよう。
1. お風呂:40度のお湯に15分、全身浴をする
朝パッと起きるためには、ぐっすり寝られるかどうかが重要なポイントの一つ。ぐっすり寝るために欠かせないのがお風呂。
おすすめの入浴法は、40度のお湯に15分、全身浴をする方法。
人間は、体温(特に脳や臓器など体の内部の体温)が上がった後、一気に下がるタイミングで眠くなる。
そのため、お風呂で体を内部まで温めて一時的に体温を上げておくことで、体温が下がりやすい状況をつくることができる。
また、頭を洗ってから湯船につかると血圧の急上昇を防ぐことができ、スムーズにリラックスモードになって眠りにつきやすくなる。
さらに、寝る1時間前にはお風呂から出て体温を上げておくと、寝る頃に体温が下がってくるので効果的だ。
脳や臓器など体の内部の体温は、朝4時ごろに一番低くなり、夜7時ごろに一番高くなるリズムをもっています(※)。
体温が一番低い朝4時ごろは脳も体も休息状態ですが、その後2~3時間かけて体温を上げていくことで脳や体が起きる準備を整え、自然と目が覚めるしくみになっています。」(小林さん)
※参照:基礎講座 睡眠改善学 第2版(ゆまに書房)[監修] 白川修一郎他
2. お風呂:炭酸ガスが出る入浴剤を使う
炭酸ガスが出る入浴剤を使うと睡眠の質を高めることができ、朝の目覚めをよくする効果が期待できる。炭酸ガスが溶け切った湯船につかることで、血行がよくなってじんわりと体が温まり、リラックスできる。
ぐっすり寝たいならシャワーだけで済ませるのは避け、お湯につかって体を内部から温めましょう。
肩までつかる全身浴が息苦しい場合は、みぞおちから下だけつかる半身浴でもOKです。
特に、女性は生理前になると体温が下がりにくくなり、夜、途中で目覚めやすくなる傾向があります。
しっかり湯船に入って体を温めることでグッと体温が上がり、その後に下がりやすくなるので、ぐっすり眠れるでしょう。」(小林さん)
3. お風呂後:下着の前にまず靴下を履く
朝パッと目覚めるための工夫として、お風呂から出た後にもポイントがある。それは、お風呂から出て体を拭いたらまず靴下を履くこと。
小林さんによると「下着よりもまず靴下を優先して履いてください」とのこと。
熱が逃げてしまう前にカバーすることが大切なので、お風呂から出たらすぐに靴下を履きましょう。
そして寝る直前、布団の上で靴下を脱いで足の甲から熱を放出させると、体温が一気に下がっていきます。
その時に深く眠ることができるので、試してみてくださいね。」(小林さん)
4. お風呂後:アロマでリラックス
眠りにつく前の時間をリラックスした状態にすることで、睡眠の質がアップし、朝の目覚めをよくする効果が期待できる。手軽にリラックスできる方法の一つが、アロマの香りをかぐことだ。
ラベンダーの香りはリラックスする神経を刺激するので、特におすすめ。
ラベンダーの香りをしっかりとかぐことで、心が和らぎ、リラックスして寝ることができる。
5. お風呂後:呼吸法でリラックス
呼吸法も手軽にできるリラックス方法。寝る前の少しの時間、布団の中でもすぐにできるから覚えておくといい。
さまざまな呼吸法があるが、ここでは10秒呼吸を紹介しよう。
3秒吸った後、2秒息を止め、その後、5秒かけて息を吐く。
これを10分ほど続けることでゆっくりとした心拍になり、リラックスして寝ることができる。
6. 寝る準備:電気を消して寝る

部屋を暗くすることで、自然な眠りを誘うホルモンであるメラトニンが増えるので、寝る前には部屋の電気を薄暗くしよう。
可能なら、寝る直前だけでなく、入浴中から薄暗くしていくのがおすすめ。
お風呂に入っている時は浴室の電気を消して脱衣所の電気をつけ、お風呂から出て着替える時は脱衣所の電気を消して浴室の電気をつけるといい。
7. 寝る準備:寝室のカーテンを少し開けておく
人の体は朝日によって目が覚めるというしくみになっているので、スッキリ目覚めるために『光』は大切なポイント。そのため、朝起きたい時刻の30分ほど前から太陽の光が差し込む寝室なら、カーテンの隙間を少し開けておくことで、目覚めをよくすることができる。
ただ、寝室が東向きの場合、真夏になると日の出時刻が早くなり、朝日が早い時間から寝室に差し込んで目覚めが早まってしまう可能性があるので、真夏はカーテンは閉めて寝よう。
そのほか、カーテンを少し開けることで夜の街灯の光が寝室に入ってくる場合、その光が眠りを妨げる可能性もあるのでカーテンは閉めて寝るほうがいい。
また、もし購入することができるなら、光目覚まし時計を利用するのもおすすめ。
光目覚まし時計とは、音ではなく、光によって起こしてくれる時計。
設定した時間の少し前から時計の光が徐々に明るくなっていき、起床時間には朝日のような明るい光が顔を照らしてくれ、自然に目が覚めるというもの。
興味がある人はチェックしてみよう。
8. 寝る準備:アラームはスヌーズ機能をつけない
アラームが鳴ってもスヌーズ機能をつけていると、「まだ時間があるからあとちょっとだけ…」とついつい二度寝をしがち。二度寝して深く眠ってしまうと起きるのが一層つらくなり、寝起きが悪くなる原因に。
そのため、スヌーズ機能はつけず、起きなければならないギリギリの時間にアラームをかけて朝アラームが鳴ったらすぐ起きる環境を整えておこう。
9. 寝る準備:「〇時に起きる」と心の中で唱える
布団の中に入ってからできるのが、寝る前に「明日〇時に起きる」と起きたい時間を心の中で唱える方法。「それだけで起きられるの?」と不思議に思うかもしれないが、人は「〇時に起きる」と意思をもつことで、起きたいと思う時間に向けて体が起きる準備を始め、自然に目覚める力をもっている。
実際に広島大学による研究によって裏付けがされているうえ、疲れが取れたと感じやすいという結果も出ているので、試してみてほしい。
10. 朝起きてから:すぐに部屋のすべてのカーテンを開ける

その理由は、眠りを誘うホルモン(メラトニン)が多く出ているからかも。
そのホルモンを減らすためには、太陽の光をたくさん浴びることが効果的。
そこで、起きたらすぐに部屋のすべてのカーテンを開けて朝日を浴びよう。
さらに太陽の光を浴びると、頭がスッキリしていき、ポジティブな気持ちになれるホルモン(セロトニン)が分泌される効果もあり、活動的に1日のスタートがきれるはず。
11. 朝起きてから:曇りや雨の日はすべての照明を全灯
朝すぐにカーテンを開けることに加えて、曇りや雨で太陽の光があまり期待できない日は、部屋のすべての電気を一番明るい状態でつけておこう。目から光を取り入れることが大切なので、部屋をできるだけ明るくして目覚めをよくしよう。
12. 朝起きてから:グレープフルーツの香りをかぐ
爽やかなグレープフルーツの香りは、活動的になれる神経を刺激するので、朝の目覚めをよくするのに効果的。グレープフルーツがあれば、切ってその香りを直接かぐのがおすすめ。
グレープフルーツのアロマでもスッキリとした目覚めを感じられるので、試してみよう。
13. 朝起きてから:ガムを噛む
朝起きてすぐにガムを噛むのも、目覚めをよくする方法の一つ。ガムを噛むことで脳の血流がよくなり、頭が活性化していく。
また、寝ている間は口の中の唾液が少なくなっているので、ガムを噛むことで唾液が出てきて朝食が食べやすく、消化もしやすくなる。
きちんと朝食をとることも、脳と体をしっかり目覚めさせるためには欠かせないポイントだ。
14. 朝起きてから:目覚まし時計を使わず、自力で起きる
人は何かに起こされるよりも、眠りが浅いタイミングで自然に目覚めると、スッキリ気持ちよく起きることができる。なぜなら、「起こされている」ということは、本来自然に目覚める時間よりも前に無理やり起きているということ。
まだ寝たい状態で起こされているので、当然目覚めが悪くなる。
また、目覚まし時計のアラームの大きな音で起きることは心拍数を高め、血圧の上昇につながるため、体にとって負担となり目覚めが悪くなる原因に。
とはいえ、朝起きるための必須アイテムである目覚まし時計を使わずに起きるのは難しいよね。
そこで、まずは数日間目覚まし時計を使わず、自分が何時間寝たら自然に起きられるかを確認しよう。
寝過ごしても大丈夫なように金曜~日曜や長期休みなどを利用して、少し早く寝てみるのがおすすめ。
日頃の睡眠時間が足りていない場合、最初は睡眠時間が長くなるかもしれないが、少しずつ睡眠不足の状態が解消されて睡眠時間が短くなり、3日ほどすると一定に落ち着いてくるはず。
その睡眠時間をもとに、何時に寝れば起きたい時間に起きられるかを計算しよう。
寝過ごすことが心配な人は、起きたい時間にアラームをセットするのではなく、自然に起きる時間の10分後くらい(それ以上寝たら遅刻する時間)にアラームが鳴るように設定してみて。
なぜ朝パッと起きられないの?

ここまで、朝パッと目覚めるための具体的な工夫を紹介してきたけれど、あまりうまくいかなかったという人は、そもそもなぜ起きられないか、その原因を見てみる必要があるかもしれない。
この機会に、日頃の生活習慣を見直し、良質な睡眠を手に入れたいという人はぜひチェックしてみよう。
眠りのリズムが乱れている
朝パッと目覚めることのできない原因の一つが眠りのリズムの乱れ。土日は平日に比べて遅寝遅起きの傾向があるという人もいるのでは?
小林さんによると、土日の遅寝遅起きの習慣による眠りのリズムの乱れは、朝パッと起きられない原因の一つだという。
上でもお伝えしたように、脳や臓器など体の内部の体温は、朝4時ごろに一番低くなり、夜7時ごろに一番高くなります。
そして、体温が一番低い4時は脳も体も休息状態で、起きる準備はできていません。
4時以降、2~3時間かけて体温を上げていくことで脳や体が起きる準備を整え、自然と目が覚めます。
土日の寝る時間と起きる時間が平日に比べて2時間以上遅い場合、体温が低くなる時間や高くなる時間も後ろにずれてしまい、結果的に月曜日の朝、体温が低く、脳も体も休息中の時間に起きなければならなくなるので『起きるのがつらい』となってしまうのです。」(小林さん)
深い眠りができていない
朝パッと目覚めることができないのは、深く眠れていない、つまり睡眠の質がよくないということも考えられる。ぐっすり眠れないことで疲れが取れず、朝のだるさにつながることもあります。
寝る前に考え事をしているとぐっすり眠れなくなることがありますので、好きなアーティストやキャラクターなどのことを考えて意識をそらしましょう。
また、15時以降に仮眠をとる人も睡眠の質がよくない可能性があります。
仮眠は適切にとれば脳の疲れが取れてパフォーマンスがアップしますが、15時以降に仮眠をとると夜の睡眠の質に影響がでて、深く眠れなくなる原因につながります。
15時以降の仮眠は避けましょう。」(小林さん)
睡眠時間が不足している
朝、眠くて起きられない場合、そもそも睡眠時間が足りていない可能性がある。人によって必要な睡眠時間は異なるが、適切な睡眠時間の確保は朝の目覚めをよくするうえで大事なこと。
睡眠は、脳・体・心を休息させ、疲れを回復する大切な役割をもっているので、必要な睡眠時間をとることで、朝元気に起きることができる。
アメリカで発表された睡眠時間に関する研究結果(※)によると、14~17歳の望ましい睡眠時間は8~10時間。
14~17歳の限界最短睡眠時間(最低限必要な睡眠時間)は、7時間です。
つまり、高校生にとっては最短でも7時間は睡眠が必要であり、推奨される睡眠時間は8~10時間なんです。
9~10時間は難しくても、できる限り8時間の睡眠はとれるといいですね。」(小林さん)
※参照:米国国立睡眠財団による理想的な睡眠時間に関するガイドライン(2015年)
朝パッと目覚めたい!早起きしたい!Q&A

そんな高校生から寄せられた質問について、小林さんに答えてもらったよ。
※ここで言う「早起き」「早く起きる」とは、いつも自然に起きられる時刻よりも早い時刻に起きる場合すべてを指します。
遅く寝て早く起きる方法はある?
睡眠時間が不足するうえ、無理な早起きは体に大きな負担がかかるので、スッキリ起きて元気に1日をスタートしたいなら避けたほうがいいでしょう。
また、睡眠不足になると記憶力や集中力が低下しますが、座学における記憶力に加えて、例えば自転車に乗るようなスポーツにおける感覚的な記憶力にも影響が出ることがわかっています。
遅寝早起きは、勉強や運動のパフォーマンスも下げてしまうのです。
そのほか、睡眠不足はイライラの原因になることも。
勉強などやりたいことのために睡眠時間を削りたくなりますが、脳・体・心によくない影響が出てしまうので、遅く寝て早く起きることはできるだけ避けましょう。」(小林さん)
朝4時に起きるには何時に寝るのがいい?
ですが、もし4時起きを習慣づけたいなら、高校生に推奨される睡眠時間の8時間をキープできるよう、夜8時に寝るのが理想的です。
さらに、平日も土日も夜8時に寝て朝4時に起きるようにして、体内時計を整えるのがおすすめです。
また、この日だけ特別に4時に起きたいという時もありますよね。
そんな時は、できるだけいつもどおりの時間に寝てください。
早く起きるために早く寝ると体のリズムが乱れてしまうので、寝る時刻を早めるとしても30分くらいにとどめるのがいいですね。」(小林さん)
朝型になるには、どのくらい前から習慣をつけるといい?
多くの人は体の内部の温度が一番低くなるのが4時ごろですが、夜型の人は6時ごろだったりします。
そうした遺伝レベルで決まっている体温リズムを変えるには1~2日では足りません。
例えば、朝型になるために起きる時間を2時間早めたいなら、1週間くらい前から習慣づけるといいでしょう。
人の体はリズムが後ろにずれるのは問題なくても、前にずれるのはしんどい構造になっています。
朝型になりたいなら、まずは少し早く寝ることが大切です。
そうすれば自然に起きる時間が早くなっていくので、それに合わせていくのがいいですよ。」(小林さん)
最高の朝を迎え、最高の毎日を

でも、毎日目覚めがよく、最高の朝が迎えられるなら、人生も最高のはずです。
子どものころの睡眠習慣が大人になってからも土台になります。
『朝パッと目覚められるようになりたい』と思ったこの機会に、適切な睡眠習慣を身につければ、受験勉強がはかどるだけでなく、朝から最高の仕事ができる大人になれるはずです。」(小林さん)
そして、改めて日頃の生活習慣を見直すことで、良質な睡眠を手に入れられることも理解できたはず。
心も体も元気に過ごすのに、重要な役割を果たす睡眠。
睡眠について興味をもった人はこの機会に深く知ってみては?
睡眠とは?役割や意味をわかりやすく解説!

睡眠ってどんな役割があるの?高校生の理想的な睡眠時間は?など、睡眠についてまるっとまとめたので、チェックしてみよう。
\睡眠の関連記事をCHECK/
高校生の理想の睡眠時間を解説!寝不足で成績が下がる?!受験生に最適な睡眠時間とは?
すぐに解消!眠気を覚ます方法【6選】専門家に聞きました
仮眠は何分がベスト?勉強の効率が上がる!理想的な仮眠の取り方
「一瞬で寝る方法」はコレだ!2分で寝られると話題!朝までぐっすり寝る方法17選
緊張して眠れないときも大丈夫! 眠くなる方法
夕方に眠くなる原因は?すぐできる対策5選!眠気を撃退して勉強効率アップ!
睡眠について深く知るには「睡眠学」を体系的に学ぶ必要がある。
「睡眠学」は主に3つの領域の学問から構成されている。
まずは治療に直結する「睡眠医学」、さらに社会経済問題からみた「睡眠社会学」、また睡眠の役割やメカニズムを研究する「睡眠科学」だ。
※出典:日本睡眠学会
興味のある人はそれぞれどんな学問なのか見てみよう!
医学について知る科学について知る社会学について知る
取材・文/ミューズ・コミュニティー 監修/小林麻利子 構成/寺崎彩乃(本誌)
※2024年4月取材時の情報になります。
【監修者の著書】
▼「わたし」と向き合う1日10分のお風呂習慣 小林式 マインドフルネス入浴法〈こころが軽くなる!眠りが変わる!人生が変わる!〉