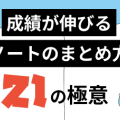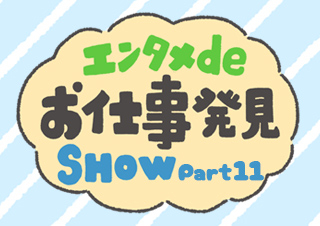部活を辞めたい高校生へ|内申への影響は?保護者・先生への伝え方は?不安を専門家と解消
「部活を辞めたい」とき、後悔しない決断を下すには、まず自分の気持ちを客観的に整理し、辞めることのメリット・デメリットを考えることが重要だ。さらに、信頼できる人への相談方法、先生や保護者への上手な伝え方、そして内申や受験への本当の影響を知ることも、君の不安を解消するカギになる。
この記事では、部活を辞めるか、続けるか、君が自分自身で心から納得のいく決断を下すためのヒントを、スクールカウンセラーとして多くの生徒と向き合ってきた田村節子先生の言葉や、少し先を歩む先輩たちのリアルな声を交えながら、一つひとつていねいに解説していくよ。
読み終えるころには、辞めるにしろ、続けるにしろ、きっと前向きな一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはず。君の人生は、君のもの。誰のためでもない、君自身にとっての最善の道を選び取ろう。
目次
- 部活を辞めたい理由は?
- 部活を辞めたいと思うのは「逃げ」じゃない!
- 「部活を辞めたい」と感じたらするべき4ステップ
- 部活を辞めたい理由を整理する
- 保護者や顧問の先生、友人などに相談する
- 部活を辞めることのメリット・デメリットを考える
- 部活を辞めることによる、内申点や大学受験への影響を考える
- 「部活を辞めた後の自分」を想像する
- 部活を辞めた後の生活は?先輩たちのリアル
- 部活を辞めなかった先輩のリアルも聞いてみよう!
- 部活を辞めると決めたらするべき3つのステップ
- 【ケース別Q&A】部活を辞めることについての悩み…どうすればいい?
- Q. 部活を辞めたいけど、保護者が許してくれない。どうすればいい?
- Q. 顧問の先生が怖くて部活を辞めたいと言い出せない。上手な切り出し方は?
- Q. 高1で入部してまだ半年。部活を辞めていいか迷っている。
- Q. 部活を辞めると「逃げグセがつく」って本当?
- 「部活を辞める=悪いこと」じゃない。君にとっての最善を選ぼう
- この記事を読んだ人におすすめ
- 実用英語技能検定(英検®)
- TOEIC Bridge® Listening and Reading Tests
- 中国語検定試験
- 韓国語能力評価試験(KLAT)
- マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)
- 情報検定(情報活用試験)【J検】
- おすすめ記事 PICK UP

田村節子先生
一般社団法人スクールセーフティネット・リサーチセンター 代表理事
公認心理師・臨床心理士・学校心理士スーパーバイザー・ガイダンスカウンセラー
主に小中学校のスクールカウンセラーとして、長年カウンセリングを行ってきた。保護者の援助力を生かし、教師と保護者が一体となって子どもを援助する“チーム援助”を提唱。その過程で開発した、「石隈・田村式援助チームシート」は、全国の教育現場に広がった。
主な著書として『大人に言えない小さな悩みが少しだけ軽くなる本』『10代のつらさに寄りそう本』(Gakken)、『子どもにクソババァと言われたら』(教育出版)などがある。
部活を辞めたい理由は?

「部活を辞めたい」と感じる理由で多いのは、「人間関係のトラブル」「勉強との両立の難しさ」「休みが少ないこと」などだ。高校生の約60%が、君と同じように「部活を辞めたい」と悩んだ経験がある。今、この文章を読んでいる君と同じように、多くの仲間が悩み、葛藤しているんだ。ここではアンケート結果をランキング形式で見ていこう。
1位:顧問の先生や部員との人間関係トラブル
アンケートで最も多かったのが、人間関係の悩みだ。顧問の先生との相性、先輩からの厳しい指導、同級生との温度差や意見の対立など、仲間であるはずのチームが、いつしか苦しい場所になってしまうことがある。
「外部コーチが、うまい子にばかりやさしく、技術が足りない人に対しては、ものすごく冷たかった。怒られ慣れていなかったこともあり、精神的に追い詰められた」(静岡県・16歳)
「部活内での数人と人間関係で悩んでいたところにスランプが重なり、競技を楽しく感じられなくなった」(鹿児島県・16歳)
「女子部員と仲が悪くなり、悪いうわさを流された」(兵庫県・17歳)
2位:勉強との両立が難しい
高校生活の本分である「勉強」との両立は、多くの部活生にとって切実な悩みだ。特に進学校の生徒や、大学受験を意識し始めると、「部活を続けていて大丈夫だろうか」という焦りが生まれる。毎日の練習で疲れてしまい、家に帰っても勉強に集中できないというジレンマも、将来への不安に直結しがちだ。
「周りの人は勉強と両立できているのに、自分はそうでもなかったから、周りと比べてしまった」(静岡県・17歳)
「試験期間の1週間前にならないと部活がなくならないので、早めに勉強をスタートできなかった」(愛知県・19歳)
「進学校で大学受験のために頑張りたい気持ちがあるのに、強豪校から異動してきた新しい顧問によって練習時間が3倍ほどに伸び、辞めようか迷った」(千葉県・16歳)
「練習がきつく、家ではぐったりしてしまって勉強ができなかった」(愛知県・17歳)
3位:休みが少ない
「週末も遊べない」「長期休みも毎日練習」など、自分の時間がほとんどないことに息苦しさを感じる声も多く聞かれた。友人との交流や趣味の時間、あるいは単にゆっくり休む時間などがなさすぎると、心身の疲労につながることは確実だ。
「朝練、自主練など、スケジュール以外の練習が多すぎた」(山口県・18歳)
「毎日長時間ある部活は、それだけでもストレスなのに、『推し事』の時間が足りない、睡眠不足などで、よりストレスがたまった」(神奈川県・17歳)
「休みが少なく練習時間が長いうえに、大会が毎年テストの日とかぶる。どの部活よりも引退の時期が遅いのも、受験への影響が心配だった」(北海道・17歳)
4位:ほかにやりたいことがある
高校生活は、部活だけで成り立っているわけではない。受験勉強、趣味、友人との時間など、ほかに優先したいことが見つかるのは自然なこと。「部活」という一つの活動に多くの時間を費やすことに疑問を感じたとき、辞めたいという気持ちが芽生えることも。
「ジムでの筋トレやランニング、部屋の模様がえ、友達と遊びに行くなど、やりたいことを余裕をもってやりたかった」(千葉県・17歳)
「文化祭など学校行事にもっと参加したい」(岡山県・18歳)
「海外留学、受験勉強、課外活動などに打ち込みたい」(京都府・17歳)
「昔から習っていたピアノを再開したい気持ちが芽生えた」(東京都・17歳)
5位:練習が厳しく体力不足やケガなどが気になる
厳しい練習、長い拘束時間、十分な休息が取れないことによる、心身の疲労も大きな理由になる。特に高校生の時期は成長期。無理が続くと、学業に影響が出るだけでなく、ケガや体調不良につながることもある。
「部活中のケガで捻挫グセが付いてしまい、ドクターストップがかかった」(東京都・18歳)
「練習量が多く、身体がついていかなかった」(福岡県・19歳)
「作品を作り上げるためとはわかっているが、厳しい言葉は精神的にキツかった」(茨城県・17歳)
「あのまま続けていたら、心身ともに完全に壊れていたと思う」(東京都・17歳)
6位以下にはこんな理由も…
6位以下にも、高校生ならではのリアルな悩みがたくさん寄せられた。6位は「レギュラーになれないなど成果が出にくい」。練習を頑張っているのに試合に出られない、努力が結果に結びつかないといった、目標を見失ってしまうことへの焦りや無力感が、辞めたい気持ちにつながるようだ。
そのほか、アンケートの自由回答では、「部費や遠征費、道具代など金銭的な負担が大きい」(滋賀県・17歳)、「何となく楽しくなくなった。飽きてしまったのかも」(新潟県・18歳)といった声や、「強豪校だと知らずに入ってしまい、練習についていけなかった」(岐阜県・17歳)、逆に「もっと本気でやりたかったのに、周りのやる気がなかった」(岐阜県・16歳)など、自分の実力や目的と部のレベルが合っていなかったという、入部前後のギャップに悩む声も見られた。
部活を辞めたいと思うのは「逃げ」じゃない!

「部活を辞めたい」という考えは、決して「逃げ」ではない。むしろ、自分の心と体を守り、新たな可能性を見つけるための「前向きで勇気ある選択」だ。
「ここで辞めたら、逃げグセがつく」。そんな一言が、まるで重い呪いのように君の心を縛り付けていないだろうか。スクールカウンセラーの田村先生は、その考え方をきっぱりと否定する。
「逃げる」という言葉にはネガティブなイメージがあるかもしれませんが、単に「新たな道を選ぶ」というだけのことです。その場を離れて、違う道を選んだ。そう考えれば、決して負けではありません。
高校生活は部活がすべてではありません。辞めたことで生まれる時間や心の余裕を使って、新しい趣味を見つけたり、勉強に打ち込んだりと、あなたの視野を広げる新たな可能性を見つけましょう。(田村先生)
「部活を辞めたい」と感じたらするべき4ステップ

「部活を辞めたい」と感じたら、①理由を客観的に整理し、②信頼できる人に相談し、③将来への影響を冷静に考え、④辞めた後の自分を具体的に想像する、という4つのステップを踏むことが大事だ。
「辞めたい」という気持ちで頭がいっぱいになると、どうしていいかわからなくなってしまうこともあるだろう。まずは絡まった思考の糸をほぐすことで、後悔しない決断に近づける。
部活を辞めたい理由を整理する
まずは、自分の気持ちを客観的に「見える化」しよう。頭の中のもやもやを一度、紙やスマホのメモに書き出すのがポイント。
頭の中を整理するための3つの視点
・事実(できごと): 「レギュラーになれない」「顧問に毎日叱られる」「勉強時間が週に5時間しか取れない」など、具体的な事実や数値を書き出す。
・未来(どうなりたいか): 「勉強に集中して志望校に合格したい」「もっと自由な時間がほしい」「イラストを描くことに挑戦したい」など、自分が望む未来の姿を具体的に描く。
保護者や顧問の先生、友人などに相談する
次は、信頼できる人に話を聞いてもらおう。少し考えが整理できたなら、もう重い荷物を一人で背負い続ける必要はない。
相談相手は、親や学校の先生、先輩や友人など、あなたのことを客観的に見てくれる、信頼できる人が一番です。特に先輩や友人は、同世代なので状況をよく理解してくれますし、親身になってくれるでしょう。ただし、人によって見方が偏ることもあるので、自分が信頼できると感じる人を選ぶことが大切です。
もし身近に相談できる人がいなければ、匿名で利用できる電話相談やチャット相談などを活用するのも良い方法です。誰かに話す、文字にするという行為そのものが、気持ちの整理につながります。(田村先生)
部活を辞めることのメリット・デメリットを考える
部活を辞めることによるメリットとデメリットを具体的に書き出してみよう。文字にすると、頭の中だけで考えているより、冷静かつ正確に比較検討できる。後悔しない選択のために大切なステップだ。
部活を辞めることによる、内申点や大学受験への影響を考える
内申点や受験への影響については「特別な推薦入試などを除き、基本的に心配する必要はない」というのが専門家の見解だ。君の長所をより発揮できる場所で生き生きと活動できれば、何も心配することはない。
むしろ、嫌な部活を我慢して続けることでストレスが溜まり、勉強に集中できなくなるほうが問題です。内申書が気になるのであれば、部活以外の場所、例えば委員会活動やボランティア、あるいは学業そのもので自分の良さを発揮できれば、何も心配することはありません。(田村先生)
「部活を辞めた後の自分」を想像する
最後のステップは、部活のない新しい高校生活を具体的にイメージすることだ。朝や放課後の時間を、どこでどのように使うのか。その未来の時間が今の自分にとって魅力的だと感じるなら、それが君の進むべき道かもしれない。
次の章では、部活を辞めた先輩、辞めなかった先輩、それぞれのリアルを探る。君の未来を想像する手助けにしてほしい。
部活を辞めた後の生活は?先輩たちのリアル

頭で考えても、変化の後の未来は想像しづらいもの。「部活を辞めたらどんな生活が待っているんだろう」。そんな君は、少し先を歩む先輩たちのリアルな声に耳を傾けてみよう。
「辞めてよかった」と思う理由とタイミングは?
辞めた先輩の多くは、「人間関係などストレスの原因からの解放」と「勉強などほかのことに使える時間の確保」を「辞めてよかった」理由に挙げているよ。心と時間に余裕が生まれることで、より自分らしい高校生活を送れるようになるんだね。
「ストレスから解放されて睡眠時間も増えたので、肌の調子も良くなった。勉強もはかどり、たくさんの検定を取得できたし、テストの点数や順位も上がった」(兵庫県・18歳)
「後悔はなくて、むしろ過去の自分に感謝したいくらい。部活を辞めたことでたくさんの機会を得られている。あの時の判断のおかげで今の自分がある」(愛知県・17歳)
「辞めた後悔はない。しいて言うなら、入ったことを後悔している。最初から入りたい部活に入るべきだった」(東京都・19歳)
「成績を上げるために辞めた。実際、勉強時間が増えて成績も上がっている」(茨城県・16歳)
アンケート結果によると、部活を辞めるタイミングで一番多いのは高校2年生。部活に慣れてきたころや、受験が視野に入ってくる時期に大きな決断をした先輩が多いようだ。
1位:高校2年生(高2の春〜冬)
最も多くの先輩が辞めたタイミングとして挙げたのが高校2年生の時期。部活の中心メンバーとなり、責任が増す一方で、大学受験という現実的な目標が目前に迫ってくる学年だ。特に高2の夏~秋に、勉強への専念を理由に辞める決断をする声が目立った。
2位:高校1年生(高1の秋〜冬)
次いで多かったのが、高校1年生の後半。入部当初に抱いていたイメージと現実のギャップに悩んだり、厳しい練習や人間関係についていけなくなったりと、「思っていたのと違う」という理由で、比較的早い段階で見切りをつけた先輩は多いよう。特に高1の冬は、1年間の活動を経験した上で、次の学年に進む前に決断する一つの節目となっている。
3位:高校1年生の入部直後(高1の春〜夏)
入部して1週間など、ごく初期の段階で辞める決断をした先輩も。活動内容や部の雰囲気が自分に合わないと判断したり、別の部活に魅力を感じたり。早期の方向転換に踏み切った先輩も少なくない。
部活を辞めた後どうしていた?チャレンジしたことはある?
部活を辞めて生まれた時間を、先輩たちは新しい可能性を広げるために使っている。勉強に打ち込むのはもちろん、部活とは違う世界に飛び込むことで、新たな自分を発見した人も多いよ。
「軽音部を辞めてダンスの練習と韓国語の勉強を始めた。いろいろあってまたバンドを組むことになったので、自主的にギターの練習も再開した」(愛知県・17歳)
「英語検定の勉強に力を入れ、放課後や週末には地域の子ども向け英語教室でボランティアとして指導経験を積んだ」(東京都・19歳)
「別の部活に入部したり、文化祭の実行委員を引き受けたりと活動の幅が広がった」(宮城県・17歳)
部活を辞めて後悔したことはある?
もちろん、物事は良い面ばかりではない。辞めたからこその心残りや、失って初めて気づくこともある。辞めて後悔したポイントも赤裸々に教えてもらったよ。
「大学受験の面接で話すことが少なくて困った」(千葉県・18歳)
「続けるのはもう限界だったけれど、後悔はするだろうなと覚悟して辞めた。自分から何もなくなった感じがした」(東京都・18歳)
「あんまり勉強時間変わらなかったのと、体力がすごく落ちた」(大阪府・17歳)
「友達と距離ができてしまった。後輩とかかわれなかったことが残念」(静岡県・16歳)
「辞めたことに後悔はしていないが、ほかの部活に転部すればよかった」(千葉県・18歳)
部活を辞めなかった先輩のリアルも聞いてみよう!

いっぽうで、「辞めたい」という苦しい気持ちを乗り越えて、部活を続ける決断をした先輩たちもいる。その先に何を見つけたのか、その声もじっくり聞いてみよう。
「続けて良かった」と思う理由は?
仲間とのかけがえのない絆や困難を乗り越えた達成感など、人間的な成長を実感した人が多かったようだ。徐々に人間関係が良くなるなど、環境が変わった人も。「続けて良かった」と感じている先輩の声を聞いてみよう。
「部活の経験を話して総合型選抜に受かった。また、引退してからも試合に呼んでもらったり、遠征に帯同を頼まれたりと、頼りにされている感じがうれしかった」(佐賀県・18歳)
「自分の心と向き合いながら、時には友達にも相談して乗り越えた。スキルが磨かれたうえに将来の選択肢も広がり、良い経験になったと思う」(茨城県・17歳)
「苦しいながらも続けることで、大会でもいい結果が残せたし、みんなで思い出を作れたと思う。我慢する力を身につけた」(愛知県・17歳)
「人間関係が徐々に良くなり、多くの人と交流できて、部活が楽しくなった。大会でも成績を残せたし、高校でしか経験できない良い財産になった」(広島県・17歳)
部活を辞めずにやり抜くためにした工夫は?
辛い時期を乗り越えるためには、一人で抱え込まず周りを頼ったり、時にはうまく力を抜いたりすることも、大切な知恵だ。先輩たちはそれぞれさまざまな工夫をこらしていた。王道のものから「今だから言える」裏技的な工夫まで、たくさん教えてもらったよ。
「部活後のご飯を楽しみにするなど、プライベートを充実させた」(山口県・18歳)
「自分よりも上手な人のプレーを見て、目標の姿やそこまでの距離を明確にすることで続けられた」(鳥取県・17歳)
「メンタルを整えるために3カ月ほど休部した。あえて、顧問の先生や部員と距離を取った。学年主任の先生や友人にたくさん話を聞いてもらった」(宮城県・17歳)
「土曜だけ休むなど、ほどほどに力を抜いた」(福岡県・16歳)
「定期的に仮病やケガしたフリをして帰っていた。家で試合の動画を見たり、筋トレしたりすることで、モチベーションが湧いてくるのを待った」(千葉県・23歳)
部活を辞めると決めたらするべき3つのステップ
.jpg?20260209)
もし辞めるという決断をしたなら、次は、①顧問の先生への報告、②仲間たちへの報告、③今後の目標設定という3つのステップを踏む必要がある。君の熟考の末の決断だ。円満に退部できるよう、堂々と力を尽くそう。
顧問の先生に報告する
最初は、君の部活の責任者である顧問の先生に、直接会って話をするのが筋だ。練習後など、先生が落ち着いて話を聞ける時間帯にアポイントを取るのがコツ。思いつきではなく、じっくり考えた結果ということを分かってもらえるよう、丁寧に誠実に話そう。
例文
「〇〇先生、少しお時間いただけますか。突然で申し訳ないのですが、〇〇部を退部したいと考えています。これまで先生にはいろいろと熱心にご指導いただきました。本当に感謝しています。でも、最近は学業との両立に悩んでいました。将来の夢のため、まずは大学受験での志望校合格を目指して、勉強に専念したいのです。
しっかり考え抜いて決めたことです。どうかご理解いただけるとうれしいです」
部活の仲間たちに報告する
これまで一緒に目標に向かって頑張ってきた仲間への報告も大切だ。部活を離れても大切な仲間でいるために、誠意をもってしっかり伝えよう。タイミングや伝え方も、チームの状況や雰囲気をよく考えて、慎重に判断しよう。
例文
「みんな、練習後にごめん。ちょっと聞いてほしい話があります。急で本当に申し訳ないんだけど、〇〇日をもって、部活を辞めることにしました。みんなと練習したり、試合に出たり、本当に楽しかったです。これからは受験勉強を頑張りたいと思っています。みんなと一緒の目標を目指せなくなるのは寂しいけど、これからはみんなのことを一番のファンとして応援していきます」
今後の目標を明確にする
部活を辞めてできた時間をどう使うのか、具体的な目標を立てよう。「次のテストで学年順位を20番上げる」「夏休みまでに資格試験に合格する」「新しい趣味を見つける」――、自分で決めることが大切。次のステップに進むことで、決断に対する迷いを断ち切り、前向きな気持ちを維持することができるんだ。
【ケース別Q&A】部活を辞めることについての悩み…どうすればいい?

Q. 部活を辞めたいけど、保護者が許してくれない。どうすればいい?
A. 保護者が許してくれないのは、君を心配しているからかも。感情的に反発するのではなく、保護者が「何に不安を感じているのか」を考え、その不安を解消する具体的な提案をすると話が進展しやすいよ。
ですから、感情的に「何でわかってくれないの!」と反発するのではなく、まず一歩引いて「保護者は私が部活を辞めることで、何に困るんだろう?」と考えてみましょう。その上で、「部活を辞めて空いた時間は、毎日2時間必ず勉強にあてる。次のテストで学年順位を〇番上げることを目指す」というように、保護者の不安を解消できるような具体的な提案をすることで、冷静な話し合いができるようになります。直接言いづらければ、LINEなど文字で気持ちを伝えるのも効果的ですよ。(田村先生)
Q. 顧問の先生が怖くて部活を辞めたいと言い出せない。上手な切り出し方は?
A. 一人で伝えようとせず、まずは保護者に相談し、三者面談などの場を設けてもらうのが最も確実な方法だ。
どうしても一人で伝えなければならない場合は、「①指導への感謝」→「②辞めたいという結論」→「③具体的な理由」→「④今後の決意」という順番で、話す内容を事前に紙に書き出し、要点を整理しておこう。感情的にならず、誠意をもって伝える姿勢が大切だ。
Q. 高1で入部してまだ半年。部活を辞めていいか迷っている。
A. 入部して日が浅くても、合わないと感じるのであれば、辞めることは問題ない。前のアンケートのとおり、早い時期に辞めた先輩の例もたくさんある。むしろ早めの軌道修正は、お互いにとってロスが少ないとも言える。どうしても判断がつかず迷う場合は、一度休部して距離を置いてみるのも有効な手段だ。
Q. 部活を辞めると「逃げグセがつく」って本当?
A. じっくり考えた末に自分で下した判断で、逃げグセがつくということはない。むしろ心身に不調をきたすほど追い詰められているのであれば、それは自分を守るための「戦略的撤退」であり、必要な決断だ。
高校生は若さもあって、見た目では限界がわかりにくい。だからこそ、自分から「しんどい」「キツい」と声を上げることが本当に大切です。いきなりメンタルの病院はハードルが高いと感じるなら、まずはかかりつけの小児科や内科の先生で大丈夫です。正直に相談してみてください。(田村先生)
「部活を辞める=悪いこと」じゃない。君にとっての最善を選ぼう

ここまで読んでくれた君は、部活を辞めるか続けるか、自分の心と真剣に向き合ってきたはず。最終的に大切なのは、君自身が「どうしたいか」を考え、納得できる最善の道を選ぶことだ。
辞めること・続けることの意味は人によって違う
ある人にとっては最高の3年間が、別の人にとっては苦痛の時間であることは、本当によくあるケースだ。人間はみんな、それぞれ違う個性をもっている。信頼できる人に相談するのは大切だが、判断を委ねてはいけない。世間一般の価値観や周りの意見に流されるのではなく、しっかり君自身の心と向き合おう。
「私はこう決めた」でいい。自分の納得を大切に
辞めるか、続けるか。君はここまで、たくさんの情報を集め、メリットとデメリットを書き出し、自分の心と向き合い、悩み抜いてきたはずだ。その時間こそが、君の決断について誰にも文句を言わせない、確かな「根拠」になる。
部活を辞める決断も、続ける決断も、どちらが正解ということはない。大切なのは、君が自分の意思で選び取ったということ。それこそが、君だけの「正解」なんだ。だから、胸を張っていい。周りと比べて焦る必要はない。君が決めたその道を、自信をもって歩き始めよう。
最後に、そんな君の背中をそっと押してくれる、田村先生からのメッセージを贈るよ。
自分で悩み、考え抜いて出した決断なら、それを信じて、もう振り返らないこと。もしその決断によって何か不都合なことが起きたとしたら、それはまたその時に、新たな課題として向き合っていけばいいのです。一番大切なのは、あなた自身が、自分の決断を大切にしてあげること。それが本当の意味で「自分を大切にする」ということなんです。(田村先生)
君がどちらの道を選んだとしても、その過程で悩み、考え抜いた経験は、必ず未来の君の血肉となる。君の決断は尊い。君の高校生活を応援しているよ!
この記事を読んだ人におすすめ
部活を辞めてできた時間を、自分の将来のために使いたい。そう考えた君は、新しい可能性の扉の前に立っている。自分の興味やスキルを形にできる「資格取得」に挑戦してみるのも一手だ。大学入試で有利になることはもちろん、将来のキャリアを考えるうえでも貴重な経験になるはず。以下に、高校生におすすめの資格を紹介するので、気になるところをチェックしてみよう。
実用英語技能検定(英検®)
大学入試の優遇措置などで定番の資格。読む・聞くだけでなく、「話す」「書く」も含めた総合的な英語力が身につき、将来どんな道に進んでも役立つ一生もののスキルになる。まずは自分のレベルに合った級から挑戦してみよう。
※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
●実用英語技能検定(英検®)について詳しく知る
TOEIC Bridge® Listening and Reading Tests
世界共通の英語能力テストTOEIC®の初・中級者向けバージョン。日常的で身近なトピックから出題されるため、英語に少し苦手意識がある人でも取り組みやすいのが特徴だ。まずはここから始めて、自信がついたらTOEIC®本体にチャレンジするのもいいだろう。
●TOEIC Bridge® Listening and Reading Testsについて詳しく知る
中国語検定試験
大学の第二外国語としても人気の中国語。経済的な結びつきが強い隣国の言葉を学んでおくことは、将来のキャリアにおいて大きなアドバンテージになる可能性がある。漢字に馴染みのある日本人にとっては、比較的学習を始めやすい言語の一つだ。
●中国語検定試験について詳しく知る
韓国語能力評価試験(KLAT)
K-POPやドラマ、コスメなど、韓国カルチャーが好きな人なら、楽しみながら学習を進められるはず。趣味が高じて資格取得につながれば、大学の学校推薦型選抜などでアピールできる「強み」になるかもしれない。
●韓国語能力評価試験(KLAT)について詳しく知る
マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)
Word®やExcel®、PowerPoint®といった、どんな大学・職業でも必須となるパソコンスキルの証明になる国際資格。レポート作成やプレゼンテーションなど、高校生活はもちろん、大学入学後にもすぐに役立つ実践的なスキルが身につく。
●マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)について詳しく知る
情報検定(情報活用試験)【J検】
パソコンやスマートフォンが当たり前の現代社会で、情報を正しく安全に「使う」能力は不可欠だ。この検定では、情報モラルやセキュリティに関する知識も問われるため、デジタルネイティブ世代の君たちが、これからの社会で必須となるリテラシーを体系的に学ぶ良い機会になるだろう。
●情報検定(情報活用試験)【J検】について詳しく知る
おすすめ記事 PICK UP
勉強と部活を両立させる方法10選!高校生が受験勉強と両立させるコツ、効率的な勉強法を解説!
”先輩が怖くて厳しい”のは昔の話! 高校生の「部活の先輩・後輩関係」のリアルを大調査!
部活引退時の後輩へのメッセージ例文60選│一言・感動・おもしろ系まで!気持ち伝わる言葉
将来何がしたいかわからない高校生へ!やりたいことのみつけ方【適職診断付き】
専門学校の資格おすすめ一覧|将来に活かせる資格と選び方をわかりやすく解説!
スクールカウンセラーとは? 必要な資格・やりがいは? お仕事密着レポ
高校生カップルがしたいこと10選!今しかできないデート&平均交際期間もチェック
取材・文/二階堂ねこ 取材協力・監修/田村節子 構成/寺崎彩乃(編集部)
※記事内のデータならびにコメントは、2025年8月に高校生620人に実施した調査(調査委託先はマクロミル)によるものです。