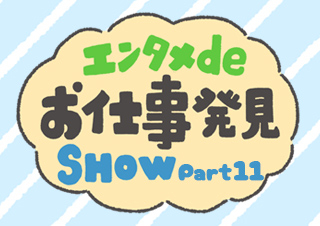社会福祉士とは?なり方、仕事内容、年収や活躍の場を解説!
社会福祉士は、福祉にかかわる相談援助の専門職。本記事では、社会福祉士の資格の取得方法や国家試験の難易度、仕事内容やについて解説します。
目次

監修者プロフィール
乾 喜一郎 リクルート進学総研主任研究員(社会人領域)
資格や社会人大学院など専門誌の編集長を長く務め、これまで取り上げてきた。
3000人以上の事例をもとに学習者の立場から提言。
文部科学省等の各種事業で有識者委員を歴任。
社会福祉士とは
社会福祉士は、社会福祉の専門職で、高齢者や障がいのある人など、日常生活を営むのに支障がある人やその家族、また生活困窮など社会生活を送るうえで困難に直面している人に対し、福祉に関する相談援助を行います。ソーシャルワーカーなどともよばれます。
相談者がどんなことに困っているのか、的確に聞き取り、一人ひとりの状況に合わせた福祉サービスを提案し、行政や関係機関とも連携。
相談者が安定した暮らしができるよう、支援を行います。
働く場は高齢者福祉施設や医療機関などさまざま。
このようにニーズの高い専門職ですが、社会福祉士を名乗って仕事をするには、国家試験に合格して社会福祉士の国家資格を取得する必要があります。
この資格は「社会福祉士及び介護福祉士法」の制定により1987年に誕生。
社会の複雑高度化、家族や人々のつながりの変化によって支援ニーズが拡大したことが背景にあります。
その後の少子高齢社会の急速な進行、人々の暮らしの多様化などさまざまな社会課題が浮き彫りになっているなか、社会福祉士の果たす役割はますます大きくなっています。
また、社会福祉士の国家資格は、「名称独占」資格です。
有資格者だけが社会福祉士と名乗ることができます。
ちなみに医師や歯科医師、看護師、助産師などの国家資格は、有資格者だけが業務に就くことができる「業務独占」資格です。
社会福祉士になるには
社会福祉士になるには、国家試験に合格して資格を取得することが必要です。この資格は名称独占資格なので、資格がなくても社会福祉にかかわる相談援助業務に就くことはできますが、多くの社会福祉施設などでは資格取得者を応募条件としているケースが多く、キャリアアップを目指すなら、資格取得は必須条件ともいえます。
国家試験の受験資格
国家試験は年1回、例年2月上旬ごろに実施されます。誰でも挑戦できる試験ではなく、複数の受験資格が定められており、いずれも受験資格を取得するには一定の養成機関などでの学習や実務経験が必要。言い方をかえると、国家試験の受験資格を得ることが、社会福祉士になるための重要な第一歩となっているのです。
受験資格の取得ルートは12通り。この記事では高校卒業後の学歴などを軸にして、受験資格を得る方法を解説していきます。
学んだ学校種や学部、履修した科目などによってルートが異なっているので要注意。
大学を卒業した人

福祉系大学など(※)を卒業している場合
※4年制大学を例にあげて解説していますが、4年制の専門課程をもつ専門学校も「福祉系大学など」に含まれ、受験資格の適用対象になります。Case1 4年制大学の福祉系学部・学科で所定の「指定科目」を履修し、卒業。
国家試験の受験資格があります。実務経験なしで受験できます。
Case2 4年制大学の福祉系学部・学科で所定の「基礎科目」を履修し、卒業。
実務経験は不要ですが、受験資格を得るには短期養成施設などで6カ月以上学ぶ必要があります。
一般大学を卒業している場合
Case3 4年制大学の福祉系ではない学部・学科を卒業。一般養成施設などで1年以上学ぶことで、受験資格が得られます。実務経験は不要。
短大・専門学校を卒業した人

福祉系の短大・専門学校を卒業している場合(3年制の場合)
Case4 3年制の福祉系短大・専門学校で所定の「指定科目」を履修し、卒業。相談援助の実務経験が1年以上あれば、受験資格が得られます。養成施設での学習は不要。
Case5 3年制の福祉系短大・専門学校で所定の「基礎科目」を履修し、卒業。
相談援助の実務経験を1年以上積み、さらに短期養成施設などで6カ月以上学ぶことで受験資格が得られます。
福祉系の短大・専門学校を卒業している場合(2年制の場合)
Case6 2年制の福祉系短大・専門学校で所定の「指定科目」を履修し、卒業。相談援助の実務経験が2年以上あれば、受験資格が得られます。養成施設での学習は不要。
Case7 2年制の福祉系短大・専門学校で所定の「基礎科目」を履修し、卒業。
相談援助の実務経験を2年以上積み、さらに短期養成施設などで6カ月以上学ぶことで受験資格が得られます。
一般短大・専門学校を卒業している場合
Case8 3年制の短大・専門学校の福祉系ではない学科を卒業。相談援助の実務経験を1年以上積み、さらに一般養成施設などで1年以上学ぶことで受験資格が得られます。
Case9 2年制の短大・専門学校の福祉系ではない学科を卒業。
相談援助の実務経験を2年以上積み、さらに一般養成施設などで1年以上学ぶことで受験資格が得られます。
社会福祉主事の指定養成機関を卒業した人、4年以上の実務経験がある人

Case10 社会福祉主事の指定養成機関(※)を卒業。
相談援助の実務経験を2年以上積み、さらに短期養成施設などで6カ月以上学ぶことで受験資格が得られます。
(※)都道府県により指定を受けている社会福祉主事養成機関(福祉系専門学校など)のこと。
Case11 行政機関で児童福祉司、身体障害者福祉司、査察指導員、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事などの職種に就き、相談援助の実務経験が4年以上ある人。
短期養成施設などで6カ月以上学ぶことで受験資格が得られます。
Case12 施設などで相談援助の実務経験が4年以上ある人。
一般養成施設などで1年以上学ぶことで受験資格が得られます。
相談援助の実務経験とは
受験資格として規定されている相談援助業務の範囲は、児童分野、高齢者分野、障がい者分野など多岐にわたっています。ただし、受験資格にかかわる実務経験として認められる施設の種類や職種が細かく定められているので、注意が必要です。
教員やキャリアコンサルタントは相談援助技術を生かせますが、実務経験とは認められていない職種です。
実務経験として認められている施設と職種の例
・児童相談所……児童福祉司、受付相談員、相談員、電話相談員、児童心理司、心理判定員、児童指導員、保育士・指定介護老人福祉施設……生活相談員、介護支援専門員(配置基準によって配置されている有資格者に限ります)
など
出典:「社会福祉士国家試験」. 公益財団法人社会福祉振興・試験センターホームページ
国家試験の難易度・合格率
社会福祉士国家試験の試験科目は19科目。社会福祉全般はもちろんのこと、心理学、保健医療、社会保障など広範囲にわたる知識が問われます。
2025年に実施された試験は、合計129の問題が出題され、配点は1問1点の129点満点です。合格基準は「総得点の60%程度」となっており、78点程度が合格基準ということになります。毎年、難易度により、合格基準点には補正が入ります。
注意が必要なのは、0点の科目があると合計点が基準点に達していても不合格になってしまうということ。広範囲にわたる試験ですが、まんべんなく知識を身につけ、受験対策を進めていくことが重要です。
2025年に実施された第37回社会福祉士国家試験の結果は次のとおりです。
・受験者数:2万7616人
・合格者数:1万5561人
・合格率:56.3%
※合格基準点は62点でした。
ちなみに近年の合格率は以下のようになっています。
・第36回試験(2024年実施) 58.1%
・第35回試験(2023年実施) 44.2%
・第34回試験(2022年実施) 31.1%
・第33回試験(2021年実施) 29.3%
こうしたデータからもおわかりいただけるように、合格率は近年上昇しているとはいえ、難しい試験といえるでしょう。
必ずしも福祉仕事を専門にしている人が受験するわけではないということや、試験範囲が広いことも難しさに影響していると考えられます。
出典:「第37回社会福祉士国家試験の合格発表について」.公益財団法人社会福祉振興・試験センターホームページ
社会福祉士の年収
「令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査実施結果報告書」(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)によると、社会福祉士全体の平均年収は403万円でした。ちなみに前回調査(平成27年度:2015年度)では平均年収377万円でしたので、26万円ほど多くなっています。
一方で、男性・女性別では、男性の平均年収は473万円、女性の平均年収は365万円で、男女で108万円の差があるという結果になっています。
ご参考までに、資格手当が支給されている割合は37.4%になり、前回調査(30.1%)と比べて約7ポイント高く、資格手当の平均支給額は月に1万827円(前回調査では1万797円)でした。
出典:「社会福祉士就労状況調査実施結果報告書」.公益財団法人社会福祉振興・試験センターホームページ
社会福祉士はどんな人を支援する? 働く場は?
社会福祉士の働く場は幅広く、さまざまな領域にわたって困っている人の支援を行っています。どんな人を支援し、どのような場所で働いているのか、以下にまとめました。
高齢者を支援する
介護が必要な高齢者や高齢者福祉施設で暮らす高齢者、その家族を支援。また、ひとり暮らしの高齢者も支援の対象となります。主な働く場
・老人ホームやデイサービスセンターなど高齢者福祉施設「生活相談員」として働きます。高齢者本人やその家族からの相談を受けたり、関係機関との連絡・調整を行うのが主な仕事。
・地域包括センター
自宅で暮らす高齢者の介護や医療など、生活の悩み相談に対応。「ひとり暮らしなので、自分に何かあったときのことが心配」といった相談にも応じ、成年後見制度の紹介なども行います。
子どもを支援する
児童虐待や不登校、子どもの非行などに関する相談に対応。子どもたちとその保護者の支援にかかわります。また、生活上の事情などで保護者からのケアを受けられない子どもや、保護者のいない子どもなどをサポートするのも社会福祉士の仕事。
障がいのある子どもとその家族に対する支援も行っています。
主な働く場
児童相談所、児童養護施設、乳児院、知的障害児施設、肢体不自由児施設など。職種名としては児童指導員、児童福祉司、少年指導員など。母子生活支援施設で母子支援員として、母子の自立に向けてサポートする社会福祉士もいます。障がいのある人を支援する
身体や知的、精神などに障がいのある人や家族などからの相談に対し、障がいのある人が社会の一員として生活していけるよう支援を行います。主な働く場
障がい者支援施設などで生活相談員や生活支援員として働きます。病気にかかっている人を支援する
病院に入院・通院している患者とその家族からの相談を受け、サポートをします。入院費用のことや、退院後の療養生活に関する支援制度を紹介したり、病院の転院先を探すなどの支援を行います。主な働く場
病院など医療機関で医療ソーシャルワーカーとして働きます。地域の人たちを支援する
高齢者、障がいのある人、子どもなど、地域に住むあらゆる人たちを対象に相談支援。生活困窮など、地域住民が抱える問題の解決に向けて助言をしたり、関係機関との連絡・調整を行います。主な働く場
自治体の役所、福祉事務所で公務員として働きます。また、各地にある社会福祉協議会も社会福祉士の活躍の場となっています。その他
・教育現場で活動小・中・高校でスクールソーシャルワーカーとして児童・生徒本人や教員、保護者からの相談に対応して問題解決のための支援を行います。
・司法関係施設で活動
少年院や更生保護施設といった司法関係施設などで罪を犯した人の社会復帰にかかわる支援に携わります。
・自分の社会福祉士事務所をもち、活動
実績を積んで自分の社会福祉士事務所を開き、専門性を生かして活動する社会福祉士も増えています。
出典:「社会福祉士の仕事場は皆さんのまちです!」公益社団法人東京社会福祉士会
社会福祉士に似ている職種・資格
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、社会福祉士と同じく、福祉分野の相談援助を行う専門職。日常生活を営むことに支障がある人や、社会生活を送るうえで困っている人からの相談に応じ、支援を行います。社会福祉士と同様、国家資格をもつことで、精神保健福祉士を名乗って活動することができます。
このように両者はよく似ている職種ですが、社会福祉士が医療・福祉にかかわるあらゆる支援を行うのに対し、精神保健福祉士は精神障がいやメンタルヘルスの問題を抱える人に高い専門性をもって向き合い、支援を行うことを主な業務としています。
社会福祉主事任用資格
福祉事務所などの行政機関や福祉施設などで、保護や援助を必要とする人に相談・指導・援助を行う仕事が社会福祉主事。社会福祉士との大きな違いは資格の種類です。
社会福祉士は国家資格ですが、社会福祉主事は「任用資格」といわれる資格。福祉事務所などで社会福祉主事として任用されるケースで必要とされる資格です。
資格を取得するには指定養成機関で学ぶなど複数の方法がありますが、大学などで社会福祉に関連する所定の3科目を履修し、卒業することで資格を得ることができます。
社会福祉主事は福祉の分野の基礎資格ともいえる位置づけで、就職・転職の際に応募要件となる場合もあります。
福祉系学部・学科なら、カリキュラムに沿って学ぶだけでほとんどの人が取れる資格です。
出典:「社会福祉主事について」厚生労働省
社会福祉士を目指せる大学・短大を探す 社会福祉士を目指せる専門学校を探す 福祉が学べる大学・短大を探す