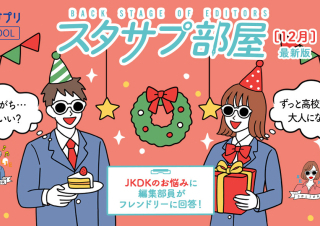法科大学院(ロースクール)とは?司法試験の仕組みや仕事もわかりやすく解説
法曹になるための主要ステップである法科大学院。本記事では、法科大学院の概要から司法試験、検察官・裁判官・弁護士のなり方についても解説していきます。目次

監修者プロフィール
乾 喜一郎 リクルート進学総研主任研究員(社会人領域)
元『法科大学院入試ガイド』編集長。資格や社会人大学院など専門誌の編集長を長く務め、これまで取り上げてきた。
3000人以上の事例をもとに学習者の立場から提言。
文部科学省等の各種事業で有識者委員を歴任。
法科大学院とは
裁判官・検察官・弁護士(=法曹三者)を養成するための専門職大学院
法曹になるためには司法試験合格が必須であり、法科大学院を修了することで、司法試験の受験資格が得られます。また、要件を満たしている場合は、法科大学院の在学中に受験も可能です。司法試験を受験するには、ほかに予備試験を受験する方法もありますが、予備試験合格自体が狭き門であることもあり、法科大学院進学は、法曹になるための中心的なステップと位置づけられます。
法学部出身でなくても入学できる?
法律の知識がゼロの方には未修者コースがあります。コースによって修業年限が異なり、法学部などで法律を学んできた人を対象とする2年制の既修者コースと、法学を学んでいない人を対象とした3年制の未修者コースがあり、それぞれ入試の内容にも違いがあります。
法科大学院の授業の特色
特色1教育方法に関しては、ソクラテスメソッドと呼ばれる対話型の授業方法を導入しています。
特色2
在学中に外部の弁護士事務所などで実務経験を積むインターンシップやエクスターンシップなども採り入れており、法曹として活躍するために必要な思考力や実践力を養うことに重点を置いています。
特色3
実務能力を養うため、研究者教員だけでなく、現役の弁護士や元裁判官などの実務家教員が授業を担当しています。
法科大学院、司法試験の最新事情
進学へのハードルを下げる取り組みが増えている
現在の各法科大学院では、進学へのハードルを下げる取り組みが活発に行われています。その一つが奨学金制度の拡充です。授業料全額・半額免除など大胆な制度を導入している大学院も。また、安価な入学検定料を設定していたり、複数の入試方式を併願する場合の割引がある場合もあります。そのほかでは、働きながら通いやすいよう夜間開講や週末開講を実施していたり、長期履修制度がある法科大学院もあります。
積極的に独自の取り組みを進める法科大学院も増えてきているので、志望校の最新情報はWebサイトなどでチェックしておきましょう。
最短ルートの法曹コース
法曹資格の取得には、大学入学から最短6年で可能な法曹コースもあり大学入学前から弁護士や裁判官、検察官を目指すと決めている場合はこのコースも視野に入れたい。法曹コースとは、法学部などを設置する大学が法科大学院と連携し、大学を3年でし、法科大学院の既修者コースの教育課程と一貫して教育が受けられるコースです。
在学中に司法試験に合格した場合、学部での3年・法科大学院での2年・合格後の司法修習生としての1年を合わせ、最短6年で法曹として活躍しはじめることができます。
最大5回まで司法試験が受験できる
法科大学院の在学中に司法試験を受験する場合は、最初に司法試験を受けた年の4月1日から5年間に5回まで受験が可能です。法科大学院修了後に受験する場合は、修了後5年間で5回までとなります。また、一度受験資格を失っても、あらためて法科大学院を修了するか、あるいは予備試験に合格すれば再度受験資格を得ることができます。
司法試験の概要
司法試験の受験資格は、①法科大学院を修了していること②法科大学院に在学し、法科大学院で所定科目単位を修得しており、大学院を1年以内に修了見込みがあること③司法試験予備試験に合格していることのいずれかになります。司法試験の試験科目
司法試験は例年7月に実施され、短答式試験と論文式試験が課されます。短答式試験の試験科目は、憲法、刑法、民法の3科目。
論文式試験の試験科目は、公法系科目(憲法および行政法に関する分野の科目)、民事系科目(民法、商法および民事訴訟法に関する分野の科目)、刑事系科目(刑法および刑事訴訟法に関する分野の科目)、選択科目(知的財産法、労働法、租税法、倒産法、経済法、国際関係法〈公法系〉、国際関係法〈私法系〉、環境法のうち1科目)の4科目です。
試験は4日間にわたって行われ、全員が短答式試験と論文式試験を受験します。
ただし、短答式試験で合格ラインに達しないと、論文式試験は採点されません。
また、短答式試験、論文式試験で最低ラインに到達していない科目が1科目でもあると不合格とされるので、苦手科目を作らないことが大切です。
なお、法科大学院の授業は司法試験対策に特化しているわけではないので、司法試験合格のためには、学生同士で作る自主ゼミ・勉強会を中心とした試験対策が重要。法科大学院によっては、教員やその法科大学院出身の先輩弁護士がチューターとなり熱心に自主ゼミの活動をサポートしている学校もあります。
司法試験の合格率
2024年度の試験では、司法試験の合格率は42.1%でした。受験者別にみると、大学院の在学中の受験者は55.2%、大学院の修了者は22.7%でした。法科大学院から法曹になるには?
1年間、司法修習生として学ぶ
司法試験合格後は、1年間、司法修習生として学びます。この間に、裁判官・検察官・弁護士の現場を経験しながら、どの道を選ぶのかを決めていきます。
司法修習生は公務員ではありませんが、国家公務員に準ずる地位として扱われます。
司法修習生への給与は月額13万5000円を給付する制度があります。
10カ月の実務修習と司法研修所で2カ月の集合修習を経て、「二回試験」と呼ばれる試験に合格すると司法修習終了となります。
この時点で、判事補任命資格、2級検事任命資格、弁護士登録資格が得られます。
【検察官・裁判官を目指す場合】
検察官、裁判官を目指す場合は、司法修習終了前にそれぞれの採用試験に合格する必要があります。採用枠が限られているため、検察官、裁判官を志望している人がすべて採用されるわけではありません。
【弁護士を目指す場合】
弁護士を目指す場合は、法律事務所などに就職活動を行います。法科大学院生、司法修習生時代に、法律事務所で活躍する弁護士としっかりパイプを作っておくことが、就職を成功させる大切なポイントです。
また、先輩弁護士に仕事を教わることができないという意味では不利ですが、法律事務所に就職せず、いきなり独立して自分で弁護士事務所を開業する道もあります。
そのほか、最近では、弁護士資格を生かして一般企業に就職し、企業内弁護士として法務部などで活躍するケースも増えています。
法科大学院合格までのダンドリ

法律の勉強ができる大学・短大を探す 弁護士を目指せる大学・短期大学を探す 裁判官を目指せる大学・短期大学を探す 検察官を目指せる大学・短期大学を探す 出典:令和7年司法試験に関するQ&A(法務省)
法曹コースについて(文部科学省)
令和6年司法試験の結果について(法務省)
法科大学院制度の経緯について(法務省)