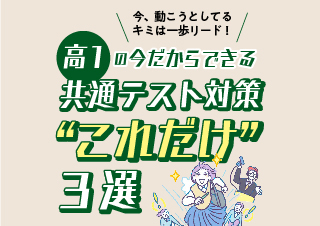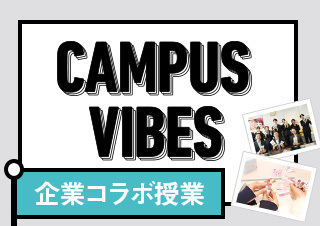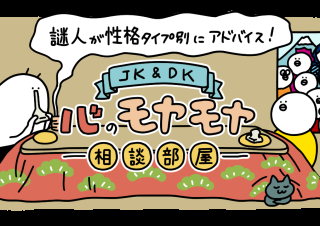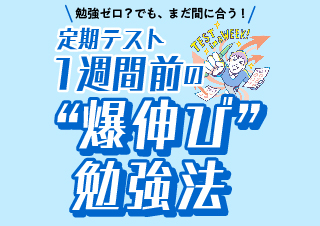専門学校の選び方完全ガイド|パンフ・オーキャンで必ず見るべき12のポイント
専門学校への進学を考えていても、分野の種類や学校の数がたくさんありすぎて、どう選んだらいいのか迷っている人も多いのでは?
でも、「何となくよさそう」「仲のよい友だちもこの学校に決めたから」といった理由で決めてしまうと、入学してから「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねない。
そこで、失敗しない専門学校の選び方について、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会事業推進課・後藤由利さんに教えてもらった。
「HP・学校パンフレットの6つのチェックポイント」と、「オープンキャンパスの6つのチェックポイント」、合わせて12のポイントを詳しく紹介する。
目次
公益社団法人東京都専修学校各種学校協会(東専各協会)
東京都内の専門学校をとりまとめる団体として、会員校との連携、協力の下、専修学校・各種学校教育の充実・振興につとめている。
1961年に東京都教育委員会から認可された東京都私立各種学校協会をルーツとし、その後、60年以上にわたって専門学校の振興と発展に力を注ぐ。
ホームページなどを通じての学校情報の発信、進学ガイドブックの制作・発行、専門学校の教員・職員対象の研修実施、中学・高校・企業との情報連絡会の開催、東京都など行政との連携事業などに取り組んでいる。
専門学校とは
専門学校とは、高校卒業以上の人を対象に、職業に直結する専門教育を行う学校。
大学が学術的・理論的な学問を学ぶ教育機関であるのに対し、専門学校は仕事の現場で役に立つ実践的な知識や技術はもちろんのこと、社会人として必要な常識やマナーも学べる。
教育内容はIT、建築、調理、美容、デザイン、医療技術など幅広い分野にわたり、仕事に必要な資格の取得を目的にした学科も多い。
修業年限は2年制の学科が多いが、カリキュラムに応じて1年制から4年制までさまざまな学科がある。
実習の授業が豊富で、就職後に即戦力として活躍するために必要な技能を身につけることができる。
失敗しない!なりたい仕事に就くための専門学校選び
専門学校はその分野のプロを養成する学校。
自分がなりたい職業に近づくための学びができることが大きな特徴だ。
その一方で、入学してから「自分がやりたいこととは違った」「予想していた授業内容ではなかった」「学習意欲がわかない」といったミスマッチが原因で、学校に行くのが苦痛になってしまうケースもある。
文部科学省の調査(※)でも、「学生生活不適応・修学意欲低下」という理由から、専門学校を中退する学生が多いという結果が出ている。
「こんなはずじゃなかった」「学校、辞めたい…」と後悔することのないよう、自分に合った専門学校を選ぶことが大切。
数多くの専門学校の中からどのようにして選べばいいのか、その段取りを解説していこう。
STEP1:将来どんな仕事に就きたいのか考える
自分に合った専門学校を選ぶために最初にやるべきことは、将来、どんな仕事をしたいのか、どんな分野で働きたいのか、考えること。
専門学校は、ひとつの分野・職業に特化して学ぶところなので、自分がなりたい仕事が何なのかわからないまま、なんとなく学校選びをしてしまうと、入学してから後悔することになりかねない。
でも、高校生が知っている職業の数は限られているので、どうしたらやりたいことが見つけられるのか、悩んでいる人も多い。
そんな人は好きなこと、得意なこと、興味があること、自分に向いていそうなことをヒントに考えてみることから始めてみよう。
幼いころからあこがれを感じていた職業、職業体験の授業で「楽しい!」と思った職業、テレビドラマを見て興味をもった職業も、やりたい仕事を見つけるきっかけになる。

STEP2:目指したい仕事の情報収集をする
働いてみたい分野や目指したい仕事が見えてきたら、仕事内容や働き方などを調べてみよう。
ポイントは、なりたい仕事に就くためにどんな知識や技術が必要なのか、必須の資格と取得する方法についての情報を集めること。
ネットや職業解説本で調べることができるし、その職業で活躍している先輩の話も紹介されている記事もあるので参考にしてほしい。

STEP3:気になる学校のHPやパンフレットをチェックする
目指したい仕事の全体像がつかめてきたら、その仕事に就くために必要な知識と技術が学べる専門学校を探してみよう。
気になる学校があればホームページをチェック!
HPから学校のパンフレットも請求できるので、複数の学校パンフを取り寄せて、比較検討してみるといい。
学校パンフの誌面には必要な情報がわかりやすく整理されているので、第一志望の学校や併願校を決めるのに役に立つ。

STEP4:オープンキャンパスに参加する
オープンキャンパスは、高校生などに向けて開催される学校紹介イベント。
専門学校のキャンパスを開放して学校説明会、個別相談会、実際の授業や実習の内容がわかる模擬授業や体験授業、校内の施設・設備を見学できるキャンパスツアーなどを行っている。
HPやパンフでも情報をつかむことはできるが、実際に現地へ行き、見たり、聞いたりすることで学校の雰囲気や特色をリアルに感じることができるので、気になる学校のオープンキャンパスには必ず参加しよう。
「オープンキャンパスに参加するとき、必ずしもやりたい仕事が一つに絞り込めている必要はないと思います。
むしろ、一つに決め込みすぎて選択肢を狭くしないほうがいいでしょう。
興味のある仕事が複数あるのなら、複数の学校のオープンキャンパスに参加してリアルな情報を集めてみてください。
そうすることで自分が本当にやりたいことがみえてきて、納得のいく専門学校選びにもつながると思います。
以前、東専各協会では高校2年生を対象に、希望する職業に関する授業を専門学校で体験してもらうという事業を実施しました。
その時に体験してもらったのは、第1希望の職業に関係する授業と、第2希望の職業に関係する授業です。
例えば、保育士と調理師、服飾デザイナーと自動車整備士といった具合に、2種類の授業を体験してもらいました。
その結果、参加した高校生から、「第1希望より第2希望の職業の授業が面白かった」という声も聞かれたのです。
参加した高校の先生方も、生徒が第2希望の職業まで授業を体験したことで、、自分の好きなことや適性、可能性を広げるきっかけになったと、おっしゃっていました」(東京都専修学校各種学校協会事業推進課・後藤由利さん、以下同)
HP・学校パンフでチェックすべきポイント
STEP3では、学校のHPやパンフレットを活用して情報を集めることの重要性を解説した。
では、具体的にどのような点をチェックすればよいのか。
HPやパンフレットで確認すべき項目は、「認可校かどうか」「授業内容やカリキュラム」「目指せる資格」「就職サポートや実績」「入試の方式」「学費」の6つ。
これらは学校選びの基本となる重要な情報であり、必ずチェックしておきたい。詳しく見ていこう。
ポイント1.認可校かどうか
専門学校は、学校教育法の規定により、都道府県知事の認可によって設置されている学校。
希望する学校が都道府県知事の認可校かどうか、HPや学校パンフで確認しておきたい。
認可校で学ぶと、公的な奨学金制度や通学定期券、学割証が利用できるなど、さまざまなメリットがある。
認可校と無認可校の違い
| 認可校 | 無認可の教育機関 | |
|---|---|---|
| 認可者 | 都道府県知事 国立の場合は文部科学大臣 公立の場合は都道府県教育委員会 |
なし |
| 裏付けとなる法律 | 学校教育法第124条 | なし |
| 修業年限の規定 | 1年以上 | 規定なし |
| 授業時間数の規定 | 年間800時間以上 | 規定なし |
| 学歴 | 専門学校卒業 | 正式な学歴とは認められない |
| 卒業して得られる称号 | 要件を満たせば「専門士」「高度専門士」 | なし |
| 大学編入・大学院進学 | 要件を満たせば可能 | できない |
| 公的奨学金 | 利用できる | 利用できない |
| 通学定期券 | 利用できる | 利用できない |
| 学割証明 | 利用できる | 利用できない |
※出典『専門学校の基礎知識』(公益社団法人東京都専修学校各種学校協会)
────────────────────────────────
専門学校の2年制以上の学科(※1)を卒業すると「専門士」、4年制以上の学科(※2)を卒業すると「高度専門士」という称号を得ることができる。
専門士は、短期大学卒(短期大学士)と同等とみなされる称号で、就職の際の待遇も短大卒と同等の評価になる。
また、専門士は大学への編入学も可能になる。
さらに上の高度専門士は4年制大学卒(学士)と同等にみなされる称号。
就職時は大学卒と同等に評価されるほか、大学院への進学も可能になる。
専門学校卒業後の進路として、大学編入、大学院進学を考えている人は、専門士、高度専門士の称号が得られる学科を選びたい。
(※1)
◇専門士の称号が与えられる学科の要件
・修業年限が2年以上。
・総授業時数1700単位時間以上(62単位以上)。
・試験などにより成績評価を行い、それに基づいて卒業を認定していること。
(※2)
◇高度専門士の称号が与えられる学科の要件
・修業年限が4年以上。
・総授業時間数が3400時間(124単位)以上。
・体系的に教育課程が編成されていること。
・試験などにより成績評価を行い、それに基づいて卒業の認定を行っていること。
ポイント2.授業やカリキュラムの内容
授業の内容とカリキュラムが、自分がなりたい職業に直結しているかどうかは、専門学校選びの重要なポイント。
HPや学校パンフレットには学部やコース、カリキュラムの内容など、詳しく書かれているので、しっかり確認しよう。
学科名やコース名が同じでも、学校によって学べる内容は異なるので、複数の学校のHP、パンフレットを読み比べてみることが大切だ。
☑ 自分が学びたいことを勉強できる学科やコースはある?
☑ 卒業までのカリキュラムは?
☑ 実習の内容や企業などでのインターンシップの状況
☑ どんな先生が教えている?
☑ 卒業までにどんな知識や技術が身につく?
☑ その学校ならではのカリキュラムの特徴
☑ 目指す職業に直結するコンクールやコンテストなどへの参加は?
「専門学校は、基本的には高校と同じように授業の時間割が決められています。
授業は週5日、毎日ぎっしり詰まっているので、どのような時間割になっているのか、HPやパンフレットでチェックしておきましょう。
毎日の授業内容だけではなく、1限めの授業の開始時刻と、その日の授業の終了時刻を確認することもポイント。
昼間部の場合、授業は9時ごろに始まって16時ごろに終了というパターンが多いのですが、朝8時台に授業が始まるケースがあるなど、学校や学科によって時間割は異なります。
遠方からだと、1限めの開始が早いと、通うのが大変になるかもしれません。
自分が無理なく通える学校を選ぶためにも、時間割は確認しておきましょう」

ポイント3.取りたい資格を目指せるか
なりたい職業に就くために必要な資格を目指せる学科・コースがあるのかどうかは、学校選びではずせないポイント。
まず、知っておきたいのは、専門学校で目指せる資格にはさまざまな種類があり、取り方もいろいろあるということ。
専門学校卒業と同時に無試験で取得できる資格(幼稚園教諭二種免許、保育士、栄養士など)もあれば、専門学校卒業と同時に資格試験を受験する資格(受験資格)が得られる資格(看護師、美容師、救急救命士、二級建築士、愛玩動物看護師など)もある。
いずれも、専門学校の所定の課程を学ぶことが必須になっているので、志望校ではそうした課程があるのかどうか、要確認だ。
また、専門学校で資格試験合格のための教育を受け、在学中に取得を目指せる資格もある(応用情報技術者、宅地建物取引士、全国通訳案内士など)。
取りたいと思っている資格が、どのような方法で取得できるのかを理解したうえで、資格取得を目指せる学校を選ぼう。
☑ 目指している資格は取得できる?
☑ 目指している資格試験の受験資格は得られる?
☑ 資格取得の実績(資格試験の合格率)は?
☑ 資格試験合格のためのサポート体制は?
「資格取得のためのサポート内容は、資格試験に向けての補習授業や実技試験対策の授業、試験対策の勉強会を実施するなど、学校によりさまざまですので、HPや学校パンフレットで調べておきましょう。
万一、不合格でも、合格するまで卒業後もサポートしてくれる学校もありますよ」

ポイント4.就職サポート体制や就職実績
専門学校は即戦力として活躍できる職業人を育てる学校。
就職指導にも力を入れている学校が多く、クラス担任と就職指導部やキャリアセンターが連携し、学生一人ひとりに合わせて就職サポートを行っている。
気になる学校ではどんな就職サポートを行っているか、卒業生の就職実績と合わせてチェックしておこう。
☑ 求人状況は?
※学校に寄せられる求人件数など。
☑ 卒業生の就職実績
※就職した分野や、具体的な就職先(企業・団体など)。
☑ 就職率
※その年の卒業生のうち、就職した学生の割合。
また、身につけた専門技能や資格を生かせる職種に就いている学生の割合も要チェック。
☑ 就職サポート体制は?
就職ガイダンス、業界セミナー、企業説明会、個別面談、履歴書の添削、インターン実習、筆記試験・面接試験対策などの内容をチェックしよう。
☑ 卒業後も転職や再就職のサポートは受けられる?
「卒業生の就職実績を調べる際、就職先の名前だけではなく、どのような企業に何人就職しているのかまで、確認しておきましょう。
直近3年分の実績を年度ごとにチェックすることをおすすめします。
同じ企業に毎年、一定数の卒業生が就職しているのなら、その企業から学校の教育や卒業生の仕事ぶりが高く評価されているということが考えられるので、就職活動でも有利になる可能性があると思います。
また、自分が興味をもつ企業へ就職できた卒業生の人数も調べておきましょう。
ただし、年度ごとの詳細な就職実績は、HPや学校パンフレットで紹介されていない場合もあるので、オープンキャンパスの時に聞いてみてください」

ポイント5. 入試の方式
専門学校の入試の形式は、主にAO入試(総合型選抜)、推薦入試、一般入試の3種類。
これら3種類は、ほとんどの専門学校で行われている方式だけど、学校や学科によって試験内容が異なるので、確認しておく必要がある。
自分がチャレンジしやすいかどうかという視点で、チェックしていこう。
☑ どんな入試報方式が行われている? 試験内容は?
※AO入試(総合型選抜)
受験生の学習意欲や適性、学校が求める学生像とのマッチングを重視して選抜する方式。
書類審査と面接で選考が行われることが多いが、作文や課題提出、適性試験などが課されるケースもある。
※推薦入試
高校(校長や担任)の推薦書などが必要となる入試の形式。
高校3年間の成績(評定平均)や欠席日数が、出願条件として設定されている。
書類審査と面接に加え、適性試験、小論文などが課されることもある。
※一般入試
書類審査と面接のほか、小論文、学科試験、実技試験が行われる場合もある。
☑ 入試のスケジュール(出願・試験時期など)は?
☑ 入試の難易度は?
※=医療系の専門学校の中には、受験者数と合格者数を公開している学校もあるので、確認してみよう。
ポイント6..学費はいくらか
気になる学校の学費をチェックすることも、専門学校選びで大切なポイント。
専門学校では授業で忙しく、アルバイトに費やす時間も限られてくるため、学費をどう工面するのか、計画を立てておくことが肝心だ。
東京都専修学校各種学校協会『令和6年度 学生・生徒納付金調査』によると、2024年度の専門学校(東京都・昼間部)の初年度納付金の平均は130万1000円。
内訳は、授業料が73万6000円、入学金が18万1000円で、その他実習費や設備費などがかかる。
これはあくまで平均の金額で、学校や分野によっても大きく異なるので、志望する学校・学科ではいくらかかるのか、必ず確認しておきたい。
さらに、家から通うのか、アパートなどで一人暮らしをするのかによって、通学や学生生活にかかる費用に違いがでてくる。
お金の問題は避けては通れないので、保護者と一緒にチェックしよう。
☑ 初年度にかかる入学金、授業料、その他の費用
☑ 2年次以降はいくらかかる?
☑ 通学のための交通費(定期券代)
☑ 一人暮らしをする予定なら、アパートなどの家賃相場
※学生寮などを設けている学校もあるので、要チェック。
☑ 利用できる奨学金制度の内容
※公的な奨学金制度として代表的なのは、独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金。
国の『高等教育の修学支援新制度』に基づき、JASSOから返済する必要のない「給付型奨学金」の支給と、「授業料・入学金の免除または減額』を受けることができる。
JASSOには、返済義務のある「貸与型(利子ありと、利子なし)」の奨学金制度もある。
そのほか、各都道府県・市区町村、民間団体が運営する奨学金、学校独自の奨学金制度や学費減免制度もある。
それぞれで利用条件などが異なっているので、調べてみよう。
「お金のことはとても大切なので、学費はしっかり確認しておきましょう。
授業料の内訳として何にいくらかかるのかまで明記している学校もあれば、「実習費などの費用込みで〇円」とか、「初年度納付金〇円~〇円」という書き方をしている学校もあります。
そのため、複数の学校の学費情報を見比べて、検討することをおすすめします。
また、初年度の学費については、『いつまでにいくら払うのか』もチェック事項です。
合格発表後、『2週間以内に〇円』などという具合に、短期間でまとまった金額の支払いが必要になることが多いので、要注意です。
学費の分割払いが可能な学校もありますから、調べてみましょう。
専門学校は授業の数が多く、アルバイトと奨学金だけで学費を工面しようと思っても現実的には難しいので、保護者ともよく話し合ってくださいね」

専門学校の学費はいくら?受験料、入学金、授業料の平均まで、学びたい分野別にチェック!
専門学校の奨学金制度。給付型とは?毎月いくら?JASOO、教育ローン等もまとめて解説!
─────────────────────
HP上の「情報公開」のページから学校の客観的な情報を得ることも、専門学校選びでは大切。
「情報公開」(あるいは「情報の公開」)として、HPの目立つ位置に配置していたり、「学校概要」などのコンテンツの中に設けている場合もあるので、チェックしてみよう。
在学者数や、定員割れが起きているかどうか(定員充足率)、卒業者数、中退者の数、卒業後の進路状況など、具体的な情報が開示されているので、学校の現在の状況を知ることができる。
また、公開されている財務情報や事業報告書などから、学校の経営状況もわかるので、保護者と一緒に確認しておきたい。

オープンキャンパスでチェックすべきポイント
続いては、STEP4のオープンキャンパスに参加した時にチェックしたいポイントを解説していく。
HPや学校パンフで概要を知ることはできても、学校や授業の雰囲気、在校生の印象、周辺環境などは、実際に足を運んでみないとわからないので、オープンキャンパスにはぜひ、参加してほしい。
オープンキャンパスで必ずチェックしたいポイントは「学校の立地や環境」「学校の設備や施設」「授業の進め方」「どんな先生が教えているのか」「海外留学・研修制度の内容」「学校の雰囲気」の6つ。
自分に合う専門学校を選ぶためにも、複数の学校を見学することが大切だ。
また、オープンキャンパスでは、個別相談会も開かれているので、わからないことや疑問点などがあれば聞いてみよう。
ポイント7. 学校の立地や環境
専門学校に入学したら、キャンパス内や学校周辺のエリアは、学生生活を過ごす場になる。
無理なく通えて、楽しく過ごせて、やりたいことをしっかり学べる環境かどうか、しっかりチェックしておこう。
☑ 自分が学びたいことを勉強できる学科やコースはある?
☑ 自宅から学校までの所要時間
☑ 自宅から学校までの交通アクセス
☑ 学校の立地
※にぎやかな繁華街にあるのか、緑豊かな郊外にあるのか、学校の場所は要確認。
毎日通う学校なので、「ここならば!」と思える学校を選びたい。
☑ 学校周辺の街の雰囲気
※学校の近くで一人暮らしや学生寮生活を考えている人は、暮らす環境としてどうなのかもチェックしておこう。

ポイント8.学校の設備や施設
専門学校で身につけた技能が、卒業後に仕事現場で通用するかどうかは、教室や実習の設備、施設がどのくらい充実しているかにかかっている。
HPや学校パンフでも動画、写真などを通じて確認はできるが、オープンキャンパスで実際に見て、体験してチェックしよう。
授業以外の時間を過ごす図書館や自習室などについても確認しておくといい。
☑ ICT機器や実習機器など、最新の学習機材が用意されている?
※目指す業界で使われているレベルに対応した学習機材なのかどうか、しっかり確認。
☑ I学習機材の数は十分にそろっている?
※学生の数に対して数が足りているのかどうか、確認しよう。
☑ I施設・設備は古すぎたりしない?
☑ I講義を受ける教室や実習室の広さは?
☑ I授業時間以外に利用できる自習室やラウンジはある?
☑ I図書館は充実している?
☑ I校内に学食やコンビニはある?
「学校の学習機材は、授業以外の時間も自由に使えるのかどうか、チェックしましょう。
服飾系など実技の課題が多い学科では、課題の内容によっては学校の機材がないとこなせない場合があります。
そのため、放課後に学校に残って課題に取り組まなければならない時もあるので、何時まで使えるのかも確認しておきたいポイントです」

ポイント9.授業の進め方
専門学校の授業はどんな感じなのか、希望している学科の模擬授業や体験実習に参加してチェックしよう。
模擬授業や体験実習は実際の授業に近い内容を受講できる、貴重な機会。
20分程度の短い時間の場合が多いが、基本的な内容を教われるので、その内容は自分が学びたいことなのかどうかがわかったり、なりたいと思っている職業に自分が向いているかどうかも確認できそう。
入学してから「学科名だけで決めてしまったけど、思っていた授業内容と違っていた…」と後悔するリスクを減らすこともできる。
☑ 授業内容に興味をもつことができた?
※専門学校の模擬授業や体験実習を受けてみて、興味が湧いてくるかどうかは、入学してから楽しく学んでいけるかどうかを判断するポイントになる。
また、体験実習で、「こういうのは苦手かも」「楽しくないかも」などと感じたら、別の進路を考えるという選択肢もありそう。
☑ 授業や先生の教え方が自分に合うか
☑ 学びたい内容が学べるか
「オープンキャンパスでは、模擬授業や体験実習に必ず参加していただきたいのですが、オープンキャンパスは参加者の皆さんに楽しんでもらい、その分野をわかりやすく理解してもらうことを目的に、趣向をこらした授業内容になっています。
通常の授業の様子も見学し、普段の授業ではどんなことをしているのか、授業の進め方などが自分に合っているかどうかを確認することも大切だと思います。
多くの学校ではオープンキャンパス以外でも、授業見学を受け付けているので、問い合わせてみてくださいね」

ポイント10. どんな先生が教えているのか
どんな先生が教えているのか、先生の経歴などを確認しておくことは、専門学校での学びの充実度にかかわるポイント。
オープンキャンパスの学校説明会や模擬授業などでチェックしよう。
☑ 自分が目指す職業・業界での経験は?
※その道のプロを目指すための専門教育を受けられるのが専門学校。
業界でどのような実績を築いている先生から教われるのか、確認しよう。
☑ 先生としての経験は?
※教え方がわかりやすいかどうか、先生としての経験がどのくらいあるのかも確認しておきたい。
☑ 模擬授業や体験実習で教わった先生に、入学後も教われる?
※模擬授業などで教壇に立った先生が、入学後に実際に教われる先生とは限らないケースもあるので要チェック。
オープンキャンパスの日程により、担当する先生が変わる場合も多いので、自分が希望する学科・コースの先生の模擬授業を体験できる日を確認しておこう。
「最先端企業に所属する人が先生として教えにきている学校も少なくありません。
そうした第一線で活躍する先生とのつながりで、その企業に学生が就職しやすくなるケースもあるので、先生がどのような企業に所属しているのか、チェックしましょう。
その一方で、先生としての経験を積んだベテランの専任教員がどのくらいいるのかも、確認してみるといいと思います。
ベテランの専任教員が多い専門学校は、教えるスキルが高い先生を大切にしていて、先生が長く勤められる学校であるともいえます。
このような働く環境が良好な学校で教える専任教員はモチベーションも高く、学生に対してていねいに教えてくれるのではないかと思います」
ポイント11. 海外留学・海外研修制度の内容
専門学校で語学系学科への進学や、卒業後はグローバルに活躍したいと考えている人は、海外留学や海外研修制度の内容は必ず、確認しておこう。
☑ 海外留学・海外研修制度はどのようなものがある?
☑ 留学提携校や研修先の数、国・地域は?
☑ 留学先・研修先への派遣人数は?
☑ 海外留学・海外研修制度を利用するための条件は?
※学内選抜などの有無や審査内容も確認しよう。
☑ 留学先・研修先での取得単位は卒業単位として認められる?
☑ 海外留学や海外研修に際して、費用面のサポートはある?
ポイント12. 学校の雰囲気
専門学校の校風や先生、在校生の雰囲気が自分に合うかどうかは、学習や学生生活の充実度を高めるための重要なチェックポイント。
HPや学校パンフレットだけではわからないので、オープンキャンパスでしっかり確認しよう。
☑ 学校の印象は?
☑ 在校生の様子
※オープンキャンパスでは在校生と話す機会もあるので、積極的に交流しよう。
そこで学ぶ学生がどんなタイプの人が多いのか、わかる。
例えば、ファッション系の学校なら、在校生の服装が自分の好みやセンスと合うかどうかも、チェックしておくといい。
☑ オープンキャンパスに参加している高校生の様子
※入学後はどんな人たちが同級生になるのか、知ることができる。
☑ 先生の雰囲気
「専門学校の雰囲気が自分に合っているかどうかは、入学後に楽しく学び続けるためには大事なことです。
直感的に『いいな!』と思えるかどうかが、ポイントになります」

──────────────────────────
専門学校選びで見逃せないポイントになっているのが、スクールカウンセラーが常駐しているかどうか、ということ。
「なりたい仕事に就くために学校を選んで入学しても、勉強に行き詰まったり、同級生との関係などで悩みを抱える学生もいます。
また、残念ながら担任の先生との相性が合わなくて、勉強が続かないという学生もいると聞いています。
そんな学生に対するフォロー体制を整えているかどうかも、学校選びでは欠かせないと感じています。
近年では、学生の不安や悩みに親身になって相談にのってくれるスクールカウンセラーが常駐している専門学校が増えています。
志望校にそうした専門スタッフを配しているかどうか、確認してほしいと思います」

先輩たちが専門学校を選んだ決め手は?
たくさんの専門学校があるなかで、先輩たちがどうやって選んだのかも気になるところ。
どんな仕事を目指すのか、学びたい分野を選んだ理由は、「好きだから」「あこがれていた」「得意なことだから」という先輩が多いようだ。
先輩たちも、自分の素直な気持ちと向き合うことでやりたいことをみつけている。
そして、目指す仕事に就くために、専門学校選びで重視したポイントは分野にもよるが、多くの先輩が「授業内容」「学校の設備」「通学のしやすさ」「国家試験の合格率」「就職実績」をチェックしている。
自分の将来のために学ぶ学校だからこそ、チェックすべきポイントはしっかり確認しておこう。
自分に合った専門学校をみつけよう!
東京都専修学校各種学校協会事業推進課・後藤由利さんから高校生のみんなにメッセージをもらったので、紹介しよう。
自分だけで考え込まず、保護者、友人や先輩、高校の先生などにも相談して、いろんな人の意見を聞いて決めるといいと思います。
肝心なのは、『早く、決めなければ!』とあせらないこと。
オープンキャンパスに1回参加したら、その学校を第一志望にしなければならないということはありません。
オープンキャンパスは無料で参加できるので、複数の学校に気軽に出かけてみてくださいね。
また、同じ学校のオープンキャンパスに何回、行ってもOKなのです。
気になる専門学校があれば、まず高校1年の夏に行き、高2の夏、高3の春にも行ってみる、という参加のしかたもあり、です。
そのときどきで印象も違うと思いますし、納得がいくまでオープンキャンパスに参加することをおすすめします。
自分が本当に行きたい専門学校を選び、『やりたい仕事に就く』という夢を叶えてほしいと思っています」
入学してから後悔しないためにも、この記事を参考に、さっそく行動しよう!
取材・文/小林裕子 取材協力・監修/公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会 構成/寺崎彩乃(スタディサプリ進路編集部)
※参考文献『学生・保護者・社会人のための専門学校ガイド 2025年度版』『東専各 専門学校オフィシャルガイド2025』(共に編集・発行は公益社団法人東京都専修学校各種学校協会)
※この記事は、2025年4月現在の取材に基づく情報になります。


専門学校の時間割は?授業の特徴・スケジュール例を分野別に見てみよう!
専門学校の学費はいくら?受験料、入学金、授業料の平均まで、学びたい分野別にチェック!
専門学校の奨学金制度。給付型とは?毎月いくら?JASOO、教育ローン等もまとめて解説!
専門学校の就職事情を調査!大学との比較、就職率、メリットデメリットを解説
専門学校の面接対策!よく聞かれる質問、面接の流れとマナー
専門学校の入試方式、出願方法、難易度を押さえて不安解消!
専門学校の志望理由書(志望動機)の書き方。手順・例文・ライバルに差をつけるコツを解説!
専門学校にも偏差値はある?大学とどう違う?難易度、倍率、入試対策を解説!