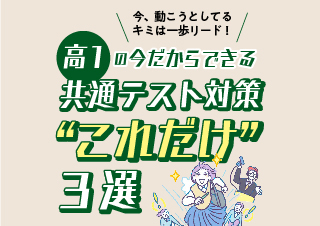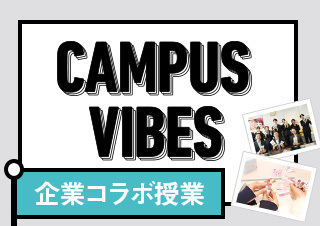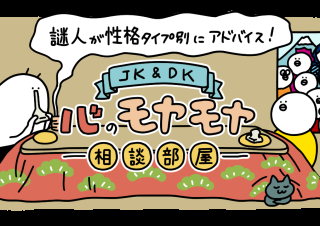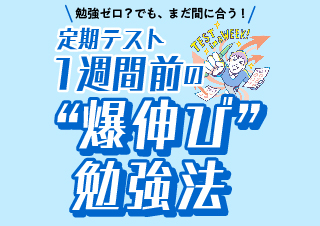専門学校を目指すなら文理選択はどうする?職業別・後悔しない選び方を解説!
専門学校への進学を考えている人の中には、高校1年生の文理選択を「自分にはあんまり関係がない」と感じている人もいるかもしれない。だけど実際には、専門学校への進学を考えている人にとっても「文理選択」は将来の職業にも影響する、とても大事な選択なんだ。
そこでこの記事では、文理選択の基本や、それぞれの違い、そして専門学校へと進学した先輩たちのリアルな声を紹介しながら、年間100人以上の高校生の進路のお悩みを解決している進路指導のプロ・神﨑史彦先生に「後悔しない文理選択の進め方」をテーマにお話を伺って解説していくよ!
目次

神﨑史彦 先生
株式会社カンザキメソッド代表取締役。スタディサプリ講師。私立学校研究家。高大接続・教育コンサルタント。
大学卒業後、大学受験予備校において小論文講師として活動する一方、通信教育会社や教科書会社にて小論文・志望理由書・自己アピール文の模擬試験作成および評価基準策定を担当。
のべ6万人以上の受験生と向き合うなかで得た経験や知見をもとに、小論文・志望理由・自己アピール・面接の指導法「カンザキメソッド」を開発する。
現在までに刊行した参考書は26冊(改訂版含む)、販売部数はのべ25万冊、指導した学生は10万人以上にのぼる。
文理選択ってそもそも何?専門学校にも関係あるの?

大学、専門学校などの進学先や将来の職業にも影響する、重要な選択なんだ。
一般的には、高2から文系と理系に分かれてクラス分け、カリキュラムが組まれるため、高1の秋ごろには選択することになる。
自分の人生を左右する選択だからこそ、「友達と一緒だから」など曖昧な理由で決めてしまうと後悔しやすく、自分自身が本当に納得して選ぶことが大切なんだ。
ここからは、専門学校の文理選択の基本について神﨑先生にお話を伺ってみよう!
文系と理系の違いって?
文系が人文科学や歴史、社会など人間や社会の活動を中心とした分野を指すのに対し、理系では農学、医学、理学など自然科学の研究を中心とした分野を指します。
以下の表で、それぞれに文系と捉えられやすい学問、理系に捉えられやすい学問を表にしてまとめてみたので参考にしてください。(神﨑先生)
| 文系 | 理系 |
| 哲学、文学、歴史学、心理学、文化人類学、言語学、福祉学、教育学、経済学、商学、法学、政治学、国際関係学など | 数学、情報科学、統計学、天文学、物理学、医学、生物学、農学、獣医学、工学、建築学など |
大学とは違う?専門学校での文理の影響
例えば、建築などの職種の場合、どうしても高校の授業で習う物理の前提知識がないと、その後の学習内容を習得しづらい。
つまり、建築系の職種を目指すのであれば、ある程度早いうちから「理系」を選択し、物理専攻を意識しておくほうがよいといえます。
建築以外にも、もし将来的に以下のような職種に就きたいと考えている場合は、早めに文理選択と専攻を明確にしておいたほうがいいといえるでしょう。
理系:建築系(物理)、医療系(生物)、農業系(生物)
※( )内は高校生のうちに専攻したい科目
なかには「この科目が得意だから」という理由で文理選択をした後に、だんだんと将来どんなことがやりたいかを絞って見つけていく生徒さんもいます。
また一部ではありますが、途中で文理選択を変更する「文転」「理転」を選択することもできます。
ただ、いずれの場合でも、自分の将来に深く関わる選択なので、進学や就職をしてから後悔をしないように、しっかりと自分で考えて選択することをおすすめします。(神﨑先生)
「専門学校だと文理選択は関係ない」って本当?
しかし、これはまったくの誤解。
おそらく、大学受験と違って専門学校には入試での選抜性が低いことが、そうした誤解へとつながっているのだと思います。
先ほども言ったように、文理選択は将来の職業に関わってくる大事な選択。
専門学校に進学する場合でも、文理選択はその先の人生に大きく影響します。
「将来やりたいことがある人」こそ、早めの文理選択を意識するようにしましょう。(神﨑先生)
専門学校の文理選択の決め方

では、文理選択を決める際には、どんなことから考え始めるのがいいのだろうか。
ここからは以下の3つの考え方から、専門学校の文理選択の決め方を神﨑先生に教えてもらったよ!
1. 得意な教科から考える
2. 好き・興味から考える
3. 将来なりたい職業や進みたい分野から考える
1. 得意な教科から考える
これまでの学校での成績や、テストへの意欲などから考えてみるとよいでしょう。
ただし、一つ気をつけたいのが「この教科が苦手だから避けよう……」と苦手を中心とした消去法で考えないほうがいい、ということ。
苦手をベースに考えてしまうと、大体の人が「その勉強をしなくて済む」という考えになってしまいます。
しかし例えば、職業によっては文系に進学しても数学が必要になる場面もありますし、将来的に必要な場面が出てくる可能性は十分にあります。
そういうときに拒否反応へとつながらないよう、「苦手なこと」ではなく「得意なこと」を中心に考えて、それを広げていくイメージで考えてみてください。(神﨑先生)
2. 好き・興味から考える
これは、その分野の知識をたくわえるのが楽しい、わからないことに興味が湧いて調べるなど、自然と夢中になれる分野のことです。
ここが先ほど考えた「得意な教科」と重なってくる場合は、そこを軸にして考えてみるとよいでしょう。
ただし、ここでも一つ注意点。
たとえ好きな分野を勉強する、好きなことを仕事にする、となったとしても、それは「苦手なことをやらなくていい」ということではありません。
例えば私にとっては、進路指導をすることで、高校生の皆さんにそれぞれ行きたい進学先に進んでもらうことが大きなやりがいですが、経理関連の業務はどうしても苦手です。
でも好きな仕事を続けるためには必要なことなので、苦手だと思う仕事も投げ出さずにいつも向き合えています。
逆にいえば、「このためだったら多少苦手なことでも向き合える」という分野を見つけることが、文理選択においても大きな一歩だといえるかもしれません。(神﨑先生)
3. 将来なりたい職業や進みたい分野から考える
将来の姿がイメージできれば、逆算して「今どんなことを学べばいいのか」がわかりやすくなるため、文理選択もとてもやりやすくなります。
ただし、多くの人は「将来の仕事」というとその職業に就いたときをゴールにして考えてしまいがちです。
ですが本来、その職業を選択したあとにも約40年間の仕事人生が待っているわけです。
できれば、その職業に就いたらどの程度の収入になり、どんなライフスタイルが送れるのか、まで想像してみてください。
例えば、「ブライダル」関連の職業はコロナ禍を経て、市場自体が小さくなりました。
もちろん職種で考えれば、結婚という幸せな門出の場面のお手伝いができるのは素敵です。
だけど、「ブライダル市場は縮小傾向」と知らずに進んでしまい、のちのち「収入が安定しない」「仕事が少ない」という状況になったら、後悔してしまうかもしれない。
もし興味がある業界があれば、一度は調べてみてから判断することをおすすめします。(神﨑先生)
先輩の声からわかる!後悔しない文理選択のポイント

先輩たちはどう選んだ?リアルな実態をアンケート!
今回は、103人の専門学校生を対象に、高校生のときの文理選択に関するアンケートをとってみたよ!まずは、先輩たちがどんなふうに考えて文理選択をしたのか、アンケートの結果から見てみよう!

上記のグラフを見ると44.7%、約半分に近い先輩たちが「得意・苦手な教科から考えた」と回答。
次いで、「好きな教科・興味のある教科から考えた」と「将来めざしている職業や業界から考えた」の人数がほぼ同じで、それぞれ全体の約1/4となっている。
それぞれの回答から、その理由も抜粋して紹介しよう!
- 将来の目標的にどちらの選択でも進むことができたので、指定校推薦をもらうためにいい成績でいたかったため苦手な教科がない方を選択した(長野県)
- 得意な教科をもっと学んで伸ばしていきたかったから(福岡県)
- 数学が苦手なため消去法で文系を選んだ(兵庫県)
- 自分は数学が得意で社会などが苦手だったので理系に決めた(大阪府)
- 地理や歴史が好きだったから文系を選んだ(東京都)
- 得意苦手でもよかったけど、好き嫌いで判断するほうが学ぶモチベーションが続くかなと思った(東京都)
- 好きなことをやって生きていきたいので、具体的に自分は何をするのが好きなんだろう、何が辛くないんだろうと考えた(埼玉県)
- 自分が何に興味があるかを見つめ直し、学んでいくうえでモチベーションを維持できるかを考えた(大阪府)
- 文系の方が将来的に自分の進む道に合うと考えた(新潟県)
- 将来が看護の世界に進みたいと思っていたため理系になると自然に思ったため(神奈川県)
- 特になりたい職業もなかったので、文系から理系に転じることはできないけど理系から文系に行くことはできるからとりあえず道の広い理系に行った(北海道)
- 自分は理学療法士を目指していたから、生物を習うことができる理系を選んだ(大阪府)
- 将来の選択肢が多いから(宮城県)
- 何となくかっこいいと思うほうを選んだ(大分県)
その結果が以下のグラフだ。

なんと、約9割の人が文理選択の仕方について「後悔していない」と回答。
逆に、「後悔している」と回答したのは11人で内訳は以下のようになった。
-「好きな教科・興味のある教科から考えた」3人
-「将来めざしている職業や業界から考えた」4人
-「その他」1人
先輩たちの声①「あこがれで選んだらついていけなくなった」
ここで注意したいのは、あこがれる気持ち自体は決して悪いことではない、ということ。
むしろ、あこがれが強いモチベーションになるケースもある。
ただし、このコメントを寄せてくれた方にとっては、理系は「苦手な教科」であり、それを無視して文理選択をしてしまったことが後悔につながってしまったのだ。
「あこがれ」だけで決めるのではなく、必ず自分の「将来」や「適性」についても考えたうえで文理選択を一歩ずつ進めていくようにしよう。
先輩たちの声②「興味があって進んだが就職に不利」
だけど、文理選択の時点でもう少しだけ将来のことを調べていれば、この人が文系・理系のどちらを選ぶかは変わっていたのかもしれない。
何度も言うけど、文理選択は進学先だけではなく自分の将来に影響する重要な選択なんだ。
専門学校に進学する場合、職業に直結する知識や技術を学ぶからこそ、文理選択の段階でその業界や就職先について調べておくことはとても大事なことだといえる。
もう一つ、この方の言う「就職を考えると理系のほうが有利」というのは必ずしも正しいとは限らない。
マスコミ・出版・教育・サービスなどを目指すならば文系を選択したほうがいいし、弁護士や行政書士といった士業は就職にも強い。
たしかに全体として理系の学生のほうが少ない分、企業からの需要は高い傾向にあるけど、それは職種にまったくこだわらない場合であって、それよりも「自分が進みたい方向に合致しているかどうか」のほうがはるかに大事なんだ。
それに、「就職に有利だから」という考えは、あくまでゴール設定が「就職」になってしまっているよね。
せっかく将来に関わることを自分で決めるのだから、ゴール設定はさらに先。
「どんな人生を送りたいか」「どんな働き方がいいか」ということまでイメージして、考えてみよう!
先輩たちの声③「やりたい仕事に必要なほうを選んだ」
それでもこの方が自分の選択に後悔していないのは、「看護師になる」という将来の夢が大きなモチベーションになっているから。
だからこそ、苦手な教科に対しても「勉強したくない」「避けたい」ではなく、「夢のために必要なこと」と前向きにとらえることができるんじゃないだろうか。
実はこのコメントは、先輩たちの声①で紹介した「あこがれで選んだらついていけなくなった」というコメントと、「理系が苦手」という点では共通している。
だけど、「自分にとってのモチベーションがどこにあるのか」は大きく違う。
「何のためなら自分が頑張れるのか」は、「文理選択」をするうえでも、とても大事な考え方だといえそうだ。
「先輩は、後輩に何を伝えたい?」アンケート結果
先ほど紹介したアンケート結果では、先輩たちが自分の選択に「後悔していない」と答えた人は9割だった。だけど、きっと中には専門学校に入ってからより将来の仕事を意識するようになって「もっとこういう観点で考えておけばよかった」と感じている人もいるはず。
そこで、今回のアンケートでは「文理選択に悩む高校生に向けて、どう考えて決めるのがおすすめですか?」という質問も投げかけてみた。
以下のグラフが、その回答結果だ。

自分が選択する際には「得意・苦手な教科から考えた」人が44.7%だったが、後輩には「将来めざしている職業や業界から考えてほしい」と感じている人が46.6%と、逆転して上回る結果となった。
この結果から読み解けるのは、「実際に自分が選んだ決め方」と「後輩にすすめたい決め方」の違い。
実際には「得意・苦手」から選んだものの、振り返ってみれば「将来目指している職業や業界」を軸に考えるほうがよかった、と感じている人が多いのだ。
専門学校に進学してから「もっと将来のことについてイメージしておけばよかった」とならないためにも、ぜひ文理選択の段階で、進学先だけでなく、仕事やその先の人生について、想像してみてほしい。
職業・分野別に見る|文理選びのヒントまとめ

文系がおすすめな職業・専門分野
文系の職業では、人と関わる機会が多く、コミュニケーションや対人スキルなどがより重要になってくる職業が多い傾向がある。また、メディアをはじめ芸能や理美容など、自分の感性を生かして何かを表現したり、アイデアを形にしたりする仕事も多い。
業界をまたいだ転職も比較的しやすいが、中には、士業、教員、保育士など資格を必要とする専門性の高い職種もある。
理系に比べると、「人や社会に関わる」「仕組みを作る」「何かを伝える」といった役割が大きいといえる。
理系がおすすめな職業・専門分野
理系の職業は、文系の職業に比べると専門性が高く、特定の知識や技術が必要とされる職種が多い傾向がある。新技術や新製品の研究・開発をはじめ、製造プロセスの改善、インフラの構築や整備など、ものづくりに関わる職種のほか、品質管理、設計、データ分析など客観的なデータに基づいた論理的思考が求められる仕事が多い。
また、専門学校で学んだ知識がそのまま仕事でも生かされることが多く、技術士、建築士、臨床工学技士など国家資格が多いのも理系の職業の特徴だ。
文系に比べると専門的な知識、技術力、論理的な思考を生かして「社会に必要なものをつくる」役割が大きいといえる。
文理どちらでもOK!進路次第で広がる職業
中には、文系や理系にかかわらず、目指せる職業もある。
これらの職業を目指す場合は、基本的には文理選択についてはどちらを選んでもかまわない。
なので、自分の得意や好きな領域の勉強をしてもいいし、成績を見てより評定を高く取れそうなほうを選んでもいい。
もしも、進学先として考えている専門学校があるのであれば、オープンキャンパスのタイミングなどで、先輩や先生に「高校でどんなことを学んでおくといいか」を質問してみるのもおすすめだ!
やりたいことが決まっていない時は?

そんな人はどんなことを考えて文理選択をすればいいのか、神﨑先生に教えてもらったよ!
「将来の夢がない」でも大丈夫!
保護者でもいいですし、友達でもいい。その方々にどんなふうにあなたの得意・不得意が見えているのか、そしてどんなことに興味がありそうに見えるのかを尋ねてみてください。
自分のことは、案外、自分からは見えないもの。
他人がとらえた客観的な自分の姿から、自分の内面が見つかることもあるはずです。
それを経て「私って、こんな人なんだ」と少し自分が掘り下げられたらバッチリです。
きっと、前よりも文理選択のことも考えやすくなっているはずです。(神﨑先生)
オープンキャンパスに行ってみよう!
その場合は何校か、自分が興味がある業界の専門学校を選んでみて、オープンキャンパスに行ってみてください。
新しい情報や、専門学校の先生や先輩たちに触れることで、より自分の興味がわかりやすくなることもあります。
「やりたいことがない」ということは、「まだ知らないことが多い」ということでもあります。
新しいことを知って、自分がどんな瞬間にワクワクしたのかが見えてくれば、きっと将来のイメージが湧いてきて、文理選択もしやすくなりますよ。(神﨑先生)
今の自分で選んでOK!
たとえ将来のことはまだ決められなくても、文理選択をしたあとから徐々に自分がやりたいことが定まってくる人もいます。
その場合は、少しでも自分自身が納得して決められるように、今の自分の内にある、興味や「好き」という気持ちに素直に向き合ってみてください。
また、文理選択をしたからといって、即座に選ばなかったほうの道が閉ざされるわけではありません。
なかには文系を選んで独学で数学を学ぶ人もいれば、理系を選んで文転する人もいます。
何をどう学ぶのかは、本人次第。あまり固く考えずに、柔軟な気持ちを持って文理選択を少しずつ進めてみてください(神﨑先生)
まとめ|文理選択は“自分を知る”第一歩

今は「どこで使うんだろう?」と感じている知識も、ある時、急に役立つことがあります。
それなら一旦、真剣になって文理選択をして「自分が学びたい」と思えるものを選び取るほうがいい。
それに、人生においては「自分で選べた」ということがなによりも自分の納得につながります。
自分で選ぶからこそ、人生を自分ゴト化できるし、主体的に生きられるようになる。
文理選択は、高校生の皆さんにとって、そんな「自分で選ぶ」という経験の第一歩です。
ぜひこの機会を、消極的に対応するのではなく、自分が納得できるような決断の機会にしてもらえたら幸いです。(神﨑先生)
※記事内のデータ及びコメントは2025年5月に高校生103名が回答したアンケートによるものです
※2025年6月時点の取材に基づいています。


専門学校の時間割は?授業の特徴・スケジュール例を分野別に見てみよう!
専門学校の学費はいくら?受験料、入学金、授業料の平均まで、学びたい分野別にチェック!
専門学校の奨学金制度。給付型とは?毎月いくら?JASOO、教育ローン等もまとめて解説!
専門学校の就職事情を調査!大学との比較、就職率、メリットデメリットを解説
専門学校の面接対策!よく聞かれる質問、面接の流れとマナー
専門学校の入試方式、出願方法、難易度を押さえて不安解消!
専門学校の志望理由書(志望動機)の書き方。手順・例文・ライバルに差をつけるコツを解説!
専門学校にも偏差値はある?大学とどう違う?難易度、倍率、入試対策を解説!