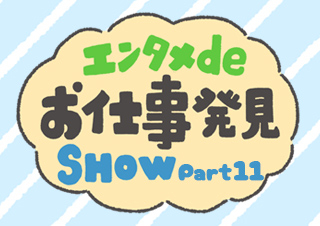大学入学共通テストの対策法。各教科別、各学年別の対策のコツを紹介
1月に実施される大学入学共通テスト。共通テスト本番までをどのように過ごせばいいの?今の勉強のしかたで合っている?と不安になっている人も多いだろう。そこで今回は、進路指導のエキスパートである堀浩司先生に共通テストの基礎知識や対策のポイントについてうかがった。さらに後半では、教科ごとに出題傾向や対策のポイントを、スタディサプリの先生たちに詳しく教えてもらったので、特に対策が不安だと感じている教科からみてほしい。
大学入学共通テストはどんな試験?
2021年から始まった大学入学共通テスト、通称「共通テスト」。どんな人が受ける必要があるのか、どんな問題が出題されるのか、どうやって対策をすればいいのか、大学受験事情に詳しい堀浩司先生に教えてもらった。
堀浩司先生
滋賀県の公立高校(守山高校、草津東高校など)で教員歴37年。
「行き先指導ではなく生き方指導」「家から近い大学ではなく夢から近い大学」などを大切にした、3年間の体系的な進路指導を推進。現在は、龍谷大学高大連携推進室フェロー、旺文社『蛍雪時代』アドバイザー、さんぽう講師としても活躍中。
大学入学共通テストの基本知識

※共通テストは全問マークシート方式
共通テストは、毎年1月中旬に行われる試験。国公立大学の一般選抜を受験する人をはじめ、私立大学の共通テスト利用入試に出願する人など、毎年、約50万人の受験生が受ける。総合型選抜や学校推薦型選抜でも共通テストを課すケースもあり、これらの選抜方式で受験する人も共通テストを受ける必要がある。全問マークシート方式で記述式問題は出題されないが、知識・技能を活用する思考力や判断力が求められる問題が出題される。受験生は、自分が出願する大学が要件に定める科目を選択して受験するため、人によって受験科目が異なるのも特徴だ。
大学入学共通テストの特徴とねらい

※以前は「大学入試センター試験」という名称だった
共通テストの最大の特徴が、読み解く文章量、理解・考察すべき情報量が多いということ。知識さえあれば解けるシンプルな問題は少なく、「理解の質」が問われる問題が多い。また、読み解く問題の分量に対して解答時間はタイトで、時間配分や解答順序など戦略を見誤ると時間内に解き切れません。問題文は、授業や「探究」学習のワンシーンを描いた会話文形式のものや、日常生活を起点に課題が設定されているなど、出題傾向に特徴があります。
いわゆる「思考力・判断力・表現力」を問うというのが出題のコンセプトになっており、「知識・技能」を試す問題が中心だったセンター試験とは、その点で大きく異なります。具体的には、複数のテキストや資料を参照しながら読解・思考・判断・分析させるような問題が、科目を問わず出題されています。
つまり、共通テストでは、長い文章や複数の資料をスピーディーに読んで理解し、即座に判断するという高い情報処理力が求められるのです。
一方、共通テストの出題範囲はあくまでも教科書の範囲内で、いわゆる難問は出題されません。
まとめると、共通テストは「難しい試験」というよりは、「(短時間でたくさんの情報を処理しなければならない)忙しい試験」であり、「(読み解くのに手間がかかる)面倒な試験」だと言えるでしょう。」(堀先生)
大学入学共通テストのスケジュール

※共通テストの本試験は1月中旬だが、追(再)試験も用意されている
令和8年度の試験から、出願の手続きはオンラインにて実施される。これまで冊子で入手可能だった、「受験案内」も大学入試センターのウェブサイトからのダウンロードでの入手となるので注意が必要だ。受験する人は共通テスト出願サイトにアクセスし、受験者自身でマイページの作成を行なった上、出願内容の登録や検定料の支払いなどを済ませ、自身で出願手続きを完了させなくてはならない。社会の受験科目数や理科の科目選択方法は出願時に決める必要があり、後から変更はできない。現役生であれば、これまで高校がまとめて出願することが可能だったが、受験者自身の手続きとなっているため、手順やスケジュールの確認は早めに行なっておこう。
共通テストの「本試験」が行われるのは1月中旬。病気などの理由で本試験が受けられなかった人のために、後日、「追(再)試験」が行われる。
共通テストは自己採点し、最終的な出願先を決める際の参考にする。なお、出願時に「成績通知」を希望した場合のみ、4月1日からマイページ上で成績を閲覧できる。
*詳しく知りたい人はこちらの記事もチェック!
2026年度大学入学共通テスト(共通テスト)の日程は?時間割、当日の注意事項も紹介!
私立大学の一般選抜と共通テスト利用入試、難易度はどう違う?
私立大学では共通テストの得点を合否の判断に用いる「共通テスト利用入試」を行っているところが多い。一般選抜と比べてどちらが難易度が高いかは一概には言えないが、共通テスト利用入試で合格するにはそれなりの高得点が必要だ。
一方、国公立大学が第1志望、併願で私立大学を受験する…という受験生の場合、共通テスト利用入試で受験すれば私立大学の個別試験対策が不要なため、メリットは大きい。
*詳しく知りたい人はこちらの記事もチェック!
大学入学共通テスト利用入試とは? 個別入試との違い、メリット・デメリットを詳しく解説!
2026年度共通テストで受験できる科目は?
2026年度の共通テストの出題教科・科目は、7教科(国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報)21科目。●国語:「国語」
●地理歴史、公民:「地理総合、地理探究」「歴史総合、日本史探究」「歴史総合、世界史探究」「公共、倫理」「公共、政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」
●数学①:「数学I、数学A」「数学I」
●数学②:「数学II、数学B、数学C」
●理科:「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
●外国語:「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」
●情報:「情報I」
自分が何を選択すべきか、先生ともよく確認しながら出願をしてほしい。
大学入学共通テスト対策のコツ

※共通テスト対策は、教科書の内容を完璧にすることが第一歩
堀先生が言うように一筋縄ではいかない共通テストだが、どう対策をすればよいのだろうか?引き続き、堀先生にうかがった。共通テスト対策はいつから始めればいい?
共通テストの出題範囲は、あくまでも教科書に載っていること。つまり、各教科の教科書レベルの知識・技能を習得することが、最初の課題となる。高校3年間でどのように対策しておくとよいか、学年別に取り組んでおきたいことについて教えてもらった。高1、高2の共通テスト対策
簡単に見えてこれがけっこう大変なのですが、3年生の夏休みが終わるまでに仕上げることを目指しましょう。1・2年生で履修する科目や分野については、2年生の3学期(通称、受験のゼロ学期)までに押さえておけるとベストです。
また、これは時期を問わずですが、授業に意欲的に取り組み、グループワークや探究的な学習に積極的に取り組むことが大事です。
というのは、共通テストでは、そういった学びのシーンが問題として設定されているケースが多いからです。実際に取り組んだ経験があれば、問題が解きやすく感じられたり、アプローチの糸口がみつけやすかったりします。受験生だからといって学校の授業を軽視しないというのは、とても大事なことです。」(堀先生)
高3の共通テスト対策
そして、共通テストでは、解答時間や解答順序の戦略がとても重要になります。時間が勝負になるため、解けない問題があったら飛ばす勇気も必要。一つの設問に固執して沼にハマってしまうと総崩れを起こしかねないので、時間をかけてでも解くべき問題か否かを判断する力も磨いていきます。
特に英語や国語は、大問ごとの「かけるべき時間」と「解く順番」が点数に影響します。模試の際に、いろいろと試しながら、自分にとってのベストなやり方をみつけていきましょう。
本番1カ月前からは、過去問や予想問題集を用いた実戦的な演習を行います。しっかりと時間を計り、解答順序なども含めて、本番のつもりで解きましょう」(堀先生)
共通テストでは何点取ればいい?
共通テストは「何点を取れば合格できる」というものではなく、国公立大学の一般選抜の場合は、大学の個別試験(2次試験)との合計点で合否が判定される。とはいえ、ある程度の目安は押さえておきたいもの。受験する大学にもよるが、「7割得点」が共通テスト受験者の一つの目標になる。
なお、難関大学をねらうのであれば7.5割は必要ですし、東大・京大といった超難関大学や医学部を受ける人は、8.5〜9割を目指したいところです。
とはいえ、完璧主義はNG。多少の失点には動じず、確実に取れるところで得点する、みんなが得点しているところは絶対に落とさないという気持ちで臨みましょう。目標としては、まずは「夏までに5割到達」を目指し、基礎を固めていきます。そして秋以降、少しずつレベルアップしていきましょう。」(堀先生)
受験する科目を選ぶ際のポイントは?
共通テストでは、特に理科と社会(地理歴史、公民)において科目選択が必要だ。自分がどの科目を選択する必要があるのか、事前にしっかり確認しておいてほしい。例えば、日本文学をやりたいのであれば日本史、国際関係を学ぶのであれば世界史、食物・栄養なら化学、看護なら生物…などが挙げられます。それが結果的に、大学での学びをスムーズに、より豊かにすることにつながります。
地理歴史、公民は6科目から最大2科目を選択し解答しますが、選択できない組み合せがあるので注意しましょう。
「地理総合、歴史総合、公共」を選択する場合は特に注意が必要です。国公立の難関大の多くは「地理総合、歴史総合、公共」の選択を認めていません。第一志望だけでなく志望変更の可能性のある大学についても確認しておきましょう。私立大学の共通テスト利用についても同様です。難関大ではほぼ認められていません。
新設科目となった「情報」にも注意が必要です。国立大学のほとんどが「情報」を必須にしていますが、配点比率は大学によってまちまちです。志望校の共通テスト全体での配点比率を確認し、力点を置く教科のバランスを慎重に検討しましょう。
また、理科は選択方式が4パターンあり、出願時に申請が必要です。出願時に担任の先生ともよく相談・確認し、間違わないよう注意しましょう。」(堀先生)
各教科のスタサプ講師が大学入学共通テスト対策のコツを解説!
対策の全体像がわかったところで、各科目の対策を見ていこう。おおまかな対策の方向性として各教科ごとの重点ポイントを紹介。共通テストの各教科の特徴や必ずおさえておきたいポイントをチェックしよう。そして試験前の9月から11月の具体的な勉強方法を紹介。試験直前のこの時期だからこそ必要な内容をアドバイスしてもらった!さっそくチェックしていこう。
【英語】共通テスト対策の基本戦略

肘井学先生
スタディサプリ「共通テスト対策講座 英語」「高3 スタンダード/ハイ/トップ レベル英語〈読解編〉」を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/hijiigaku/
【英語】新傾向のリーディングに要注意
★リーディングの大問構成が6問から8問に変化!リーディングの大問数が従来の6問から8問に変更になりました。時間配分が従来のものと異なることに要注意です。特に新しく出題された2つの問題に注意して、問題演習を重ねていきましょう。
★第4問の論理把握・文章校正問題と第8問の内容整理・要約問題に注意する!
新形式のリーディング第4問では、論理把握・文章校正問題が出題されました。文と文のつながりを見抜く、いわゆる論理力が試される試験になっています。
新形式のリーディング第8問では、内容整理・要約問題が出題されました。登場人物の主張を理解、要約して、各登場人物の主張の共通点を見抜く問題などが出題されます。
★過去問には触れずに、共通テストの試行調査・本試験・予想問題で演習
形式も配点も違うので、センター試験の過去問はおすすめしません。リーディングは長文読解のみなので、「読むための英文法」の力がついたら、さまざまな長文を読む経験を重ね、共通テストの過去問 ・予想問題で演習してください。
【英語】9月から11月までの勉強法は?
☑︎9月中旬までを目標にSVOC の文型や頻出の構文を理解し、長文を読むための基礎力をつける。
■おすすめの参考書
『肘井学の読解のための英文法が面白いほどわかる本』(KADOKAWA)
☑︎リーディング、リスニング、単語の実力を並行して伸ばすために、読解の参考書に集中して取り組む。
■おすすめの参考書
『大学入試レベル別英語長文問題 ソリューション1 スタンダードレベル』(かんき出版)
CD付きなので聞くだけでなく後について音読するシャドーイングを実践しよう。
☑︎共通テストの過去問 ・予想問題でひたすら演習する。
※スタディサプリを受講している生徒は、「共通テスト対策講座(リーディング編・リスニング編)」と12月から開講される冬期講習の「共通テスト対策講座(リーディング編・リスニング編)」がおすすめ。この2つの講座で、共通テストの試行調査・本試験・予想問題のすべてを学習できる。
■おすすめの参考書
最新の共通テストの過去問で演習したい人は、『きめる! 共通テスト英語 リーディング 改訂版』(Gakken)・『きめる! 共通テスト英語 リスニング 改訂版』(Gakken)で演習して、解き方・時間配分をマスターしよう。
さらに問題演習をしたい人は『共通テスト実戦模試 英語リーディング・リスニング』(Z会)がおすすめ。予想問題がたくさん掲載されている。
不安が自信に! 人気英語講師・関 正生先生が教える 大学入学共通テスト<英語編>
【数学】共通テスト対策の基本戦略

山内恵介先生
スタディサプリ「共通テスト対策講座 数学IA」「共通テスト対策講座 数学IIBC」を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/yamauchikeisuke/
【数学】個人戦から団体戦へ対話による実力養成が肝
★「なぜ公式が成立するか」証明のプロセスが問題に数IA の試行調査では会話スタイルで正弦定理の成り立ちを解きほぐすプロセスが、2021年度の共通テストでは二次方程式の解が有理数・無理数になるための条件について考えるプロセスがそれぞれ出題されました。単に公式を使って計算する力だけでは解けず、その場で初めて読む文章や会話・資料の理解力やその出題意図を推し量る力が求められます。
★変化を予測する想像力や課題解決の発想力も必要
グラフ表示ソフトで二次関数をスライドさせたらどうなるかを計算せずに考察するなど、ICTを反映した問題も新傾向。
また階段の踏面について三角比で、バスケットボールや噴水の軌道について二次関数で考察するというような、日常的な課題を取り上げる問題も出題の可能性があります。
★解法を説明し合うなど今までにない対策が有効
自分の解法を人に伝える力、相手の思考プロセスに共感する力(違和感をもつ力)が出題者の意図を理解する力につながっていきます。ペアやグループで試行調査や過去問、予想問題を解き、解法について説明し合う経験が有効でしょう。
【数学】9月から11月までの勉強法は?
☑︎基礎固めにセンター試験の過去問に触れ、マーク・誘導形式に慣れる。
☑︎試行調査・共通テストの過去問をていねいに解く。
☑︎共通テストの思考プロセスを問う問題に対応するため 、センター試験の過去問などを利用し、仲間をみつけて解法を説明し合う。解説を読み、出題意図や、正答に至るまでの流れを理解する。
☑︎共通テスト予想問題に取り組む。
☑︎予想問題や共通テストの過去問を制限時間内に終わらせる訓練を開始。問題の解法や出題者の意図について仲間と話し合う。また、疑問をぶつけ合い、根拠を交えて説明できるようにする。終わらない場合、原因は苦手分野であることが多いので、弱みを自覚し、共通テストの過去問などを繰り返して解くことで時間短縮を目指す。
【国語(現代文)】共通テスト対策の基本戦略

小柴大輔先生
スタディサプリ「高3スタンダード/トップ&ハイレベル」を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/koshibadaisuke/
【国語(現代文)】どこが変わる?どこが同じ?敵を知れば冷静に準備できる
★複数の資料に変化2025年度からの大変化として新第3問が追加されました。図表と文章の読み取り問題です。試験時間も80分から90分に拡大。もう一つの変化があります。センター試験から共通テストへの移行の際、第1問の評論も第2問の小説も、メイン文章に加えてサブ文章が付く“複数資料”という特徴になったはずが、単一資料に戻りました。かくて複数資料は、この新第3問に集約した格好となりました。
大問1~3がすべて現代文で「文章量が増えた!?」とあわてないでOK。評論と小説の総文字数はセンター試験時代の平均より少なめです。また各設問の選択肢も五択から四択が基本になりました。また最終問題での「生徒による探究ノート形式」や「生徒による対話形式」など設問形式の小さな変化に惑わされないこと。むしろメイン文章の理解のヒントになっているくらいです。
センター試験では定番だった小説での慣用句の知識問題は、共通テストになってからは出題されない年度もあります。でも語彙力は文章理解と選択肢吟味で常に大事です。
総合的にはセンター試験時代から変わらぬ設問形式が主ですから、各社から発刊されている予想問題を含む「共通テスト問題集」や模試を利用しながらも、センター試験の過去問も使えます。
★新第3問は時事問題・身近な社会問題がテーマ
評論でも小説でもない実用文と図表の読み取りが新第3問では課されます。試行テスト(サンプル問題)も含めて参考にすれば、テーマは外来語・今どきの言葉遣い・環境問題など身近で時事的な分野のようです。解答時間が10分程度しかないため、先に選択肢を読んでから図表や文章を読む順番が有効です。新聞をはじめ時事ネタに興味をもち、現代社会の知識を蓄えておきましょう。
★変わらない部分について過去問の活用は有効
「資料のタイトル」→「設問条件(棒線の理解、表現に関する説明)」→「該当箇所を中心に答え探し」の順で読み、正答にたどり着く道筋は変わりません。また漢字5問、語句の意味3問も変わらないので、過去問が有効です。
【国語(現代文)】9月から11月までの勉強法は?
☑制限時間内で解く練習をスタート。
☑間違ったら、解説を読みミスの原因を知る。
☑「のみ」「すべて」「べき」など、誤った選択肢の典型的なパターンを知る。
☑漢字・語句の意味などは高配点だから、知識モノ参考書でしっかり強化。
☑新聞やニュースで、現代の社会問題を知る。
☑過去問・予想問題などを古文漢文含む【国語】として90分で解く練習。
☑雑にならないよう、評論や小説など単体をじっくり解答する練習も入れる。
☑理系学部志望なら3日で1時間など、科目の比重に合わせて正しいルーティンを決める。
☑マークシート付きの予想問題集などを購入し、マークシートでの解答に慣れる。
不安が自信に! 人気現代文講師・兵頭宗俊先生が教える!大学入学共通テスト
【国語(古文・漢文)】共通テスト対策の基本戦略

岡本梨奈先生
スタディサプリ「共通テスト対策講座 古文」「高3古文〈文法編〉」その他を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/okamotorina/
【国語(古文・漢文)】基礎固めをしっかりして勝つための戦略を立てよう
★複数テクスト問題の対策が必要複数の資料をからめた問題や、生徒同士や生徒と教師の会話文を読んで解く問題などが出題される可能性が高いです。資料は現代語の場合もあれば、古文の場合もあり、長さもまちまちです。共通点と相違点を意識して読むことが重要です。
会話文は解答には関係のない相槌のようなものも書かれているため、一言一句ていねいに読み込むのではなく、必要そうな情報とそうではない情報をその場で判断しながら、読むスピードを変えられる読み方の練習などが必要です。
★解答に必要な知識は従来と同じ
素材の多さという新傾向はあるものの、問われる内容は今までと大差なし。古文は語意、敬語などを含む文法、心情や理由、内容解釈、和歌の解釈、修辞の問題、漢文は漢字の読み・意味、返り点や書き下し文、解釈、内容理解などが中心になりそうです。これらに加えて上記の新傾向の問題が出題される形のはずです。
★過去問+予想問題に当たり時間配分などの戦略を立てる
古文は単語・文法・読解方法・古文常識・和歌の修辞法など、漢文は語順・句法・単語・漢詩など、土台を固めて設問形式別解法もつかんでから実践にトライ。
過去問は解く順番や時間配分などの戦略を立てるのに有効ですが、新課程は問題数や制限時間も違うので気をつけましょう。ただし、時間内に解ききる大変さは過去問と同じはずなので、イメージをつかむ練習になるはずです。新課程に関するものは試作問題と、昨年度のものしかないため、それらを参考にして戦略を立てるとよいでしょう。
共通テスト過去問自体もまだ数回分しかないため、試行調査や過去のセンター試験の本試・追試も手に入るものは実施し、市販の共通テスト予想問題なども解いて参考にしましょう。
【国語(古文・漢文)】9月から11月までの勉強法は?
☑︎文法・句法・単語などの土台をマスター。
☑︎読解方法、和歌・文学史なども理解する。
☑︎実際の過去問に触れていく。大問別でもよい。時間はいくらかけてもOK。
☑︎過去問の文章や選択肢を正確に読み取る(=精読)練習をする。
☑︎間違えた問題を分析し、ミスを繰り返さない。
☑︎解く順番や時間配分などの戦略を立てる。
☑︎制限時間で解けない場合、文法や単語がすぐに答えられないことが多いので、苦手単元や単語を反復して、秒速で答えられるくらいにする。
☑︎オリジナル予想問題なども利用して、共通テスト特有の複数資料や会話文問題を解く練習も重ねる。
【世界史】共通テスト対策の基本戦略

村山秀太郎先生
スタディサプリ「共通テスト対策講座 世界史B」「高3トップ&ハイレベル 世界史〈通史編〉」を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/murayamahidetaro/
【世界史】教科書より何より過去問!これが最短&最速の対策
★読むべき資料が増えた分、速さ、正確さが一層必要試行調査で出たトルコの碑文、綿の価格推移表のような今までにない資料を複数組み合せた問題が出るでしょう。読む要素が増えるので、ざっと目を通して設問を勘違いせず読み取る事務処理能力が今まで以上に必要です。
★素材は目新しくても問われるレベルは大差なし
新傾向に驚くかもしれませんが、出題形式は変わっても、問われている内容はセンター試験と同レベル。識別問題に必要な知識は、大谷翔平、三苫薫、錦織圭のうちサッカー選手は誰ですか?というレベルが大半ですから、過剰な心配は無用です。
★わからなくても過去問に触れ「ノート」で知識を定着
膨大な世界史の範囲を最短でカバーできるのは、過去問で間違いなし。
過去4年分の共通テスト「34問×2試験×3年=204問」に加えて、センター試験23年分の本試験と追試験「36問×2試験×23年=1656問」に接し、解答の根拠となる知識を自分でノート(マイノート)にまとめる。
ただし、決して綺麗な芸術品のようなノートを作成しないこと。時間の無駄。勉強と“作業”は異なる。メモ書き集、もしくは教科書の当該箇所に下線を引くというマイノート(教科書そのものでもいい)、これが一番の対策だ。
★グラフ問題への最強かつ必須の対策は年号を覚えること
共通テストの折れ線グラフ問題の多くが時期を問うものであるので、“年代”の識別能力が必要。そのためには“年号”を地道に覚える努力を怠らないように。
【世界史】9月から11月までの勉強法は?
☑︎「薄く広く」でいいので、ひとまず全体を知るために過去問に目を通す。わからないなら、答えを同時に見て時間を短縮。正答の根拠を理解する。
☑︎問題から得た知識を、「土地の利用」「官吏の登用」などテーマ別にノートに書き留める。
☑︎市販の共通テスト予想問題集、塾などの対策講座で新傾向に触れ、複数資料に慣れる。
☑︎過去問による世界史の理解を続ける。全問終わったら反復も効果的。
☑︎過去問と予想問題を繰り返し解いて理解を深める。正答、誤答の根拠の理解を心がける。
【日本史】共通テスト対策の基本戦略
【日本史】知識のインプットは早期着手・早期完成が基本
★テスト形式が変わっても知識のインプットは必須共通テストでは、思考力や判断力などを活用して解く問題が増え、以前より時間がかかるようになりましたが、ほとんどが教科書の知識の習得を前提にした出題。とはいえ、去年は自分も会場で受験したのですが、教科書「欄外」部分まで出ていたのでプロでも迷うものもあり…注意が必要です!
教科書や一問一答集などを使って、全範囲の知識をインプットする3カ月にしましょう。
★「忘れない」ために毎日取り組むことが重要
知識をインプットする際に意識したいのは、少ない時間でもいいので毎日取り組むこと。例えば同じ週3時間の勉強でも、週に1日だけ3時間やるより、1日30分を週6日(30分×6日=3時間)続けるほうが知識は定着します。
一問一答集は3周を目安に、全問解き直すよりも、正解したものはチェックを入れておき、間違えた問題だけを回すほうが効率的です。その際、(欄外を含む)教科書レベルよりも難しい問題はもちろん「1周めすらやらない(=手をつけない)」方式をとってください。共通テストしか受験しないと決まっているなら、共通テスト用の一問一答集をやるのも一つの手です。その際、漢字をかきなぐる必要はありません。共通テストは全問マークセンス方式ですから。
★過去問や対策問題集に取り組み、新傾向問題に慣れよう
共通テストでは、リード文が長く図版・グラフ・史料を利用した設問がふんだんに見られ、そもそも「読むのに時間がかかる=解くのに時間がかかる」ことも注意したいポイント。35年も仕事しているプロのぼくですら、本番だからと注意して解いたら45分くらいかかりましたよ。現段階では、過去問だけではまだ年数が少ないため、共通テスト対策問題集や模試を使って出題形式に慣れましょう。
【日本史】9月から11月までの勉強法は?
☑3カ月で全範囲の知識をインプット。学校や塾・予備校の進度が遅い場合は先取り学習(進度が早かった場合はOK!無理に繰り返しやらない)。
☑用語の周辺情報や因果関係を1回で正しく理解するつもりで集中。できごとの原因や背景、結果、影響のつながりを意識。結果的に勉強時間の短縮になる。
☑普段は本棚の飾りにしているであろう図説資料集をこまめに使い、資料(史料・地図・写真・グラフ)から読み取る力を養う。
☑一問一答集を使い、覚えられているかどうか確認 (1周め)。間違えた問題のチェックを忘れずに。
☑一問一答集を使い、覚えられているかどうか確認 (2周め)。間違えた問題だけを解いて、間違えた問題は再度チェック。
☑過去問の問題形式を確認する。初めは制限時間を決めずに解いてみる。
☑一問一答集を使い、覚えられているかどうか確認 (3周め)。間違えた問題だけを解いて、間違えた問題は再度チェック。
☑苦手な「時代」は、教科書を読み直して理解する。
☑共通テスト対策問題集や模試を使って出題形式に慣れる。この段階では時間を計るといい。多くの問題に触れ、さまざまな問われ方に対応できるようにしておく。日本史の場合、「同じ」問題を繰り返すことに意味はありません。「同じような」問題を解いて知識を抽象化する(どの角度から聞かれても〇〇は要するに〇〇なんだなと理解する)ことが大事。基本的に解くのは1度きり!
【公民】共通テスト対策の基本戦略
【公民】知識のインプットプラスアルファの対策が有効
★「公共、倫理」:共通テスト特有の出題形式に慣れておく「公共」は基礎科目なので当然ですが、「倫理」は青年期・源流思想・西洋近現代思想・日本思想・現代の諸課題という5つの分野すべてから出題されるので、まずは全範囲の知識をインプット。教科書の欄外レベルも出ます。
特に苦手な人が多い「西洋近現代思想」は差がつく(配点も多い!)ので、きちんと教科書・テキスト・参考書などをフル回転し、過去問や共通テスト問題集の解説を読み込みましょう。共通テスト対策の問題集で、対策を万全にしておきましょう。
★「公共、政治・経済」:普段からグラフや表を読み取る訓練を積もう
「公共」「政治・経済」共に欄外や図などの解説を含む教科書の細かい知識を問う問題が必ずあります。図説資料と合わせて一つひとつの分野をていねいに取り組んでください。
時事的な話題も含めて、教科書の隅々まで学習しておかないと高得点は難しいでしょう。短期決戦だと舐めてかかると大変!今日からすぐ本気を出してください。
また、会話などからなるリード文だけでなく、グラフや表の読み取り問題もあるので、グラフの作成意図・目的を考察する訓練を。
【公民】9月から11月までの勉強法は?
☑1カ月半で全範囲の知識をインプット。学校や塾・予備校の進度が遅い場合は先取り学習。早い場合はさらに繰り返す必要なし。
☑一問一答集を駆使し、基礎的な知識を確認。3周を目安に、間違えた問題だけを回すのが効率的。漢字も書けなくていい。得点力をつけることに特化。
☑過去問や共通テスト対策問題集や模試を使って出題形式に慣れる。必ず時間を計ること(プロの自分でも倫理は会場の緊張感のなかで受験したら制限時間ギリギリだった…!)。解くのは1度きり(最高でも2度)という気合で多くの問題に触れ、さまざまな問われ方に対応できるように。
☑5分野の教科書の記述量に応じて勉強にかける時間を配分。軽めでいいが舐めていると痛い目にあう。
☑「年代」「世紀」そのものよりも、分野ごとの「前後関係」を押さえる。人物や語句を暗記するだけでなく、背景や歴史的順序をチェックするようにしよう。
☑最新の統計が収録された用語集・図説・資料集を使う。最新の統計をもとにした問題が出題されるので、兄姉や先輩からもらったものではなく、最新のものを使う。
☑インターネット・新聞・テレビなどを通じて時事的な話題に慣れ親しむ。特に現代は毎日のように世界が激動しているので、10月ごろまでの話題は最低限押さえる!
【地理】共通テスト対策の基本戦略

鈴木達人先生
スタディサプリ「共通テスト対策講座 地理B」「高1・2・3地理〈地誌編〉」を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/suzukitatsujin/
【地理】じっくり時間をかけて解く!解き方をつかめば点は伸びる
★統計データから意味を読み取る力がカギ共通テスト 地理総合、地理探究では統計データ関連の問題は今まで以上に配点が高く、考えさせる内容になっています。さまざまなデータに触れ、数字やグラフから意味を読み取る力、A→B→Cと事象が変化する流れをつかむ力を磨きましょう。
★ヒントやトリックをみつける訓練を積む
従来の旧課程と傾向や難易度は変わらないので、過去問は有効。地理は推理小説のようにヒントやトリックが織り交ぜられた問題が多く、「着眼点はどこか?」「決め手は何か?」を1問ずつ理解していけば解き方のパターンがつかめます。
★得点アップの近道は時間をかけて解くこと
暗記問題は実はわずかで、メインは考えれば解ける思考力問題。じっくり時間をかけるほど確実に点数がアップします。ちなみに1題は超難問が出るのがお約束のパターン。「全部解けなくていい」という気構えでOKです。
【地理】9月から11月までの勉強法は?
☑︎基本知識のおさらいは中学校の問題集で十分。最低2冊やり終えれば 、知識面はクリア。
☑︎夏から9月にかけて共通テストの過去問を最低10回分解く。
☑︎過去問で出た統計グラフは『データブック オブ・ザ・ワールド』などの資料で確認し補強を。
☑︎過去問は解答だけでなく解説もよく読み、根拠を理解する。
☑︎模試や予想問題は時間配分の参考程度に活用。対策自体は過去問のみでOK。
☑︎10回分の過去問をやり終えたら、主要科目のすき間時間にリフレッシュをかねて復習。
【物理】共通テスト対策の基本戦略

中野喜充先生
スタディサプリ「共通テスト対策講座 物理」「共通テスト対策講座 物理基礎」を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/nakanoyoshimasa/
【物理】基礎から実践へ。まずは教科書の理解が重要
★教科書を使って全分野の知識の定着を確認2022〜2024年度の共通テストでは、センター試験のころと同じような問題は少なく、試行調査のような、探究活動の内容や日常生活で起こる現象を題材にした問題が主に出題されました。しかし、2025年度はセンター試験のころのようなタイプの問題も多く出題されました。この先もこの折衷傾向が続くと思います。
見慣れない問題が多めでしょうが、前提となるのは教科書の基礎知識。3カ月間で、各分野の重要事項(式・法則)を正確に理解しましょう。
★データやグラフの問題は復習して確実に理解
センター試験のときよりも、実験データの解析問題や、グラフ読み取り問題の出題が多めに出題されると予想されます。現象を理解していなければかなり手を焼くので、模擬試験や問題集で解けなかった問題は、必ず復習して確実に理解しましょう。
★共通テストの出題形式に慣れるために問題演習を
共通テストの問題には癖が多いからこそ、いかにして問題演習を行うかが対策のカギです。
そこで活用したいのが、市販の共通テスト対策問題集。正解を見ながらでもいいので、まずは解説をしっかり読んで、出題の形式に慣れましょう。もちろん,過去問も大事です。センター試験のものも含めてしっかりと取り組みましょう。
【物理】9月から11月までの勉強法は?
☑︎各分野の式の種類と内容を把握する。力学、電磁気学、熱力学、波動、原子の順に学習を進める。
☑︎教科書の章末問題を解き、式の使い方を理解。
☑︎苦手分野は学校配付の問題集の類似問題に挑戦。
☑︎教科書に載っているグラフについてもチェックしておく。
☑︎実験結果をグラフで表す練習を行う。
☑︎選択問題だった原子についても触れておく。
☑︎共通テスト対策問題集を使って出題形式に慣れる。初めは制限時間を決めずにじっくり解くことを意識する。
☑︎共通テスト対策問題集を使って出題形式に慣れる。制限時間を計って時間内に解く練習を重ねる。
☑︎過去問で演習。センター試験の過去問も数回分でいいので必ず触れておく。
【化学】共通テスト対策の基本戦略

坂田薫先生
スタディサプリ「共通テスト対策講座 化学」「共通テスト対策講座 化学基礎」を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/sakatakaoru/
【化学】「化学の本質」を追究し、問題演習を積み重ねる
★「なぜそうなるのか?」と原因を考え理解を深める初見のデータをもとに考察する問題、結果だけでなく実験操作を与えられる問題、見たことのない物質を扱った問題の出題が予想されます。そういった問題に対応できるよう、日頃から「なぜそうなるのか?」を考えて理解を深めておきましょう。
★実験問題は資料集でイメージトレーニング
情報を読み取るのに苦労する実験問題が出題される可能性があります。資料集に掲載されている写真は、実験の内容をイメージするのに役立つので活用したいところです。プロセスや操作、現象の変化を押さえましょう。
★共通テスト予想問題集や私大マーク式入試問題を使った共通テスト対策
大問の中に分野をまたいだ問題が出題される可能性があります。分野混合の問題に対しては、共通テスト予想問題集や私大マーク式入試問題で対策するのが効果的です。
【化学】9月から11月までの勉強法は?
9月
☑︎3カ月かけて、公式や典型的な解法を理解する。
☑︎理解があやふやなテーマは「なぜそうなるのか」を追究する(スタディサプリの授業で確認する)。
10月
☑︎単元ごとに、公式や解法を使って問題を解いて定着させる。
11月
☑︎共通テスト予想問題集や私大マーク式入試問題に取り組み、形式に慣れる。
9月
☑︎各反応について、反応のしくみ(「どんな物質の組み合せで反応が進行するのか」「反応の結果、生成物は何なのか」)を1カ月かけて理解する(スタディサプリの授業で確認する)。
☑︎主要テーマ(気体・工業的製法など)を押さえる。
10月
☑︎暗記事項(「沈殿を作るイオンの組み合せ」や「沈殿の色」など)を覚える(暗記事項は早ければ早いほど良い)。
☑︎分野別のマーク式問題集を解いて定着させる。
11月
☑︎共通テスト予想問題集や私大マーク式入試問題に取り組み、形式に慣れる。
9月
☑︎構造異性体は構造式を書き出せるように、立体異性体は異性体をみつけられるように練習しておく。
☑︎理解があやふやな反応は「何が起こっているのか」を追究する(スタディサプリの授業で確認する)。
10月
☑︎有機化合物の反応と高分子化合物の知識を一とおり頭に入れる。
☑︎分野別のマーク式問題集を解いて定着させる。
☑︎有機化合物や高分子化合物の計算問題を解いておく。
11月
☑︎共通テスト予想問題集や私大マーク式入試問題に取り組み、形式に慣れる。
【生物】共通テスト対策の基本戦略

牧島央武先生
スタディサプリ「共通テスト対策講座 生物」「共通テスト対策講座 生物基礎」を担当。
https://studysapuri.jp/course/teachers/makishimahirotake/
【生物】正しい知識を得ることが共通テスト対策の第一歩
★教科書を使って全単元の知識の定着を確認共通テストは、グラフや図から情報を読み取る問題や、実験考察問題が中心となりますが、基礎知識が土台となることに変わりありません。まずは教科書で全単元の知識を確認しながら、文章を読むことに慣れましょう。
★3~5年分の過去問を用意し、考察問題に取り組む
3~5年分を目安に、過去に出題された考察問題を通じて、練習しましょう。間違った内容の選択肢も、どうすれば正しい文章になるのか考えて有効に活用しよう。
★問題集を活用して初見のデータから読み取る練習
共通テストで注意したいのが、教科書に載っていない初見の実験やデータから情報を読み取る問題。単に教科書を暗記する学習では対応できません。共通テスト対策問題集に取り組み、初見のデータから読み取る練習を行いましょう。
【生物】9月から12月までの勉強法は?
☑︎教科書と傍用問題集の基礎問題で全単元の知識を確認。
☑︎全単元の授業が終わっていない人は先取り学習。
☑︎教科書の生物用語を言葉で説明できるように。
☑︎観察・実験の授業があるなら 積極的に参加し考察。
☑︎教科書や図説のグラフを見直して、読み取る練習をしよう。
☑︎傍用問題集の標準問題を全単元解く。
☑︎「何を問われているか」を意識しながら問題演習。
☑︎本番と同じ時間・形式で過去問に取り組む。
☑︎共通テスト対策問題集を使って出題形式に慣れる。
☑︎間違えた問題は、解説の読み込みにも時間をかける。
☑︎教科書を読み直して、単元同士のつながりに気づく。
まずはこの記事で登場した先生たちのアドバイスをしっかり聞いて、不安を自信に変えていこう!
文/笹原風花 監修/堀浩司 構成/スタサプ編集部
※2025年7月情報更新
1回約15分の神授業で共通テスト対策!

★【共通テスト】関連記事をチェック!
●2026年度大学入学共通テスト(共通テスト)の日程は?時間割、当日の注意事項も紹介!
●大学入学共通テスト利用入試とは? 個別入試との違い、メリット・デメリットを詳しく解説!
●【2026年度版】共通テストに遅刻!試験は受けられる?大学入試トラブル対処法
●共通テストに失敗したらどうする?5つの選択肢【先輩たちの体験談つき】