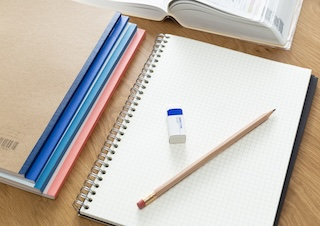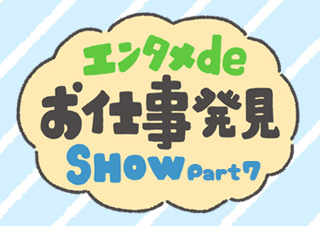CAMPUS VIBES 学校の垣根をこえる!学びの越境
大学・専門学生の生活や進路トレンドをお届け!今回のテーマは「越境授業」。大学や専門学校の垣根をこえて、もっと自由に学べる時代になっているよ。
他校の授業に参加し、新たな知識や仲間に出会える「学びの越境」の魅力をお伝え!
これを読めば、未来のキャンパスライフがもっとリアルに見えてくる!
目次
ニューヨークの大学生と一緒に!国境を超えたゲーム開発授業がすごい

京都コンピュータ学院が、アメリカ・ニューヨークの名門ロチェスター工科大学(RIT)とコラボ。
国も文化も違う学生たちがチームを組み、オリジナルゲームを制作。言葉の壁をこえて挑む、ものづくりの現場とは?
プロも驚くハイクオリティのゲームが完成
 今回作るゲームテーマは「kawaii」。国によって感じ方や定義が違うため、まずは何をkawaiiと思うかからディスカッションし制作を開始。
今回作るゲームテーマは「kawaii」。国によって感じ方や定義が違うため、まずは何をkawaiiと思うかからディスカッションし制作を開始。言葉の壁も翻訳アプリやカタコトの英語などを駆使して乗り越え、完成を目指した。
作業は各メンバーの得意を生かして分担。開発を進めるなかで、技術交流ができるのも大きな刺激に。
 最後のステージ発表ではバラエティ豊かなゲーム作品が揃い、プロも思わずうなる完成度!
最後のステージ発表ではバラエティ豊かなゲーム作品が揃い、プロも思わずうなる完成度!
次回はしっかり英語で会話したい!」
(H.Tさん・3回生)
同時に自分の足りなさも痛感したので次はもっと成長した自分で挑みたい!」
(A.Tさん・2回生)
(S.Mさん・3回生)
(K.Yさん・4回生)
大学の壁がない!?八王子市is街ごとキャンパス説

東京都・八王子市の大学・短大・高専が力を合わせ、街ぐるみで学生を応援。
学校の垣根を越え授業やイベントに参加できる、まるで街全体がキャンパスのような取り組みがあるんです。
キャンパスの壁を超えて集まる学生発表会

学生同士で研究や活動の成果を発表する聴講自由のイベント。
新しいアイデアや挑戦に出会えて刺激がいっぱい!新たな友達が増えるのも◎。
街の魅力を発信!学生CMコンテスト

多様な学生がオリジナルCM動画を作るコンテスト。
八王子の魅力をアイデアで表現し、学びも交流も同時に楽しめる。
学部も大学も関係ない、学生が主役のフェス!

八王子の街全体を舞台にできる学生中心のお祭りイベント。
市や学生委員会との共催で、当日はライブや屋台など、学生も地域の人も一緒に盛り上がれる最高の体験に。
先輩たちも体感中!“大学の枠”を越える授業
学校の枠を越えたワクワク授業は、全国でも拡大中! 普段とは違う学びって実際どう?先輩たちのリアルを聞いてみました。「商業や金融に興味があり、他大の商学部の授業に参加。
日々学んでいる情報連携学部と、商学部の学びが合わさることで、社会のしくみをより深く理解でき、学びの幅が広がりました。」
(たかりおさん・大1・東京都)
「実務的な体験をしてみたいと、現役弁護士を招いた模擬法廷や判例ディスカッションを通じた実践中心の授業に参加。
同じ学部でも大学が違うとアプローチ方法も変わり、最新の法学トピックを深掘りできた。」
(JISSさん・大2・岐阜県)
「普段は芸術系学部ですが、栄養学部で骨密度など体のしくみについて学びました。
楽しいだけでなく、自分の体を科学的に理解でき、新しい視点が増え、知識や表現の幅が広がるのを実感。」
(みくさん・大1・埼玉県)
「普段は文学部ですが、前から興味のあった他大学のデータサイエンスの授業や、女子大学のジェンダーの授業に参加。
オンデマンドで手軽に、気になる分野の授業が受けられるのが◎。」
(はまゆうさん・大4・神奈川県)
おわりに
自分が通っている学校以外の授業が受けられたり、交流が深められるのってすごいよね!
みんなが気になっている学校にも仕組みがあるかもしれないから、ぜひ調べてみてね◎。
Edit・Text/Noriko Taki, Design/Mari Shimazu(ma-h gra)